この記事はで読むことができます。

ねぇTom、私って説明が下手ってよく言われるんだけど、自分じゃどこが悪いのかわかんなくて…。

あるある(笑)。でも実は、説明って“センス”じゃなくて“順番”とか“考え方”の問題だったりするんだよ。

え、そうなの?じゃあ練習すれば上手くなれるってこと?

もちろん。実際、説明が上手い人ってみんな同じような“話し方の型”を持ってるんだよ。

そういうの知りたかった!なんか、言いたいことがうまくまとまらなくて、伝わってない気がして…。

うん。今回は“伝わる人だけがやってる3つの共通点”を紹介するね。意識するだけでも、ぐっと変わると思うよ。
「一生懸命説明したのに、全然伝わっていなかった…」そんな経験はありませんか?説明の上手さは、センスではなく“構造”で決まります。
本記事では、説明が上手い人に共通する3つの話し方のポイントを紹介し「何から話すか」「どうまとめるか」といった実践テクニックを学びます。会話・プレゼン・指示出しなど、あらゆるビジネスシーンで“伝わる人”になるヒントが詰まっています。
説明が下手な人は、“結論”を最後に持ってくるなど、話の順序で損をしていることが多いです。逆に、順番を整えるだけで伝わり方が一気に変わります。
「結論から話す」「情報を3つに絞る」「相手目線で話す」といった、誰でもすぐに実践できる型が紹介されています。意識するだけで、説明の伝わり方が見違えます。
覚えるべきポイントは少なく、シンプル。普段の仕事や会話ですぐに使える“話し方の工夫”を身につけることができます。
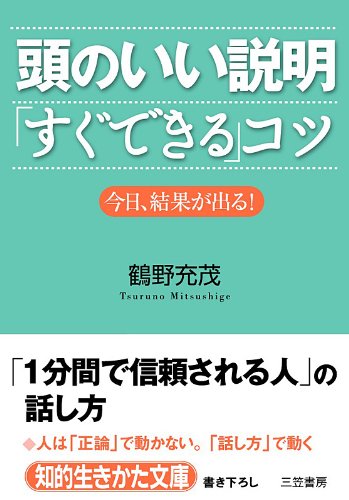
| 著者 | 鶴野 充茂 |
| 出版社 | 三笠書房 |
| 出版日 | 2008年11月20日 |
| ジャンル | 人間関係・コミュニケーション |
説明が上手な人の最大の特徴は、「結論を最初に伝える」という話し方を徹底していることです。なぜなら、最初に結論があると、聞き手はその後の情報を“整理された状態”で受け取れるからです。本書でも「まずは“何が言いたいのか”を一言で言う」と何度も繰り返されています。
たとえば、「A案で進めたいです。理由は3つあります」と切り出されると、聞く側も構える準備ができます。逆に、理由から入ってしまうと、聞き手は話のゴールが見えず、途中で注意がそれてしまいがちです。
私自身も仕事で報告をするときに、結論を後回しにしてしまい、「で、結局どうしたいの?」と聞き返されたことがありました。しかし、「結論→理由→具体例」という流れを意識するようになってから、話がスムーズに伝わるようになりました。
これはプレゼンや報告書だけでなく、日常の会話でも効果を発揮します。“先に言ってくれると分かりやすい”というのは、どんな立場の人にも共通する心理です。つまり、説明をうまくしたいなら、まず「結論から話す」ことを習慣化するのが第一歩です。
説明が上手い人は、話す情報を多くしすぎず、「3つにまとめる」ことを意識しています。なぜなら、人は一度に覚えられる情報の数に限りがあり、3つ程度がもっとも理解・記憶しやすいからです。本書では「3は人が最も納得しやすい数字」として、根拠や理由を3つに絞る方法が紹介されています。
たとえば、「この企画を推す理由は、①コストが安い、②スピードが早い、③他社との差別化ができる」のように、3点にまとめると説得力がグッと上がります。
私も以前は、思いつくままに5つ6つと理由を並べていたのですが、結局どれも印象に残らず終わってしまうことが多かったです。しかし、あえて「3つだけに絞る」と決めてから、聞き手の反応が明らかに良くなりました。そのため、このブログもポイントを3つに絞って解説しています。
選ばれた情報だからこそ、“大事なことなんだ”という印象も強まります。これは報告や資料作成、メール文章にも応用できる非常に使いやすいテクニックです。
情報はたくさんあるほど良いのではなく、“選ばれているかどうか”がカギになります。つまり、「話を3つに整理する」ことで、聞き手の理解と納得は大きく変わるのです。
説明がうまい人は、自分の言いたいことを一方的に話すのではなく、「相手が聞きたいこと」に合わせて話を組み立てています。なぜなら、説明とは“伝えること”ではなく、“伝わること”が目的だからです。本書でも「相手の関心や立場を想像して話すことが、説明力の本質」と明記されていました。
たとえば、上司に報告するときと、後輩に指示するときでは、言葉の選び方も順番も変える必要があります。上司には「結果と理由」を簡潔に伝える方が良く、後輩には「背景や目的」から丁寧に説明する方が効果的です。
私自身も、相手の立場に合わせて話すことを意識するようになってから、説明後のリアクションが格段に良くなりました。相手の興味や不安を想像して話すことで、「話がわかりやすい」「信頼できる」と感じてもらえるようになります。
説明力とは、聞き手の“脳内に道筋をつける”スキルとも言えるかもしれません。自分本位ではなく、相手目線で言葉を選ぶことこそが、説明を成功させるカギなのです。つまり、信頼される説明は、「相手の立場に立つこと」から始まるのです。
会話やプレゼン前に、「まず何が言いたいのか?」「なぜそう思うのか?」「具体例はあるか?」の3点をメモに整理してみましょう。わずか1〜2分の準備で、話の伝わり方が格段に変わります。即興で話すより、少し“形を整える”だけで説明力はぐっと上がります。
何かを伝えるときは、理由や要点を3つに絞るクセをつけましょう。「結論+3つの根拠」は相手にとって理解・記憶しやすく、説明の説得力が増します。話す前に「3つにまとめる」と意識するだけでも、説明の質は一気に洗練されます。
同じ内容でも、「上司に話すなら?」「後輩に話すなら?」と2パターンを考えてみましょう。相手の立場や知識量に応じて説明を組み替えることで、“伝わる説明”の感覚が身についていきます。想像力を使ったトレーニングが、説明力の大きな差を生みます。
本書には「すぐに使える説明のコツ」が豊富に紹介されており、職場での説明スキル向上に即効性があります。特に「結論から話す」「お願いで終える」といった技法は、日常業務に直結する実用性が高い内容です。だが、事例の一部がやや冗長で、すべてのビジネスシーンに合うとは限らないため、満点は控えました。
具体例と反面教師のパターンを繰り返す構成により、「何が良くて何が悪いか」が非常に明確に示されています。語り口も柔らかく、専門用語も少ないため、誰にでも読み進めやすい内容です。読み手が迷子にならないよう工夫されており、分かりやすさは極めて高いです。
主にビジネスパーソン向けに書かれており、特に管理職や営業職にとっては有効な内容ですが、専門職や非営利分野では使いにくい部分もあります。また、対面コミュニケーションに偏っており、デジタル時代の非同期的なやりとりには一部適用が難しいと感じました。
軽妙な文体と適度なユーモア、視覚的な工夫でテンポよく読めます。章立ても明快で、途中からでも読み始められる点も魅力です。ただし、中盤以降はやや内容が重複してくる印象があり、若干の冗長さを感じる部分がありました。
「説明の技術」に関しては非常に深掘りされていますが、学術的裏付けや体系的理論には乏しいです。実務経験ベースで説得力はあるものの、ロジカル・シンキングやプレゼンテーション理論との接続が弱く、専門書としての厚みはもう一歩です。

なるほど〜。結論から話すとか、3つに絞るとか、意外とできてなかったかも。

でしょ?説明がうまい人って、実はちゃんと“型”を持ってるんだよね。

なんか、自分の話が伝わらなかった理由がちょっと見えてきた気がする…。

それだけでも大きな進歩だよ。あとは場面に合わせて話し方を少し変えるだけで、相手の反応が全然違ってくると思う。

よし、まずは“結論→理由→例”の順番を意識してみる!

いいね。型を身につければ、説明ってどんどん楽しくなるよ。
説明が上手くなるコツは、「センス」より「順番」と「意識」。誰にでもできる小さな工夫が、あなたの伝え方を大きく変えてくれます。
