この記事はで読むことができます。

うちの子、最近おしゃべりも増えてきて、成長してるなーって思うんだけどさ…将来、ちゃんと勉強できるようになるのか不安なんだよね。

今はまだ1歳だけど、「言葉の理解が遅いかも?」とか気になっちゃってさ…。

早くから何かやった方がいいのかなって思って、本とか読み漁ってるんだけど、どれもざっくりしててピンとこない。

わかる!でもね、この前読んだ本に「勉強が伸びる子には、学び方に合った環境が必要」って書いてあって、ちょっと納得したんだよね。

へぇ〜、まだ小さいうちから“学び方”って意識した方がいいのか。

うん、1歳でも“考える力の土台”をどう育てるかって、大事らしいよ。親の関わり方で、その後の伸びが全然違うんだって!
1歳のうちは「まだ早い」と思いがちですが、実はこの時期からの関わりが将来の学力を左右します。
この記事では、勉強が伸びない子に共通する原因と、今からできる親の声かけや関わり方のヒントをご紹介します。
勉強時間が確保できていても、理解や定着につながっていない原因は「学びのタイプ」にあります。子どもの特性に合った学習法を選ぶことが成果への近道になります。
知識を詰め込む前に、「考えるための土台」が整っていないと応用力が育ちません。思考のクセや自己肯定感のズレを調整することで、勉強がぐっと身につきやすくなります。
子どもの成績を左右するのは、勉強内容だけでなく、親の声かけや関わり方も大きく影響します。日々の声かけを見直すことで、子ども自身のやる気と理解力が大きく変わってきます。
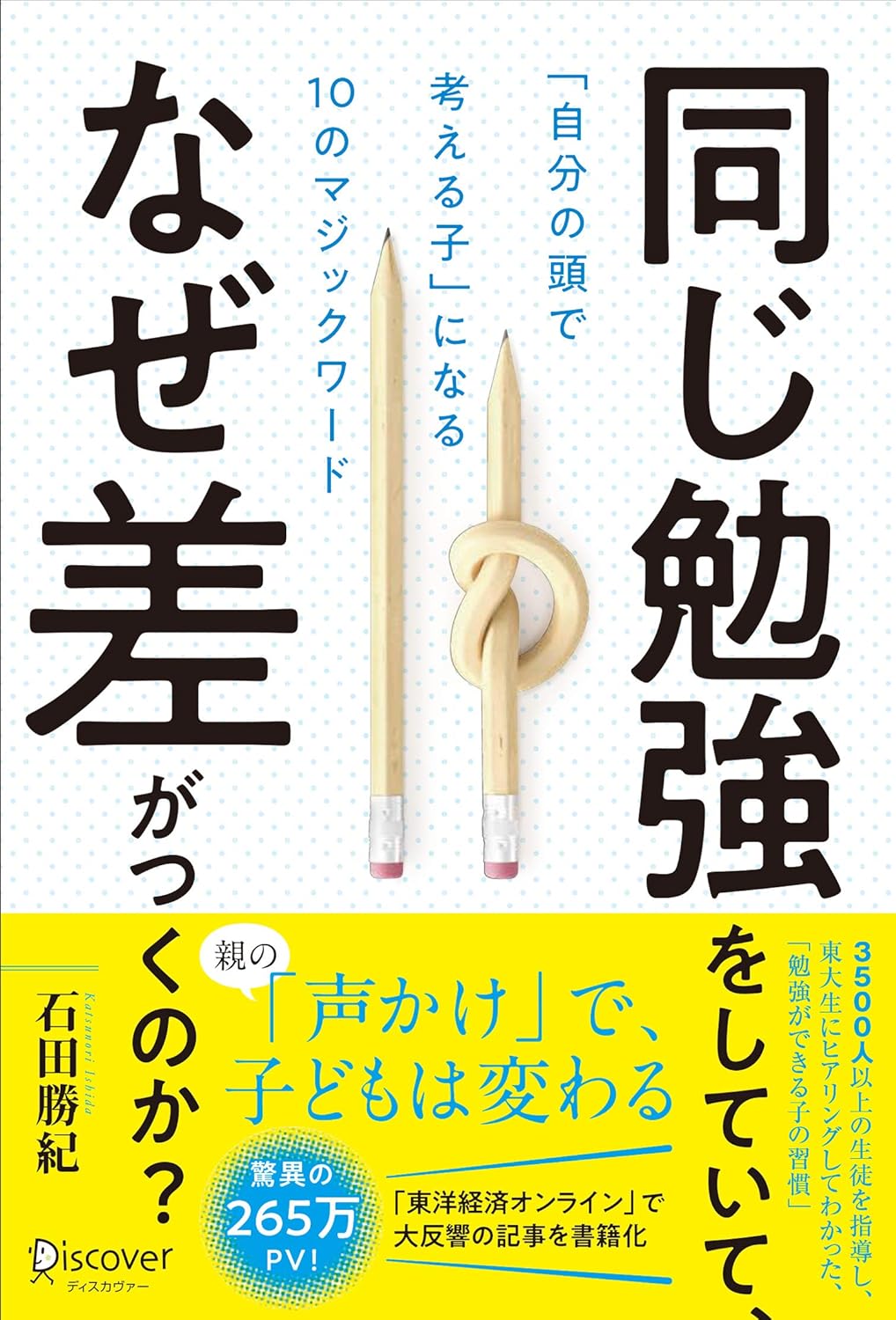
| 著者 | 石田 勝紀 |
| 出版社 | ディスカヴァー・トゥエンティワン |
| 出版日 | 2020年2月21日 |
| ジャンル | 勉強法・学習法 |
本書では、子どもを「論理型」「感覚型」「行動型」などのタイプに分け、それぞれに合った学び方を提案しています。すべての子どもに同じ教え方をしても、理解度や定着には大きな差が出ると著者は強調します。
たとえば論理型の子には、「なぜそうなるのか?」というプロセス重視の解説が効果的です。感覚型の子には、図や色、体験などを使って視覚・感覚に訴える教材が合います。行動型の子には、実際に手を動かす学習や、体験ベースの問題が向いています。このように学び方の“相性”を見極めることで、努力が結果につながるようになります。
逆に、合っていない方法で続けると、やる気や自信を失ってしまう恐れもあります。タイプを知ることで、親も「なんで覚えられないの?」というモヤモヤが軽くなります。子どもの理解スタイルを尊重する姿勢が、学びを支える一番の基盤になります。
学力がなかなか伸びない理由は、知識の量ではなく「考える力の土台」にあると著者は述べています。これは、パソコンの処理能力のようなもので、“OS”が整っていないと、どんなアプリ(勉強内容)も正しく動きません。
たとえば、文章題が苦手な子は、読解力や論理的な思考が十分に育っていない可能性があります。これは単なる「勉強不足」ではなく、「思考回路の準備」が整っていない状態なのです。この“OS”を整えるには、日常的な対話や思考トレーニングが効果的です。「なぜ?」「どう思う?」といった問いかけが、考える力を伸ばします。
また、ミスを責めるのではなく「どこで間違えたか?」を一緒に考える姿勢もOSの成長を促します。勉強の成果が出ないとき、つい“内容の難易度”ばかりを見がちですが、実は“土台”を整える方が早道かもしれません。思考のOSに目を向けることが、学力アップの抜け道になります。
勉強において、内容そのものよりも“親の関わり方”が子どもの伸び方を左右するケースは少なくありません。本書では、子どもに自信をつけさせる“マジックワード”として、「なんでそう思ったの?」という問いかけを紹介しています。
この言葉には、「あなたの考えを聞きたい」というメッセージが込められており、子どもの自己肯定感を高める効果があります。「ちゃんと見てもらえている」「考えることを評価されている」と感じることで、子どもは意欲的に取り組むようになります。逆に、「まだ覚えてないの?」「何回言ったらわかるの?」といった否定的な声かけは、やる気を失わせる原因になります。小さな言葉の積み重ねが、子どもの“学びの土壌”をつくっているのです。
また、問いかけによって子ども自身が自分の考えを整理する力もつきます。親の言葉は、教材以上に子どもの思考を育てるツールです。何を伝えるかではなく、どう問いかけるかが、子どもの未来を変える鍵になるのです。
普段の遊びや会話の中から、子どもが「どう理解しているか」「どんな説明に反応しているか」を意識して見てみましょう。視覚型か、論理型か、感覚型かの傾向が見えるようになれば、勉強のアプローチも自然と変わります。合わない方法を繰り返さないことが、最も効果的な学習支援になります。
「どう思う?」「なぜそう思ったの?」といった問いかけを意識的に使い、子どもに思考のプロセスを話してもらう機会をつくりましょう。これは“正解”を求めるのではなく、“考えようとする力”を育てるための関わりです。毎日の中での小さな対話が、思考のOSをじわじわと育てていきます。
テストの点数や結果ばかりに注目するのではなく、「がんばったね」「自分でやろうとしたのがすごいね」といった過程への共感を意識して伝えてみましょう。結果が思わしくないときこそ、親の言葉が子どもにとって安心材料になります。「わかってくれている」という実感が、次の挑戦への原動力になります。
本書は子どもの学習能力や大人の思考力を高めるための具体的な方法を提示しており、現場で活用できるアイデアも豊富です。特に「マジックワード」による思考促進法は、すぐに実践に移せる点が魅力です。ただし、成果を出すには継続的な実践が求められるため、万人に即効性があるとは限りません。
著者自身の体験談や事例がふんだんに盛り込まれており、内容は親しみやすく構成されています。一方で、抽象的な概念(例:OSの比喩表現)や長い導入部が繰り返されるため、肝心の要点がやや散漫になりやすい印象です。
学習指導や教育現場だけでなく、企業研修や自己啓発など多方面に応用できる内容になっています。日常会話でも使えるフレーズが紹介されており、家庭や職場でのコミュニケーション改善にもつながる構成です。ただし、教育分野に強く寄っている点から、汎用性には若干の偏りも見られます。
語り口は親しみやすく、やさしい言葉で書かれていますが、同じ内容の繰り返しやエピソードの冗長さがやや目立ちます。また、章構成がやや散漫で、ポイントが絞りにくい部分もあるため、読者によっては集中力が途切れるかもしれません。
教育現場の実践に基づいたノウハウが中心であり、専門的な学術的裏付けはあまり強くありません。「頭脳のOS」などの比喩は分かりやすい反面、学問的な正確さに欠けるため、専門書としての信頼性はやや低くなっています。

いやー、読んでみて思ったけど、勉強ってただ“やらせればいい”もんじゃないんだな…。

ほんとそれ。タイプが違えば、合うやり方も全然違うっていうのが衝撃だったよね。

しかも、親の声かけ一つで子どものやる気や理解度まで変わるなんて…。

1歳の今だからこそ、考える力の“土台づくり”を意識しとくのって大事かもね。

うん、まだ早いとか思ってたけど、今の関わり方が将来の学びに繋がっていくってわかっただけでも読んでよかった。
子どもの学力を伸ばすには、努力量ではなく“方向性”が大切です。本書は、学びのタイプや親の関わり方を見直すことで、子ども本来の力を引き出すヒントをくれます。
「うちの子、頑張ってるのに伸びない…」と感じたときこそ、ぜひ一度読んでみてください。
