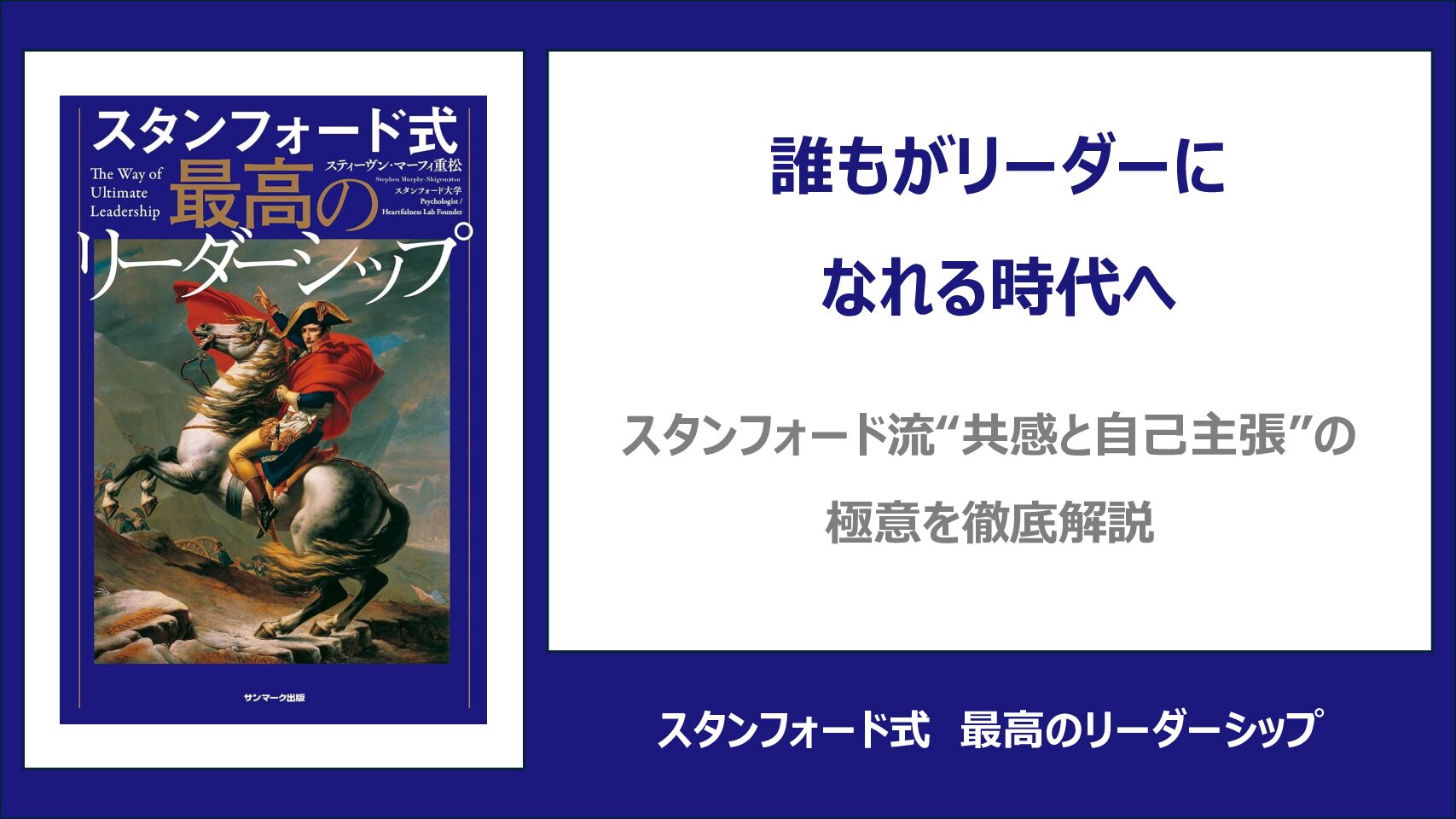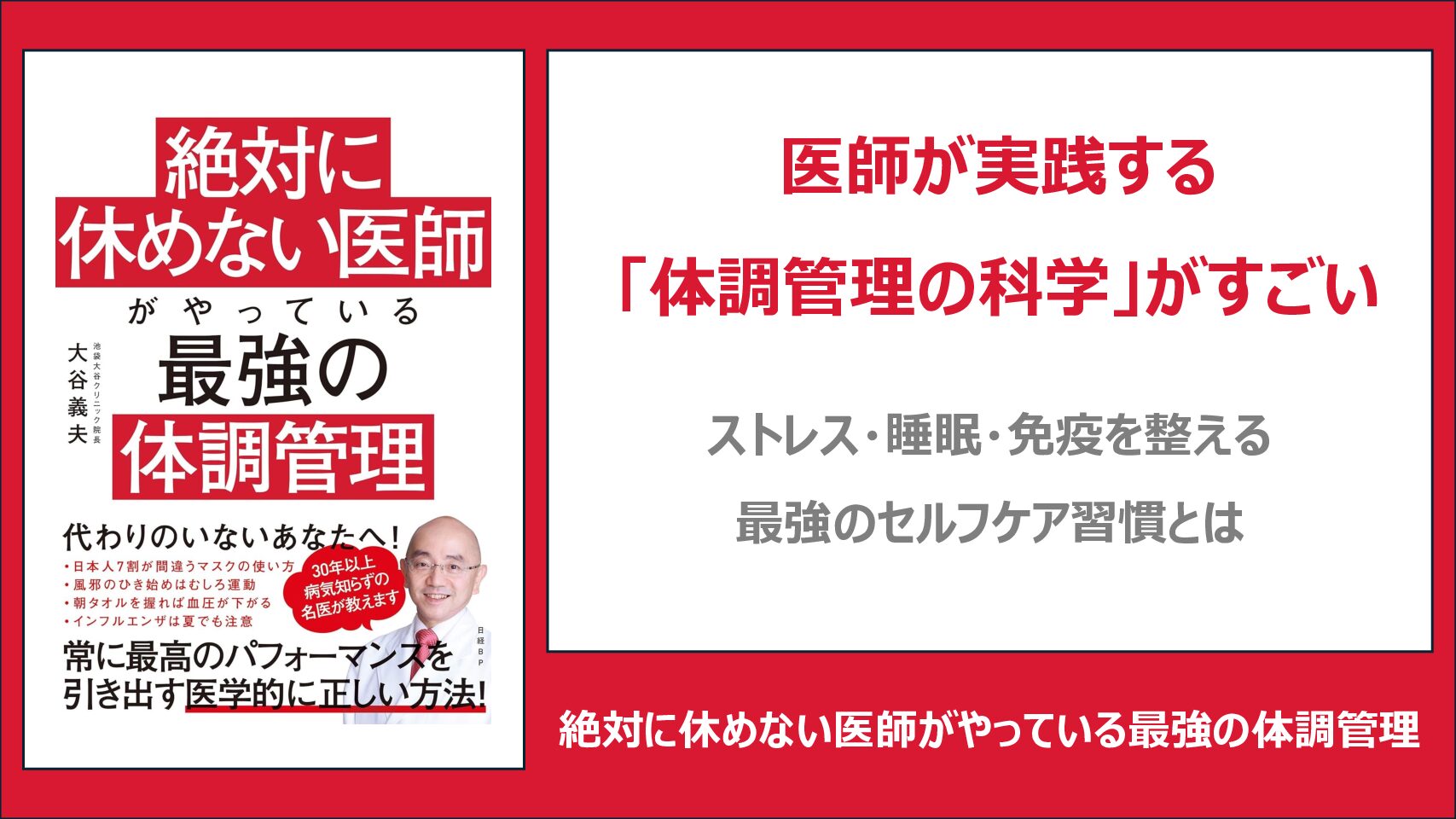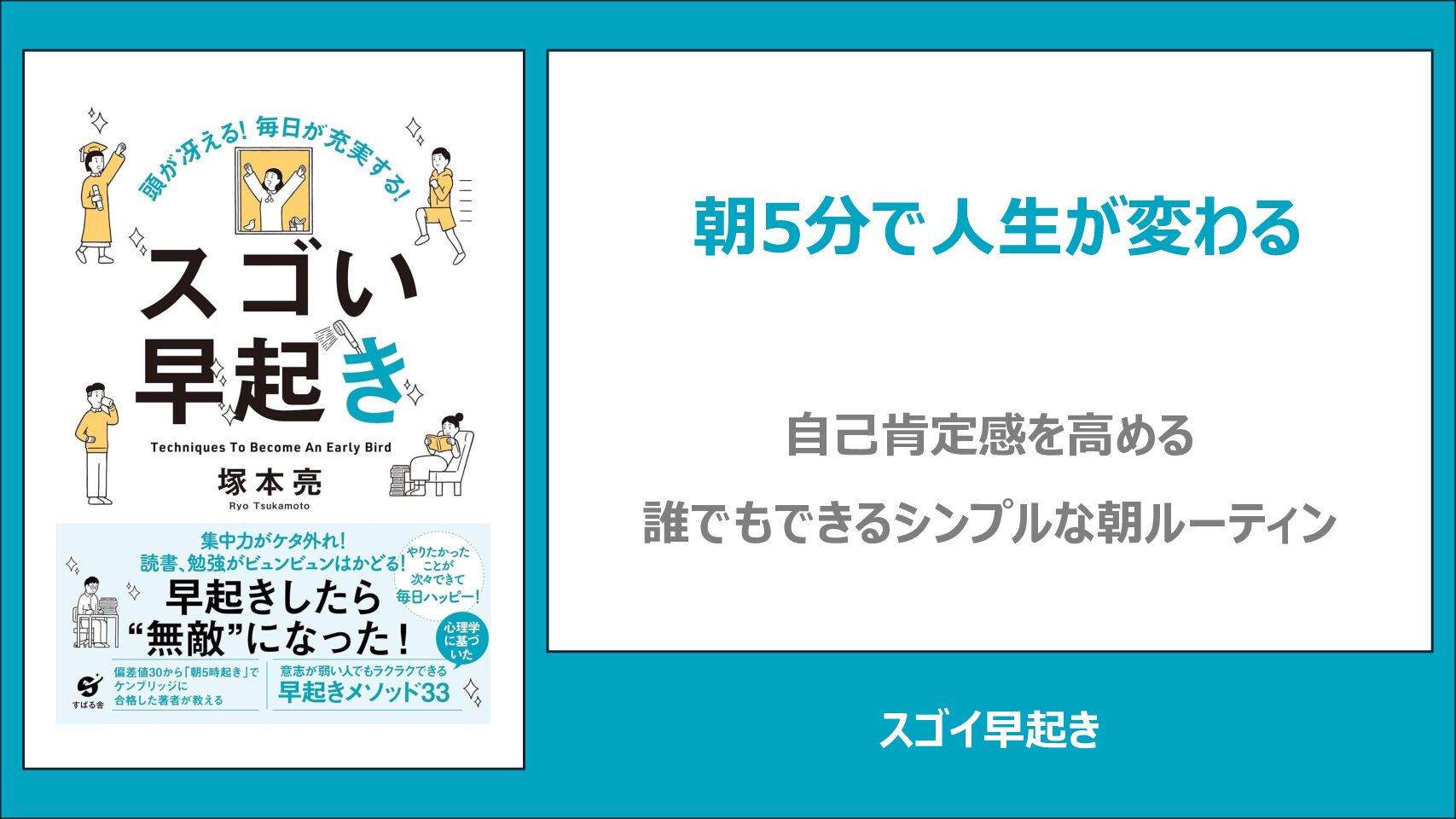この記事はで読むことができます。

ねぇTom、「リーダー」ってさ、なんか自分には縁がない存在って思ってたんだけど、ある本を読んで考え方が変わったんだよね。

へぇ、また面白い本見つけたの?っていうかMam、リーダーって会社の上司とか政治家の話でしょ?

それがさ、『私たちは皆リーダーである』って、スタンフォードの先生が言ってて、めちゃくちゃ衝撃だったの。

え、自分がリーダー?いやいや、俺ただのサラリーマンだし…。何をどうすればいいっていうのさ?
「リーダーって上に立つ人だけの話でしょ?」
そんな固定観念を覆すのが、本書『スタンフォード式 最高のリーダーシップ』です。誰もが自分の人生の“リーダー”であるという視点から、心理学や脳科学に基づいたリーダーシップの本質を、スタンフォード大学の実践とともに紹介しています。
リーダーシップは役職や権限とは無関係に、すべての人が発揮できるスキルです。自分の意思で動き、周囲に良い影響を与えることが、真のリーダー像です。
完璧であろうとするよりも、自分の弱さを受け入れたときにこそ、本当の信頼と共感が生まれます。チームを動かす力は、強さではなく“人間らしさ”に宿ります。
指示命令型ではなく、信頼・共感・対話が組織のパフォーマンスを高めます。心理学的に裏づけされた“アサーティブ・リーダーシップ”が鍵となります。
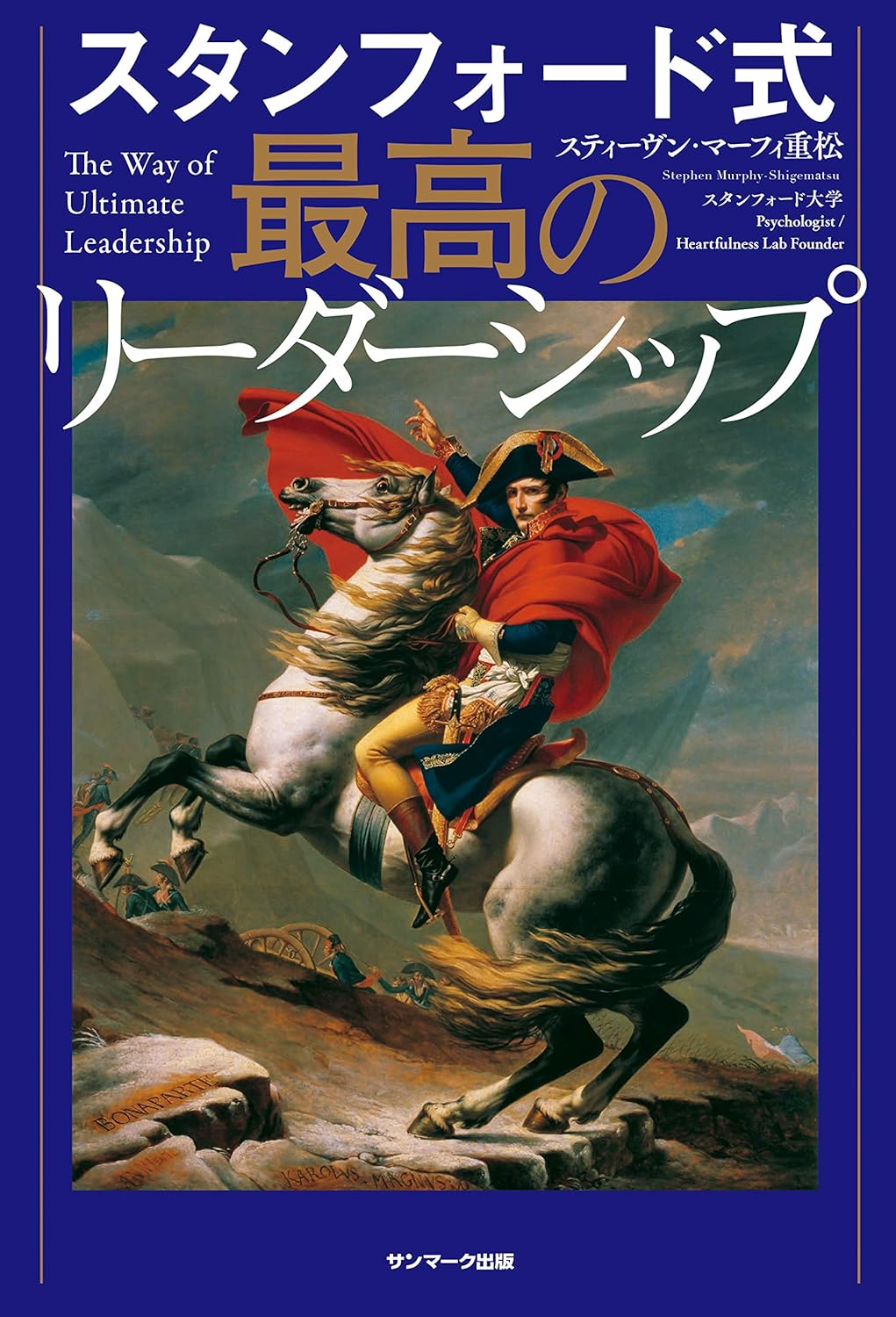
| 著者 | スティーヴン・マーフィ重松 |
| 出版社 | サンマーク出版 |
| 出版日 | 2019年4月24日 |
| ジャンル | リーダーシップ・マネジメント |
「リーダーとは肩書きのある人」という常識は、スタンフォードの最新心理学では完全に否定されています。本書の主張は、リーダーシップとは“行動の質”であり、誰もが発揮できる能力だということです。
実際、スタンフォード大学の授業では「あなたはリーダーである」と学生たちに伝え、その結果、多くの人が主体的に行動を変えています。これは単なる精神論ではなく、脳の可塑性や動機付け理論といった科学的裏付けを持った概念です。特に印象的だったのは、家庭や地域社会でも、立場に関係なくリーダーシップを発揮できるという視点でした。
「自分には影響力なんてない」と思っている人こそ、実は日々のふるまいで周囲に大きな影響を与えているのです。自分の子ども、同僚、友人、誰もが私たちの言動から刺激を受けています。著者は「リーダーとは、自分の人生を自分の意志で引っ張る人のこと」と言い切ります。この言葉には、他人に指示する前に、自分の価値観で動けるかどうかが問われているというメッセージがあります。
また、現代は予測不能なVUCA時代(変動・不確実・複雑・曖昧)とも言われ、マニュアル通りに動くフォロワーより、自ら判断できるリーダーシップが求められています。会社や組織も、トップダウン型では限界があり、現場の一人ひとりの判断力と行動力が鍵を握ります。
誰もが「小さなリーダー」としての役割を持つべき時代なのです。この新しい価値観を受け入れることこそが、自分の可能性を広げる第一歩になります。つまり、「リーダーになる」は一部の人の夢ではなく、全員が持つべき“生き方”の選択肢なのです。
従来、リーダーといえば「完璧で強い人」が理想とされてきました。しかし本書では、「弱さを認められること」こそが、最強のリーダー資質だと断言しています。その背景には心理学の概念「ヴァルナビリティ(脆さ)」があります。これは、自分の欠点や失敗、知らないことを隠さず開示することで、人間関係に安心と信頼をもたらすという理論です。
例えば、医療現場で起こったミスの多くは、上下関係の壁が強く「言えなかった」ことが原因だといわれています。強い医師が上にいると、看護師や技術者が意見を言いにくくなり、結果として事故が起きる。つまり、「強すぎるリーダー」は周囲を沈黙させ、組織を弱体化させてしまうのです。
一方、自分の失敗を隠さず、時には「わからない」と口にできるリーダーは、チーム内に率直さを育てます。そうした心理的安全性が、結果として組織のパフォーマンスを押し上げるのです。
また、“失敗を経験したリーダー”の話には人を動かす力があります。著者が紹介するエピソードでは、スポーツで致命的な失敗を経験した学生が、自分の脆さと向き合い、心理学の力で再生し、最終的にビジネスリーダーとして成長していく過程が描かれていました。この実話が示すのは、「傷があるからこそ人は強くなれる」ということです。
弱さを見せることは、信頼されないリスクではなく、むしろ“人間らしさ”を通じて共感を得る最短ルートです。そして共感こそが、リーダーが人を動かすために欠かせない感情の土台となります。つまり、リーダーにとっての強さとは「何も失敗しない」ことではなく、「失敗を共有できる」力なのです。
リーダーは生まれつきのカリスマがなるもの——そうしたイメージを覆すのが、本書の最大の魅力です。リーダーシップは訓練と知識によって後天的に身につけられるスキルであり、それは心理学と脳科学によって証明されています。特に本書で印象的なのは、EQ(心の知能指数)やマインドフルネス、ナラティブ心理学といった学問分野の知見をふんだんに取り入れている点です。
EQは、自分の感情を理解し、相手の感情にも配慮する能力です。リーダーとして部下に寄り添いながら、冷静な判断ができるようになるためには、このEQが必須です。加えて、サーブアンドリターン(相互的なやりとり)という概念も紹介されており、これは一方通行の指示よりも“やりとり”によって信頼関係が育まれることを意味しています。
また、著者は「アサーティブ・リーダー」という概念を提唱しています。これは“強すぎず、弱すぎず”、主張と共感のバランスを取る理想的なリーダー像です。アメリカ型の自己主張型リーダーとも、日本的な自己犠牲型リーダーとも違い、「自分と相手の両方を尊重する」ことを軸にしています。このアサーティブさは訓練で身につけられるとされ、本書ではその方法論も豊富に解説されています。
さらに、脳科学の知見によって、ポジティブな感情が脳の認知能力を高めることや、習慣によって集中力が養われることなども実証されています。つまり、リーダーシップとは精神論でも才能論でもなく、「実験と理論に基づいた科学的スキル」だということがよくわかります。この視点は、多くの人に希望を与えるものです。「自分には向いていない」と思っていた人こそ、学びと実践を重ねることで、立派なリーダーに変わることができるのです。
日々の中で「誰かの判断を待つ」のではなく、「自分ならどうするか?」を意識して行動しましょう。たとえば、会議で黙っているのではなく、自分の視点を一言でも加えるよう意識することが、リーダーシップの第一歩になります。
わからないことや苦手なことを隠すのではなく、素直に打ち明ける姿勢が信頼を築きます。「教えて」「助けて」と言えることは、チーム全体の健全さを保つ土台になります。まずは小さな場面から始めましょう。
リーダーとしての自分を育てるために、自分が得意なこと・不得意なことをリストアップしてみましょう。そのうえで、「どう活かすか」「どう補うか」を考えることが、科学的な自己成長につながります。
本書では、スタンフォード大学での教育・研究実践に基づいたリーダーシップ理論を、心理学や脳科学と融合させて紹介しており、職場やチームで即応用可能な内容が多いです。ただし、抽象的な理念や自己啓発的な話に傾く箇所もあり、すべての読者にとってすぐに使えるとは限りません。具体例は豊富ですが、読者の状況に応じた「カスタマイズ」の余地が残されています。特に組織上層部以外の人には距離を感じる場面もあります。
筆者の語り口は丁寧で、心理学的知見の紹介も意欲的ですが、表現が抽象的になりがちな部分や、専門用語や概念の重複が多く、読み手に負担がかかるところがあります。また、一部では冗長に感じる構成がテンポを削いでおり、全体の論点がぼやけることもあります。たとえば「弱さの共有」や「アサーティブ」という概念が繰り返されますが、場面によって使われ方に微妙なブレがあります。
リーダーシップを役職や地位に限定せず、「誰もがリーダーである」とする点は、多くの立場の人にとって学びがある内容です。ビジネス、医療、教育など多様な現場を想定しており、多職種での応用可能性があります。一方で、アメリカと日本の文化的背景が前提になっている部分があるため、他国や業種では当てはまりにくいケースも考えられます。
構成自体は章立てが明確で、リーダーシップの要素を段階的に紹介しているものの、ページによって情報量や論点が詰め込まれており、読む側に一定の集中力が求められます。プロローグから用語が多く出てくるため、一般の読者には少々とっつきにくい印象もあります。また、文体が説明的で抑揚に欠ける部分もあり、読了感にばらつきがあります。
心理学や脳科学、人間性理論など、筆者の専門性が随所に活かされており、学術的な裏付けが強く感じられます。ハーバードやスタンフォードでの経験に裏打ちされたエピソードも信頼性があります。ただし、科学的知見が時に著者の思想的主張に結びつけられすぎることがあり、エビデンスとの距離感がやや曖昧になる場面も見受けられます。

いや〜、「強いリーダー」が正解じゃないって、ちょっとホッとしたわ。

わかる。むしろ“弱さ”をさらけ出せるほうが信頼されるなんて、目からウロコだったな。

「私たちは皆リーダー」って言葉、前よりちょっと実感湧いてきたかも。

俺も。とりあえず、職場で黙ってないで意見言ってみようかな(笑)
「リーダーとは、特別な誰かのことではない」
自分の行動に責任を持ち、まわりと誠実に関わろうとする人こそ、現代に必要なリーダーです。この本が教えてくれるのは、“変えられるのは自分”という、力強くて優しい真実でした。