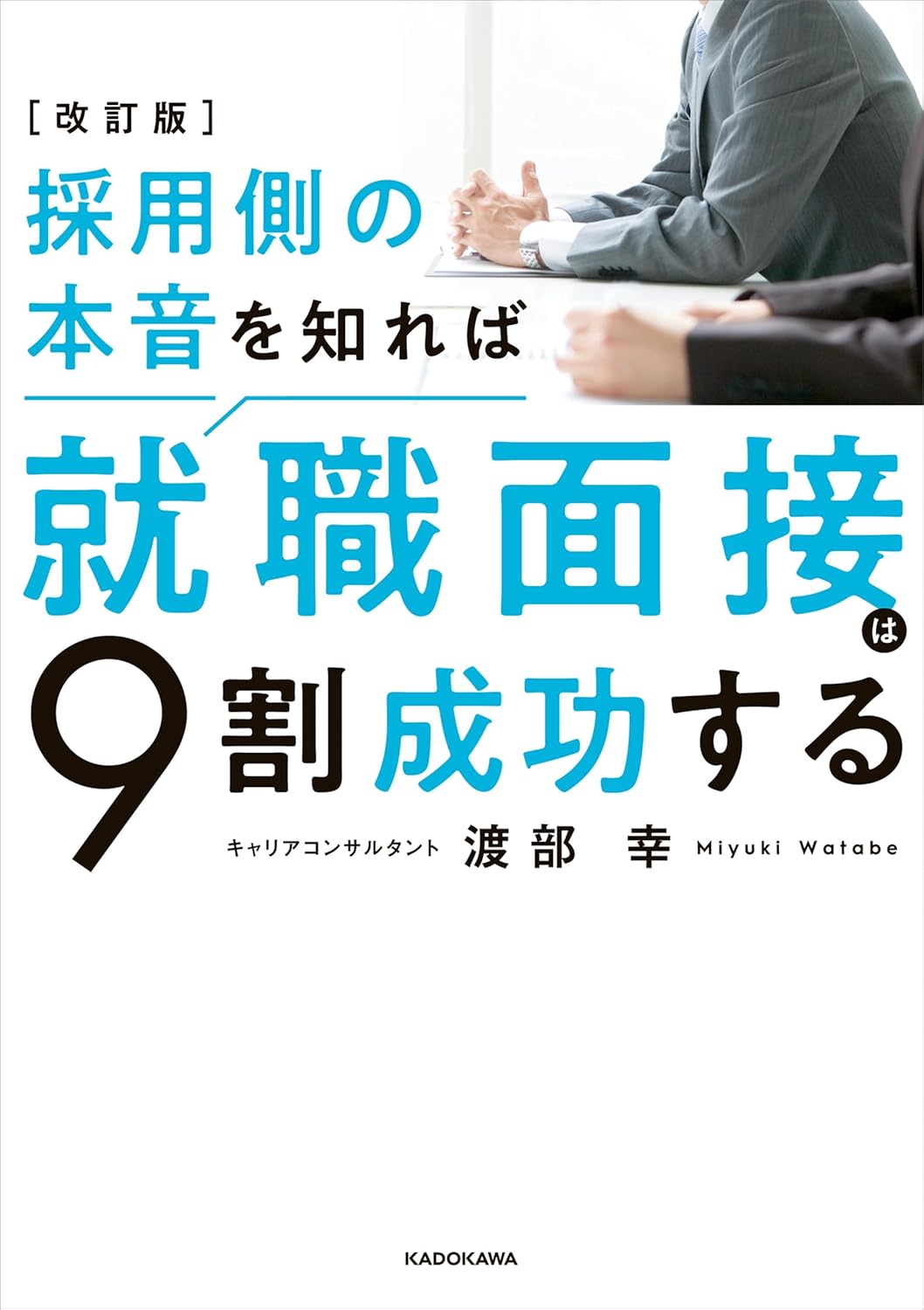この記事はで読むことができます。

ねえTom、私さ、就活の面接ってほんとに怖かったんだよね…。

ああ〜、あの“圧迫感”みたいなのわかる。変なこと言っちゃったらどうしようってドキドキしたもん。

しかも「志望動機は?」とか「自己PRしてください」とか、当たり前すぎて逆に何言えばいいかわかんなくてさ。

そうそう!頑張って準備したのに「なんか薄いね」とか言われると、心がぽきっと折れるよね…。

今思えば、あのとき“面接官が本当に見てるポイント”を知らなかったのが敗因だった気がする。

うん。NG回答とOK回答の差って、実はちょっとした意識の違いだったのかも。

じゃあ今の学生さんには、そのコツを伝えてあげたいよね。笑って面接出られるように。
就活の面接が怖いと感じるのは、あなただけではありません。本記事では「なぜその回答では通らないのか?」「どんな回答が面接官に刺さるのか?」を丁寧に解説していきます。
なぜ同じ質問に対して、通る人と落ちる人がいるのか?面接官の視点から見た“伝わる回答”のコツが理解できます。
タテマエではなく、あなた自身の考え方や価値観を見抜くのが面接の目的です。質問の裏にある“意図”を知ることで、ズレのない受け答えができるようになります。
話がまとまらない、緊張して言葉が出てこない…そんな悩みも“構造的な話し方”を身につければ克服できます。誰でも実践できる3ステップのフレームワークをご紹介します。
どんなに目立つ経験がなくても、通過する学生には“答え方の型”があります。特別な経歴や成績よりも、自分の考えを整理して言語化する力が大切です。本書では、自己PRや志望動機において「内容」よりも「伝え方」が重要であることが繰り返し語られています。
たとえば、同じアルバイト経験でも「なぜそれを選び、何を学んだか」を語れるかどうかで評価が変わります。面接官は、“この学生は一緒に働けるか?”を見ているため、人柄や考え方の一貫性に注目しています。だからこそ、「結論→理由→エピソード→再結論」の流れで話すことが効果的なのです。
自分がどう考えて行動したかを冷静に分析できる学生は、それだけで一歩リードできます。経験の大小にとらわれず、“意味づけ”の力を鍛えることが面接突破の鍵になります。「普通」こそ武器になる――それがこの本の大きなメッセージです。
面接官は、学生の回答そのものよりも「この人はどう考える人なのか?」を見ています。たとえば、「将来どんな仕事がしたいですか?」という質問の裏には、「この人は自分で目標を設定し、行動できるか?」という意図があります。つまり、正解を答える必要はなく、自分の価値観や判断軸を言葉にできればいいのです。
本書では、こうした“質問の裏にある意図”を解説しながら、どのように自分の軸を表現すればよいかを丁寧に示しています。また、面接官の立場になって質問を考えることで、「なぜこの質問がくるのか?」という視点が身につきます。これにより、場当たり的な回答ではなく、論理と感情が通った受け答えが可能になります。
就活生の多くが、答えることに必死で“意図”を見失いがちですが、ここを意識するだけで印象が大きく変わります。見せるべきは正しさではなく、“自分という人間の軸”。それを支える考え方がこの本では学べます。
本書では、「話を盛る必要はない。シンプルに、整っていればそれでいい」と何度も強調されています。これは、面接という短時間で印象を残すには、情報の多さよりも“筋の通った話”が重要ということです。
たとえば、自己PRでは1つのエピソードに絞り、その中で課題→工夫→結果→学びという流れを明確にします。エピソードが複数にまたがると、聞き手に伝わらず“なんとなく印象が薄い”結果になります。また、一貫性のある話は信頼感につながり、面接官が安心して話を聞けるようになります。
本書では、話が散らかりやすい学生に向けて、構成を整えるテンプレートやチェックポイントも豊富に紹介されています。“うまく話す”ことよりも、“わかりやすく伝える”ことが最優先であるという考え方が非常に実践的です。
面接官の立場から見ても、シンプルで論理的な話は採点しやすく、評価が上がりやすくなります。結局のところ、準備すべきは“派手な話”ではなく、“筋の通った自分の物語”なのです。
「結論→理由→具体例→結論」という構成で、自分の経験を整理してみましょう。内容よりも伝え方に意識を置くことで、面接官に伝わる“筋の通った話”になります。
「なぜこの質問をされたのか?」と自分に問いかけてから答えるだけで、的外れな返答を防げます。練習段階から“質問の裏”にある目的を意識してみましょう。
無理にたくさんのネタを用意するのではなく、1つの経験を深く掘り下げて話せるようにしておくことが大切です。何度も練習して言語化することで、自然な一貫性と自信が生まれます。
実際の面接に即した内容で構成されており、形式別(集団、GD、Web、動画など)のポイントや具体的な回答例が豊富に掲載されています。面接官の「本音」を明かしながら解説しているため、実践的かつ今すぐ役立てられる構成です。細部にわたって面接対策をカバーしており、面接未経験者にも有益です。
図解やチェックリスト、具体例が随所にあり、内容は非常に親しみやすく、平易な言葉で書かれています。ただし、情報量が非常に多く、時に冗長に感じられる部分もあります。情報の密度が高い分、読み進めるのにやや根気が要るかもしれません。
業界別の特徴や面接対策が詳しく解説されており、幅広い志望業界の学生に対応できます。ただし、基本的に新卒学生を対象としているため、転職者や中途採用向けには少し応用が必要です。OB訪問やリクルーター面談にも触れている点は、就活全体に広く役立つ内容です。
全体的に語り口は優しく、励ましの言葉も多いので心理的ハードルは低いです。ただし、テンポが一定で、視覚的なメリハリや章立ての工夫が乏しく感じられる部分もあります。もう少し要点の整理やビジュアル的要素が加わるとさらに読みやすくなります。
キャリアコンサルタントとして6万人以上を支援してきた著者の知見が反映されており、面接対策の専門性は高いです。業界研究の方法や面接形式ごとの対応まで網羅的に扱っており、経験に裏打ちされた実践的なノウハウが豊富です。ただし、心理学的視点や人事評価制度の深掘りなどはやや浅めです。

こうして見てみると、面接って“話し方”より“考え方”が大事なんだね〜。

うんうん。エピソードを盛るんじゃなくて、自分の中にある軸を見せるのが本質って感じ。

昔の私にこの本読ませたかったよ…「バイト頑張りました!」しか言ってなかったもん(笑)

それ、まさに“浅い回答”の代表やん。でも、逆に言えば型を知れば誰でも深くなるってことだね。

面接が怖くても、「何を聞かれそうか」と「どう答えるか」が見えてれば安心だしね。

就活って、自分のことをちゃんと見つめ直す機会でもあるし。この本、学生みんなに配ってほしいくらい。
就活の面接で悩んでいるなら、この1冊は必ず役に立ちます。面接官の視点を知り、自分の言葉で自信を持って語れるようになるために、まずは本書の型を身につけてみてください。
“特別な何か”がなくても大丈夫――大切なのは、あなた自身の考えを伝える力です。