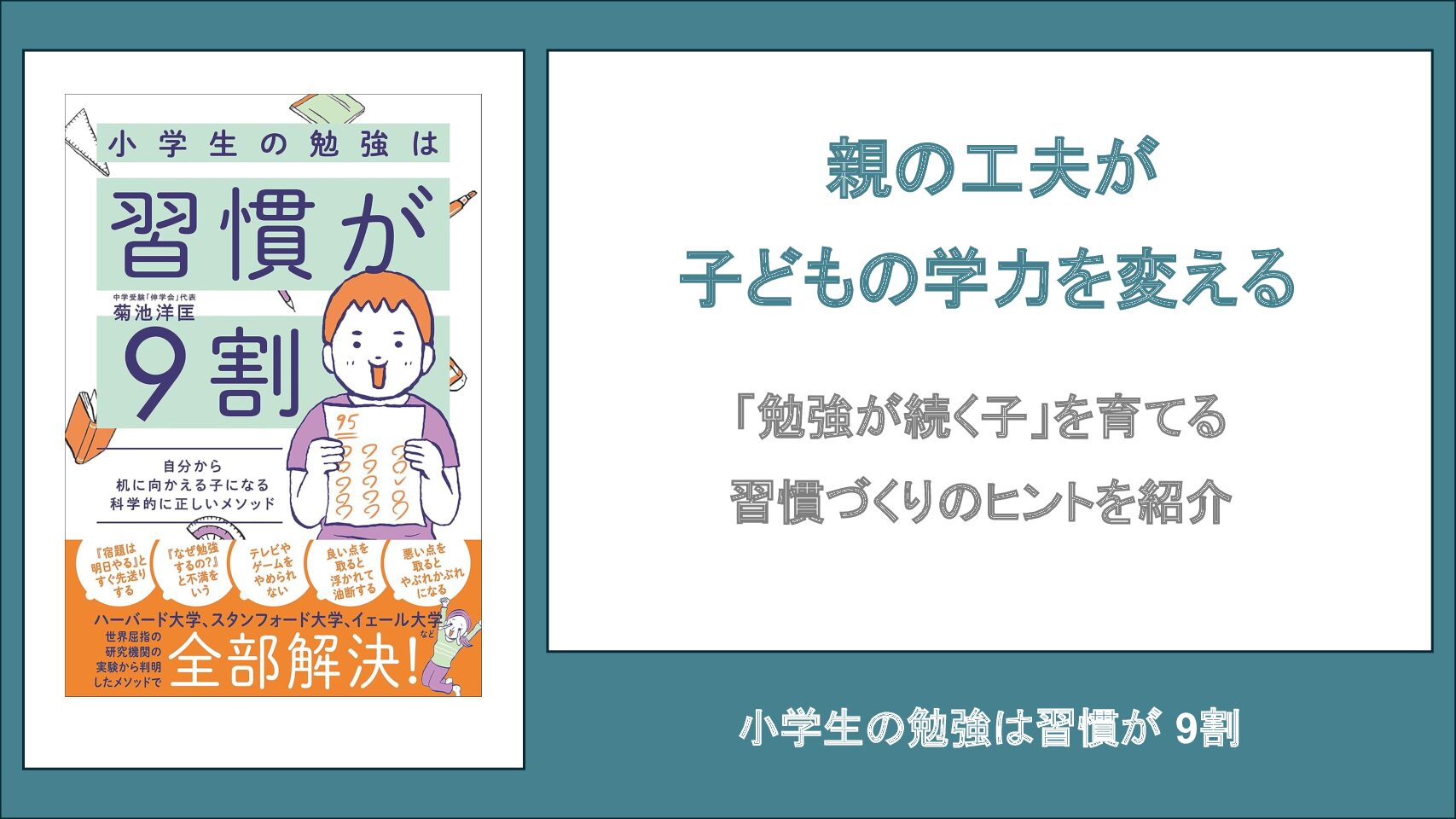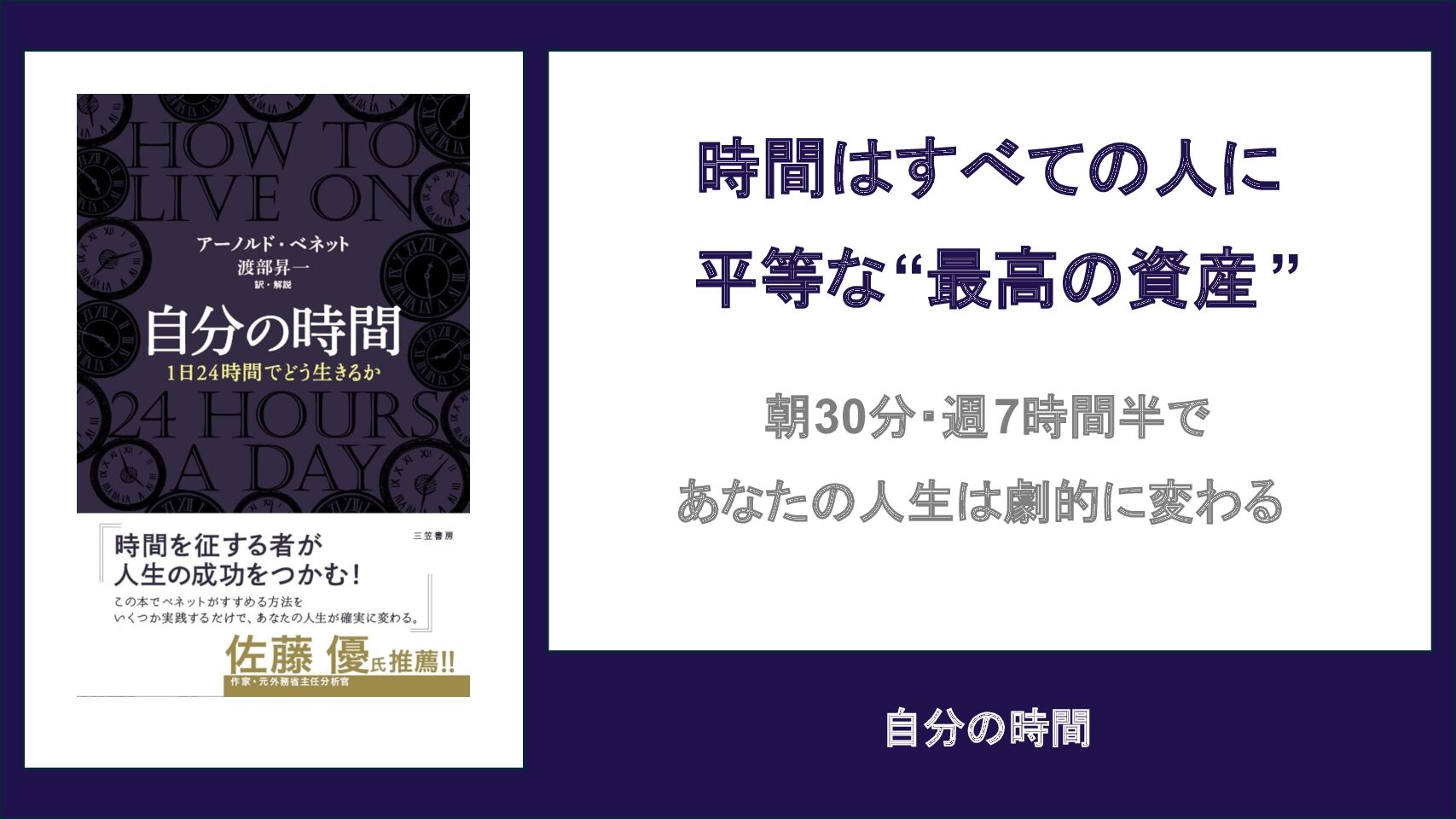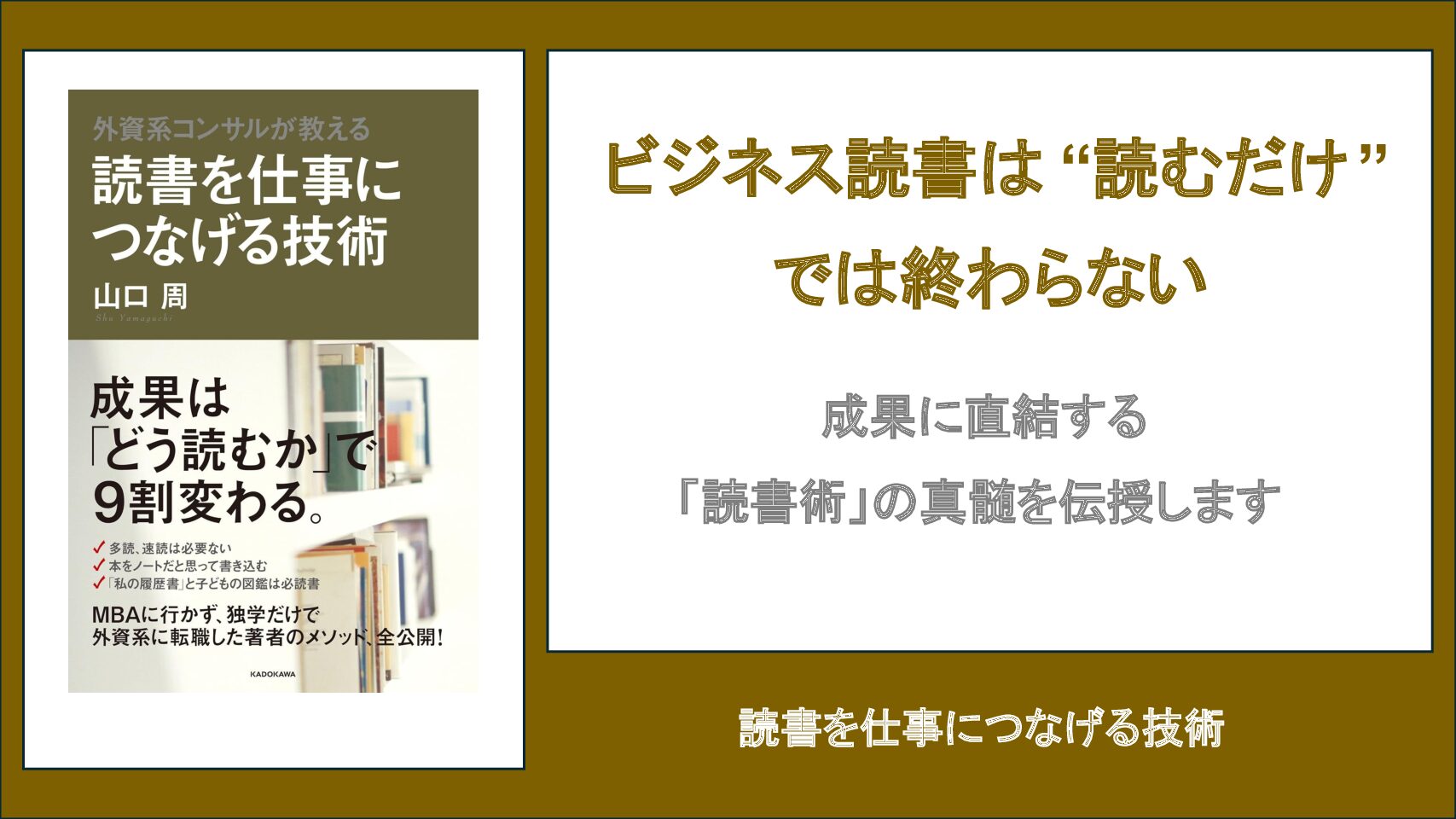この記事はで読むことができます。

Tom、最近息子に絵本読んであげてると、ちょっとずつ反応が変わってきた気がするの。嬉しいけど、これって将来の勉強にもつながるのかな?

うーん、どうなんだろうね。まだ1歳だし、正直そこまで意識してなかったけど…でもママが毎日続けてるのはすごいよ。

ありがとう。でもね、この前読んだ本に「小学生の成績は習慣で決まる」って書いてあって、なんかハッとしたのよ。今の積み重ねが将来を作るんだって。

習慣か…たしかに、いきなり小学校に上がって“さあ勉強しよう”って言っても難しいもんね。小さいうちから自然に身につけておくのがいいのかも。
子どもの学力や成績は、生まれつきの才能ではなく、日々の小さな習慣の積み重ねによって大きく変わります。今回ご紹介する書籍『小学生の勉強は習慣が9割』では、勉強が自然と続く子どもを育てるために、親が日常の中でできる具体的な関わり方や声かけのコツが紹介されています。
「うちの子、勉強が苦手で…」と悩む前に、親としてできることは何か? 本書を読むことで、毎日の生活リズムや家庭環境が、子どもの学ぶ姿勢や意欲をどう育てていくのかがわかります。習慣が未来を変える、その第一歩を一緒に踏み出してみませんか?
子どもの成績は、遺伝的な知能や一時的なやる気よりも、日々の勉強を続ける力に大きく影響されます。親の働きかけによって、自然と学ぶことが当たり前になる環境を整えることが大切です。
親が子どもの気持ちに寄り添いながら、無理なく取り組める学習の仕組みをつくることがカギです。例えば声かけの仕方や、時間の使い方を工夫することで、子どもが自ら学ぶ姿勢が身につきます。
「勉強しなさい」と指示するよりも、親自身が学ぶ姿勢を見せたり、日常会話に学びの要素を取り入れたりすることが効果的です。強制せずとも、子どもが自分から取り組みたくなる雰囲気づくりが成績アップの秘訣です。
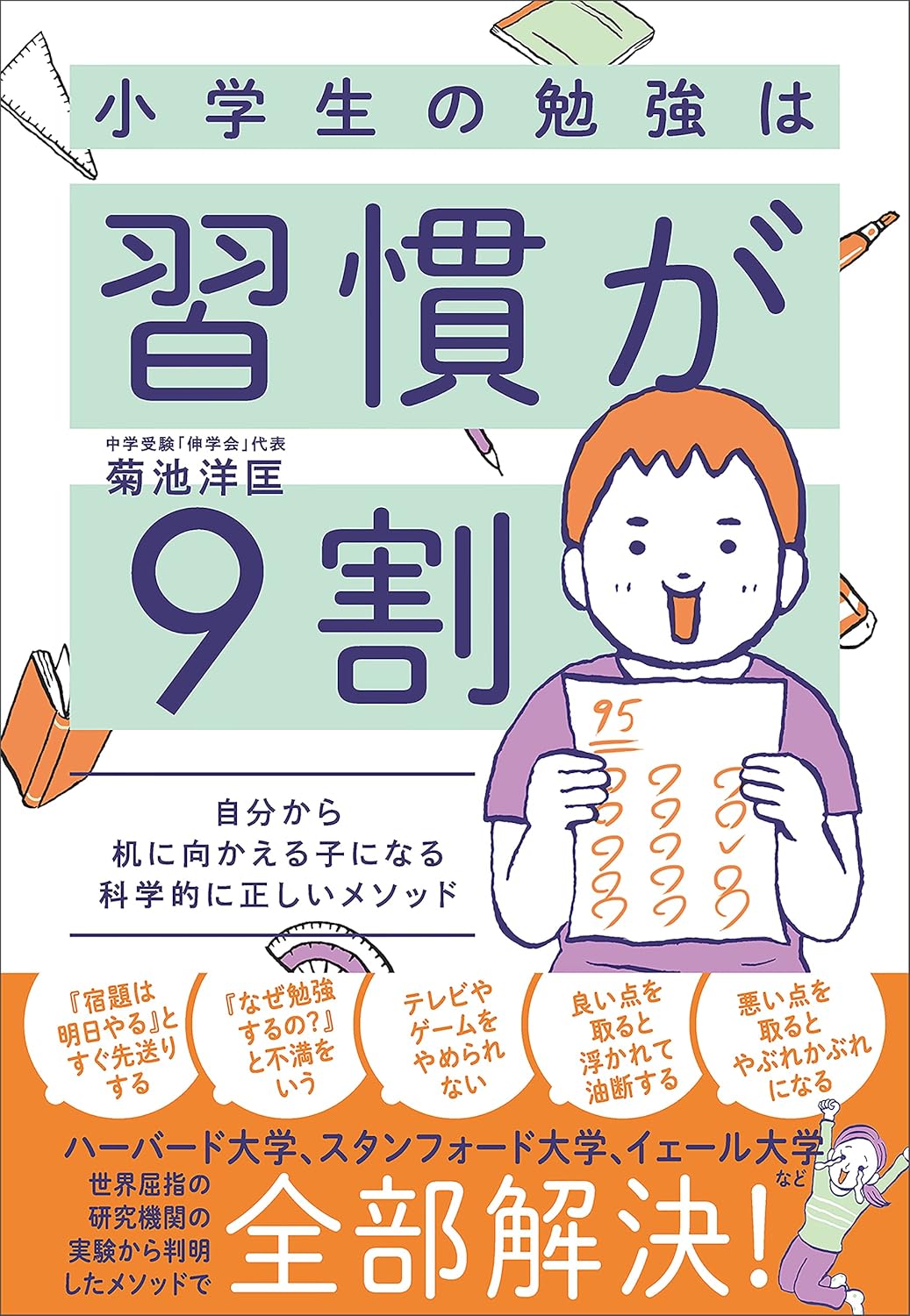
| 著者 | 菊池 洋匡 |
| 出版社 | SBクリエイティブ |
| 出版日 | 2021年12月1日 |
| ジャンル | 子育て・教育法 |
子どもが自然と勉強をしたくなるような環境を整えることは、成績を上げるための第一歩です。リビングの一角に学習コーナーを設けたり、机の上に必要な文具だけを並べたりするだけでも、集中力は大きく変わります。勉強しやすい空間は、子どもにとって「ここでは勉強するのが当たり前」という意識を育てます。
さらに、静かな環境だけでなく、照明や温度なども意外と大切です。集中できる明るさや、快適な室温を保つことで、子どもの「やる気スイッチ」を自然と入れられます。また、子どもがすぐに手に取れるように本棚に興味を引く本を並べたり、カレンダーに学習スケジュールを一緒に書き込んだりするのも効果的です。そうすることで、子どもは自分で学習を管理しているという自覚が芽生えます。
親が「今日はどこまで進んだの?」と関心を持って声をかけることも、子どものモチベーションを高めます。決して強制するのではなく、「応援してるよ」という姿勢が子どもには伝わります。失敗や忘れ物があっても、責めるのではなく一緒に振り返る姿勢が、子どもの「やってみよう」を支えます。
習慣は一朝一夕には身につきませんが、環境を整えることで自然と身につけられます。そして最も重要なのは、子どもの努力をしっかり見て、毎日小さな成功を喜ぶことです。「できたね!」「よく頑張ったね」といった言葉が、勉強に対するポジティブな印象を与えてくれます。子どもが「勉強って楽しいかも」と感じることができれば、それは何よりの学力の土台となります。だからこそ、家の中での「学びの場づくり」は、何よりも大切なのです。
子どもがコツコツ勉強を続けられるかどうかは、親の関わり方に大きく左右されます。まず大切なのは、「命令」ではなく「共感」をベースにしたコミュニケーションです。
たとえば、「宿題やったの?」ではなく、「今日はどんな宿題があるの?」という聞き方をすることで、子どもは安心して話しやすくなります。子どもがやる気をなくしている時こそ、感情に寄り添う姿勢が必要です。「疲れたよね」「今日は学校どうだった?」といった声かけが、子どもにとっての安心材料になります。
そして、子どもが頑張っている姿を見逃さずに、適切に褒めることがモチベーションを高めます。「漢字を最後まで書けたね」「今日は集中してたね」など、行動を具体的に評価することが効果的です。また、目に見える形で努力を記録しておくと、子ども自身も達成感を味わえます。カレンダーにシールを貼ったり、進捗表を一緒に書いたりするだけでも大きな励みになります。
親も一緒に何かに取り組む姿を見せるのも、子どもにとっては良い影響を与えます。たとえば、読書や資格勉強などを一緒の時間にする「親子学習タイム」は、共通の習慣を育てる機会です。子どもは親の真剣な姿を見て、自分もやってみようと思えるのです。
逆に、親がスマホばかり見ていたり、「また勉強してないの?」と否定的な言葉を繰り返すと、子どもは心を閉ざしてしまいます。だからこそ、親は「見守る」「寄り添う」「励ます」ことを心がけるべきです。毎日の小さな声かけの積み重ねが、子どもの「続ける力」を育てていきます。
勉強を毎日の当たり前にするためには、「学習の型」をつくることが大切です。決まった時間に同じ流れで勉強することで、子どもの脳はそのパターンに慣れていきます。
たとえば、「学校から帰ったらまずおやつ」「その後に15分間の復習」「終わったら自由時間」というような流れを決めておくと、迷わず行動に移しやすくなります。このように、一連のルーチンを作ることで、習慣化のハードルはぐっと下がります。
ポイントは、はじめから完璧を目指さないことです。最初は5分の音読でもOK。「毎日続ける」ことを最優先にしましょう。小さな目標を設定して、それを達成したら少しずつレベルを上げていくのがコツです。また、習慣が定着するには時間がかかるものです。3日坊主になっても責めず、リセットするタイミングを親が一緒に決めてあげることが大切です。「明日からまた始めようね」と前向きに促す姿勢が、子どものやる気を維持します。
さらに、子どもが自分でスケジュールを管理する力も育てたいところです。ホワイトボードに「やることリスト」を書いて、一つずつ消していくなどの方法も効果的です。視覚的に「できた」を感じることで、自己肯定感も高まります。最後に、習慣の型には「楽しさ」も組み込むとより続きやすくなります。たとえば、勉強の後に親子でミニゲームをする、好きなシールを貼るなど、ワクワクを取り入れる工夫がポイントです。
このように、「いつ」「どこで」「何を」「どんな順で」勉強するかを決めておくことで、子どもは自然と学習を日常に取り入れられるようになります。
子どもの学習机の周りを整理整頓し、不要なものを取り除いて集中できるスペースを作りましょう。照明や室温も意識して、子どもが快適に過ごせる環境を整えることが大切です。
文房具や本は子どもの手の届きやすい場所に配置し、学習に必要なものをすぐ取り出せるようにすると、勉強へのハードルが下がります。さらに、子どもの好きなキャラクターのカレンダーや表を活用して、学習記録を可視化し、達成感を感じられる仕掛けを加えると継続意欲が高まります。
子どもが「やりたくない」と言ったときは、「そうだよね、疲れる日もあるよね」と共感から始めましょう。勉強に取り組んだ際は、内容ではなく「頑張った行動」に注目して褒めることを意識してください。
日々の学習で達成したことを親子で振り返る時間を持つことで、自信と継続力が養われます。また、親自身も読書や資格勉強に取り組む姿を見せることで、子どもにとって「学ぶことは大人もやること」という認識が生まれ、学習が身近なものになります。
毎日同じ時間に勉強をするルールを決めて、まずは1週間だけでも親子で実践してみましょう。ルーティンの例としては、「夕食後に10分の音読」「お風呂の前に宿題」など、生活リズムに合わせて無理のない範囲で設定すると続けやすくなります。
子どもと一緒に「やることリスト」を作り、達成した項目にシールを貼るなどの視覚的なごほうびを取り入れると、やる気もアップします。予定が崩れたときには「今日はイレギュラーだったからOK。明日からまた頑張ろう」と前向きな声かけでモチベーションを保ちましょう。
子どもの学習習慣を改善するための具体的な方法や心理的背景、親の関わり方まで幅広く取り上げており、家庭での実践に役立ちます。特に「コーピングプランニング」や「スモールステップ」など、実行可能なテクニックが多く紹介されています。ただし、やや理論の紹介に比重がかかり、家庭によっては「合わない」「ハードルが高い」と感じる場合もあるかもしれません。
例え話や図表の活用、親しみやすい語り口など、読者を引き込む工夫が随所に見られます。「マシュマロ・テスト」や「性格は変えられる」といった要素を噛み砕いて説明しており、知識のない親でも理解しやすいです。ただ、心理学的背景の説明が一部やや専門的で、読む人によってはやや難解に感じるかもしれません。
中学受験を目指す家庭向けに書かれているため、対象が限定的です。習慣形成のノウハウは大人にも応用可能ですが、文中の多くが小学生や受験生にフォーカスしており、一般的な学習者や社会人には少しフィットしにくい面もあります。
ストーリー形式や会話パートも含まれており、テンポよく読み進められます。筆者の個人的な経験談が親しみやすさを高めていますが、ややページ数が多く、重複表現も散見されるため、途中で集中力が切れやすい読者もいるかもしれません。
行動科学や心理学の研究をベースにしており、一定の信頼性と根拠があります。ただし、学術的な深掘りは少なく、あくまで実用書レベルでの解釈に留まっています。専門書を期待する読者には物足りなく感じられる可能性があります。

今日読んだ本、すごく参考になったね。やっぱり習慣の力って大きいんだなって実感したよ

うん、特に『環境を整える』って話は目からウロコだったな。勉強机の周り、ちょっとごちゃごちゃしてたし。

私も思った。あと、子どもに共感して励ますことって、簡単そうで意外とできてなかったかも。

たしかに。『頑張ったこと』を認めてあげるっていう視点は、これから意識したいね。
本書『小学生の勉強は習慣が9割』を通じて、学力の差は才能や遺伝ではなく、日々の小さな積み重ねであることが明らかになりました。特別な能力がなくても、家庭の関わり方次第で「勉強が続く子」へと成長する道は誰にでも開かれています。
親子で一緒に学ぶ姿勢をつくり、子どもが前向きに取り組める環境を整えることこそが、未来への最高の投資です。今日から始められる小さな習慣を、ぜひあなたの家庭でも取り入れてみてください。