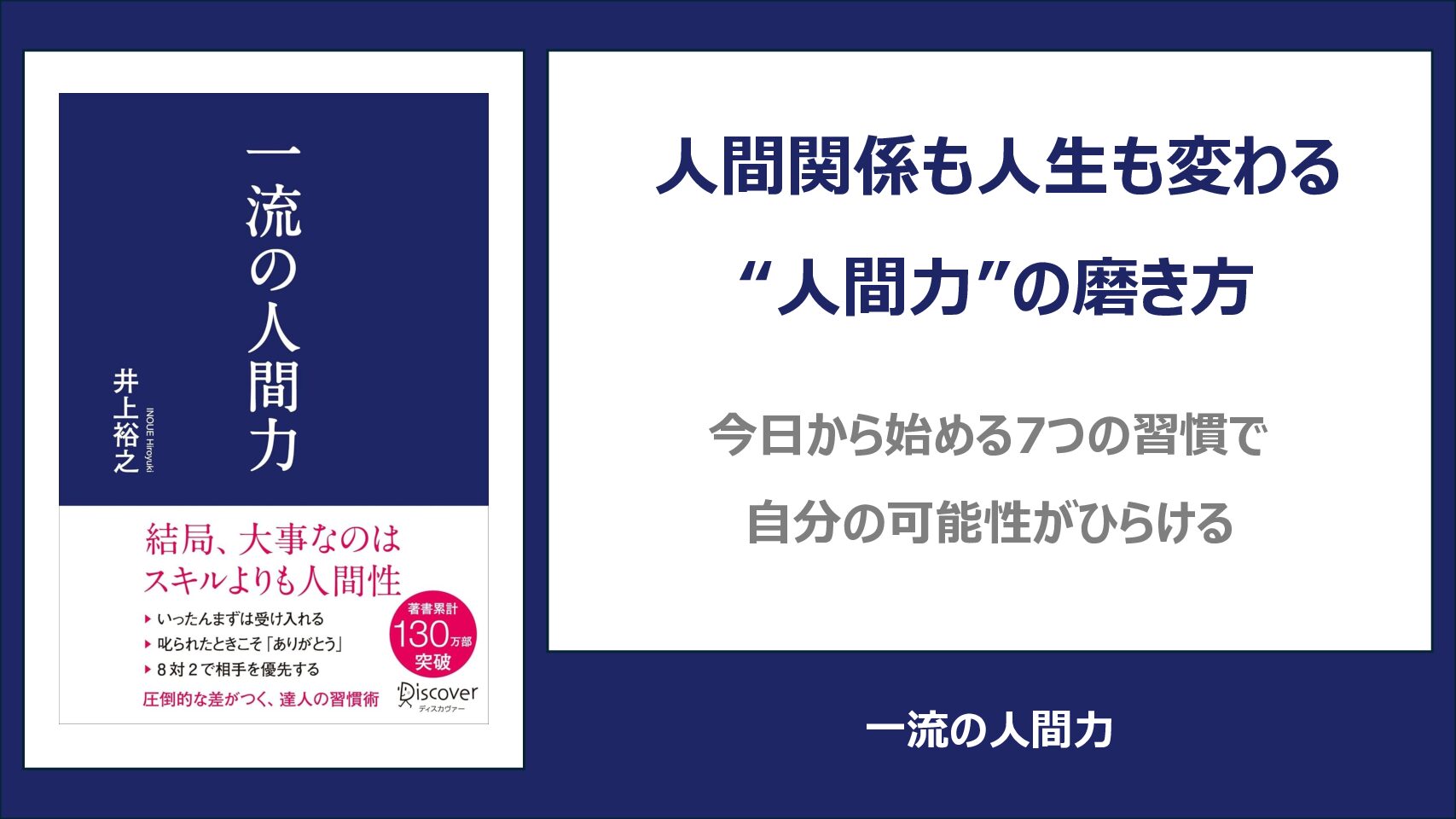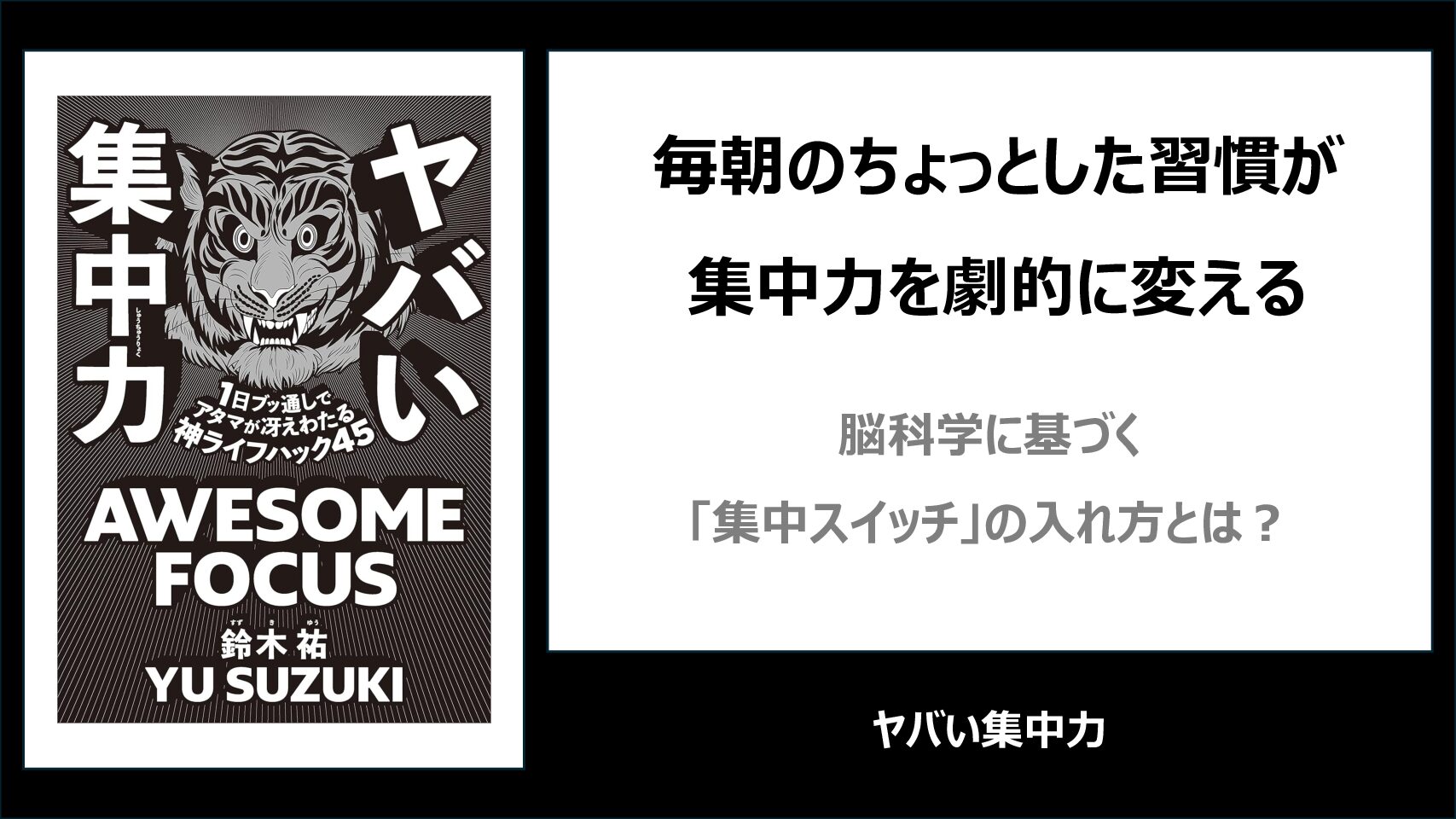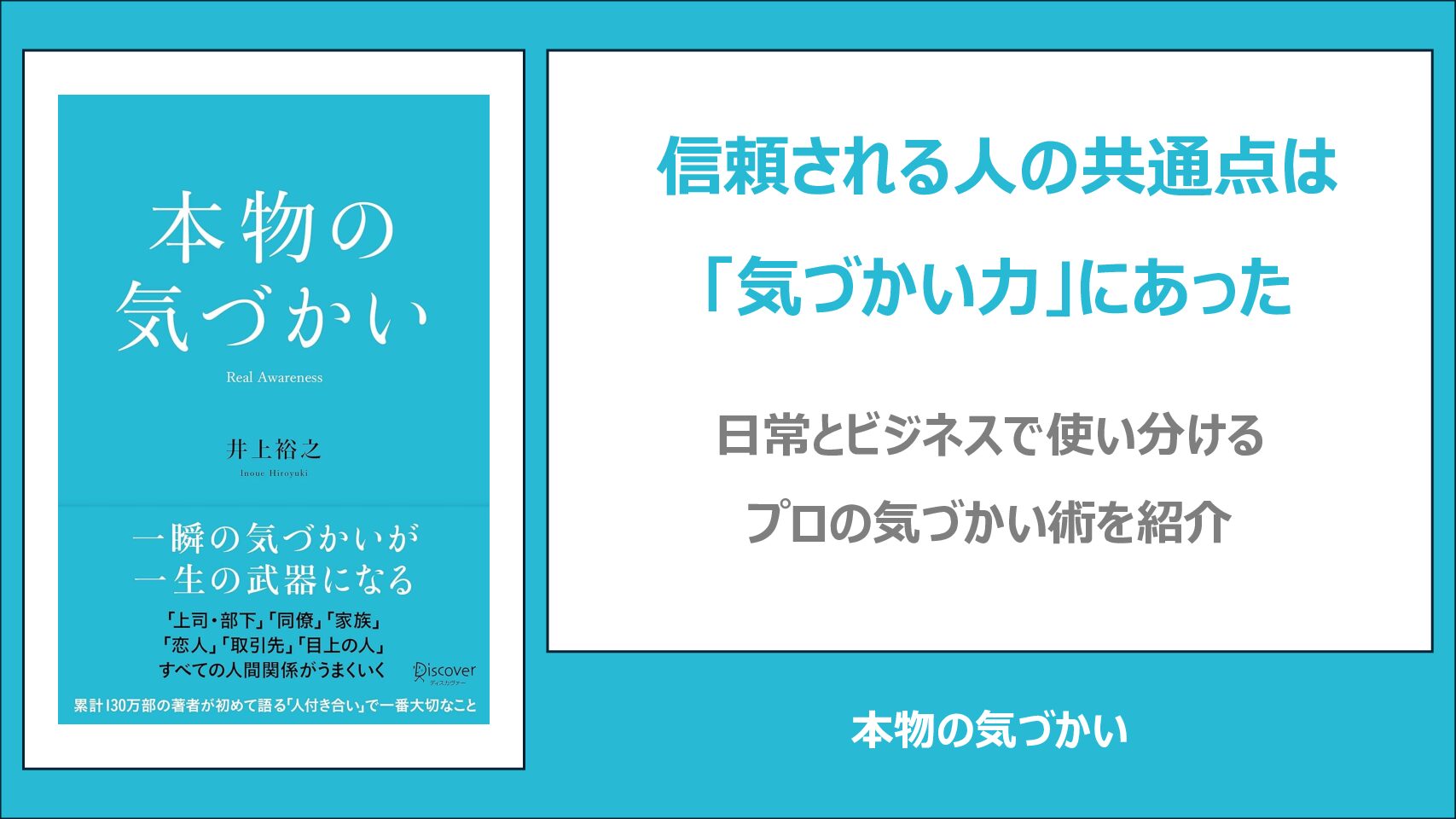この記事はで読むことができます。

ねぇTom、最近ちょっと思うことがあるの。頑張ってるのに人間関係もうまくいかないし、仕事でも空回りしてる気がして…

あ、それ、俺も感じてた。努力してるのに評価されなかったり、話がうまく通じなかったり、なんだろうねこの「噛み合ってない」感。

それって、もしかしてスキルや知識じゃなくて、「人間力」ってやつの問題なのかなって最近気づいたんだ。

「人間力」って言われてもピンとこないけど、たしかに人間関係がうまくいってる人って、なんか根本的に“感じがいい”よね。空気を読むとか、信頼されるとか、そういうの。

そうそう!でね、この前読んだ本に、「人間力を高める7つの習慣」が紹介されてて、これがまたすごく納得感あったの。

へぇ、7つもあるの? なんか自己啓発っぽいけど、ちゃんと実践できそう?
人間関係がうまくいかない。努力しているのに評価されない。そんな悩みを抱えているあなたにこそ、読んでほしいのが本書『一流の人間力』です。
著者が提唱する「人間力」とは、ビジネススキルや知識ではカバーしきれない、人としての総合的な魅力や信頼、そして行動力を指します。スキルがあっても信頼されなければ評価はされない。逆に、特別な才能がなくても人間力を高めれば、周囲に好かれ、仕事も人生もうまく回り始める——本書ではその道筋を7つの習慣という形で明確に示しています。
しかも、その習慣はどれも難しいものではありません。「素直さ」「感謝」「学び」「自責」「礼儀」「自愛」「成長」といった、日々の暮らしの中で誰もが少し意識すれば実践できる内容ばかり。人間関係のトラブルから、自分自身の成長まで、幅広いテーマを網羅しています。
この本を読めば、今までうまくいかなかった原因が明らかになり、人生を根本から変える第一歩を踏み出せるはずです。それでは次に、「この書籍でわかること」を3つの観点から紹介します。
「人間力」とは、単なる性格の良さではなく、他者との信頼関係を築くための“総合的な魅力”を指します。素直さ・責任感・感謝・礼儀といった複数の要素が重なり合って形成される力です。
いくらスキルがあっても、傲慢だったり不誠実な人は周囲に信頼されず、長期的に見るとチャンスを逃します。逆に、人間力のある人は自然と応援され、結果的に多くのチャンスを手に入れやすくなるのです。
特別な才能や環境は必要ありません。7つの習慣(素直さ、学び、自責、礼儀、立ち直り、自愛、成長)を日常生活に取り入れることで、誰でも人間力を高めていくことができます。
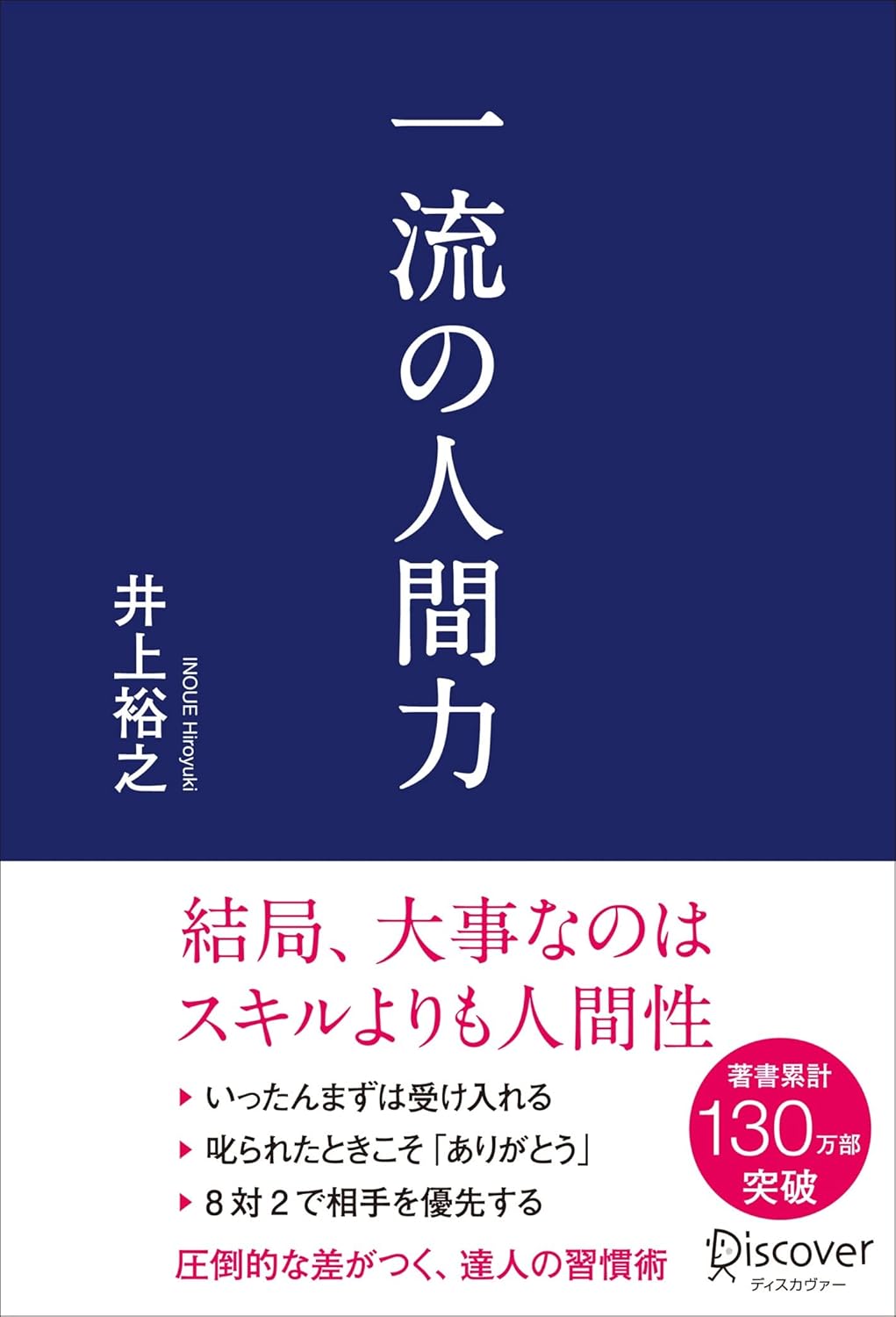
| 著者 | 井上 裕之 |
| 出版社 | ディスカヴァー・トゥエンティワン |
| 出版日 | 2023年5月26日 |
| ジャンル | マインド・心構え |
「素直さ」は人間力の中でも最も重要な要素として、著者が繰り返し強調しているポイントです。実際、仕事でもプライベートでも、人に好かれやすく信頼されやすい人の多くは「素直」であることが共通しています。人の意見を聞き入れ、柔軟に行動に移せる人は、周囲からの応援を得やすくなります。
たとえば、上司や先輩にアドバイスを受けたとき、「でもそれは…」「前にこう言われたので…」とすぐに否定から入ってしまう人は、相手の熱意や信頼を失ってしまいがちです。反対に「わかりました、やってみます」と即答できる人は、アドバイスをくれた相手から「この人は伸びる」と思われ、次の機会も与えてもらえる可能性が高まります。
また、著者が提唱する「パーフェクトなありがとう」も素直さの延長線上にあります。ただ形式的に「ありがとうございます」と言うのではなく、心を込め、相手の目を見て、気持ちよく伝えること。この小さな行動が、大きな信頼と好感を生むのです。
素直であることは、自分の価値観を一度置いて相手の意見を受け入れること。これは決して自分を否定することではなく、柔軟性の証であり、成長の入口です。自分の考えに固執せず、多様な価値観に耳を傾ける姿勢があれば、視野は広がり、人生の選択肢も増えていきます。
さらに、著者が例に挙げるように、大谷翔平選手が高校生のときから「人間性」を意識していたことも印象的です。能力だけでなく人間力を磨いてきたからこそ、周囲に応援され続け、現在の成功を掴んでいるのです。
本書で紹介されている通り、「素直さ」は人間関係を改善するだけでなく、自分の内面の成長を促進する“起点”とも言えます。そして何より、「素直さ」は誰もが今日から実践できることでもあるのです。
多くの人が「成長したい」「もっと変わりたい」と願っているにも関わらず、なかなか結果が出ないと感じているのはなぜでしょうか?その原因の多くは、継続の力=「続ける力」の不足にあります。本書では「続ける力」こそが人間力の中核であり、あらゆる成長のベースであると力強く語られています。
「続ける力」は一見すると地味で派手さはありません。しかしこの力を持つ人は、間違いなく信頼され、成果を出し、人生のあらゆる局面で優位に立てるのです。たとえば、著者の歯科医院でのエピソードに登場するアシスタントのNさんは、最初は何もできなかったものの、「続ける」「学ぶ」「練習する」を習慣化した結果、今ではどこの医院に行っても通用する一流の人材に成長したと紹介されています。
この話から分かるのは、「才能」や「センス」よりも、「やめないこと」「継続すること」がいかに重要かということ。人は、ある程度までなら誰でも頑張れます。しかし、それを長期間維持することができる人はごくわずか。その“ごくわずか”な人が、いわゆる一流と呼ばれるのです。
では、どうすれば続ける力を手に入れられるのか?本書が提示する答えは「目的を明確にする」ことです。著者自身も「人前に立つときに理想の体型でありたい」という目的があるから、週3回のジム通いを何年も続けられると語っています。「続けるためには明確な目的が必要」——これは多くの人が見落としがちな視点です。
さらに、「続ける」ためには完璧を求めすぎないことも大切です。著者は「たった1ミリの成長でもいい」と言います。昨日の自分より、ほんの少しでも前に進んでいれば、それは確実な成長なのです。人と競わず、過去の自分と比べて微差を積み重ねる。それが“圧倒的な差”を生み出す原動力になります。
「続ける力」は、あなたの人生を静かに、でも確実に変えていきます。自己投資、習慣づくり、仕事、学び——すべての基盤にあるのは、地道な継続です。小さなことでもいい、今日も昨日と同じように“積み重ねる”。それだけで、確実に前へ進めるのです。
「なんであの人はわかってくれないんだろう」「どうしてこんなことになったのか、相手が悪い」――そんなふうに誰かを責めたくなること、ありますよね。でも、そこで視点を変え、「自分にも何か原因があったのでは?」と考えることができたとしたら、実はその瞬間から、人生は大きく好転し始めるのです。
本書で語られる「自責思考」は、すべての出来事を「自分の責任」として引き受ける考え方です。一見するとストイックに感じるかもしれませんが、実はこの思考こそが“自由”と“成長”への鍵だと著者は語ります。なぜなら、責任を自分に置いた瞬間、状況を変える力が「自分の中にある」と気づけるからです。
例えば、人間関係でトラブルが起きたとき。「あの人の態度が悪いから」と考えている間は、相手が変わらない限り状況は好転しません。でも、「もしかすると、自分の言い方やタイミングが良くなかったのかも」と思えたとき、自分の行動を変える余地が生まれます。そして、現実も変わっていきます。
印象的だったのは、著者が紹介していた「問題改善シート」の話です。問題が起きたときに「何が起きたか」「なぜ起きたか」「どんな影響が出たか」「どう改善するか」を紙に書き出すことで、問題を感情ではなく“事実”として捉え直す。この習慣があると、同じ失敗を繰り返さず、冷静に対処できるようになるのです。
もちろん、自責が“自分を責めること”になってはいけません。大切なのは「起きた出来事にベクトルを向けること」。つまり、「なぜこんなことが起きたのか?次に活かすにはどうすればいいのか?」という視点です。感情的になるのではなく、構造的に考える。これが本物の「責任を取る」姿勢であり、未来を変える力なのです。
さらに著者は、「自責思考を持つ人は、相手の感情にも敏感になれる」と言います。たとえば、パートナーが不機嫌なときに「何よ、その態度!」と責めるのではなく、「何かあったのかな」と一歩引いて想像し、寄り添う。これだけで、人間関係は大きく変わるのです。
自責は、決して自分を苦しめるための思考ではありません。むしろ、自由になるための考え方。自分の人生の舵を、自分で握ることができるようになる。それが「自責思考」の本質です。
素直な人の特徴は、反応が早く、行動が早く、そして感謝の表現が豊かです。この3つを意識するだけで、周囲からの信頼度が劇的に変わります。まずは「ありがとう」を毎日5回、意識して口にすることから始めましょう。特に注意したいのは、注意や指摘を受けたとき。「ありがとうございます。次からこうしてみます」と即座に受け止め、ポジティブな姿勢を示すことが“人間力の高さ”として伝わります。
また、身近な人(家族、同僚、友人)からのアドバイスや依頼に対して、「でも」「それはちょっと…」と言いがちな自分を客観視し、まずは一度やってみる姿勢を持ちましょう。素直な反応ができる人は、どんな環境でも引き上げてもらえる存在になります。「すぐにやってみる→感想を伝える→お礼を言う」という3ステップを、今日から一つのルールとして取り入れてください。これは、思考の柔軟性だけでなく、相手との関係性を深める最高のトレーニングになります。
続ける力を身につけるためには、「なぜやるのか?」を明確にすることが最初のステップです。たとえば、筋トレを週3日続けたいなら、「健康を維持して好きな服を着こなしたい」「年齢を重ねてもカッコいい大人でいたい」など、行動の裏にある目的を紙に書き出して可視化しましょう。人は“意味”があると感じられることしか継続できません。
次に、「毎日やること」をリストにして、記録することを習慣にします。日記1行、スクワット10回、英単語を5個覚えるなど、些細なことでも構いません。重要なのは“積み上げている”という実感です。たとえば、専用の手帳やアプリを使って「〇」や「チェック」を付けるだけでもモチベーションになります。もし3日坊主になりがちなら、2日に1回、週に3回など、ハードルを下げてOK。自分に合った頻度で“続けられる設計”を意識してください。
さらに、「誰かと一緒にやる」「SNSで進捗を報告する」といった“外の力”を借りることも有効です。続ける仕組みを整えておくことが、結果的に自信と成長につながります。
自責思考を育てる第一歩は、「うまくいかなかった出来事」を“他人のせいにしない”視点で見つめ直すことです。そのためにおすすめなのが、毎晩3〜5分で書ける「振り返りノート」です。以下の4つの質問を自分に問いかけて書いてみてください。
1. 今日、うまくいかなかったことは何か?
2. その原因に自分が関わっていた部分はどこか?
3. 相手ではなく“できごと”に目を向けると、どんな構造だったか?
4. 明日はどう行動を変えるか?
この習慣を1週間続けるだけでも、驚くほど冷静に自分と向き合えるようになります。大切なのは「自分が悪い」と責めるのではなく、「どうすれば改善できるか?」にフォーカスを移すことです。
さらに、感情的にモヤモヤしたときには、「深呼吸→一拍おいてから反応する」を意識しましょう。感情のままに言葉を発すると、後悔する確率が高まります。感情を外に出す前に、“原因は自分にあるとすれば?”という視点を持つだけで、対応の質が格段に変わります。
こうした“内省”と“改善”のサイクルを回すことが、結果的に周囲からの信頼も高まり、自由度の高い人生へとつながっていくのです。
本書で紹介される「人間力を高める7つの習慣」は、日常生活や仕事においてすぐに応用できる内容が多く、実践的です。ただし、やや抽象的で行動への具体的落とし込みが甘い部分も見受けられます。加えて、自己啓発の枠を出ていない内容も多く、読者によっては効果を実感しにくい可能性もあります。具体例をもう少し多様な業種や立場で展開すれば、さらに実用度が高まると感じました。
文章自体は平易な語り口で読みやすく書かれていますが、文法的に甘い部分や構成の乱れ、編集の粗さが目立ちます。特に「素直さ」や「ありがとう」に関する繰り返しが多く、くどさを感じる箇所があります。また、内容の重複が多く、読者の理解を助けるというよりは冗長さを生んでいます。説明の流れも若干散漫な印象を受けます。
「人間力」というテーマは広く応用できるものの、著者自身の職業(歯科医師)にやや寄りすぎたエピソードが多く、職種や年齢によって共感度に差が出る恐れがあります。特に若年層や非医療分野の読者にとっては、直接的な活用が難しい箇所もあります。また、価値観が固定的でアップデートされていない印象を受ける部分もありました。
繰り返しや冗長な表現が多く、また構成がやや整理されていない印象があるため、全体として読みにくさを感じました。文体も口語調が混ざり過ぎていて、文章としての品位が若干落ちています。段落の分け方や強調の仕方にも改善の余地があり、読者の集中力を保つ工夫に欠けています。
「人間力」という抽象的なテーマに対し、心理学的、社会学的な裏付けが乏しく、著者の経験談と持論が中心になっています。読者が納得できるようなデータや研究の引用が少なく、説得力に欠ける面がありました。専門書としてではなく、あくまで自己啓発書として位置づけられるべき内容です。

Tom、どうだった?この本読んでみて。

いやぁ、正直びっくりしたよ。すごくシンプルなことしか書いてないのに、「あ、これができてなかったな」ってめちゃくちゃ気づかされた。

わかるー!特に「素直さ」とか、当たり前すぎて意識してなかったけど、確かに人間関係にすごく影響してるよね。

そうそう。俺、すぐ言い訳しがちだったなぁって反省した(笑)。あと、「続ける力」のところは本当に胸に刺さった。俺、すぐに結果出ないとやめちゃうタイプだったし。

でもこの本読むと、「ちょっとずつでいいんだ」って思えるよね。1ミリの成長でも続ければ大きな差になるって言葉、すごく励みになる。
本書は、誰でも今すぐ始められる小さな行動を通して、自分自身と周囲の関係を豊かにするヒントを与えてくれます。スキルや肩書きではなく、人としての「あり方」が問われる今の時代において、本書は確かな指針となる一冊です。
人間関係で悩んでいる方、自分を変えたいと思っている方、そしてもっと信頼される人間になりたいすべての人におすすめします。まずは今日から、あなた自身の“人間力”を育てる一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。