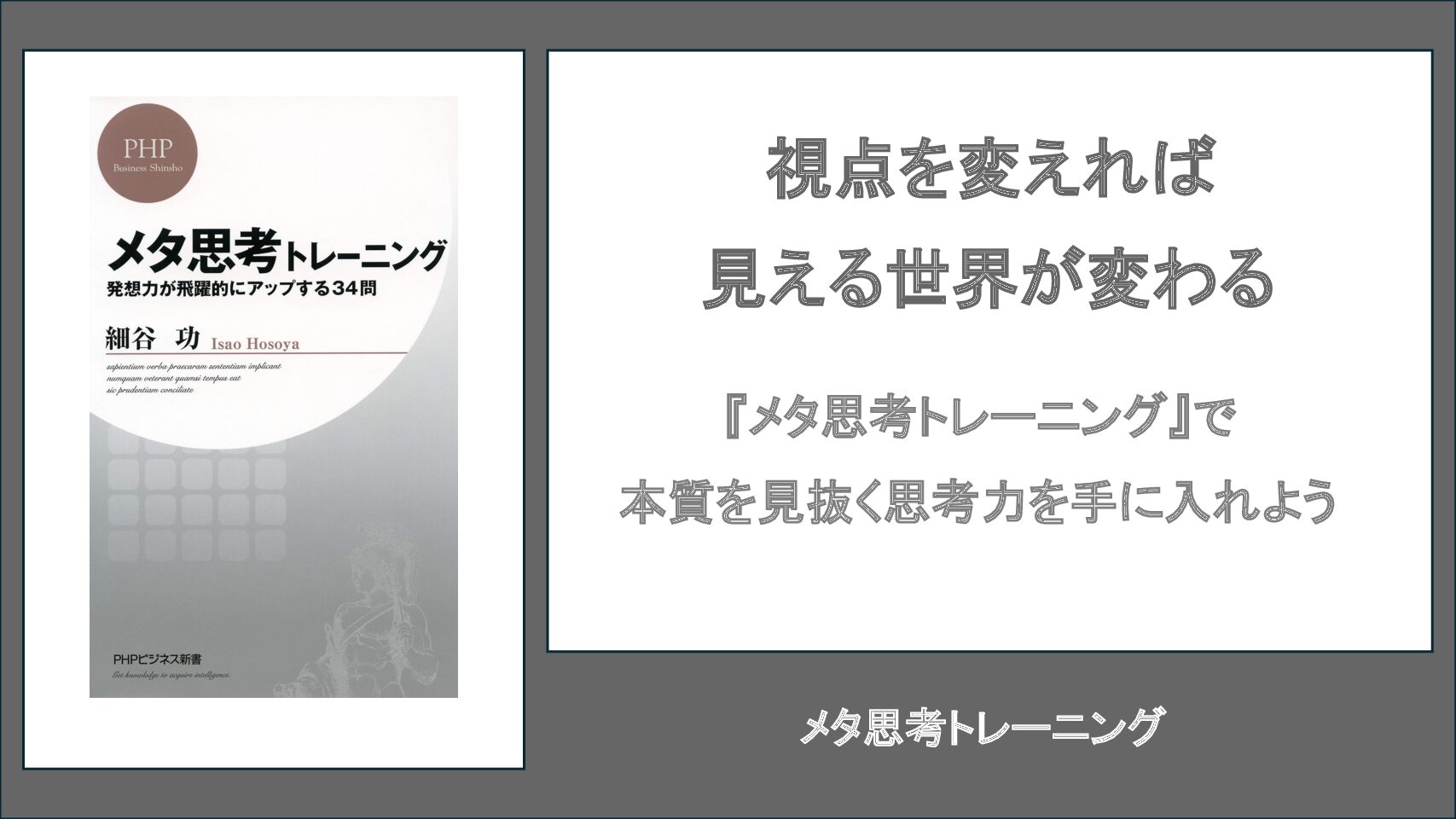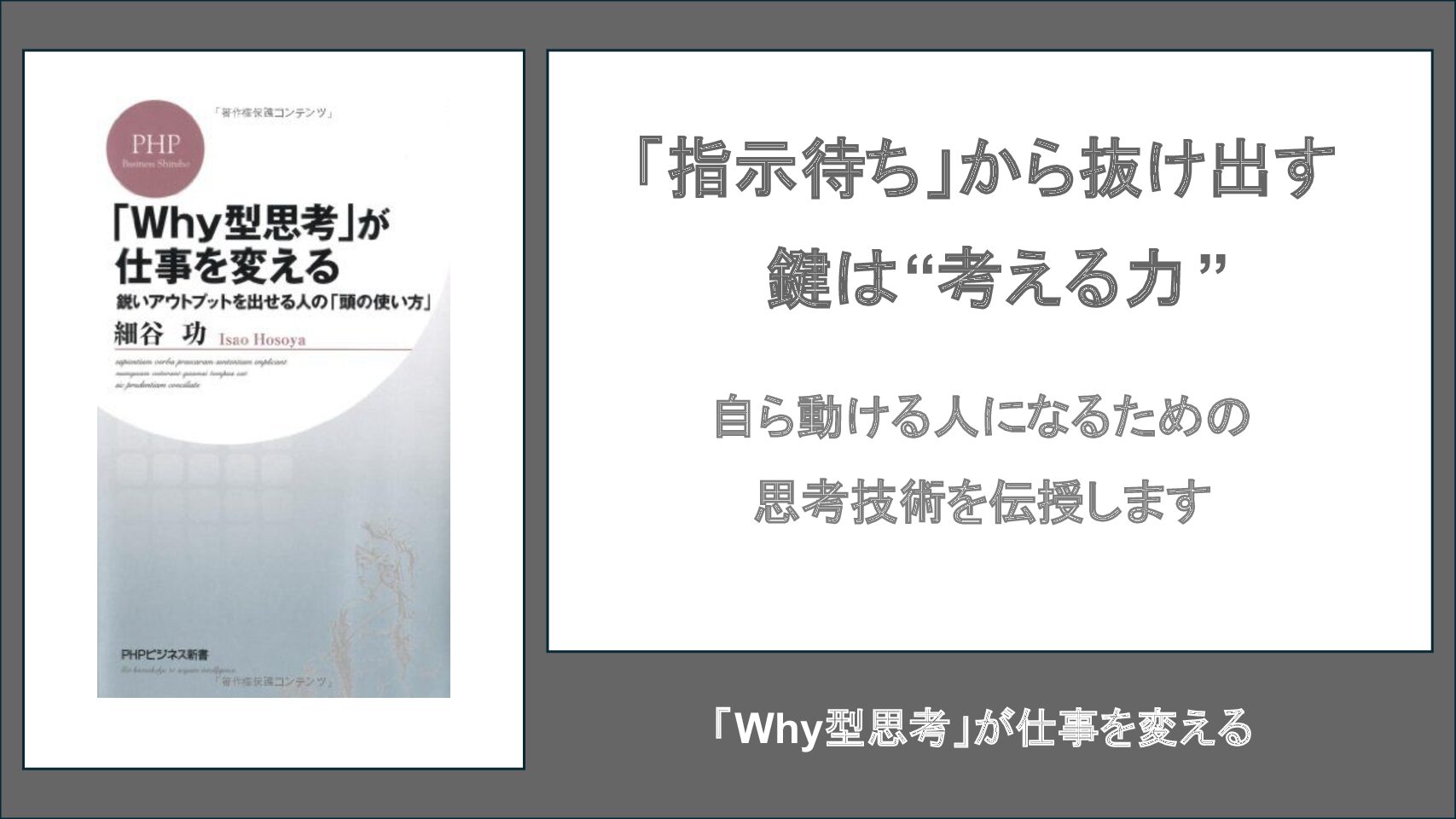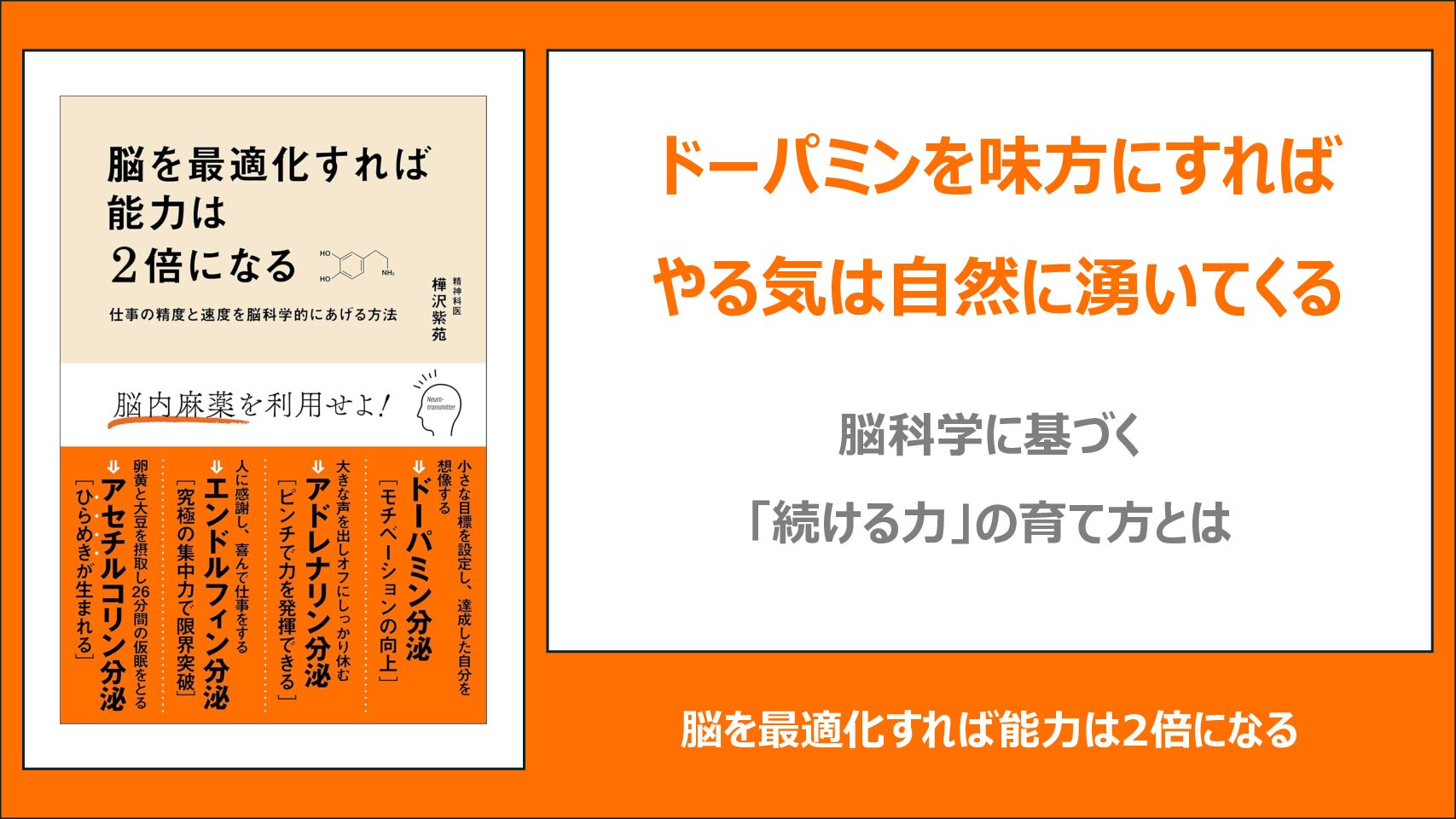この記事はで読むことができます。

最近、会議で意見を言ってもなんだかズレてるって言われるのよね…

それって、問題の本質を捉えきれていないのかもね。

うーん、確かに。解決策ばかり考えて、そもそも「何が問題か?」って深く考えてないかも。

そういう時におすすめなのが『メタ思考トレーニング』。問題を一段高い視点から見直す訓練ができるんだ。
「もっといい解決策はないのか?」「なぜ議論がかみ合わないのか?」―そんな悩みを抱えたとき、役に立つのが“メタ思考”です。『メタ思考トレーニング』は、物事を俯瞰し、本質を見抜く力を鍛えるための思考法を紹介しています。
著者の細谷功氏はコンサルタントとして多くの課題解決に関わり、その経験から導き出された“メタな視点”は、ビジネスパーソンに限らず、すべての人に有効な視点転換の技術です。
私たちはつい「答え」を探しがちですが、そもそも「正しい問い」が立てられていないことが多いです。この本は、問題の定義そのものを見直す視点を与えてくれます。
視点が固定されると、見えるものも限られてしまいます。視点を意図的に変えることで、新たなアイデアや問題の本質に近づくことができます。
メタ思考は「考え方を考える」プロセスです。この書籍では、身近な例を使ってメタ思考を訓練する実践的なトレーニングが紹介されています。
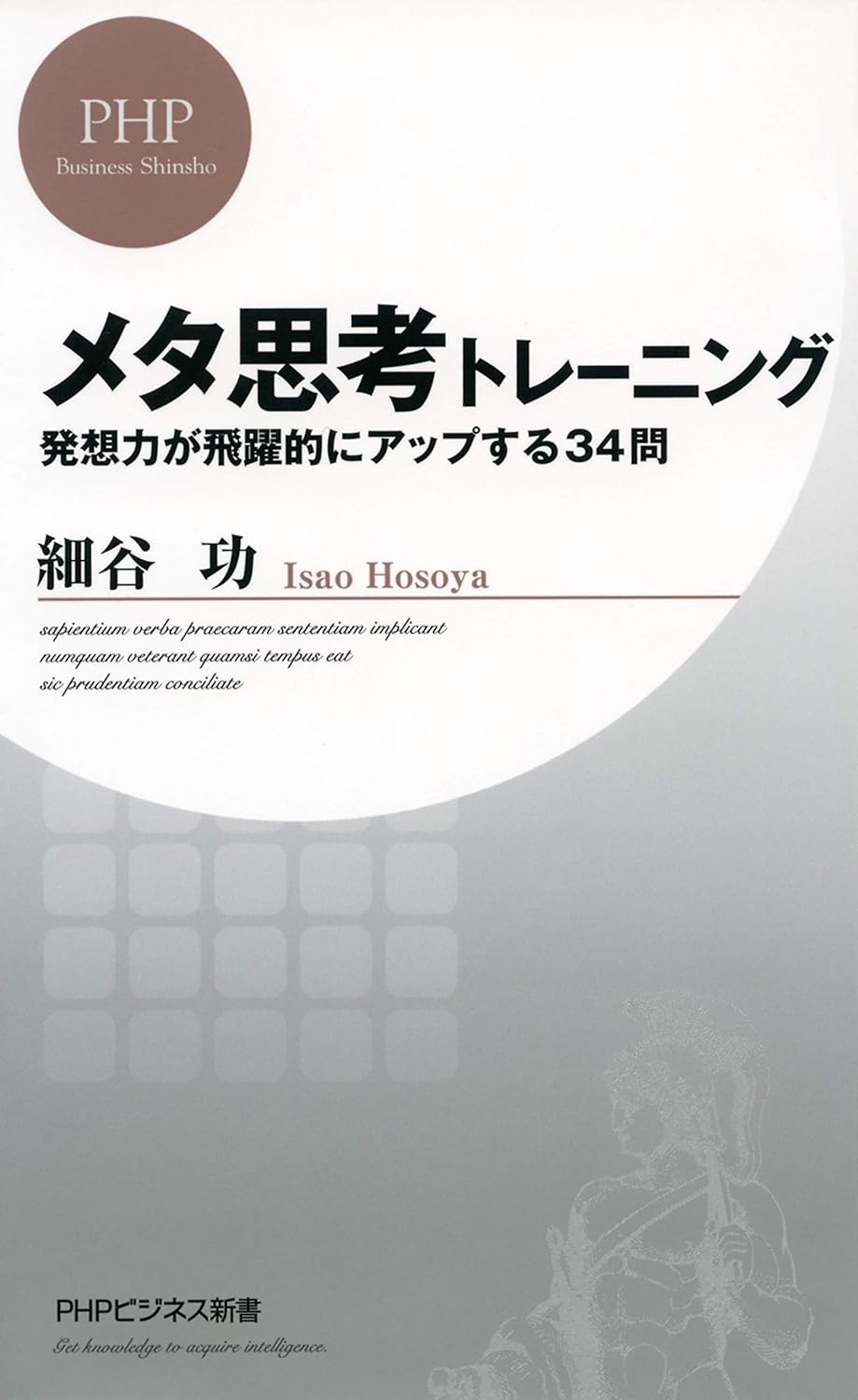
| 著者 | 細谷 功 |
| 出版社 | PHP研究所 |
| 出版日 | 2016年5月18日 |
| ジャンル | スキルアップ・自己研鑽 |
私たちは日常的に「問題をどう解決するか?」という視点から物事を考えがちですが、本当に重要なのは「その問題設定は正しいのか?」を見極める力です。たとえば売上が下がったとき、「広告を増やす」「価格を下げる」といった解決策を考える前に、「なぜ売上が下がっているのか?」という根本的な問いを立て直す必要があります。
このように、表面的な原因に飛びつく前に、問題の構造や背景を問い直すことで、本質的な課題が見えてきます。『メタ思考トレーニング』では、「そもそもこの問題は何のためのものか?」とメタな視点で問い直す方法を数多く紹介しています。
たとえば、「時間が足りない」という悩みも、「本当にやるべきことは何か?」という問いに置き換えると、優先順位の見直しや行動の削減といった新しい選択肢が出てきます。このように問いを変えることで、アプローチ自体が変化します。
自分の思考の前提を疑うことは難しい作業ですが、そこにこそ本質を見抜く力が宿ります。良い問いを立てる人は、良い答えを導く人でもあるのです。本書では、思考の起点である「問い」の重要性を繰り返し強調し、実際にどのように問いを再設定すべきかが丁寧に解説されています。
さらに、誤った問いがいかに多くの時間やエネルギーを無駄にするかの例も示されており、「問う力」の重要性を実感できます。問いを立てるスキルは、単なる知識よりも汎用性が高く、あらゆる分野に応用できます。
この力があれば、問題に対して的確にアプローチできるようになり、結果として無駄な試行錯誤が減るのです。問いを問い直す―この地道な習慣が、思考の質を劇的に高めてくれます。
同じ出来事でも、見る角度を変えれば全く違った意味が見えてきます。これは、認知心理学でも知られている「フレーミング効果」に近い現象です。たとえば、上司の指示を「強引で無理」と捉えるか、「現場を知らないからそう判断したのかも」と捉えるかで、その後の対応はまるで変わります。
『メタ思考トレーニング』では、「時間軸を変える」「他者の立場から考える」「抽象度を上げる」など、視点をずらす具体的な方法が多数紹介されています。問題の本質は、見えにくい場所に隠れていることが多く、そこにたどり着くには“視点の移動”が不可欠です。
たとえば、短期的な損失ばかりに目が行っていると、長期的な利益や信頼関係の構築という重要な要素を見落としてしまいます。視点を切り替えることで、隠れていた要因や選択肢が見つかるようになり、問題解決の幅が広がります。
また、異なる立場での考え方を理解することは、対人関係にもプラスの影響を与えます。意見が対立した時こそ、「相手の視点ではどう見えているか?」を想像することで、建設的な対話が生まれます。こうした視点移動の訓練を積むことで、思考に柔軟性が生まれます。
本書では、例題や図解を通じて視点移動の効果を具体的に体感できる構成になっており、読者が日常にすぐ取り入れられる工夫がなされています。視点を変える力は、知識や経験とは別の「知恵」の領域です。常に同じレールの上で物事を見るのではなく、レールそのものを変えてみることが、新たな発見への第一歩なのです。
メタ思考の核は、「自分の思考を対象化する」ことにあります。つまり、「なぜ自分はそう考えたのか?」「他の考え方はなかったのか?」と、自分の思考プロセスそのものを見つめ直す姿勢が重要です。
多くの人は自分の考えを「事実」として扱いがちですが、それは実は「判断」に過ぎないことが多いのです。本書では、「自分の思考パターンに気づく→それを分析する→別のパターンを試す」という循環を習慣化することで、思考の質を飛躍的に高める方法が紹介されています。
たとえば、「すぐに否定的に考えてしまう」というクセがあれば、それに気づくだけで他の選択肢を模索する余地が生まれます。さらに、考えを言語化することで自分のクセや偏見に気づきやすくなります。日記をつけたり、誰かに話したりすることが、メタ思考のトレーニングにもなるのです。自分の思考を一歩引いて観察することで、不要な感情的反応を抑えたり、論理の飛躍を修正することが可能になります。
本書では、こうした習慣を作るための実践例も豊富に紹介されており、読者が日常の中で自然とメタ思考を使えるよう設計されています。「考えることを考える」ことで、自分の視点の偏りや狭さに気づき、より自由で創造的な発想が可能になります。
これは単に頭を使うということではなく、頭の使い方そのものを見直すことを意味しています。自分の思考の質を高めたいならば、「自分の思考に対する関心」を高めることが第一歩です。何気ない日常の中で、「今、自分はどう考えているのか?」を問い直す習慣を持つことが、人生をより深く、豊かにしてくれるのです。
毎週1つ、「今抱えている問題」の問い方を変えてみましょう。たとえば、「どうすれば成果が出るか?」ではなく、「なぜ成果が出ていないのか?」と視点を変えて書き出します。答えに詰まった時ほど、問いそのものを見直す時間をつくるのが効果的です。
日々の仕事や生活の中で、「他の立場だったらどう見るか?」と考えるクセをつけましょう。意見が食い違ったときには、相手の立場や価値観からその発言を解釈してみることで、冷静な対話が可能になります。日記に「今日の出来事を別の立場で振り返る」習慣をつけるのもおすすめです。
ノートやアプリを使って、自分の考えたプロセスを言語化しましょう。「なぜこう考えたのか?」を追跡し、週に一度見直すことで、自分の思考のクセが見えてきます。過去の自分の判断と照らし合わせることで、思考の成長を実感できます。
本書はビジネス現場で頻繁に直面する思考停止や「手段の目的化」を防ぐ実践的なフレームワークや演習問題を豊富に提供しています。現実の業務や対人関係で応用可能な例が多く、実務での活用度は高いです。ただし一部、やや抽象度が高く、訓練を重ねなければ日常で即使えるレベルに落とし込めない場面もあります。誰にでも即効性がある内容とは限らないため、最高点は避けました。
「Why型思考」や「アナロジー思考」など、メタ思考の枠組みは図解や例え話を多用して解説されており、比較的理解しやすい構成になっています。一方で、説明が長文化しがちで、図や演習問題の解説が十分でない箇所もあり、読者の解釈に委ねる部分が少なくありません。また抽象度が高い用語が多く、読解力が必要なため、平均よりやや高めにとどめました。
ビジネスだけでなく、教育、日常生活、さらには自己啓発にも応用可能な思考法を取り扱っており、あらゆる場面に通用する普遍的な視点を提供しています。視野を広げる訓練として汎用性は非常に高く、分野や業界を問わず有効です。演習問題も日常の身近な事例から構成されているため、読者の背景に関係なく取り組みやすく、満点としました。
語り口は丁寧でユーモアも交えられており、親しみやすい印象を受けます。ただし、文が冗長になる傾向があり、論点が散漫に感じられる箇所も多くあります。段落構成や図表の配置に改善の余地があり、読み飛ばしたくなる読者も出るでしょう。気軽に読める軽快なビジネス書と比べると、若干読み進める労力がかかります。
心理学、教育学、ビジネス戦略など幅広い知見を取り込みながら、それを独自の枠組みで整理している点は評価に値します。ソクラテスの「無知の知」から現代の営業課題まで幅広く網羅し、理論と実践を融合しています。しかし、特定分野の学術的専門性に深く踏み込んでいるわけではなく、「実務知の広さ」に軸足を置いているため、学術的な専門書という意味では満点には至りません。

なるほどね、答えを探す前に問いを見直すって発想、すごく新鮮だった!

そうだね、問題の定義を変えるだけで、全然違う解決策が見えてくるんだよ。

視点を変える練習、ちょっとずつやってみようかな。

うん、自分の考えをメタ的に見られるようになると、仕事でも人間関係でも役に立つよ!
『メタ思考トレーニング』は、今の時代に欠かせない「考える力」を鍛えるための必読書です。視点を一段上げることで、あなたの世界の見え方が一変するかもしれません。問題解決の力を本質から磨きたい人に、ぜひ手に取ってほしい一冊です。