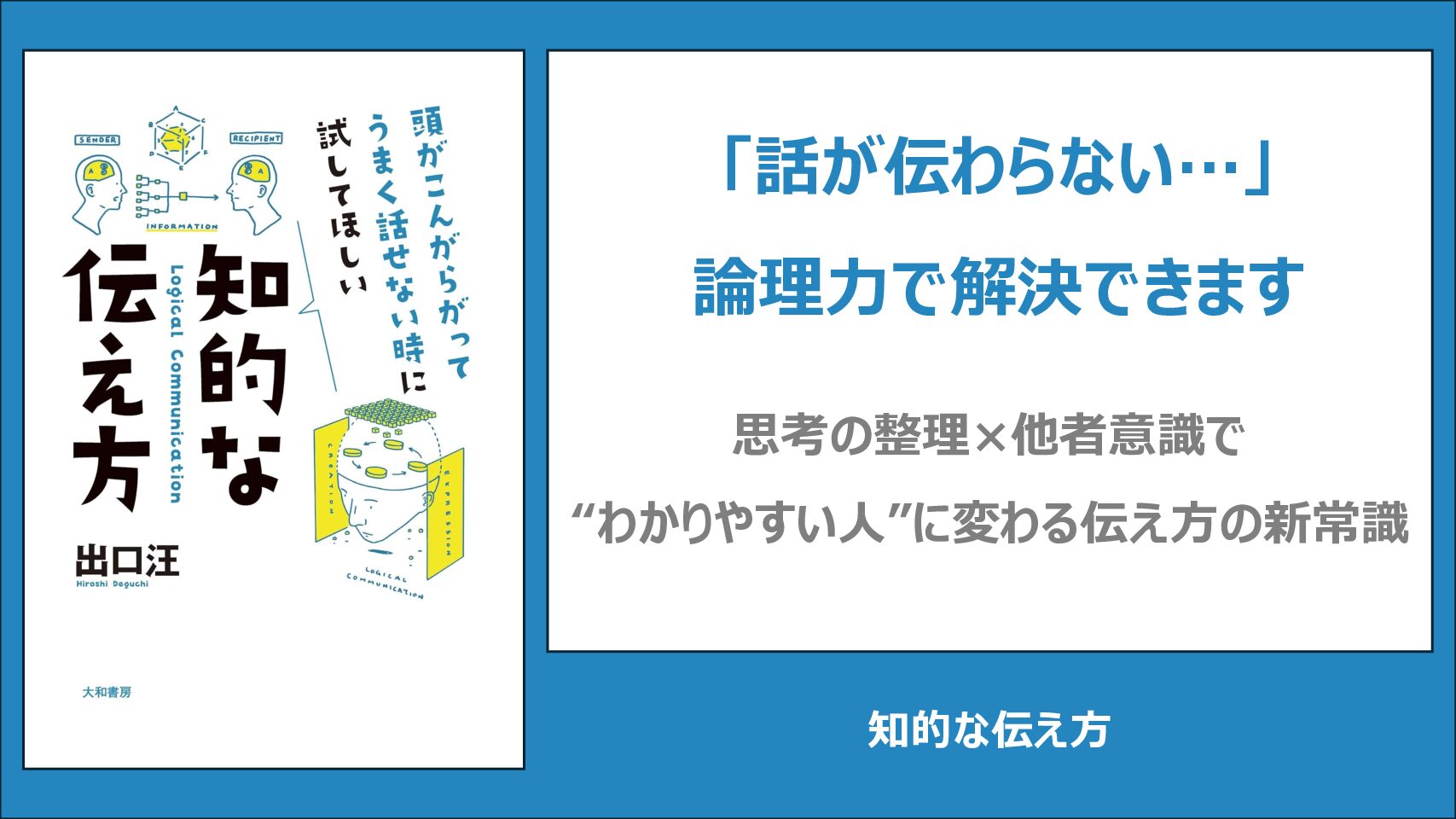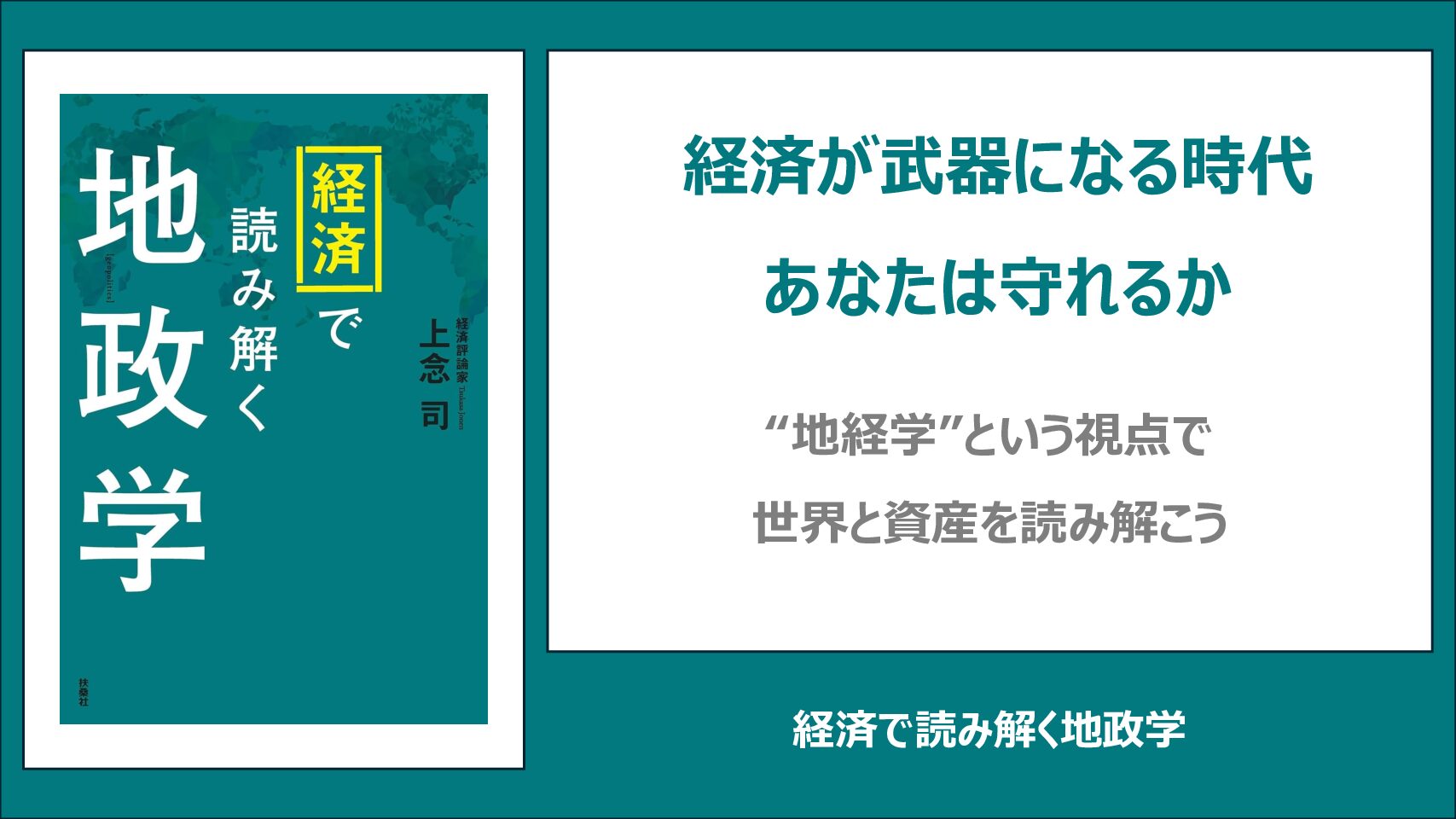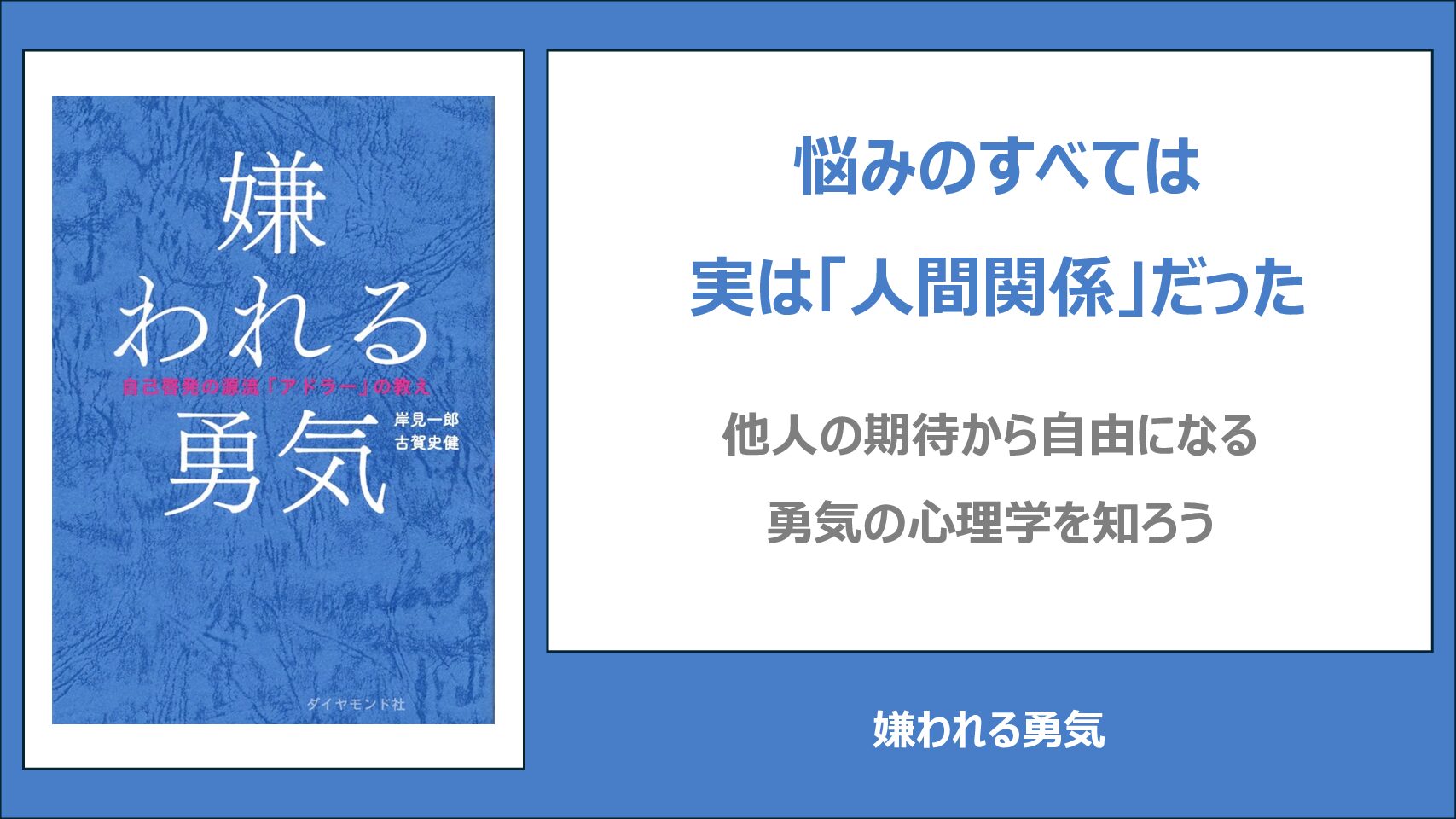この記事はで読むことができます。

ねぇTom、私、また「何が言いたいの?」って言われちゃったのよ。ちゃんと話してるつもりなのに。

それって、よくあるよね。でもMamって、伝えるの苦手なタイプじゃないでしょ?

そう思ってたんだけどね…SNSとかプレゼンで言葉がまとまらなくて、自信なくしそう。

それなら、論理的に伝える力=論理力を鍛えるといいかも。最近読んだ本があってさ。
会話が噛み合わない、説明が伝わらない、そんな悩みを持つ人は少なくありません。でも、それはセンスや才能ではなく、「論理力」を鍛えることで誰でも克服できます。本記事では、書籍『知的な伝え方』をもとに、伝わるコミュニケーション術を紹介します。
ただ思いついたことを口に出すのではなく、伝える順番や構造にルールがあることが分かります。論理力を鍛えることで、聞き手に伝わる話し方ができるようになります。
自分視点で話していることが、相手の理解を妨げている可能性があります。「他者意識」の欠如が、コミュニケーションのズレを生むのです。
話す力と書く力は密接につながっています。書く力を鍛えると、論理の構造が身につき、話す際にも自然と筋道だった説明ができるようになります。
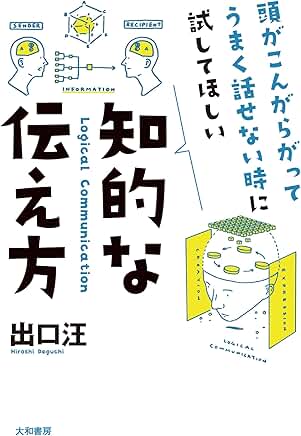
| 著者 | 出口 汪 |
| 出版社 | 大和書房 |
| 出版日 | 2017年6月21日 |
| ジャンル | 人間関係・コミュニケーション |
話が伝わらない大きな原因は、「自分の言いたいこと」ばかりに意識が向いてしまい、「相手がどう受け取るか」まで考えが至っていないことです。これを本書では「他者意識が欠けている」と指摘しています。
他者意識とは、相手の背景、価値観、知識量を想像しながら言葉を選ぶ力のこと。たとえば専門的な知識を持つ人に基本的な説明をしてしまうと、回りくどく感じられます。一方、初心者に難解な言葉で説明すると、内容が全く伝わらないまま終わってしまいます。
つまり、相手に合わせて話し方・説明の深さ・例え方を調整する必要があります。本書ではこの「相手視点」を持つことが、論理力の土台であると繰り返し説かれています。会話でもプレゼンでも、まずは「この人は何をどれくらい知っているか?」を把握することが第一歩です。さらに、「相手は自分のことを何も知らない」という前提で伝えることで、伝わる力はぐっと高まります。
他者意識を持てば、「どう話せば相手がわかるか」という思考に切り替わります。それは、話す内容の順序、選ぶ言葉、例の出し方など、すべての選択に影響します。自分の中では完璧な話でも、相手に伝わらなければ意味がない——この事実を受け止めることが、論理的な伝え方への第一歩なのです。
他者意識を持つとは、同時に思いやりであり、伝える技術でもあります。だからこそ論理力とは、相手を理解しようとする努力の積み重ねなのです。
本書で紹介されている3つの論理的思考の基本ルールは、「イコールの関係」「対立の関係」「因果の関係」です。これらは、聞き手にわかりやすく、説得力のある話を組み立てるための道具となります。
「イコールの関係」とは、抽象と具体を結びつけて説明する方法です。たとえば「この人は誠実だ」という抽象的な評価に、「財布を拾って交番に届けた」といった具体例を加えると、説得力が一気に高まります。反対に、複数の具体例から共通点を見出し、抽象的な結論を導き出す方法も使えます。これはプレゼンやレポートでも多用される、基本中の基本です。
次に「対立の関係」。これは、ある主張を際立たせるために、反対の例を持ち出して比較する手法です。たとえば「日本の治安は良い」と言いたいなら、「海外の治安の悪さ」を例に出すことで、日本の安全性がより引き立ちます。また、弁証法のように、対立する意見を統合して新しい主張を生む高度な応用も可能です。
そして「因果の関係」。これは「AだからBになった」というように、原因と結果を明確にする方法です。「昨日3時間しか寝なかった。だから今日の会議で集中できなかった」といった話は、非常にわかりやすいです。ただし、因果を無理に結びつけると誤解を生むため、注意も必要です。
この三法則を意識するだけで、話の組み立てに筋が通り、聞き手の理解度が格段に上がります。とくにプレゼン・営業トーク・文章作成など、説明責任が伴う場では非常に強力なツールです。これらを日常的に使いこなせるようになると、あなたの伝え方は一段も二段もレベルアップするでしょう。
話す力を高めたい人ほど、実は「書くこと」に注力すべきだと本書は教えてくれます。なぜなら、文章は話し言葉以上に論理性が求められるからです。口頭では多少順番が曖昧でも感情や身振りで補えますが、文章は構造が崩れると一瞬で伝わらなくなります。
書く力を鍛えることは、自分の思考を整理する力を養うことでもあります。本書では、「ストックノート」という手法が紹介されています。これは、左ページに読んだ内容の要約、右ページに自分の考えを書くというトレーニングです。これによって、論理構造を自然と頭に定着させることができます。
さらに、文章を書くことで「要点」「理由」「補足」「例示」など、話を組み立てる基本要素が明確になります。頭の中で考えていたことを文字に起こすと、自分の考えの曖昧さにも気づけます。この「気づき」こそが、伝える力を伸ばす最大の材料なのです。
また、文章にすることで客観視しやすくなり、修正や改善もできます。日常的に書く習慣がある人ほど、話すときも論理的に構成された表現が自然とできるようになります。話す力と書く力は双方向の関係にあり、どちらも鍛えることで相乗効果が期待できます。論理的に話す力をつけたいなら、まずは1日1つでも「書いてみる」ことから始めましょう。
話す相手が誰か、その人はどんな知識や経験を持っているのかを事前に考え、3つ程度のポイントをメモしておきましょう(例:「新卒だから基礎から」「営業職なので数字に強い」など)。それをもとに、「どこから話せばわかりやすいか」「例え話は何が適切か」を組み立ててみてください。たった数分の準備が、話の伝わり方に大きな差を生みます。
たとえば「この映画はよかった(主張)」→「感動的な実話だったし(イコール)」→「逆に最近のアクション映画は展開が雑で…(対立)」→「だからこういう話が心に残るんだと思う(因果)」といった感じです。雑談でも練習できるので、日々の会話をトレーニングの場として活用しましょう。
「つまり」「しかし」「だから」といった接続語を意識的にチェックしながら読むことで、論理の流れが視覚化されます。慣れてくると、文章の構造が自然と読めるようになります。こうした読み方が、のちに自分の書く力・話す力の土台になります。
本書は「伝え方」について多くの具体例やテクニックを挙げており、ビジネスや日常の対人関係でそのまま使える内容が充実しています。特に論理力の三原則(イコール・対立・因果)や「空白の時間の活用」「接続語の重要性」など、すぐに実践できる指針は評価できます。ただし、日常生活で常にここまで厳密に実行するのは難易度が高く、実用にはある程度の慣れが必要です。したがって、初心者には若干ハードルが高く感じる可能性があります。
身近な例や著者自身の経験談を交えて説明している点は評価できます。また、論理的に段階を踏んで解説しており、章立ても明快です。ただし、ページによって冗長な表現や、やや繰り返しが多い箇所もあり、すっきりとした理解を妨げる場面がありました。一部、表現の癖や口語的な展開が過剰に感じられるところもマイナス要素です。
論理力や他者意識に基づいた伝え方は、ビジネスだけでなく教育、恋愛、SNS、家族関係など、あらゆる場面で応用が可能です。抽象と具体、対比や因果などの原則は普遍性が高く、誰にでも関係のある内容です。また、書く力・話す力の両面に言及しているため、活用の幅が広い点は非常に優れています。
文章量が多く、情報の密度も高いため、集中して読む必要があります。一部の章では脱線や表現の冗長さ、やや説教臭さが目立つ点が読者のテンポを阻害するかもしれません。また、語り口調が軽快な反面、やや自己主張が強すぎる印象も否めません。もう少し簡潔さやリズムの工夫があれば、さらに読みやすくなるでしょう。
内容は論理学や心理学の基本に根ざしてはいるものの、学術的というよりはあくまで実用・自己啓発寄りです。著者の実体験や直感に基づく記述が多く、専門的な裏付けや文献への言及は少ないため、専門書を期待する読者には物足りないかもしれません。ただし、一般向けには過不足ないレベルです。

やっぱり伝えるのって、相手のことをどれだけ考えられるかってことなんだね。

そうそう。他者意識と論理力さえあれば、伝わる力は誰でも伸ばせるよ。

今度のプレゼンでは、ストックノートで整理してから話してみる!

いいね。きっと「わかりやすいね」って言われるはずだよ。
伝える力に自信が持てない…そんな悩みを抱えている方も、論理力を鍛えれば確実に変われます。感情を整理し、構造を意識することで、あなたの言葉は相手の心に届くようになるはずです。話すこと、書くことが楽しくなる未来へ、今日から一歩踏み出してみませんか?