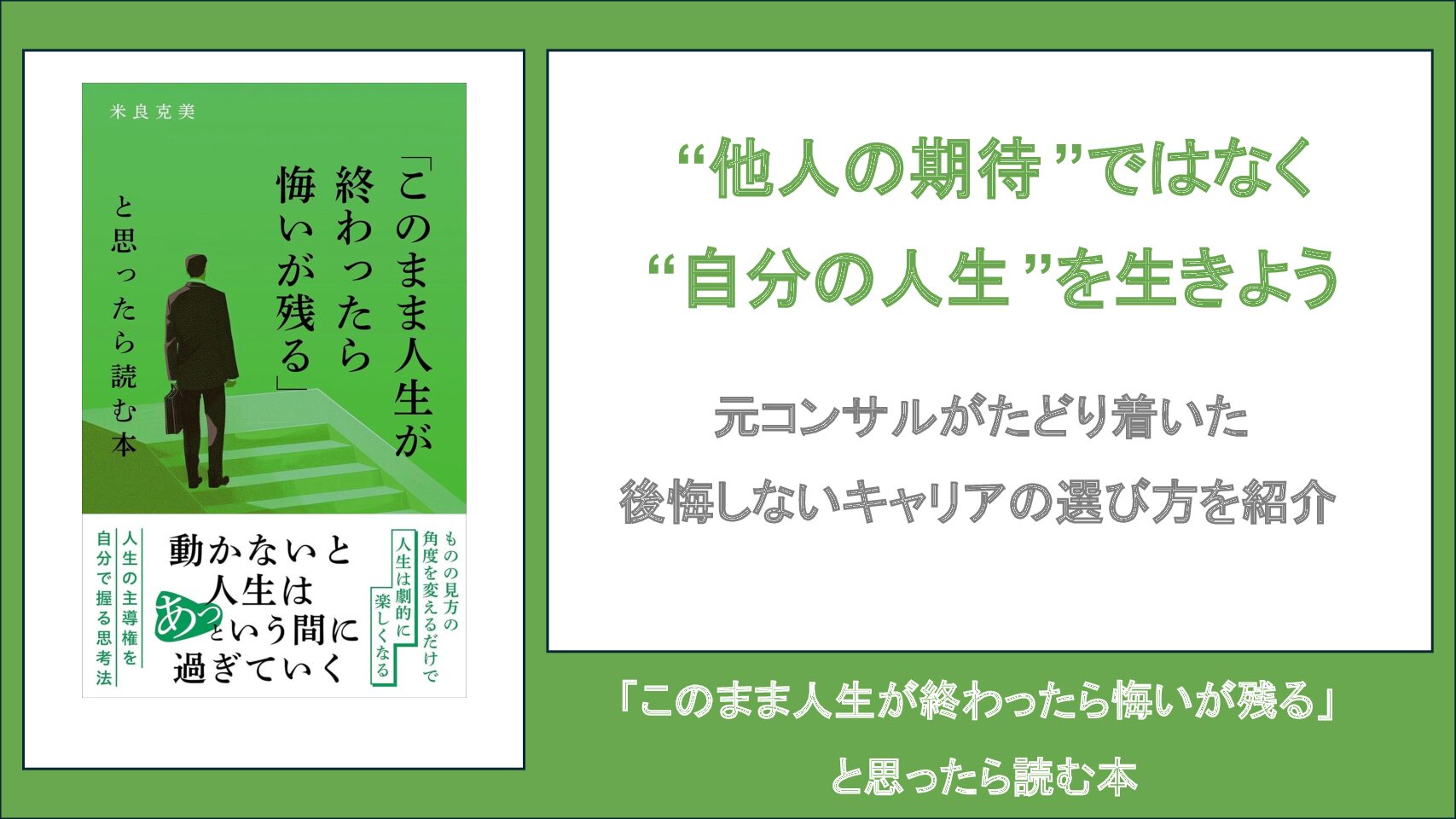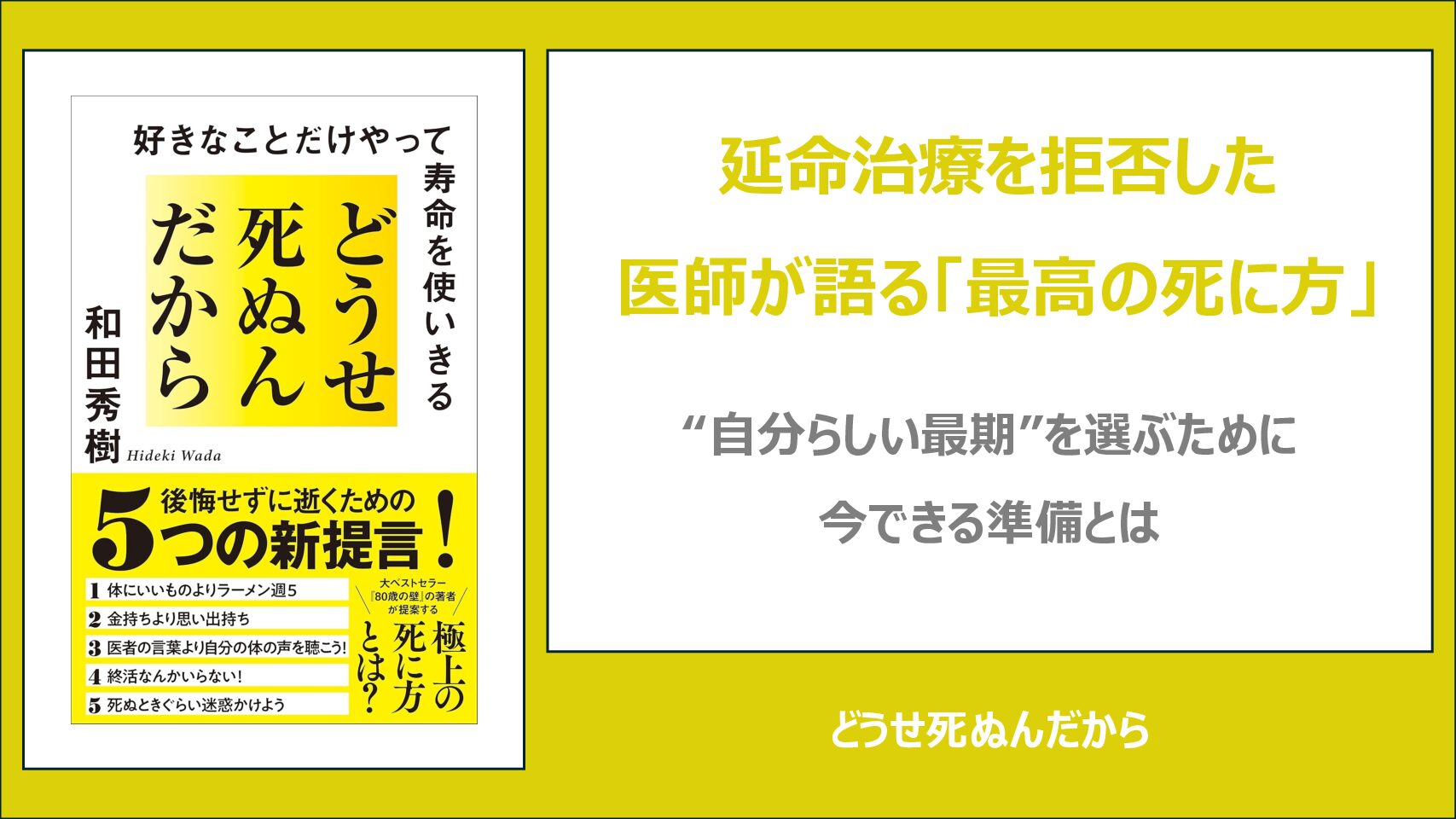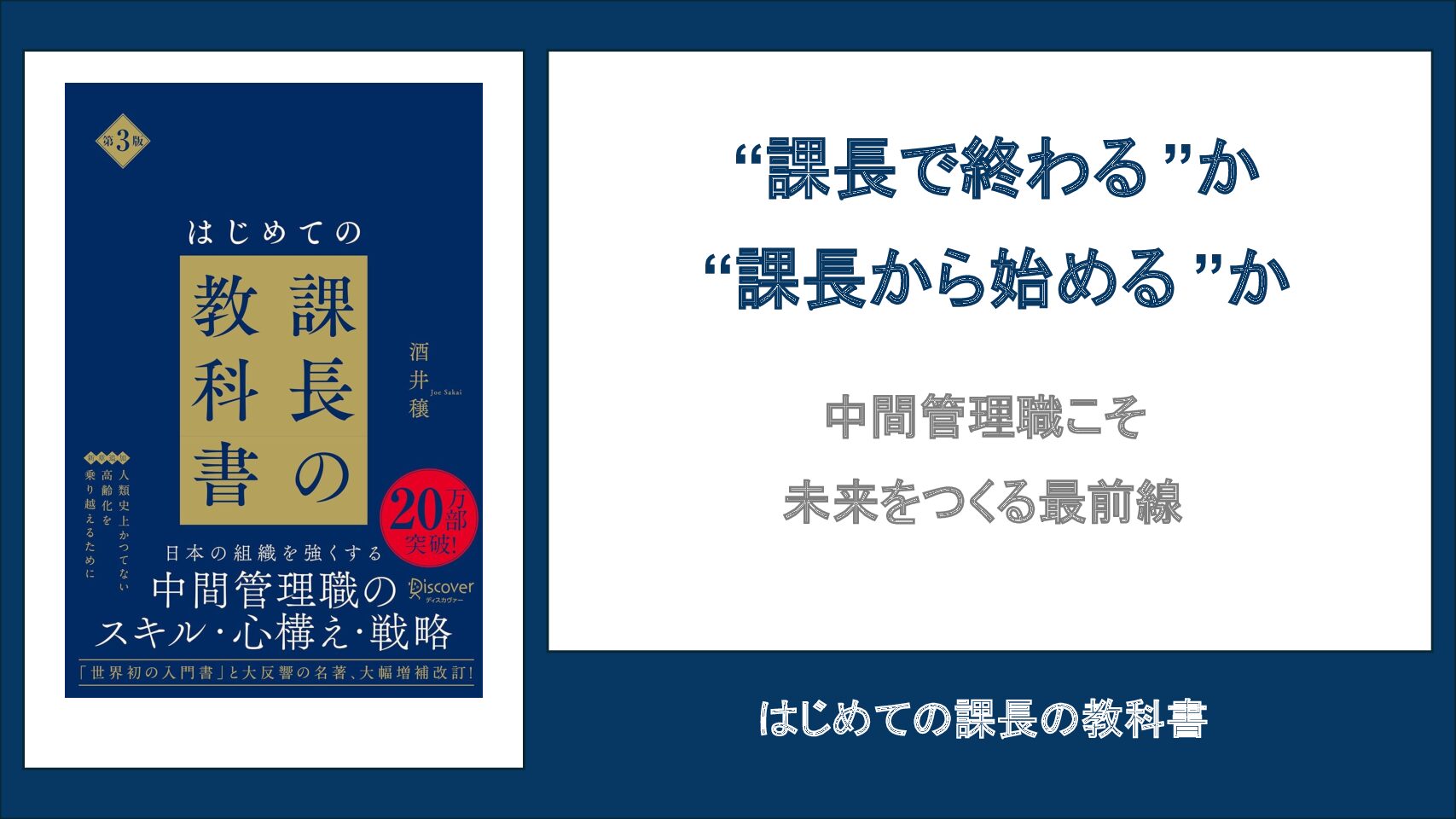この記事はで読むことができます。

ねぇTom、最近仕事してても「これ本当に私がやりたいこと?」って思う時ない?

あるある。年収やポジションは上がってるのに、なんか心が置いてけぼりって感じでさ…。

実はそんなときに読んだのが、元コンサルの人が「自分の人生を生きる」ってことをテーマに書いた本なんだけど、もうね…ズシンときたのよ。

それ気になるな。仕事バリバリやってた人がどうやって「自分らしさ」にたどり着いたのかって興味ある!
「年収は悪くない、地位もある、でも満たされない――」
そんな違和感に向き合い、自分らしいキャリアを見つけ直した著者・米良克美氏の実体験を通じて、社会人が見落としがちな「自分軸」の大切さが語られています。
数々のキャリアチェンジや挫折を経たからこそ語れる、リアルで実践的な人生哲学が詰まった一冊を要約します。
現代社会では結果を出し続けなければならないというプレッシャーが蔓延しています。その正体を理解することで、自分の働き方や選択に新たな視点を持てるようになります。
やりたいことが分からないのは、自分と向き合う時間が足りないからかもしれません。自己理解の重要性と、保留し続けることのリスクについて学べます。
他人の期待や社会的成功を優先してきた人にとって、「誰のための人生か?」という問いは非常に本質的です。この問いに真剣に向き合うことで、人生の主導権を自分に取り戻すヒントが得られます。
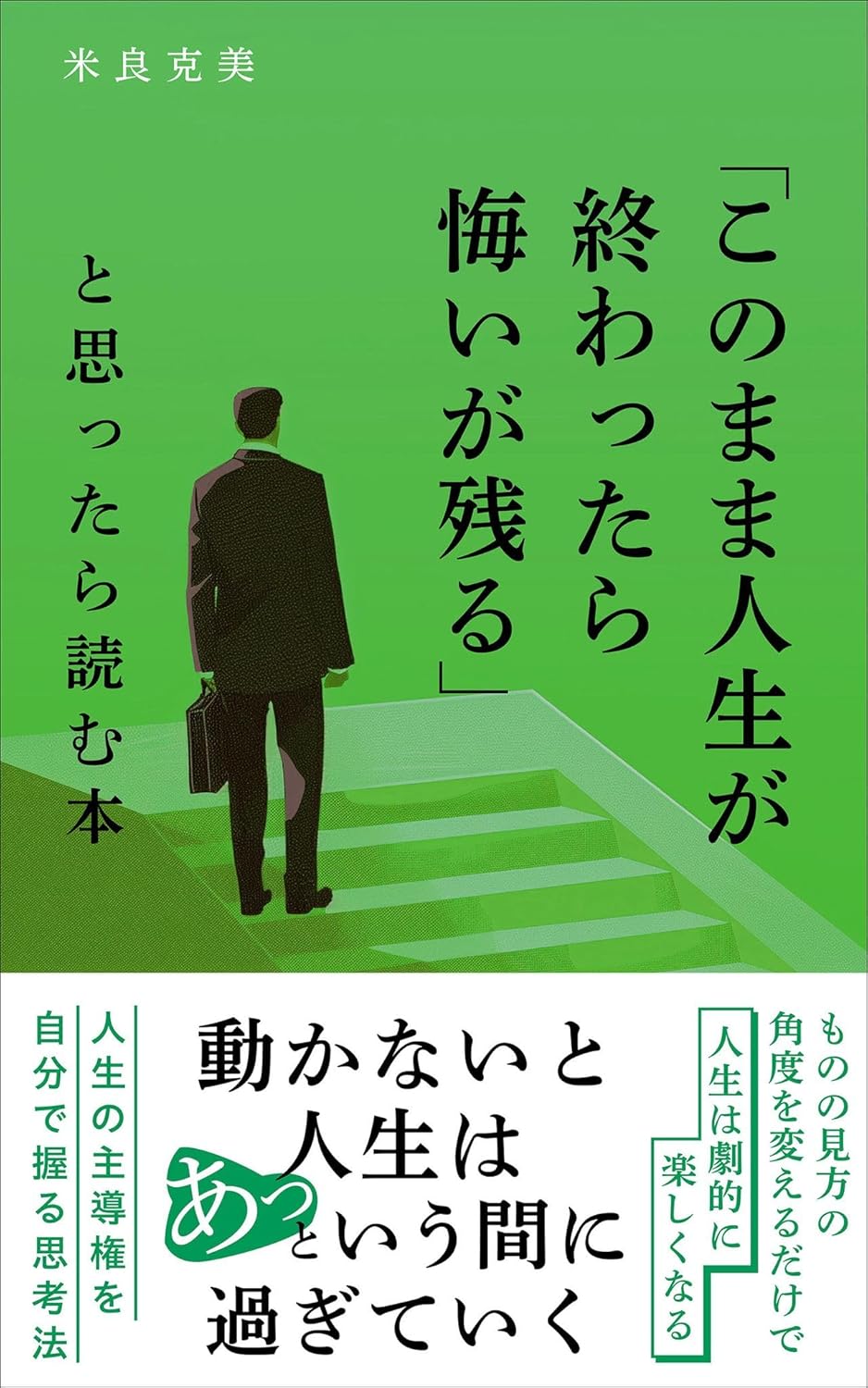
| 著者 | 米良 克美 |
| 出版社 | Kindle |
| 出版日 | 2024年10月2日 |
| ジャンル | キャリア・人生設計 |
働く人の多くが無自覚のうちに感じている焦りや不安は、実は社会構造と価値観の影響によるものです。とくに「年齢に応じてこれくらいはできて当然」という無言のプレッシャーや、SNSで他人の成功が可視化されることによる比較の連鎖は、精神的な余裕を奪います。
著者は、製薬会社での安定した地位にありながらも、「これが自分の本当にやりたいことか?」と疑問を持ち始めたことをきっかけに、自己との対話を始めました。結果を出し続けなければという焦りは、時に自分を追い詰め、心身のバランスを崩す原因にもなり得ます。著者自身も、外資系コンサルでの激務の中で心が壊れ、休職に追い込まれるほどの限界を経験しました。
そこから回復するプロセスで見えてきたのは、「他人の期待ではなく、自分の価値観で生きる」という視点の重要性です。プレッシャーとは、外部から押しつけられた基準や評価軸によって生まれるものです。それに対抗するには、自分が何を大切にしているかという“内的基準”を明確にする必要があります。
焦りを感じる場面で、「この選択は誰のため?何を満たしたいと思っているのか?」と問い直すことが、軸を取り戻すきっかけになります。著者は「結果を求められる社会では、プロセスや挑戦の価値が軽視される」と語りますが、その状況こそが自分をすり減らす原因だと気づくことが大切です。
たとえば、昇進のライバルが先に管理職になったとしても、「自分が本当にその役割を望んでいるか」と考えると、案外どうでもよかったりします。周囲との比較をやめ、過去の自分との比較に切り替えるだけでも、心はかなり軽くなります。人生には“タイミング”もあり、一見遅れているように見えても、自分にとってベストな時期というものがあるのです。焦らず、自分のペースで歩む覚悟を持てば、プレッシャーに振り回されずに済みます。
つまり、焦りに勝つには、まずその正体を知ること。外のノイズではなく、自分の内なる声を聴く時間を日常に持つこと。それが、ブレない自分をつくる第一歩なのです。
多くの人が、「やりたいことが分からない」と悩みます。しかし、著者は「やりたいことは最初から明確である必要はない」と断言します。頭の中でどれだけ考えても、答えは出ません。なぜなら、「興味」や「適性」は体験を通じて育つものだからです。著者自身も、研究職、製薬会社、外資系コンサル、起業と、さまざまな職を経験する中で、ようやく「人の成長に関わることが好き」という核心にたどり着きました。
重要なのは、「とりあえずやってみる」という姿勢です。完璧に見極めてから動こうとする人ほど、行動に移せず、時間だけが過ぎていきます。三日坊主でもかまいません。何かを始め、違うと思ったらやめて、次を試す。それを繰り返す中で、自分の感情が動くポイントが見えてくるのです。著者は筆ペンで名言を書く「めらち書道」を始めた時も、「どうせ3日坊主になる」と思っていたそうです。ところが、やってみると楽しくなり、今でも続いているといいます。
このように、小さな行動でも、その積み重ねが将来の自分を形成していきます。「興味が湧いたからといって、すぐに情熱にはならない」と著者は語りますが、それでも始めなければ何も見えてこないのです。行動することは失敗のリスクも伴いますが、それ以上に“情報”が手に入ります。「これは違うな」という感覚も、貴重なデータです。逆に、何も動かずに保留し続けることこそ、最大のリスクだと著者は指摘します。
何も見つからないなら、とにかく動く。たとえ3日でやめても、その経験が何かに繋がる。だからこそ、「やりたいこと」は動きながら探すのが正解なのです。
「誰のために生きるか?」という問いは、著者の人生を根底から変えた一言です。多くの人が無意識のうちに、親、会社、社会といった“他人軸”に従って生きています。著者もかつては「大手だから」「年収がいいから」という理由でキャリアを選んでいました。しかし、心身を壊したことをきっかけに、初めて「自分の人生に本当に必要なものは何か」と考えるようになったのです。
この問いは決して簡単ではありません。なぜなら、「自分のために生きる」ことが、時にわがままや自己中心的だと誤解されるからです。しかし、著者は「自分のために生きることが、結果的に社会の役に立つ」と確信を持って言います。実際に、キャリアを人材開発に切り替えてからの著者は、クライアントや学生と関わる中で、最も社会に貢献している実感を得たといいます。
大きな決断をする際には、必ず周囲の反対があるものです。著者も、転職やキャリアチェンジのたびに「もったいない」「恵まれているのに」といった声を浴びせられました。しかし、実際に応援してくれたのは、同じように挑戦した経験のある人たちでした。このことから、「反対するのはやったことのない人、応援するのは経験者」という法則を著者は見出します。
「誰のために生きるのか」という問いに正解はありませんが、この問いを持ち続けることが、自分軸を強くするトレーニングになります。そして、その軸があるからこそ、他人に流されず、自分らしい選択ができるのです。たとえ迷いながらでも、向き合う姿勢こそが、本当の意味での“自分の人生”をつくっていきます。
人生は一度きり。他人の期待ではなく、自分の声に従って選んだ人生にこそ、納得と満足が宿るのです。
日々SNSで感じる他人との比較から距離を置くために、1日30分の「ノーSNS時間」を設けてみましょう。自分の考えや価値観を紙に書き出す時間を確保することで、焦りや不安の正体が見えてきます。また、自分の中の「~でなければならない」思考を一つずつ疑ってみるのも効果的です。
「やりたいことがない」状態でも、気になることに触れる習慣を始めましょう。例えば、毎月1回は新しいジャンルのイベントに参加してみる、興味が湧いた本を即購入する、など小さな挑戦を積み重ねます。「3日坊主でもOK」と割り切って、完璧を目指さないことが継続のコツです。
月に一度、自分の行動や選択が「誰のためのものか」を振り返る習慣をつけましょう。手帳に「今月の決断で、自分らしかったものは?」と書いてみると、自分軸の精度が上がっていきます。また、反対された時の対応を事前にイメージしておくことで、周囲の声にブレずに選択を進められます。
この本はキャリア形成や人生観の見直しに具体的なヒントを多く提供しており、実際に行動に移しやすいアドバイスも豊富です。「とりあえずやってみる」「3日坊主でもOK」といった行動原理は、行動を後押しする実用的な指針として有効です。ただし、体系的な方法論やワークシートなどのツールはないため、実践的なフレームワークとしてはやや物足りません。より即効性を求める読者には、具体的ステップの不足がネックになるかもしれません。
平易な日本語と親しみやすい語り口で書かれており、誰でもスムーズに読み進めることができます。著者自身の経験談が豊富に盛り込まれており、内容が具体的かつリアルで理解しやすいです。例え話や名言の引用も適度に挿入され、抽象的な内容にも説得力が加わっています。難解な表現や専門用語は避けられており、読者層を選ばない構成です。
本書のメッセージは「自分らしく生きる」「自分の人生を生きる」という普遍的なテーマであり、多くの人に共通する悩みに寄り添っています。ただし、著者のキャリアパス(製薬・MBA・コンサル)に共感できる層にやや偏っており、異業種や非ビジネス職の読者には一部のエピソードが遠く感じられるかもしれません。また、「日本的常識を捨てろ」などの価値観は共感を得にくい層もいるでしょう。読者の価値観や状況によって適用範囲が制限される場面がある点で、汎用性は中程度と評価しました。
文体は親しみやすく、会話調を取り入れながらテンポよく進んでいくため、ストレスなく読めます。章立ても整理されており、トピックごとに明確に区切られていて理解が進みやすい構成です。過度な情報詰め込みや冗長な表現もなく、読み手に配慮した文章運びがなされています。途中に挟まれる体験談や問いかけが読者の感情に響き、自然と引き込まれます。
キャリア支援や心理学的観点、ウェルビーイングといった分野についての記述は一定の知見に基づいています。特に「幸福学」「ポジティブ心理学」に触れるなど、表層的な自己啓発にとどまらない視座があります。しかしながら、学術的な裏付けや理論展開は浅く、参考文献の提示やデータ分析も見られないため、専門書としての深みはやや不足しています。より高度な専門性を求める読者には物足りなく感じられるかもしれません。

正直、「誰のための人生か?」って、今まで考えたことなかった…。

わかる。でもそれって、自分の人生を取り戻すためにめちゃくちゃ大事な問いなんだね。

うん。行動しながら探していくっていう姿勢も勇気が出たし、「3日坊主でOK」っていうのにも救われた。

プレッシャーに潰されないって、自分の軸を持つってことなんだな。
人と比べず、自分と向き合い、「誰のために生きるのか?」という問いを持ち続けること。その姿勢こそが、自分らしい働き方、そして後悔のない人生をつくる第一歩です。この一冊が、あなたにとっての「人生の軸」を見つけるヒントになれば幸いです。