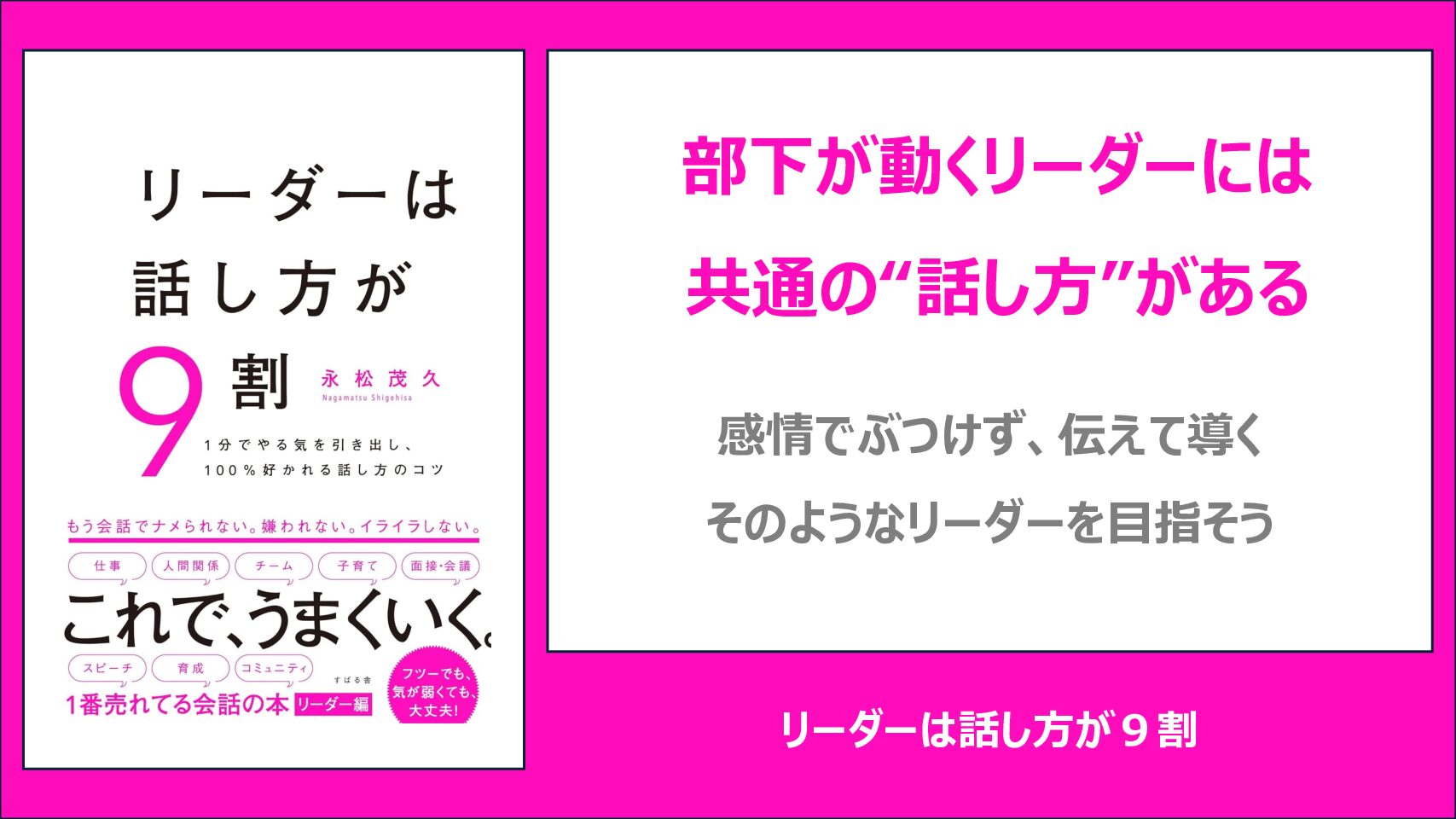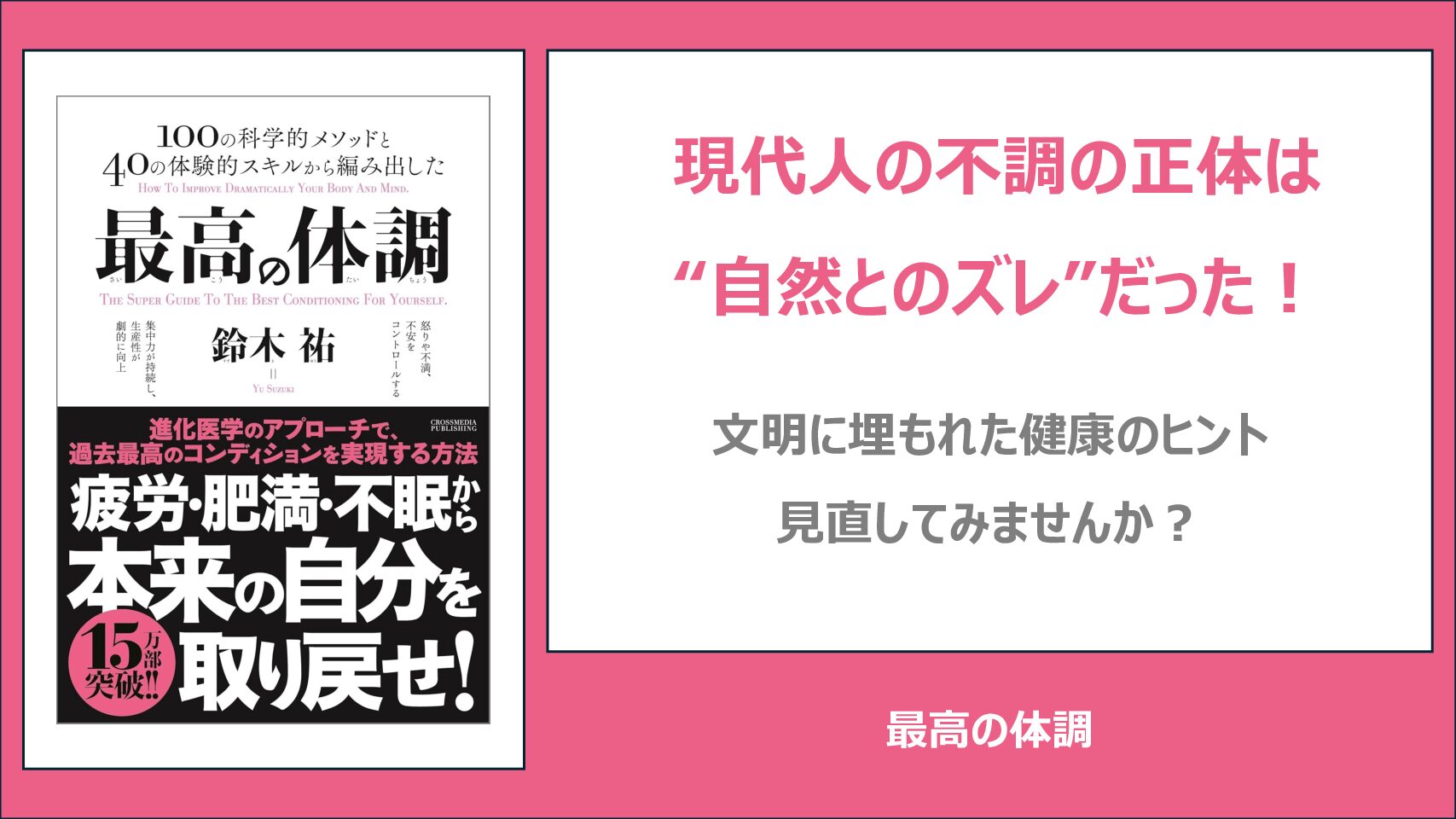この記事はで読むことができます。

ねぇTom、最近職場で後輩に話しても全然伝わってない気がするのよ…。私、将来はリーダーに向いてないのかもって凹んでる。

ああ、それ俺もわかるわ〜。「どうして伝わらないの!?」ってもどかしくなる瞬間あるよな。

注意したのに翌日また同じミスされると、「私の話し方が悪いのか?」って自信なくしちゃう…。

それ、話し方っていうか“伝え方”のコツがあるんだよ。最近読んだ本がめちゃくちゃよかった。

えっ、何それ?興味ある!できれば怒らずに済む方法がいいんだけど…。

まさにそれ。部下の心に響くリーダーの話し方、読むと「なるほど…!」ってなると思うよ。

それはぜひ知りたい!もう「感情で話す」から卒業したいし(笑)
「伝えたのに、なぜか伝わっていない」「部下に嫌われないよう気をつかっても、結局距離が縮まらない」
そんな“話し方の壁”にぶつかっているリーダーは少なくありません。この記事では、誰でも実践できる「相手に届く話し方の極意」を、実例や脳科学の視点をもとに解説します。
「怒る」と「伝える」はまったく別物。感情的な言葉は、脳を“防御モード”にし、内容が届かなくなります。冷静に順序立てて話すことで、部下はあなたの意図を受け取れるようになります。
効果的な会話は一方通行ではなく、キャッチボールが基本。「サーブアンドリターン」のやりとりが、信頼を育て、相手の理解力や共感力を育てます。
「まず共感」→「次に理由」→「最後に提案」。この順番だけで、伝わらなかった話が驚くほどスムーズに部下に届くようになります。

| 著者 | 永松 茂久 |
| 出版社 | すばる舎 |
| 出版日 | 2022年12月7日 |
| ジャンル | 人間関係・コミュニケーション |
「怒る」とは、リーダー自身の感情をそのままぶつける行為であり、「叱る」とは相手の行動を正しい方向に導くためのコミュニケーションです。この2つは似ているようでまったく異なるものですが、実際の現場ではしばしば混同されがちです。
リーダーがイライラや焦りに任せて怒鳴ってしまった場合、たとえ正論を言っていたとしても、相手の脳は“戦うか逃げるか”の状態=防御モードに切り替わってしまいます。すると、内容が一切届かなくなり、ただ威圧されたという記憶だけが残ってしまうのです。
本書では、まず“叱る前に一呼吸おく”ことの大切さを繰り返し説いています。呼吸を整えることで、怒りを抑え、冷静に「伝える」体制に入れるからです。
さらに、感情を整理したうえで「何をどう伝えたいのか」を明確にすることで、相手も“聞く姿勢”になりやすくなります。叱ること自体が悪いのではなく、“どう叱るか”が重要なのです。
リーダーの目的は相手を言い負かすことでも、黙らせることでもありません。相手を理解し、成長へと導くことこそが本来の役割です。冷静で整った言葉には、相手の心を動かし、関係性を築く力があるのです。
本書で紹介されている「サーブアンドリターン」とは、テニスのラリーのような“やりとりの反復”を意味します。相手が「サーブ(発信)」し、リーダーが「リターン(反応)」する。この繰り返しが、相手の脳の成長や信頼関係の構築に大きく貢献します。
ビジネスの現場でもこれはまったく同じで、リーダーが一方的に話すだけでは、部下の思考力や意欲は育ちません。部下の反応をしっかりと受け取り、それに応える姿勢を見せることで、「自分の声が届く」「話を聞いてもらえている」という安心感が芽生えます。
たとえば、ミスをした部下に「なぜこんなことをしたんだ!」と責めるのではなく、「どうしてそう思ったのか教えてくれる?」と問うだけで、相手の脳のモードは受信から発信へと変わります。このやりとりがあることで、部下の中に“自分で考える”力が育ち、関係性もより良いものになります。
リーダーとして「話す力」よりも「反応を返す力」が求められるというのは、意外に思えるかもしれませんが、非常に本質的な視点です。毎日の小さなやりとりの中で、部下の心と可能性を育てていく。これが優れたリーダーが自然とやっている“会話のリズム”なのです。
本書で紹介されている「共感→理由→提案」という3ステップは、叱る場面に限らず、あらゆる対話シーンで効果を発揮するシンプルかつ強力なフレームです。
まず最初にやるべきは、相手の感情に寄り添う「共感」です。「嫌だったよね」「驚いたよね」「悔しかったんだね」といった言葉をかけるだけで、相手は自分の気持ちを理解してもらえたと感じ、心を開きやすくなります。
次に、「なぜそれが困るのか」「どういう理由で問題なのか」を説明する段階です。ここでは感情ではなく事実を冷静に伝えることで、相手も論理的に受け止めやすくなります。
そして最後に、「次はどうしようか?」「こういう方法もあるよ」と提案を加えます。この“建設的な終わり方”が、相手の思考を前向きにし、再発防止への意欲も自然と引き出します。
頭ごなしに叱るのではなく、順序だてて話すことで、相手にとっても「自分で考える」時間が生まれます。このステップを使えば、伝える側の気持ちも整理されるため、無駄な言葉や感情の爆発も抑えることができます。
どれだけ完璧にできなくても、この流れを意識するだけで、伝え方の質は格段に上がるのです。「話すこと」は技術であり、習慣です。だからこそ、この3ステップはすべてのリーダーにとって心強い武器になるはずです。
感情が高ぶったときには、すぐに言葉を発するのではなく、まずその場を静かに見渡しながら3秒ほど深呼吸をしてみましょう。その間に「いま自分は何を伝えたいのか?」を一言で心の中でつぶやいてみるのがおすすめです。
たとえば「誤解を防ぎたい」「行動を変えてほしい」など目的を明確にするだけで、怒りではなく“伝えるモード”へと自然に切り替えることができます。また、手元にマグカップがあれば一口飲んでから話す、席を移動して少し距離を取るなどの“行動の切り替え”も有効です。
これらのワンクッションがあるだけで、言葉選びが変わり、結果として相手との信頼関係を壊さずに話せるようになります。
部下が話しかけてきたり、ちょっとした表情や仕草を見せたときには、それをスルーせず、短くても必ずリアクションを返すように意識しましょう。
たとえば、部下が「ちょっと悩んでて…」と口にしたら、「そうなんだ、どんなこと?」と軽く問い返す。あるいは報告を受けたときに「OK」だけで終わらせるのではなく、「ありがとう、よく気づいてくれたね」といった感謝や称賛を一言添えるのです。
これにより、部下は「自分の存在が認識されている」「ちゃんと見てくれている」と実感し、自己重要感が高まります。LINEやチャットでも「スタンプだけ」で終わらず、短文でも反応の返報を意識するだけで、コミュニケーションの質は格段に上がります。
たとえば、部下が資料の提出期限を過ぎてしまったとしましょう。その際、「なんで遅れたの!?」とすぐに指摘するのではなく、まずは「提出間に合わなかったんだね。きっと忙しかったんだよね(共感)」と受け止めます。
そのあと、「ただ、資料が遅れると会議の準備が間に合わなくなって、全体の進行に影響が出ちゃうんだ(理由)」と状況の影響を伝えましょう。そして最後に、「次からは前日の段階で一報くれると助かるな(提案)」というふうに、今後の改善点を建設的に伝えます。
この順番を守ることで、相手は防御モードにならず、素直に受け入れる態勢になりやすくなります。普段の会話や雑談の中でもこの3ステップを練習しておくと、いざというとき自然に出せるようになります。
リーダーとしての話し方の具体例が豊富で、すぐに現場で試せる内容が多かったです。ただ、やや精神論や抽象的なアドバイスに寄る部分があり、厳密な「即効果」を求める読者には少し物足りないかもしれません。そのため満点には至らず、実用性は4点としました。
平易な日本語で、例え話やストーリーが豊富なため、非常にわかりやすかったです。専門用語も極力避け、誰でもスッと読める構成になっていました。読むストレスが全くなく、迷わず満点評価です。
ビジネスの現場だけでなく、親子、学校、コミュニティなど幅広いシーンで応用できる点は素晴らしいです。ただし、「部下」「リーダー」という前提が強く、あまりリーダーシップに関係ない立場の人には直結しづらいので、厳しめに4点とします。
話し口調がやわらかく、1章ごとのボリュームも適切で、サクサク読めました。適度にエピソードが挟まっていて、読者の集中力を切らさない工夫も見事でした。ストレスフリーな読書体験だったので、ここは満点にしました。
リーダー論や心理学の理論も触れていますが、あくまで「実体験ベース」で、学術的な裏付けは少なめでした。専門書ではなく実用書として書かれているため仕方ないですが、より深い理論背景を求める人には物足りなく感じるかもしれません。そのためここは3点としました。

いや〜今回の本、読んでてちょっとグサッともきたけど、かなりヒントもらえた!

わかる。「話し方で変わる」って、ほんとだったんだなって思ったよ。

「共感→理由→提案」って、やるだけで伝わり方が全然違うのね。

それに「叱る前に深呼吸」、これだけでも家庭も職場も平和になりそう(笑)
リーダーの言葉は、チームの未来をつくります。話し方ひとつで、空気は変わり、部下の成長も加速します。だからこそ、怒るのではなく、“伝える”力を身につけましょう。