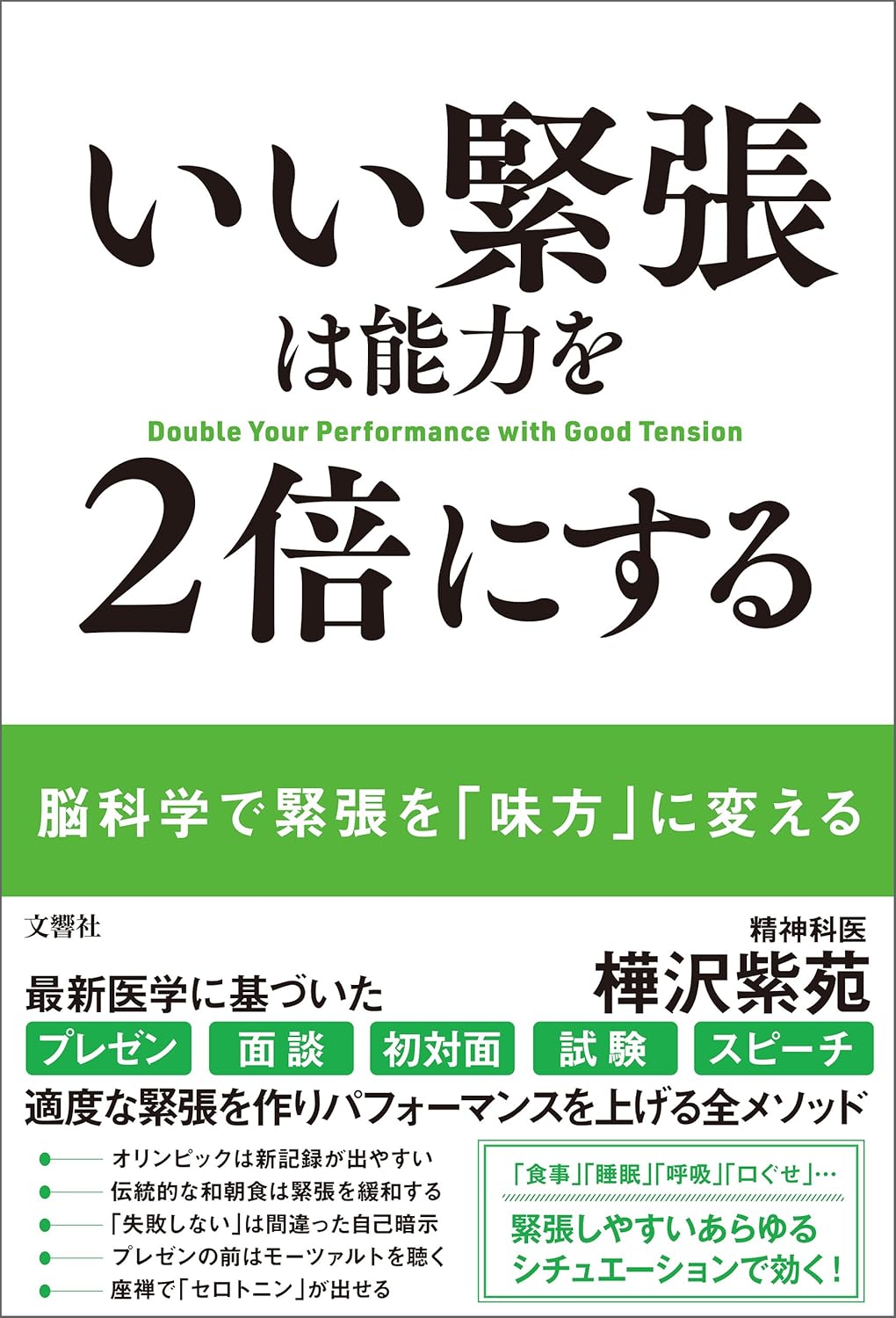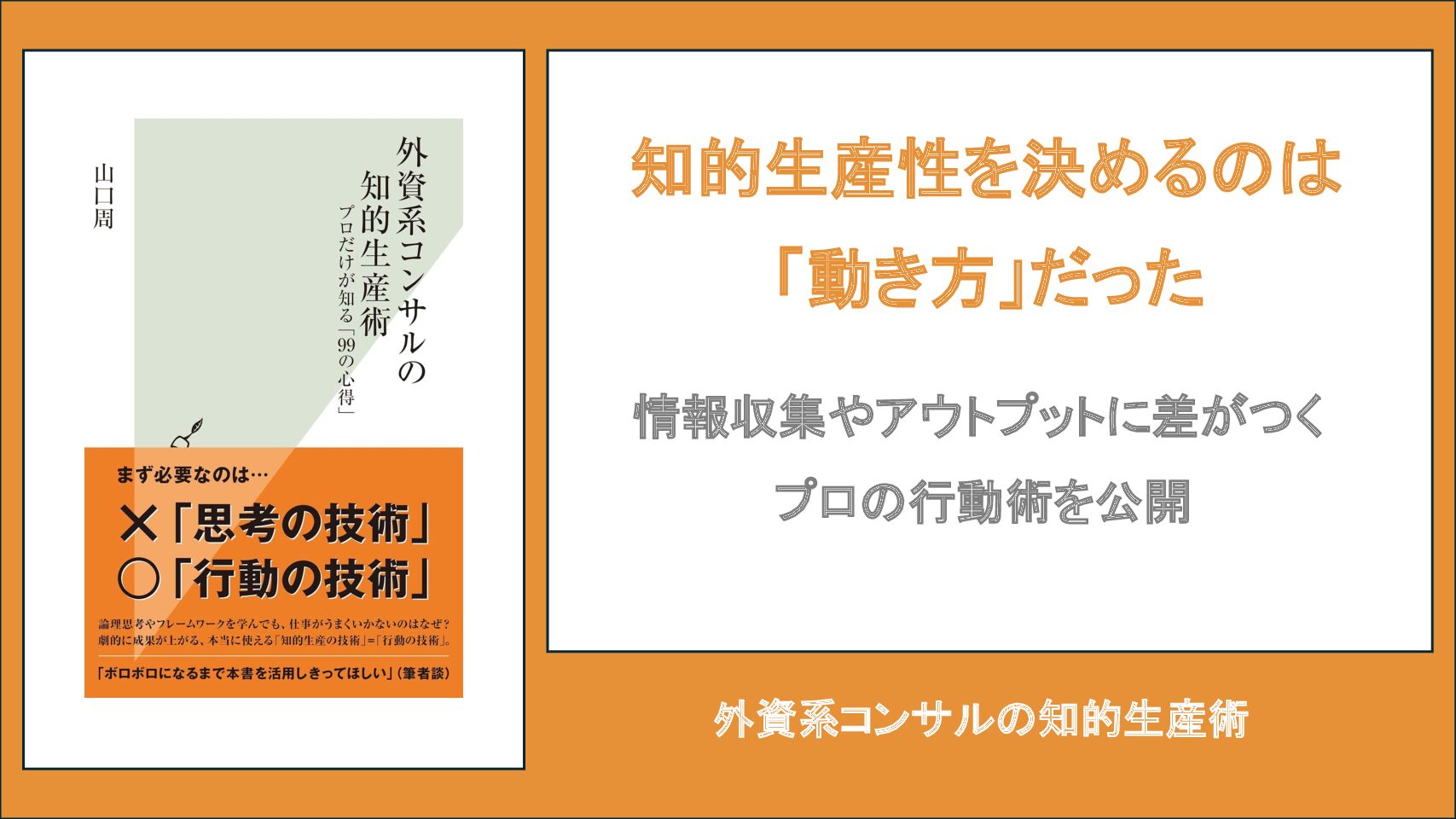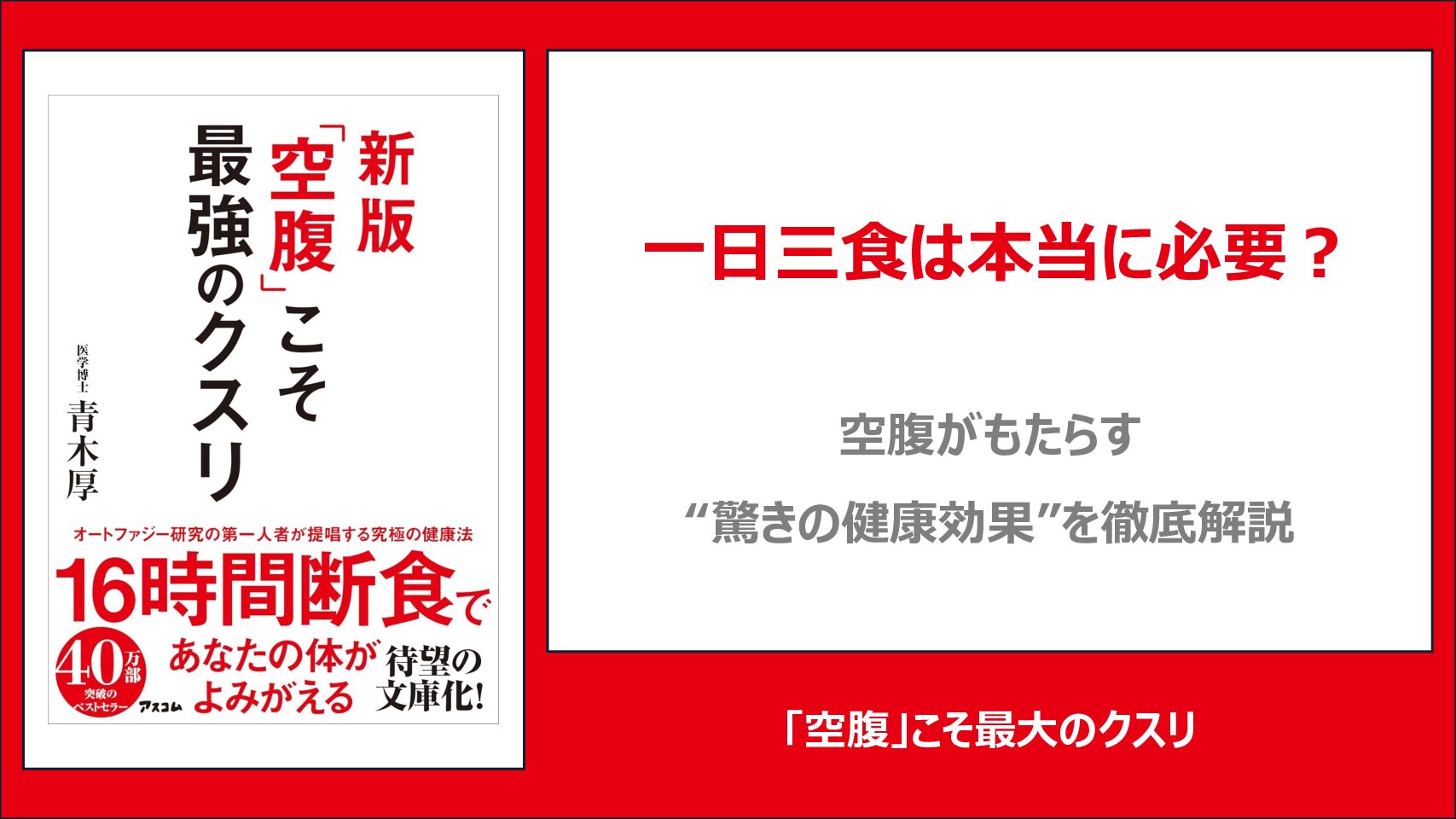この記事はで読むことができます。

ねぇTom、私ってすぐ緊張しちゃうタイプでさ…プレゼンの前とか、頭が真っ白になるんだよね。

それわかる。俺も大事な面接とかで、心臓バクバクして言いたいこと全部吹っ飛んだことあるよ。

この間なんて、初対面の人と話すだけで手が震えてさ。なんでこんなに緊張しやすいんだろうって、自分にがっかりしちゃった。

俺もよく「緊張しないように」って自分に言い聞かせてるけど、逆に余計に緊張しちゃうんだよなぁ。
「緊張するな」と言われれば言われるほど、余計に緊張してしまう…。そんな経験、あなたにもありませんか?
大事なプレゼン、面接、試験、初対面の会話――人生を左右する場面ほど、緊張は私たちを襲います。多くの人が「緊張=悪いもの」と思い込んでいますが、それは大きな誤解。本当に必要なのは、緊張を「なくすこと」ではなく、「コントロールすること」。
本記事では、精神科医・樺沢紫苑氏の著書をもとに、緊張を敵ではなく“最強の味方”に変える脳科学的アプローチをご紹介します。誰でも実践できる具体的な方法が満載です。
多くの人が緊張を「克服すべきもの」と捉えていますが、それは思い込みにすぎません。緊張には科学的なメカニズムがあり、正しく理解すれば味方にできます。
深呼吸や姿勢の調整、笑顔のトレーニングなど、誰でもすぐに実践できるテクニックが多数紹介されています。脳科学や自律神経の仕組みに基づいた方法だからこそ、効果が高いのです。
実は、緊張しやすい人は「エネルギーの塊」。それを適性緊張に変えられれば、プレゼンでも試験でも驚くほどの成果を出せるようになります。
緊張という感情は、多くの人にとって厄介なものと思われがちです。実際、「緊張しすぎて失敗した」という経験を持つ人は少なくありません。しかし本書では、緊張そのものが悪いのではなく、「過緊張」や「リラックスしすぎ」が問題だと明確に示されています。
最も力を発揮できる状態は、適度な緊張――つまり「適性緊張」です。これは、ヤーキーズ・ドットソンの法則としても知られ、覚醒度とパフォーマンスの関係を示す心理学の基本法則でもあります。実験では、電気ショックの刺激が適度な時に最も高い学習効果が得られたという結果も出ており、これは人間のパフォーマンスにも応用できるとされています。
実際、オリンピックの選手たちが緊張する場面で新記録を出すのは、「緊張=集中」のスイッチが働いているからです。つまり、緊張は集中力や判断力、筋肉のパフォーマンスを最大限に引き出す「味方」なのです。緊張を恐れず、「よし、来たな」と捉えることで、気持ちは大きく変わります。
本書の中では「緊張のスピードメーター」を使って、自分の状態を数値化し、過不足のないテンションに調整する方法も紹介されており、感情を客観視する力が養われます。緊張を“敵”ではなく“風向きの良い追い風”として受け入れられれば、これまでとは全く違う自分を引き出すことができるでしょう。そう、緊張は「潰すもの」ではなく、「利用するもの」なのです。
「緊張はコントロール不能なもの」という思い込みが、多くの人に根強くあります。しかし、著者はその考え方に対して「科学的な視点を持てば緊張は必ずコントロールできる」と断言します。
本書では、緊張の原因は「交感神経の過剰な働き」「セロトニンの不足」「ノルアドレナリンの過剰分泌」の3つに集約されると説明されており、非常に明快です。この3つの要因に対してそれぞれ対処法が用意されており、自分に合った方法を選ぶことで緊張を根本から解決できる仕組みになっています。
交感神経に関しては、深呼吸や笑顔、ストレッチなどの簡単な習慣で副交感神経優位に切り替えることが可能です。セロトニンは、朝日を浴びる、リズム運動、バナナや納豆ご飯といった朝食で活性化することができます。ノルアドレナリンの過剰は、イメージトレーニングやポジティブワードの習慣、準備・予行演習によってコントロールが可能です。
つまり、緊張というのは曖昧な感情ではなく、特定の脳内反応によって引き起こされているということが科学的にわかっています。だからこそ、闇雲に「落ち着こう」「緊張するな」と自分に言い聞かせるのではなく、身体と脳の仕組みに合ったアプローチが必要なのです。
このように原因を特定できれば、対処も非常にシンプルになります。「緊張の正体がわかれば、恐れは消える」という言葉の通り、自分が今どの状態にあるかを分析し、必要な対応を取れることが、自己コントロールの鍵となります。
どんなに優れた緊張緩和法も、「ここぞ」という場面で実行できなければ意味がありません。本書では、緊張を味方にするために必要なのは「練習」ではなく「習慣化」だと繰り返し強調されています。
特に「深呼吸」は最強の緊張コントロール術とされており、正しい方法で毎日行うことで、副交感神経のスイッチをいつでも入れられる状態にしておくことが必要です。また、笑顔のトレーニングや姿勢を正す習慣も、脳内物質のバランスを整える重要な手段となります。試験開始1分前やプレゼンの冒頭など、緊張のピークが訪れるタイミングで自然と対応できるようになるには、日常のルーティーンの中に小さなトレーニングを組み込むことが効果的です。
たとえば、電車内での深呼吸、鏡を見ながらの笑顔練習、朝の光を浴びる散歩など、どれも数分で済むものばかりです。しかもこれらの習慣は、緊張だけでなくメンタルの安定や集中力の向上にも繋がるため、一石三鳥の効果があります。
緊張は「コントロールできる技術」ではなく、「整えておく体質」だという視点の転換が重要なのです。だからこそ、「やろう」と思ったその日からコツコツ続けることで、あなたの脳と身体は確実に変わっていきます。3ヶ月続けることでセロトニンの自己調整機能が整うという科学的根拠もあるため、継続による成果は保証されています。
何より、「準備をしている」という安心感が、自信と落ち着きを生み出します。つまり、緊張に強くなるための最大の秘訣は、日常の中に“緊張に備える習慣”を根づかせることなのです。
まずは「緊張は悪者ではない」と言葉にして、毎日声に出してみましょう。手帳やスマホの待ち受けに「緊張=味方」と書いておくのも効果的です。プレゼン前や試験前に「緊張してきた、よし、力を出せるぞ」と意識的に思考を変換しましょう。反射的にネガティブにとらえない“習慣”を作ることが重要です。
朝は5分の散歩で日光を浴び、朝食に納豆ご飯やバナナを取り入れてセロトニンを活性化しましょう。人前に立つ前は「手先ブラブラ」「肩ストン」「1分深呼吸」などで副交感神経優位に切り替えます。大事な場面前はポジティブな一言「私はできる、大丈夫」と唱える習慣をつけましょう。自分の状態を数値化し「今は70キロくらいかな」と冷静に観察する癖も役立ちます。
電車内や歯磨き中など、毎日の“ついで時間”に1分深呼吸を習慣づけてください。鏡を見るタイミングで自然に笑顔を作る「笑顔トレ」も、毎日の癖にしましょう。プレゼンや試験本番前は「1分間呼吸法」や「満面の笑み+第一声」をルール化しておくと安心です。こうした小さな積み重ねが、本番での落ち着きに直結します。
本書では緊張をコントロールするための具体的な方法が豊富に紹介されており、実生活ですぐに試せる技法が多く含まれています。特に呼吸法や姿勢、笑顔トレーニングなどは汎用性があり、状況を選ばず使えます。ただし、一部の方法は準備や継続的なトレーニングが前提となっているため、忙しい読者にはすぐ活かしにくい部分もあります。
内容は豊富な比喩と体験談で補足されており、読者にとって共感しやすく、理解を助ける工夫が随所に見られます。ヤーキーズ・ドットソンの法則など、科学的な理論も一般向けに噛み砕いて説明されています。しかし一部に情報過多で整理が追いつかない章もあり、初心者には少し長く感じるかもしれません。
本書はプレゼン、試験、人間関係など様々な場面における「緊張」に対応できるように工夫されています。読者の年齢や職業を問わず、誰でも自分の課題に当てはめられる内容になっている点は高く評価できます。各章がそれぞれ独立して機能するため、必要な部分だけ読むという使い方も可能です。
文体は語りかけるようにやさしく、親しみやすい一方で、繰り返しや冗長な表現が多く、全体の構成がやや冗長に感じられます。段落ごとのまとまりに欠ける部分や、感嘆符が多用されるなど、ビジネス書としての洗練さはやや劣ります。章ごとに要点を明示するなど、整理されていればより読みやすくなるでしょう。
著者が精神科医であることから、脳科学や心理学に基づいた理論的な裏付けがしっかりとされています。科学的研究や臨床経験を元にした解説が多く、信頼性は高いです。ただし、専門用語や論文の引用が少なく、あくまで一般向けに調整された内容のため、専門書としての深さは限定的です。

いや〜今回の内容、読んでて「それ私じゃん!」って思う場面が多すぎて笑っちゃったよ。

わかる。「緊張は悪いもの」って思い込んでたけど、実は力になるって発想は新鮮だったな。

私、今日からさっそく「スピードメーター」イメージして緊張を調整してみようかな。まずは“70キロ”目指して(笑)

俺もまずは満員電車の中で深呼吸チャレンジしてみるわ。地味だけど、効きそうだもんな。
緊張は、決してあなたを邪魔する存在ではありません。正しく理解し、日常に小さな工夫を取り入れるだけで、そのエネルギーは大きな味方になります。
本番に強くなりたい。自分の力をちゃんと出したい。
そう願うあなたにこそ、今すぐ始めてほしい緊張コントロールの習慣。「緊張してきた…」そう感じたときこそ、成長のチャンスです。