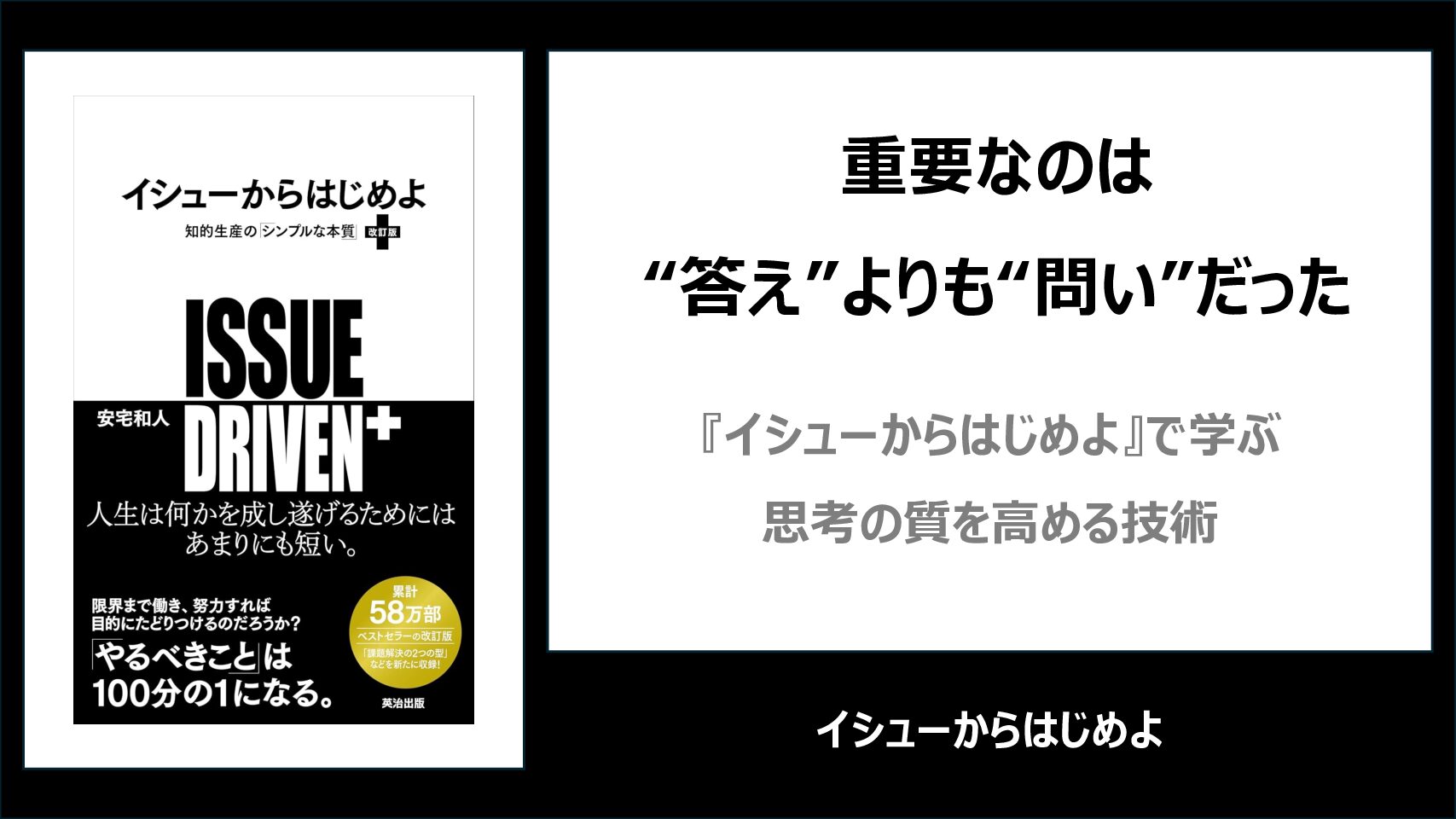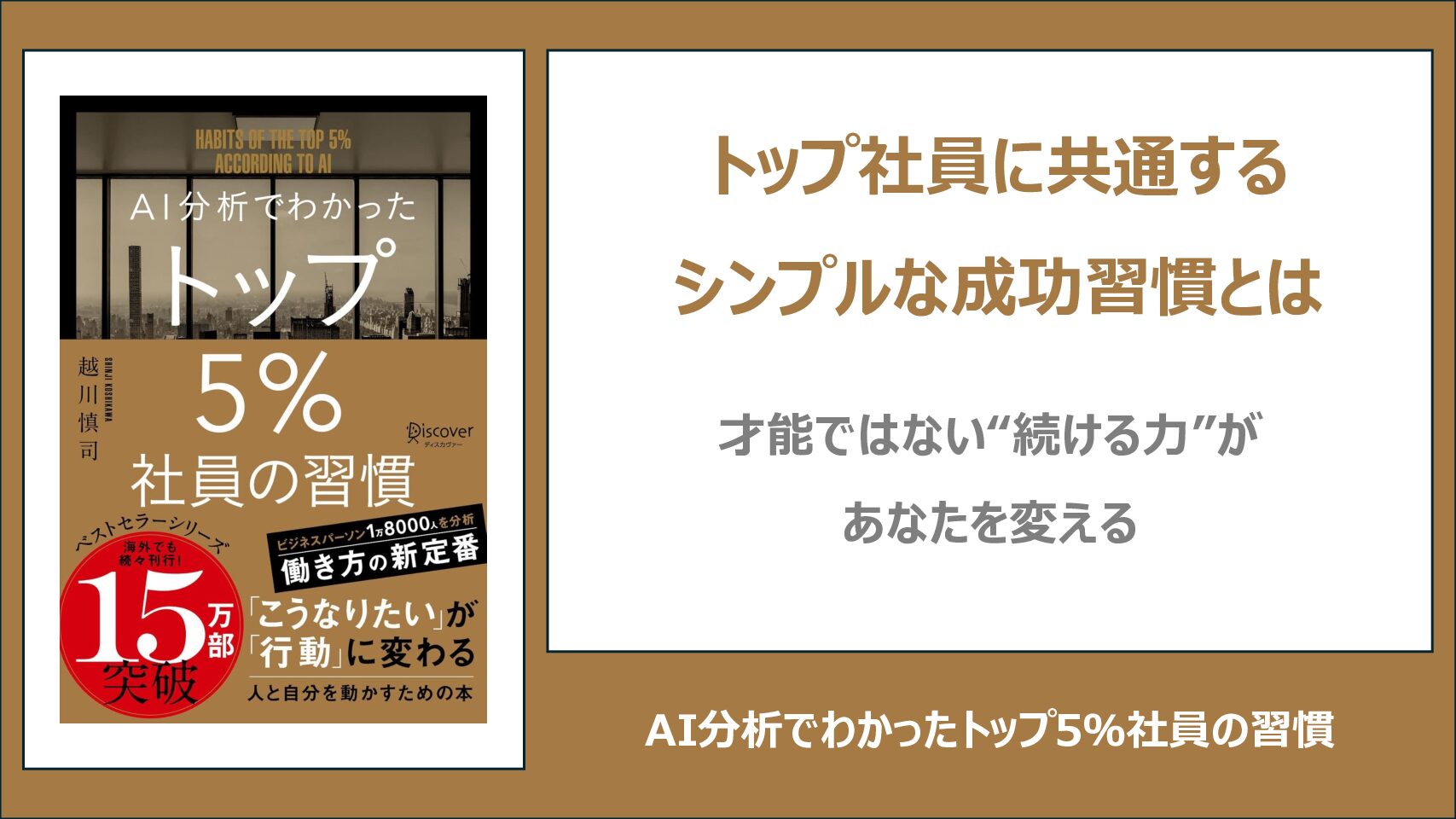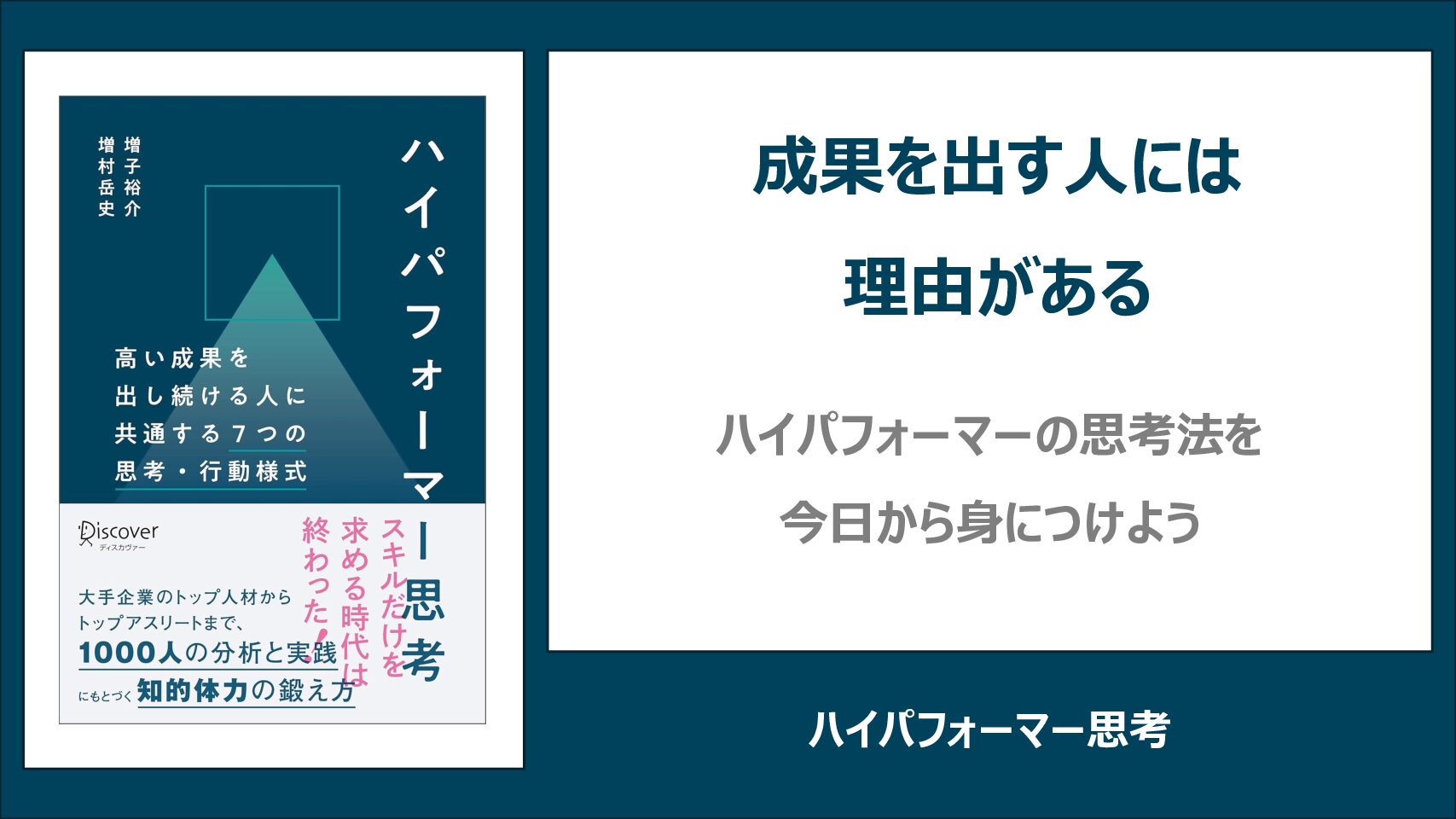この記事はで読むことができます。

最近、やることが多すぎて、どれから手をつけていいかわからないのよね…。

それって、「イシュー」になってないのかもしれないよ。

イシュー?何それ?重要そうなことからやってるつもりなんだけど…。

実は、重要そうに見えることと、本当に重要なことって違うんだ。『イシューからはじめよ』って本を読んだら、すごく参考になったよ。
ビジネスでも日常生活でも、私たちはたくさんの課題やタスクに囲まれています。しかし、本当に取り組むべき“重要な問題=イシュー”に向き合えている人は意外と少ないのです。
『イシューからはじめよ』は、膨大な情報や選択肢の中から「何に注力すべきか」を明確にするためのフレームワークを教えてくれる一冊。本記事では、イシューを見極め、より少ない努力で大きな成果を得るための考え方を紹介します。
イシューとは「本質的で、かつ自分が解決すべき課題」のことです。数ある情報や業務の中から、価値ある問いに絞り込む力が求められます。
時間やリソースが限られる中で、どの問題に取り組むかを判断するスキルが成果を左右します。問題の重要性と解決可能性の2軸で分類し、価値のある問いを特定します。
やみくもに考えるのではなく、論点を整理し、仮説思考で効率的に進めることが鍵です。情報収集の目的を明確にし、議論や資料の質も向上させます。

| 著者 | 安宅 和人 |
| 出版社 | 英治出版 |
| 出版日 | 2024年9月22日 |
| ジャンル | 生産性・時間管理 |
どんなに優れたアイデアや手法を持っていても、それが的外れな問題に対して使われていれば、大きな成果にはつながりません。だからこそ、最初に「自分が今、本当に解くべき問いは何か?」を明確にする必要があります。
本書では、それを“イシュー”と呼び、「本質的かつ、自分が取り組むべき課題」と定義しています。つまり、自分の仕事や目標と密接に関係していて、答えを出すことに意味がある問いがイシューです。
たとえば、資料を作る、会議を開く、プレゼンを行う…といったタスクも、「何のためにやっているのか?」という問いに戻って考えると、余計な作業をカットできることが多いのです。イシューを明確にすることは、仕事の効率を高めるだけでなく、無駄な努力を避け、成果を最大化するための出発点になります。
そしてその定義は人によって違います。同じ会社でも、経営者と現場スタッフでは解決すべきイシューは異なります。だからこそ、自分の役割や目的に応じて「この仕事で本当に問うべきことは何か?」と繰り返し問い直すことが重要です。
イシューが曖昧なまま行動を起こしても、途中で方向性がブレて迷走することが多くなります。逆にイシューを定義した上で動けば、自分の判断軸が明確になり、あらゆる行動が一貫性を持ちます。
また、チームで働く場合も、「私たちは何の問いに答えようとしているのか?」を共有することで、コミュニケーションロスが減り、より建設的な議論が可能になります。イシューとは単なる疑問ではなく、「取り組むに値する問い」であり、そこから考え始めることが、質の高い仕事の第一歩なのです。
私たちの手元には、常に多くの課題や問題が並んでいます。その中から何を優先するかを見極めるのが、成果を左右するカギです。
本書では、解くべき問いを「重要性」と「解決可能性」の2軸で評価することを勧めています。重要性とは、その問いの答えが得られたときにどれだけインパクトがあるか、すなわち意思決定や業務成果に大きく寄与するかという視点です。解決可能性は、その問いに対して現時点の自分(またはチーム)が答えを出せるか、リソースがあるか、という現実的な視点です。
例えば、「今後10年の業界動向を予測する」という問いは重要かもしれませんが、具体的なデータが少なければ解決可能性が低く、時間ばかりかかるリスクがあります。反対に、目の前の小さな課題はすぐに解決できるかもしれませんが、それが重要でなければ優先度は低くなります。
この2軸を使ってマトリクスを作ると、自分が今取り組むべき「価値ある問い」が見えてきます。特にビジネスの現場では、重要性が高く、かつ今すぐ解ける問題に集中することが、成果を出す近道です。また、重要だが解決可能性が低い問題は「将来のイシュー」として保留にしておく判断も必要です。
感情や上司の一言に振り回されるのではなく、冷静なロジックで問いの優先順位を判断することが、時間と労力の無駄を減らします。この選定プロセスを習慣化すれば、意思決定のスピードも質も上がり、迷いのない行動ができるようになります。
現代は情報があふれる時代です。インターネットや社内データベースを使えば、どんな情報も手に入りそうな気になります。しかし、本書が強調しているのは、「情報収集の前に目的を明確にすること」です。つまり、ただ集めるのではなく、「この情報はどんな仮説を検証するために必要なのか?」を意識する必要があります。
目的のない情報収集は、調べれば調べるほど混乱を招き、時間だけが無駄に過ぎていきます。逆に、仮説を立てた上で情報を集めれば、必要な情報が何かが明確になり、検索やヒアリングの効率が格段に上がります。
例えば、「このサービスが若年層に人気があるのはSNS経由の流入が多いからではないか」という仮説を立てれば、SNSデータや年代別のアクセス解析を中心に調べることになります。このように、情報はあくまで手段であり、目的に従属するものです。
また、情報分析でも同じことが言えます。どんなに高度な分析をしても、「何を証明したいのか」が曖昧であれば、意味のあるアウトプットにはなりません。良質な仮説を持つことは、レポートやプレゼンの説得力にも直結します。
さらに、本書では「解のイメージを持ってから情報を集める」ことも推奨しています。つまり、最終的にどういう答えが出ると意味があるのか、出口を想定してから動くということです。このプロセスは時間を短縮するだけでなく、チームとの認識共有もスムーズになります。情報に流されるのではなく、情報を使いこなすためには、この“目的先行型”の姿勢が不可欠です。
日々の仕事や生活の中で、「この作業はどんな問いに答えようとしているのか?」を自問しましょう。何かを始める前に、5分でも良いので紙に「何を解決したいのか?」と書き出してみるのがおすすめです。その問いに明確に答えられない場合は、まずイシューを掘り下げる時間を取りましょう。
リスト化した課題や悩みに対して、「重要性」と「解決可能性」の2軸でマトリクスを作りましょう。縦軸に重要性、横軸に解決可能性を取ると、自分が今向き合うべき問いが一目瞭然になります。重要だが今は解けない問いは、保留フォルダに入れておきましょう。
資料作成や会議準備などで情報を集めるときは、「何の仮説を検証するためか?」を紙に書いてから作業に取り掛かってください。仮説→必要な情報→調査、という流れを習慣化することで、情報収集がぐっと効率的になります。
本書はビジネスや研究など知的生産において「成果を出すこと」に直結する実践的なフレームワークを提示しています。「イシュー度」や「解の質」など、仕事の選び方から取り組み方、アウトプットの磨き方まで、実用性が非常に高いです。著者自身の豊富な経験と具体例が理論を裏付けており、すぐに仕事に活かせる内容になっています。特に、「犬の道を避ける」「悩むな、考えろ」というメッセージは、日々の行動指針として有効です。
論点は明確で、構造的に展開されていますが、内容の密度が高く、一読で全容を掴むのはやや難しい面があります。専門用語も丁寧に説明されていますが、読者の知的体力がある程度求められます。例示や比喩は豊富で、抽象概念を具体化しようという工夫は随所に見られます。とはいえ、知識や経験が浅い読者にとっては、最初の導入やフレームワークの理解に時間がかかるかもしれません。
知的生産を行うすべての人に役立つ内容で、業種や職種に関係なく応用可能です。ビジネス、研究、教育、政策などあらゆる分野で活用できる「考え方の原理」を扱っている点は非常に価値があります。一方で、実務経験が少ない人や現場感覚に乏しい人には、抽象度がやや高く感じられる場面もあります。読者の前提知識や状況により、実行力に差が出ることがあり、万人に同じ効果が出るわけではない点で満点には至りません。
文章は誠実で丁寧に書かれていますが、情報量が非常に多く、集中して読まないと消化しきれません。話が時折脱線したり、自身のエピソードが長く続く部分があり、テンポがやや重くなる印象があります。また、意識的に構造化されてはいるものの、章立てや小見出しのメリハリがやや弱く感じられる部分もあります。結果として、一気読みよりも分割して丁寧に読むスタイルが求められる書籍です。
著者のバックグラウンド(コンサルティング・脳神経科学)に裏打ちされた内容は深く、多角的な視点が盛り込まれています。「仮説ドリブン」「イシュー分析」など、実務の中でも高度な思考を要する概念を取り上げており、専門的と言えます。ただし、学術的な厳密さや論文的な根拠提示までは追求されていないため、「理論の体系化」という点では少し軽めです。ビジネス実務書としては極めて高い専門性を持つ一方、学術書とは一線を画します。

なるほど~!最初に「何を解くべきか」をはっきりさせるのがポイントなんだね。

うん、問題を間違えたら、どんなに頑張っても意味がないからね。

さっそく、今日のタスクもイシューで整理してみるわ。

いいね!その視点があるだけで、仕事の質もスピードも上がるよ。
『イシューからはじめよ』は、「考える前に考えるべきこと」を教えてくれる実践的な一冊です。何かに取り組むとき、その前に「それは本当に解くべき問いなのか?」と立ち止まるクセを身につければ、あなたの仕事や人生はぐっと洗練されたものになります。