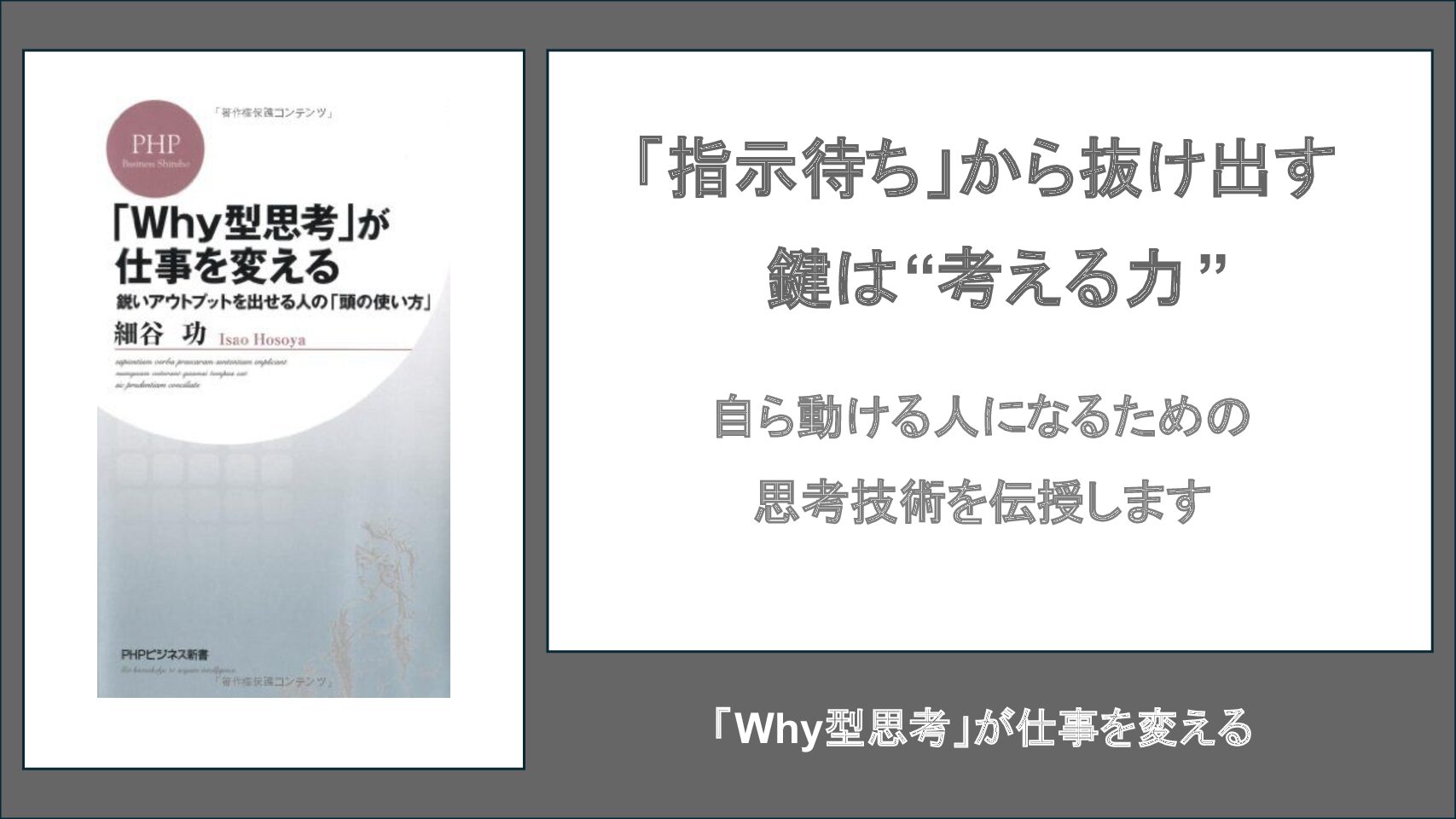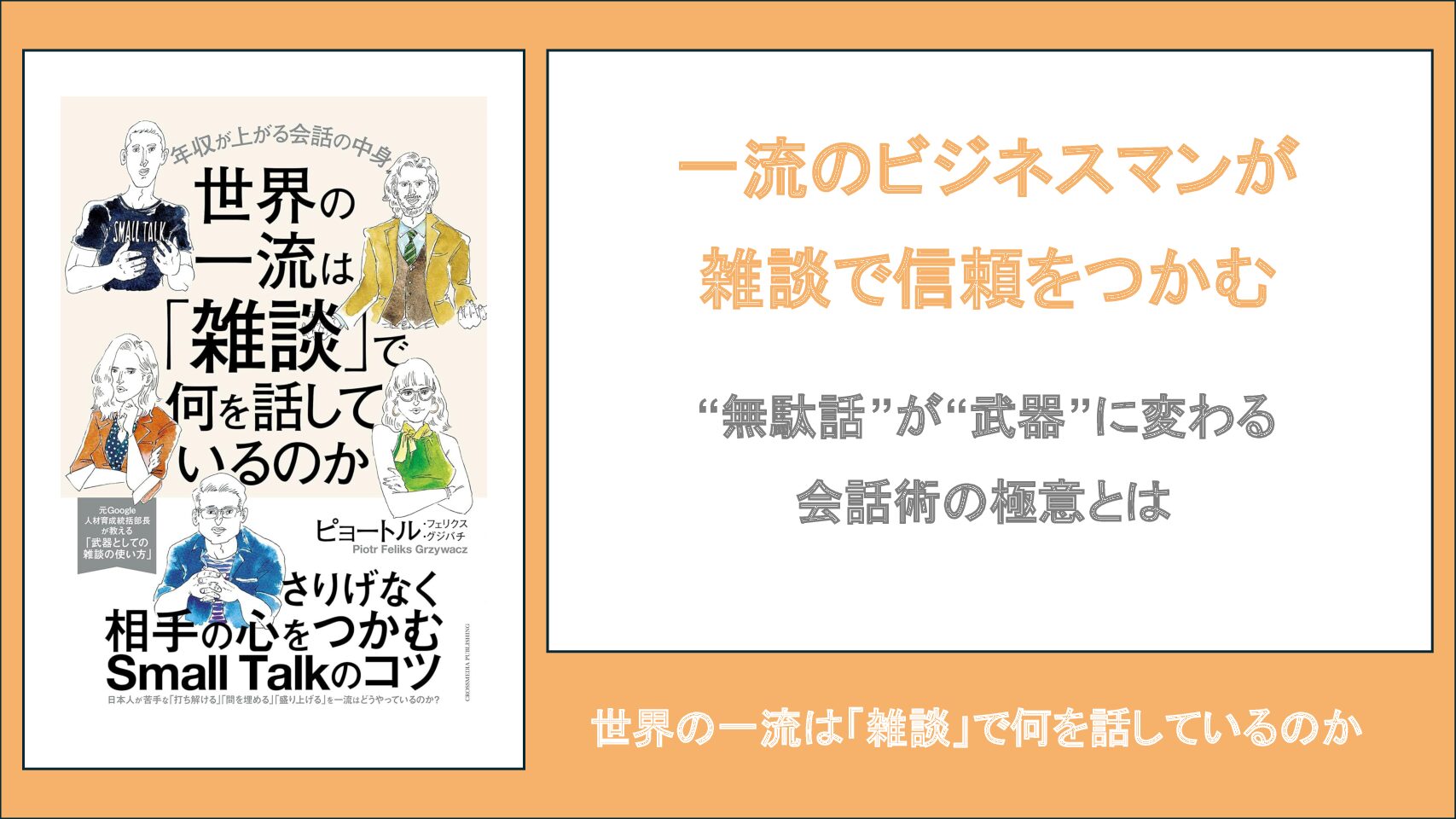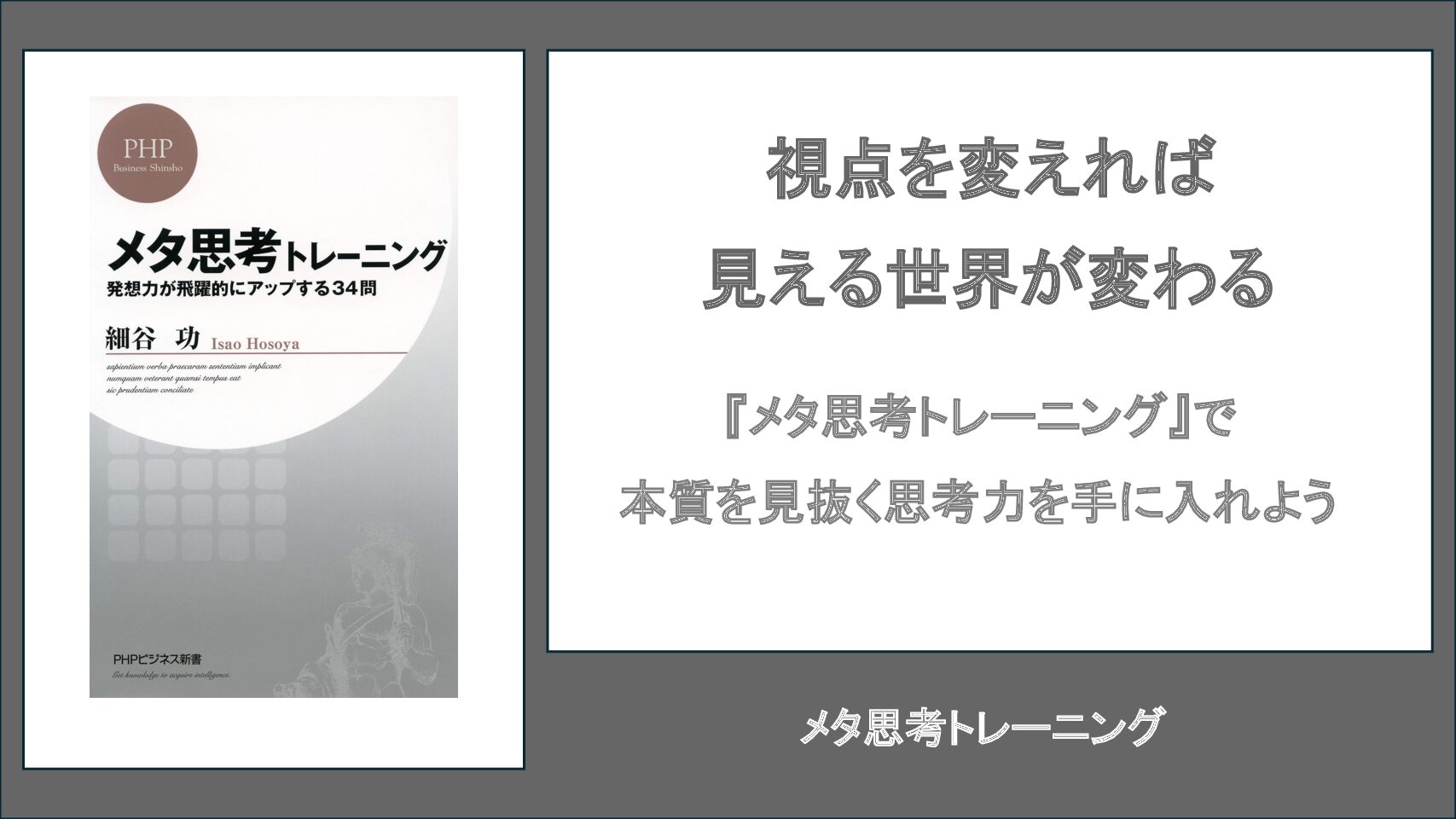この記事はで読むことができます。

最近さ、仕事で「もっと自分で考えて動いて」って言われることが増えてきたのよね。

それってつまり「指示待ち人間」って思われてるってことかもよ?

うっ…図星かも。でも、どうしたら自分から動けるようになるのか分からないの。

だったらこの本、『「Why型思考」が仕事を変える』を読んでみたら?自分で考えて行動する力が身につくらしいよ。
現代のビジネス環境では、「言われたことをやるだけ」では評価されにくくなっています。主体的に考え、自ら行動する力が求められる中で、多くの人が「どうやって考えるか」を学ばずに大人になります。
そんな“思考停止”状態から脱却するための鍵が詰まった一冊が『「Why型思考」が仕事を変える』。本記事では、この本の要点を分かりやすく解説し、明日から使える思考法を紹介します。
物事の本質を見抜くためには、表面の事象だけにとらわれず、「なぜ?」を掘り下げる習慣が不可欠です。これにより、問題の根本原因が明確になり、的確なアクションにつながります。
仮説を立てて検証するプロセスは、仕事のスピードと精度を劇的に高めます。思いつきではなく、意図的に考える訓練をすることで、説得力ある提案や行動が可能になります。
指示を待つのではなく、自分で「何をすべきか」を判断するには、自ら問いを立てる思考法が有効です。思考の型を身につけることで、誰でも主体的に動けるようになります。
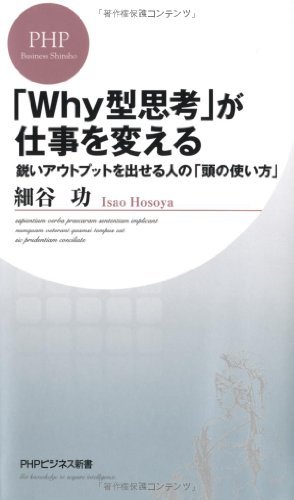
| 著者 | 細谷 功 |
| 出版社 | PHP研究所 |
| 出版日 | 2010年8月19日 |
| ジャンル | スキルアップ・自己研鑽 |
問題を解決しようとするとき、私たちはつい表面的な原因だけを見て終わらせてしまいがちです。しかし、そのアプローチでは一時的な対処にとどまり、同じ問題が何度も繰り返される恐れがあります。
そこで重要になるのが「なぜ?」という問いを繰り返すことです。これは「5回のなぜ」とも呼ばれる技法で、トヨタが品質管理の現場で使っていることでも知られています。
たとえば「納期に間に合わなかった」という問題に対して、「なぜ?」を繰り返していくと、「作業工程に遅れがあった」「作業工程の見積もりが甘かった」「過去のデータを活用していなかった」など、原因が深掘りされていきます。1回だけの「なぜ?」では本質にはたどり着けません。3回、5回と繰り返すことで、問題の根本構造が明らかになるのです。
このプロセスは一見手間のように思えるかもしれませんが、後々の無駄なトラブルや再発防止の効果を考えると、非常に効率的な方法です。また、この思考法はビジネスだけでなく、日常生活や人間関係の中でも活用できます。
たとえば「子どもが宿題をしない」という問題も、「なぜ?」を繰り返せば、「やり方が分からない」「疲れている」「親が忙しすぎて関われていない」など、思わぬ要因が見えてくることがあります。日々の小さな問題にもこの問いを習慣化することで、物事を見る目が養われます。そして本質を捉えた解決策を打ち出せるようになるのです。最終的に、「考える力」が身につき、周囲からも信頼される存在へと変わっていけるでしょう。
仮説思考とは、「こうではないか?」という予想を立て、それを検証していくという考え方です。この思考法の最大のメリットは、行動のスピードが上がることです。
情報が完璧に揃うまで待つのではなく、不完全な状態でも予測をもとに動くことができるのです。現代のビジネスは変化が激しく、のんびり構えているとすぐに競合に先を越されてしまいます。そこで有効なのが仮説を立てて検証するという流れです。
たとえば「新商品の売れ行きが悪い」という現象に対して、「ターゲット層に届いていないのでは?」という仮説を立て、それに基づいて販路や広告内容を見直す、というアクションが可能になります。仮説が外れていた場合でも、それを踏まえて次の仮説を立て直せばよく、試行錯誤の中で精度が上がっていきます。
このように仮説思考は「考えながら動く」スタイルを自然に身につける手助けとなります。また、仮説を持つことでチームとのコミュニケーションもスムーズになります。なぜなら「私の仮説はこうです」と伝えることで、議論のスタート地点が明確になるからです。
さらに、仮説に基づいた行動は、後で振り返りやすくなります。「このとき、こう考えたからこう行動した」という記録が思考の軌跡として残るため、学びが蓄積されるのです。仮説思考はセンスではなく、訓練によって誰でも身につけられるスキルです。日常の小さな選択でも仮説を立ててみるクセをつけることで、あなたの行動力と判断力は大きく進化していきます。
「主体的に動けない」という悩みを抱える人の多くは、実は「どう考えればいいのか分からない」ことに原因があります。つまり、思考の方法を知らないまま「自分で考えろ」と言われている状態なのです。だからこそ、まず取り組むべきは「思考の型」を習得することです。
本書では、フレームワーク(例:ロジックツリー、MECE、3C分析など)や「問いを立てる技術」など、具体的な思考の型が紹介されています。たとえばロジックツリーを使えば、複雑な問題も「構成要素は何か?」「それぞれの要素の原因は何か?」と整理しながら考えられます。問いを立てることで、問題の焦点が定まり、考えるべきポイントが見えてきます。
このように思考のプロセスが明確になると、自分で判断するための材料も増え、自信を持って行動に移せるようになります。型を知っていれば、「とりあえず様子を見る」「誰かが言ってくれるのを待つ」といった受け身の姿勢から脱却できます。
また、思考の型は繰り返し練習することで自然に使えるようになります。最初は時間がかかっても、使っているうちに自動的に頭の中で整理できるようになっていきます。主体性は、「考える習慣」が土台となって初めて育つものです。
だからこそ、最初は型を真似してでもいいから実践してみることが大切です。「考え方のレシピ」を持つことで、行動力は後から自然とついてくるのです。そして、それが周囲からの信頼や成果にもつながっていくのです。
日々の仕事や生活で問題が発生したときに、必ず「なぜ?」と5回問い直す習慣を取り入れましょう。メモ帳やノートに「問題」と「なぜ?」をセットで書き出すことで、思考が整理されやすくなります。
時間があるときに、過去の失敗や課題を振り返って「なぜ?」を深堀りする練習をするのも効果的です。初めは難しく感じるかもしれませんが、繰り返すことで思考が深まる感覚が身についていきます。
何かを始める前には、まず「仮説=自分なりの予想」をノートに一言で書いてみましょう。たとえば「このプレゼンは反応が良いはず」といった簡単なもので構いません。その後、実行した結果を振り返り、仮説が正しかったかどうかを確認するようにします。このサイクルを続けることで、仮説と検証の精度が高まり、実践的な思考力が育ちます。
ロジックツリーやMECEなどの思考フレームワークを、自分のノートや議事録に活用してみましょう。具体的な課題や案件に当てはめながら繰り返し使うことで、型が自然と身についていきます。
たとえば「この企画の目的は?」「成功の要因は何があるか?」など、毎回同じ問いを立てることで思考が安定していきます。最初は教科書通りでも良いので、迷ったときに立ち戻れる「思考の地図」を持つことを意識しましょう。
本書はビジネス現場でありがちな「思考停止状態」を改善するための明快なフレームワークを提示しており、管理職や若手ビジネスパーソンにとって非常に有用です。特に「そのままくん」と「なぜなぜくん」という擬人化による対比は、現場での思考や行動の指針としてすぐに使える実践的な観点を与えてくれます。ただし、「実際にどうすればよいか」の方法論に関してはやや抽象的で、誰もが即実行できるレベルまで細分化されているとは言い難いため、1点減点しました。
WhyとWhatの違いを「人形と人形師」などの比喩で説明し、「見える世界」と「見えない世界」という視点で読者の認知を促す構成は非常に分かりやすいです。例え話や企業内のあるあるケースがふんだんに紹介されており、読み手は自分の経験に引き寄せながら理解を進められます。専門用語も少なく、難解な概念も平易な言葉で丁寧に解きほぐされているため、読者の理解を妨げる要素がありません。
本書の考え方は教育、行政、日常生活など幅広い領域で応用可能です。ただし、記述のほとんどがビジネス、特に日本的な組織文化を前提としており、業種や文化圏が異なる環境ではそのまま適用するには工夫が必要です。また、Why型思考の重要性が強調される一方で、What型思考の価値や必要性については限定的にしか言及されていないため、バランスという点では課題が残ります。
語り口は非常に親しみやすく、例え話も豊富で、テンポよく読み進めることができます。擬人化されたキャラクターを通じて読者の関心を惹きつける工夫も評価できます。ただし、ページによってはやや繰り返しが多く、メッセージの整理が甘いと感じられる部分もあるため、少しだけ読みやすさを損なっています。
本書の内容はビジネス思考法としての専門性を有していますが、学術的な理論や体系的な研究に基づいているわけではなく、筆者の経験と観察に基づいた知見が主軸となっています。そのため、コンサルティングやマネジメントの実務に携わる人には有益ですが、専門的な裏付けや統計的根拠を求める読者にとってはやや物足りない印象を与えるかもしれません。

「なぜ?」を繰り返すって、思ったより深く考えるきっかけになるのね。

だろ?仮説思考も慣れると判断が早くなるし、ミスも減るよ。

私、まずは毎日の出来事をノートに書いて「なぜ?」を3回やってみることにする!

それいいね。思考の型が身につけば、自然と動ける人になれるよ。
『「Why型思考」が仕事を変える』は、ただのノウハウ本ではありません。誰でも実践できる「思考の型」を身につけることで、自ら考え、行動する力が養われます。今の自分を変えたい、もっと主体的に動けるようになりたいと感じているなら、今日から「なぜ?」を問い、仮説を立てる習慣を始めてみませんか?