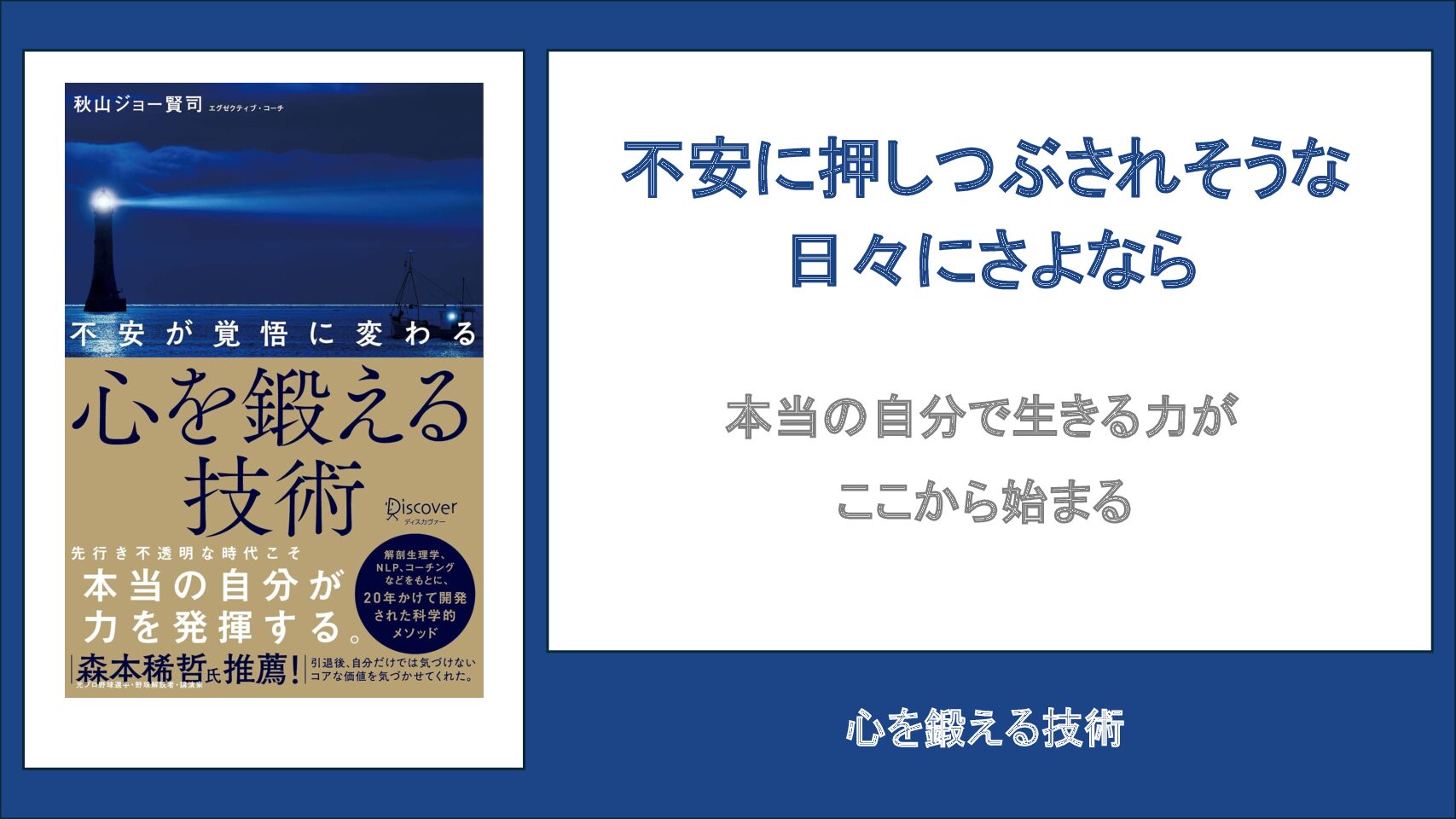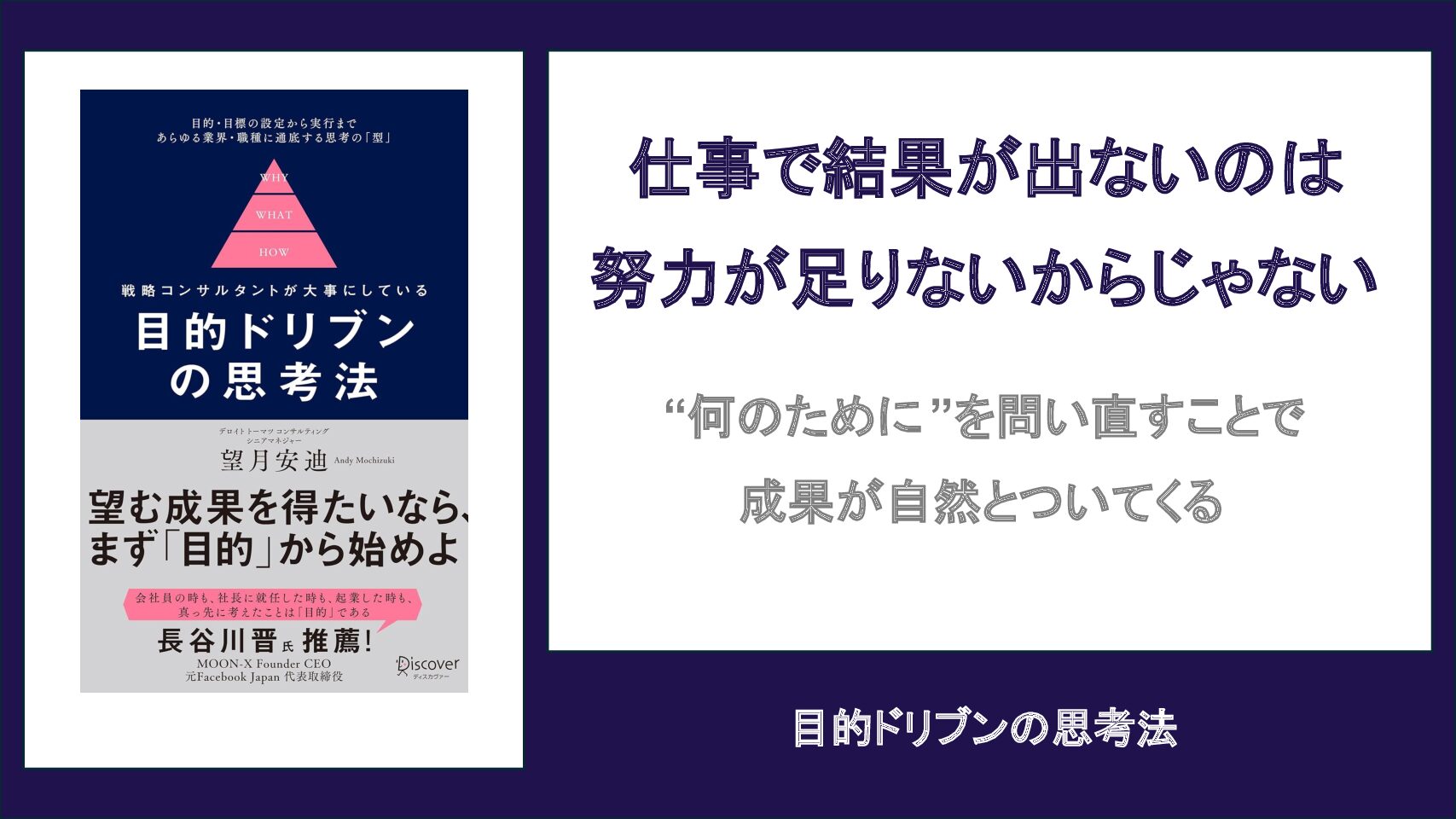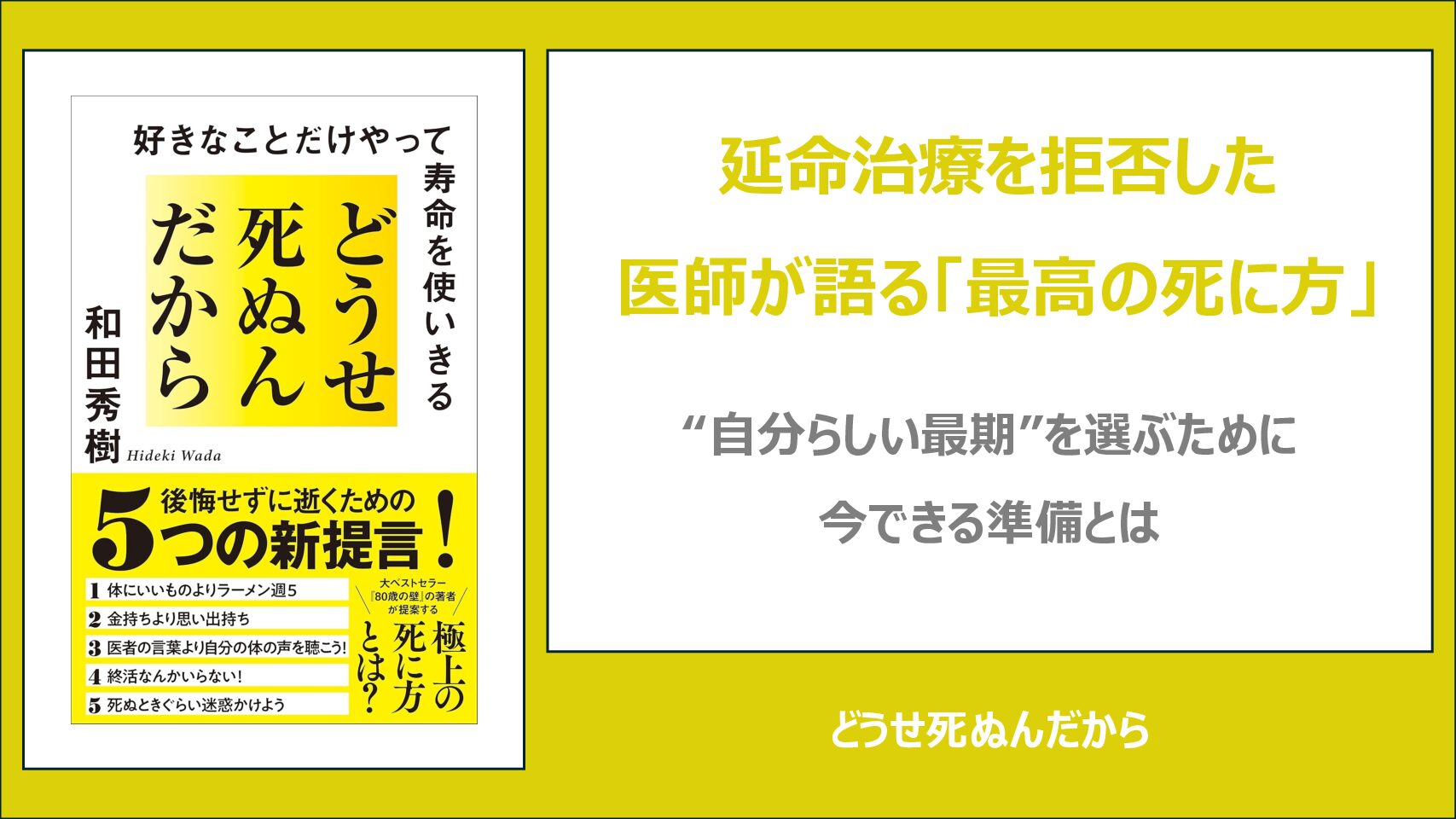この記事はで読むことができます。

ねぇTom、最近なんか、ずっとモヤモヤしてて…自分が何したいのかも分からないし、急に不安に襲われたりするの。

あー、それ、俺もあるわ。急に「このままでいいのか?」って考え込んじゃって、落ち込むっていうか。

そうそう、SNSで頑張ってる人見ちゃうと、「私だけ何も成し遂げてない…」って自己嫌悪になったり。

でもさ、なんか「本当の自分」って探せば見つかるもんなのかな?俺、見つけたことないわ。
多くの人が抱える「理由はわからないけれど生きづらい」という感覚。その正体は、社会や他人の期待に応えようとして“偽りの自分”を演じていることにあるかもしれません。
本記事では、脳科学と心理学をベースに「不安が覚悟に変わる心のトレーニング」をご紹介します。“本当の自分”と出会い、自分の人生に誇りを持てるようになるための実践的アプローチをまとめました。
人間の脳は未来をシミュレーションする機能を持っています。しかし、それがネガティブに働くと、「まだ起こっていないこと」への妄想が身体反応を引き起こし、不安として表れます。つまり不安は“脳の機能”であり、正体を知れば対応が可能です。
自分を「足りない存在」だと感じて生きている人は、無意識のうちに「偽りの自分」を演じている可能性があります。尊敬されたい、優秀さを証明したい、ワクワクを装いたい…。その行動の裏には、“穴”を埋めようとする心理が隠れています。
理想の自分を“味方”にすることで、自己対話が始まります。そこから、不安→安心→自信→勇気→覚悟という4ステップを通じて、心が鍛えられていくのです。これは誰でも取り組める“内面トレーニング”です。
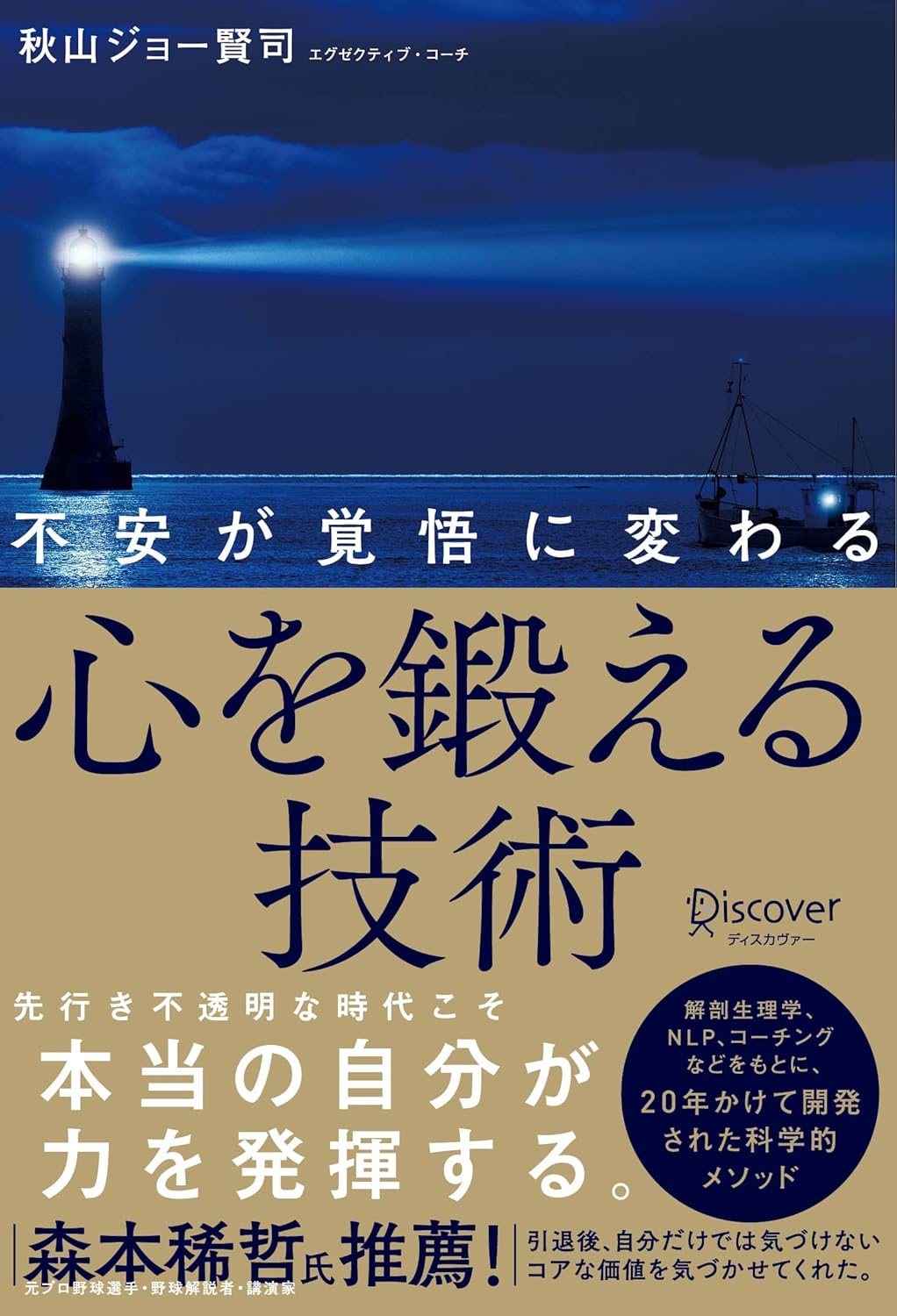
| 著者 | 秋山ジョー賢司 |
| 出版社 | ディスカヴァー・トゥエンティワン |
| 出版日 | 2021年11月19日 |
| ジャンル | マインド・心構え |
私たちが日々感じる漠然とした不安の正体は、「まだ起きていない未来を、脳がネガティブに想像してしまう」ことにあります。つまり、不安とは“現実”ではなく、“脳内の仮想イメージ”によって生み出されているのです。
たとえば、「この仕事、うまくいかなかったらどうしよう」と思った瞬間、脳はその未来の映像を自動的に作り出し、同時に「心臓がドキドキする」「身体が重くなる」といった生理的な反応を引き起こします。
この一連の流れを人は「不安」と呼びます。けれども、これは脳の“誤作動”ではなく、本来は「危険を回避するための優れたシステム」です。問題はその機能を“ネガティブな未来”ばかりに使ってしまうことにあります。
この本では、ネガティブな未来ではなく、「自分にとって嬉しい未来」をイメージすることで、脳と体にポジティブな反応を起こすことができると説いています。つまり、「不安を生む脳のメカニズム」は、そのまま「希望を生む装置」にもなるということです。
たとえば、緊張していたプレゼン前に、「拍手されてホッとしている自分」を思い描いただけで、身体が軽くなり、堂々と話せたという経験がある人も多いでしょう。このように、「未来の使い方」さえ変えれば、脳と体は味方になってくれます。
大切なのは、「不安は感じていい。でも、それをどう使うかが大事」という視点です。未来の設計図を“自分で描ける”ということに気づけば、もはや不安は恐れるものではなくなります。だからこそ、この本では「妄想=想像力の力」を逆手に取り、自分にとって都合の良い“脳内映画”を再生することを推奨しているのです。
未来が見えないからこそ、“どうなるか”を選ぶ権利は、常に自分の手の中にあります。不安は「悪いもの」ではなく、「選び直せるもの」。それに気づくことが、不安を覚悟に変える第一歩なのです。
自分自身を見失う最大の原因のひとつが、「偽りの自分」として生きてしまっていることです。本書では、偽りの自分には5つの典型的なパターンがあると述べています。「尊敬されたいモード」「優秀さの証明モード」「被害者モード」「マウンティングモード」「偽ワクワクモード」の5つです。
これらはいずれも、「自分には何かが欠けている」「このままではダメだ」という思い込みから生まれます。その“心の穴”を埋めるために、私たちは無意識に「他人の評価」や「理想のイメージ」にしがみつこうとします。
たとえば「優秀さの証明モード」では、「私はできる人です」ということを証明しようとするあまり、相手の話に割って入ったり、過剰に知識を披露してしまうことがあります。その結果、相手は「なんだか押しつけがましい」と感じ、関係がうまくいかなくなる…。
こうしたズレは、誰にでも起こりうることなのです。にもかかわらず、多くの人は「自分が偽っている」ことに気づいていません。むしろ、「これが自分だ」と思い込んでいるケースがほとんどです。
だからこそ重要なのは、「自分を客観的に見る目=メタ認知」を持つことです。本書では、偽りのパターンに気づくことで、“本当の自分”へと戻るきっかけを得られると説いています。
偽りの自分に騙されていることに気づけば、「もうそれはやめよう」と思えるようになります。そして、自分を偽っていた時期でさえ、「それも自分を守るための手段だった」と受け止められるようになるのです。
そうなったとき、偽りの自分は“過去の味方”となり、手放せる存在になります。自分の心のクセや演じていた役割に気づくことは、自己理解の最初の一歩。偽りから抜け出す勇気が、新しい自分を形づくる鍵になるのです。
本書の核心とも言えるのが、「理想の自分」との自己対話という考え方です。これは一般的な“ポジティブ思考”や“自己肯定感”の話ではありません。今の自分と“未来にこうなりたい自分”を分け、それぞれが対話をするという独自のセルフコーチング手法です。
この方法のユニークな点は、理想の自分を「味方」や「メンター」として使うことにあります。多くの人が理想像を「自分を責める材料」にしてしまう中、この手法では逆に、理想の自分が“今の自分に共感し、励ます存在”になるのです。
たとえば、過去に後悔した行動に対して、「なんでできなかったの?ダメだな」ではなく、「あのときは悔しかったよね」「ちゃんと頑張ろうとしてたの、私は知ってるよ」と声をかける。それが理想の自分です。こうした対話を続けていくと、自分に対する見方がどんどん優しくなっていきます。そして、不安や迷いがあっても、「私は私の味方がいる」と思えるようになり、行動力が湧いてくるのです。
また、理想の自分とともに「価値観」や「強み」を整理していくことで、自分がどう生きたいのか、何を大切にしたいのかが明確になってきます。そうすることで、「他人軸」で生きていた人生が、「自分軸」へと変わっていくのです。このプロセスの中で、「不安→安心→自信→勇気→覚悟」という4つのステップを自然と登れるようになります。理想の自分は、もはや憧れではなく、“内面のナビゲーター”として自分の人生に寄り添う存在となるのです。
この自己対話の習慣は、日記でも音声でも構いません。形式は自由です。重要なのは、「問いかけ」と「応答」を繰り返すこと。あなたの中にすでにある“理想の自分”に耳を傾け、会話を始めてください。その対話こそが、人生を動かす最初の一歩になるのです。
不安を感じたときは、その感情を否定せず「脳が働いている証拠」と受け止めましょう。そして、その不安の内容を紙に書き出し、「それが現実に起きた場合、どう感じるか?」「その逆にうまくいったら、どうなっているか?」と両面を想像します。
うまくいっている未来の自分をできる限り細かくイメージし(例:表情、場所、発言)、その映像を繰り返し思い描くことで、脳の反応をポジティブに書き換えていきます。この“脳内シミュレーション”の方向性を意識的に変えるだけで、不安は「目標に向かうナビゲーション」に変わるのです。
まずは、自分の思考や行動が「偽りの自分」になっていないかを振り返る習慣を持ちましょう。日記やスマホメモに、1日1回「今日の自分はどのパターンだったか(例:尊敬されたいモードなど)」を書き出してみてください。
パターンに気づいたら、「なぜそう振る舞ったのか」「本当はどうしたかったのか」と、理由を深掘りしてみましょう。1週間分がたまると、自分のクセや傾向が客観的に見えるようになり、偽りに引っ張られそうな瞬間に立ち止まれるようになります。
理想の自分との対話は、「質問」と「回答」を分けてノートに書くのが効果的です。たとえば、「今日、自分が一番後悔した行動は?」「それに対して理想の自分ならなんて言ってくれる?」といった形式で書きましょう。
最初は違和感があるかもしれませんが、1週間も続ければ自然に“理想の自分の声”が頭に浮かぶようになります。この習慣を続けることで、自己否定ではなく自己共感が身につき、日常のあらゆる場面で心の支えとなる“内なるメンター”が育っていくのです。
読者が日常的に直面する「不安」や「自己否定」などの心理的課題に対し、再現性の高いワークやセルフコーチング手法を提供している点は非常に実用的です。また、著者自身の経験や多くのクライアントの成功事例をもとに構成されており、具体的な活用イメージが持ちやすいです。ただし、自己啓発の枠組みを超える根拠や実証性の面ではやや弱く、すべての読者に対して普遍的に役立つとは言い切れません。もう一歩、行動計画の定量的な設計まで落とし込めれば、さらに実用性が高まると感じます。
図解やステップ形式の説明、実例が豊富で、文章構成も親しみやすく読み進めやすい内容です。専門用語も平易に噛み砕いており、心理学や行動科学の知識がなくても理解できるよう配慮されています。ただし一部、同じテーマが何度も繰り返されている印象があり、論理の飛躍や主観的な解釈が読者の混乱を招く可能性もあります。読者のレベルやニーズに応じて、もう少し論点を整理・要約してもよいと感じました。
扱われている悩みや行動傾向は多くの人に共通するため、テーマ自体は非常に汎用的です。ただし、本書の中心的な技法である「理想の自分を用いた自己対話」は、ある程度の自己認識力や想像力が前提となっており、万人向けとは言いづらいです。また、文化的・社会的背景によって受け取り方に差が出そうな内容も含まれており、やや「日本人向け」に偏っている印象を受けます。汎用的な概念に加え、もう少し多様な背景や視点を取り入れれば、より広い層に適応できたでしょう。
口語的で親しみやすい語り口、豊富なエピソード、段階的な構成により、読み進めるハードルは低く設定されています。読者に語りかけるようなスタイルも、共感を呼びやすく心理的な安心感を与えています。ただし、語りがやや冗長に感じられる箇所もあり、文章全体としてはやや長く感じる部分もあります。一定のテンポやリズムで構成されてはいるものの、章ごとの繰り返しを抑えるとさらに洗練された印象になります。
心理学や行動科学の理論に一部言及があるものの、学術的な裏付けや体系的な知見の引用は限定的です。著者の経験則やクライアント事例が中心で、主観的な論理展開にとどまっている点が否めません。一部でマクスウェル・マルツやドゥエックの理論を紹介していますが、それらが本書の構造を支えるほどではなく、断片的に使われている印象です。より客観性と信頼性を補強するためには、科学的な根拠とのリンクが必要です。

いや〜、この本読んで思ったけど、不安って「脳の仕組み」だったんだね。なんかホッとしたかも。

俺も。自分の考え方が原因かと思ってたけど、ちゃんとメカニズムがあるって知ると違うよね。

あと、「理想の自分」をメンターにして対話するって発想が新鮮だったな〜。叱られるんじゃなくて、共感してくれる感じ。

あれなら続けられそう。自分で自分を育てていくって、今の時代に合ってる気がする。
不安は、あなたが“間違っている”から起きるのではなく、脳があなたを守ろうとしている証拠。その不安を否定するのではなく、理解し、受け入れ、“覚悟”へと変えていく力は、あなたの中にすでにあります。自分の心と丁寧に向き合い、本当の自分と共に前に進む人生を、今日から一歩ずつ始めてみませんか?