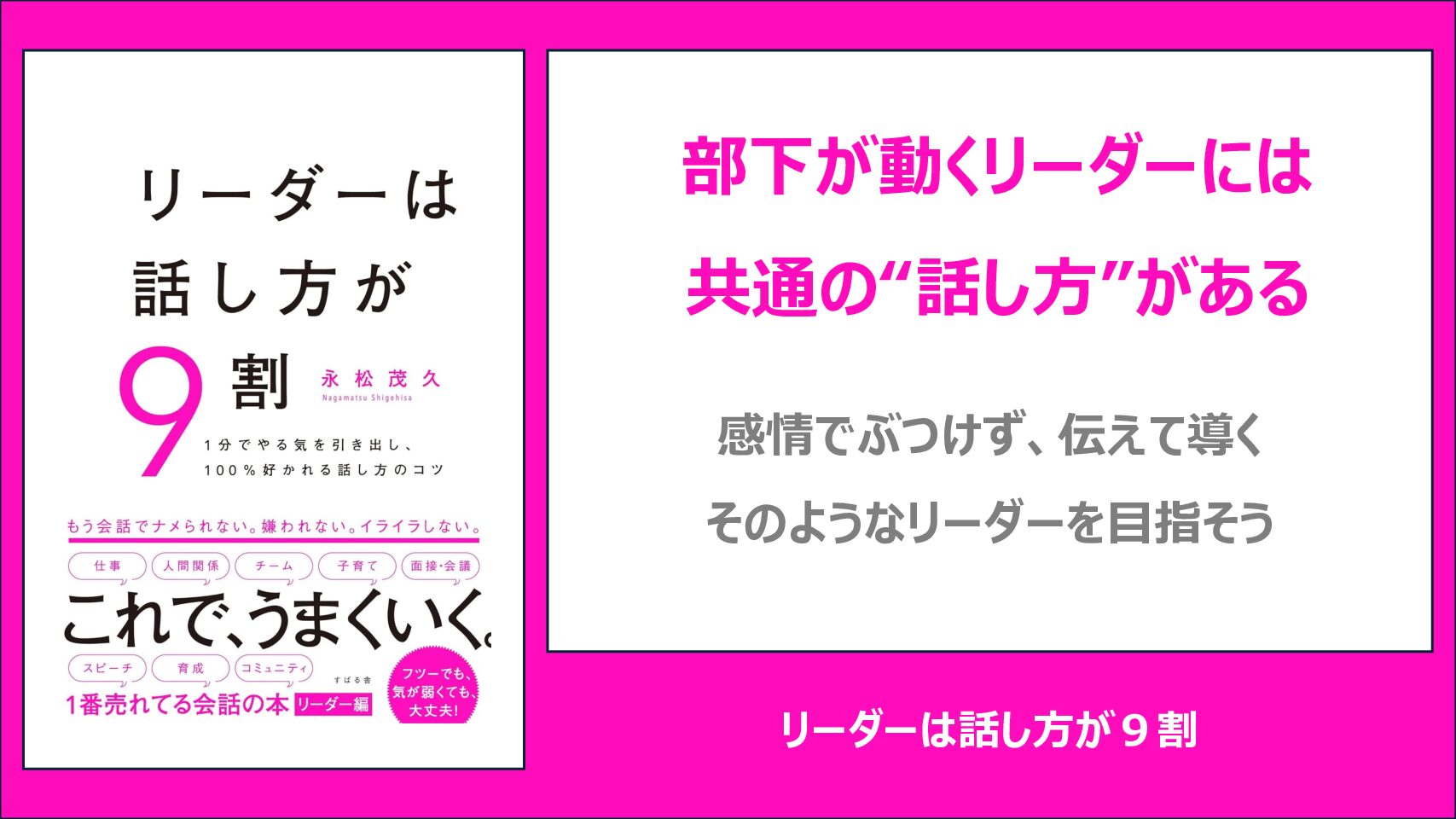この記事はで読むことができます。

ねえTom、初対面の人と話すときって、すごく緊張しない?

うん、わかるよ。何を話せばいいのか分からなくて、沈黙が怖いんだよね。

そうそう!でも最近読んだ本に、「聞き方」を変えるだけで会話がうまくいくって書いてあってね。

「話す」じゃなくて「聞く」ってこと?

うん!実は、会話がうまい人って“話し上手”じゃなくて“聞き上手”らしいの。

へえ、それは気になる。聞き方を工夫するだけで、印象まで変わるの?

そうなの。ちょっと内容をシェアするね。話すのが苦手でも、すごく使えるテクニックばかりだったよ。
「初対面の会話が苦手」「沈黙が怖い」「とにかく緊張する」——そんな悩みを抱えている方は少なくありません。でも安心してください。実は“話す力”よりも“聞く力”を磨くほうが、コミュニケーションはうまくいくのです。
本記事では、話さずとも好印象を与える「聞き方」のコツをご紹介します。
多くの人は自分の話を聞いてほしいと思っているため、聞き役に回ることで相手に安心感を与えることができます。「聞く人」はそれだけで希少価値があるのです。
リアクションや表情、うなずきの工夫だけで「話さずとも」相手との関係がスムーズになります。話さなくても場が持つ“技術”を学べます。
うなずき・笑顔・感嘆のひと言など、聞き方の具体的なテクニックを身につけることで、誰でも聞き上手になれます。会話が自然と弾むようになります。

| 著者 | 永松 茂久 |
| 出版社 | すばる舎 |
| 出版日 | 2021年12月9日 |
| ジャンル | 人間関係・コミュニケーション |
多くの人が「会話では話す人が主導権を握っている」と考えがちですが、実際には聞く側の態度が会話の方向性を決定づけています。相手が気持ちよく話せるかどうかは、聞く人のリアクションやうなずき、表情によって左右されるのです。
たとえば、真剣にうなずいてくれる人には自然と話を続けたくなりますし、逆に無表情で腕組みされたままだと、話す側は委縮してしまいます。聞き方が上手な人は、話す相手のリズムを崩さず、むしろそのペースを引き出してあげることができます。
これはまるで野球で、キャッチャーがピッチャーの球種やタイミングをリードするようなもの。見た目には派手な動きをしないキャッチャーこそ、試合の流れをコントロールしているのです。
聞き上手な人は、目立たずとも会話の中で最も重要な役割を担っている存在です。また、会話が苦手な人でも、話さずに流れを整える“聞き方”の技術なら習得しやすく、実践のハードルも低いのが特徴です。
主導権を握るのに「おもしろく話す力」は必要ありません。むしろ、話してもらえる空気をつくることが、信頼関係を築く第一歩となるのです。
聞き方を少し工夫するだけで、「話さずとも好かれる人」になることができます。その鍵となるのがリアクションです。
たとえば「うんうん」とうなずいたり、「へえ、それはすごいね」と一言添えるだけで、相手は「自分の話がちゃんと届いている」と感じます。このような小さなリアクションは、相手の話を肯定し、共感を伝えるメッセージでもあります。
特に印象的なのは、うなずきの強弱や表情のバリエーションによる効果です。軽くうなずく“弱”、しっかりと頷く“中”、深くうなずいて大きく共感を示す“強”を使い分けることで、話にリズムが生まれます。
話している側もその反応に乗って、どんどん言葉が出てくるようになります。リアクション上手な人は、まるで会話の指揮者のように、相手の話を自然と引き出していきます。
そしてこれは誰にでもできるスキルです。話すのが得意でなくても、表情や反応を丁寧に返すだけで、相手との距離が縮まっていくのです。
「聞き方」を学ぶと、つい仕事や初対面の場面など、外の世界での応用を想像しがちです。でも、まずは一番身近な人の話を丁寧に聞くことから始めるのが効果的です。
親、パートナー、子ども、友人——日々接している人たちとの会話の中にこそ、練習の機会があふれています。近しい関係ほど、気が緩んでリアクションを省略しがちですが、そこにこそ聞き方の真価が問われます。
たとえば、家族の話を聞くときに「ふーん」と流すのではなく、「そっか、それは大変だったね」と一言添えるだけで、相手の気持ちは大きく変わります。安心感を持って話してもらえることが信頼関係を強くする鍵になるのです。
また、緊張感の少ない環境だからこそ、聞き方の工夫が自然に試せて、習慣化しやすくなります。いきなり大勢の前で使うよりも、まずは“聞く癖”を家庭内でつけておくのがベストです。
そして、その姿勢は自然と外のコミュニケーションにもにじみ出て、あなたの印象を一気に変えていきます。
話す相手の方にしっかり体を向けて、軽く前のめりになるような姿勢をとってみましょう。スマホを机に置き、相手の目を見るだけでも「ちゃんと聞いてくれている」と伝わります。たったそれだけで、安心感や信頼感を持ってもらいやすくなります。
「うんうん」と軽くうなずくだけでもOKです。少し大げさに「へえ〜!」と驚いた表情をしたり、笑顔でうなずいたりするだけで、相手は気持ちよく話せます。強弱をつけるとより自然ですが、まずは“リアクションを返す”ことを意識するだけで十分効果があります。
難しいことは考えず、「今日は1分だけ家族の話をちゃんと聞こう」と決めて実践してみましょう。うなずいたり「それでどうなったの?」と相づちを打つだけでOKです。ほんの少しの変化で、相手の反応がやわらかくなるのを感じられるはずです。
聞く力を伸ばす具体的なテクニックや心構えが多く、日常生活や職場ですぐ活かせる内容でした。特にリアクションの仕方やオンライン会議での態度など、現代的な場面への適応も意識されています。ただし、状況に応じた細かな応用例が少なく、万能とは言いきれない点がマイナスです。
基本的にやさしい言葉と口語調で書かれているため、読み進めやすい工夫はされています。ですが、同じ趣旨の話が何度も繰り返されて冗長に感じる箇所が多く、要点がぼやける場面が目立ちました。章ごとにもっと簡潔なまとめがあれば、さらに理解が進んだでしょう。
「聞く力」はどの年代、どの立場の人にも必要なスキルであり、幅広いシーンで応用が可能です。とくに家庭、職場、友人関係などあらゆる人間関係に応用できる視点で書かれていました。ただし、やや「日本人特有の文化」に寄りすぎた説明もあり、国際的な汎用性はやや限定的です。
内容は前向きでやさしいトーンですが、話の繰り返しや例話の脱線が多く、集中力が持たない箇所がたびたび出てきます。章をまたいで似た話が何度も展開されるため、整理されていない印象を受けました。全体をもっとコンパクトにできれば格段に読みやすくなると思います。
著者自身の体験をベースにしているため、実感のこもったリアルな内容には好感が持てます。ですが、心理学や行動科学といった学術的な裏付けが乏しく、一般論に留まっている点が専門性を低くしています。エビデンスや他者研究の引用があれば、より説得力が増したはずです。

どうだった?やっぱり「聞く力」ってすごく大事でしょ?

うん、今まで“話す力”ばかり磨こうとしてたけど、逆だったんだね。

リアクションとか、ちょっとした工夫だけでも印象が変わるって分かったよね。

これなら今日からでもできそう。まずは身近な人の話をよく聞くところから始めてみるよ。

うん、それだけで人間関係もグッとよくなるはず!
「話すことが苦手…」そんなふうに悩む必要はもうありません。聞き方を変えるだけで、誰でも自然と好かれる人になれます。今日から実践できる“聞き方改革”、あなたも始めてみませんか?