この記事はで読むことができます。

ねぇTom、最近うちの職場にも「元・研究者」って人が入ってきたんだけど、正直どんな仕事してるのか全然想像つかないのよね〜。

あ〜、たしかに“研究者”って聞くと、白衣着てフラスコ振ってるイメージあるもんね(笑)。実は俺も、前は大学で研究してたんだよ。いまは企業で研究開発に関わってる。

えっ!? 研究ってアカデミアの世界だけの話じゃないの?

いやいや、むしろ企業での研究は“社会にどう還元するか”って視点が重要になるんだよ。アカデミアとは考え方も成果の出し方も全然違うんだ。

へ〜、面白そうだけど…大変そうでもあるね(笑)

まぁ、慣れるまではギャップに戸惑うかも。でも逆にそこを押さえたら、キャリアはめっちゃ開けると思うよ。
アカデミアと企業研究職では、求められる視点や成果の出し方、人との関係性まで大きく異なります。
本記事では、アカデミアから企業に転身したい方、あるいはすでに企業研究職として働く方に向けて、「キャリアを築くための3つの視点」を具体的に解説します。
論文発表をゴールとするアカデミアと違い、企業では社会実装や事業貢献が重視されます。評価軸の違いを理解することで、転身後のギャップに迷わなくなります。
企業では「社会にどう役立つか?」という問いを常に持つ必要があります。技術力だけでなく、社会との接点を意識した思考がキャリアの鍵になります。
企業研究職では1人の力よりもチームでの協働が成果に直結します。周囲との信頼関係を築くことが、長期的な活躍を支える土台になるのです。
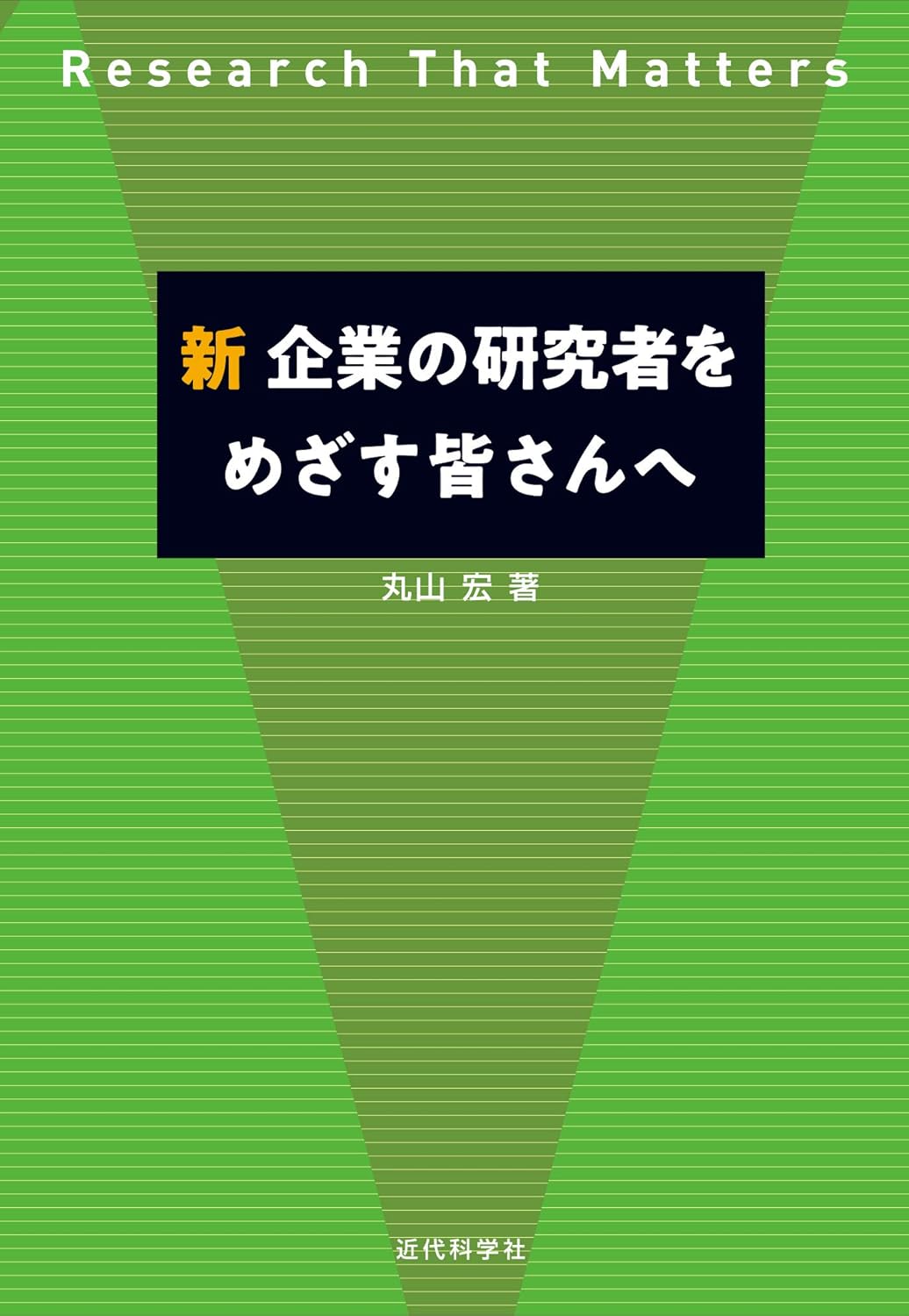
| 著者 | 丸山 宏 |
| 出版社 | 近代科学社 |
| 出版日 | 2019年12月21日 |
| ジャンル | キャリア・人生設計 |
アカデミアでは、研究の成果とは論文として公表されることが最大の目的とされてきました。そこでは「新規性」や「学術的意義」が重視され、実用性や市場性はあまり求められません。しかし、企業研究職においては、研究のゴールは“知の蓄積”ではなく、“事業や社会への貢献”です。
たとえば、新技術の提案が新製品の開発につながったり、既存技術の改良によってコスト削減や顧客満足度向上につながるような、明確な“価値提供”が求められます。つまり、いくら技術的に優れたアイデアでも、それが社内外で活かされなければ意味を持たないのです。この違いを理解しないまま企業に転職すると、「ちゃんと研究しているのに評価されない」というギャップに苦しむことになります。
企業では、スピードやチームとの連携も成果の一部とされるため、自分一人の“研究の完成度”だけでは不十分です。また、上司や事業部と早い段階で“使える成果とは何か”をすり合わせる力も必要になります。
知識を深めることがゴールだったアカデミアから、知識を活用することがゴールとなる企業へ――このパラダイムシフトを理解することが、研究職としての第一歩になります。
企業の研究者にとって、最初に問われるべきは「この研究は社会の役に立つか?」という視点です。自分の関心や専門性からテーマを選ぶことが許されていたアカデミアとは異なり、企業では“世の中の課題”からスタートする必要があります。そのためには、ニュースや業界動向、ユーザーの声に日常的に触れておく感度が求められます。
たとえば、SDGsや脱炭素といった時代の流れを意識した研究テーマの選定は、企業価値の向上にも直結します。社会課題を自分ごととして捉え、それに科学でどう応えるかを常に考える姿勢が重要です。さらに、事業部との連携を通じて、実際の製品やサービスに技術をどう落とし込むかという“橋渡し”の力も問われます。
著者は、「顧客の視点に立つことが企業研究職の本質」と語っており、ユーザーインタビューやマーケティング部門との協業も必要になるとしています。このような“社会との接点”を意識し続けることで、自分の研究が誰の役に立つのかを具体的に描けるようになります。
社会性のある研究テーマは、社内の理解や協力も得やすく、結果として実現可能性が高まるのです。つまり、企業研究職は技術者であると同時に、社会を変える提案者でもあるということです。
企業では、どれだけ優れた技術力があっても、“チームで成果を出せる人”でなければ評価されません。アカデミアのように、研究室で一人黙々と取り組むスタイルでは限界があるのです。企業の研究開発は多くの場合、他部署との連携や複数の専門家との共同作業で成り立っています。そのため、コミュニケーション力や情報共有の習慣が非常に重要になります。
たとえば、自分のアイデアを他部門にわかりやすく説明するプレゼン能力、議論の中で相手の立場に配慮できる柔軟性、成果を一人占めせずチームで共有できる姿勢などが求められます。また、社内の評価制度も“チーム成果”を前提としていることが多く、個人のパフォーマンスだけでは限界があるのが現実です。
著者は、「信頼とは技術力ではなく、“姿勢”に宿る」と述べており、周囲と良好な関係を築くことの大切さを説いています。さらに、上司や関係部署と継続的にフィードバックをやり取りすることで、研究の方向性がズレずに済むという利点もあります。
孤高の研究者ではなく、“人と成果を共有できる研究者”こそが、企業内で長く信頼される人材になるのです。これは、技術スキル以上に重要な“ビジネススキル”とも言えるでしょう。
今取り組んでいるテーマが「どんな製品やサービスに繋がるのか?」を一度書き出してみましょう。ビジネス的価値や顧客ニーズとの接点を探ることで、研究の方向性がより明確になります。「誰の、どんな課題を、どう解決できるか?」という問いを常に持つことが重要です。
ニュースや専門メディア、企業のIR資料などを定期的にチェックし、研究テーマとの関係を考えてみましょう。社会との接点を持つことで、研究の意義やアプローチが変わってきます。週に1回でも、自分の研究を“社会文脈”の中で見直す時間をつくるのがおすすめです。
ミーティングでは自分の考えを“伝える”だけでなく、他の視点を“取り入れる”意識を持ちましょう。自分の研究内容をわかりやすく共有する練習や、異なる部署との交流を通じて、共創の力が高まります。成果を「独占」ではなく「共有」するスタンスが、信頼される研究者への第一歩です。
この本は著者の企業研究者としての豊富な経験に基づき、研究課題の選び方、チーム運営、キャリア形成、技術移転まで、実務に直結する具体的なアドバイスが詰まっています。企業で研究職を志す人にとって極めて実用的です。特に、統計的仮説検定やプレゼンテーション術など、研究成果を価値に変えるスキルにまで踏み込んでいます。
平易な日本語で書かれており、一般の理工系大学院生にも理解しやすい表現になっています。ただし、専門用語の説明がやや冗長だったり、章構成がやや長く感じられる箇所があり、読み手によっては途中で集中力が切れる可能性もあります。
企業研究者向けと銘打たれているものの、研究全般や技術マネジメント、プレゼンや論文執筆、英語でのコミュニケーションなど、広く研究活動に従事する人全般に役立つ内容が含まれています。ただし、研究職以外のビジネス職には一部内容が響きにくい部分もあるため満点とはしません。
内容が豊富な分、1つ1つの話題が長めで詰め込み感が強く、読み切るには根気が必要です。随所に体験談やエピソードがあり親しみやすさはありますが、もっと章を絞ってテーマを明確にしたほうがテンポよく読めたかもしれません。
企業研究とそのマネジメント、キャリア形成における深い洞察が随所に見られます。実際のプロジェクトや研究現場の描写も生々しく、アカデミックと産業界の差異にも精通している筆者ならではの専門性が強くにじみ出ています。

うーん、正直、研究職ってもっと“職人っぽい”仕事かと思ってたけど、話聞いてたら全然違うのね…。

まぁ確かに、アカデミアにいたときは「ひたすら掘る」って感じだったけど、企業では「どう使われるか」も見ていかないといけないんだよね。

社会との接点とか、チームで成果を出すとか…なんか、研究っていうより“事業”に近い感じがする。

まさにそれ!でもそこに面白さもあるんだ。誰かの役に立つ実感があると、モチベーションも全然違うよ。

いや〜、企業研究職、ちょっとイメージ変わったかも。…でも私にはムリかな(笑)

いやいや、少しでも「知識を活かしたい」って気持ちがあるなら、きっと向いてるよ。あとは“どこに視点を置くか”だけ。
企業研究職への転身やキャリア継続には、アカデミアとの“視点の違い”を理解することが不可欠です。社会とのつながり、成果の意味、仲間との関係──この3つの視点を意識するだけで、企業の中での立ち位置がガラリと変わります。
研究に携わるすべての方にとって、視野を広げるヒントになれば幸いです。
