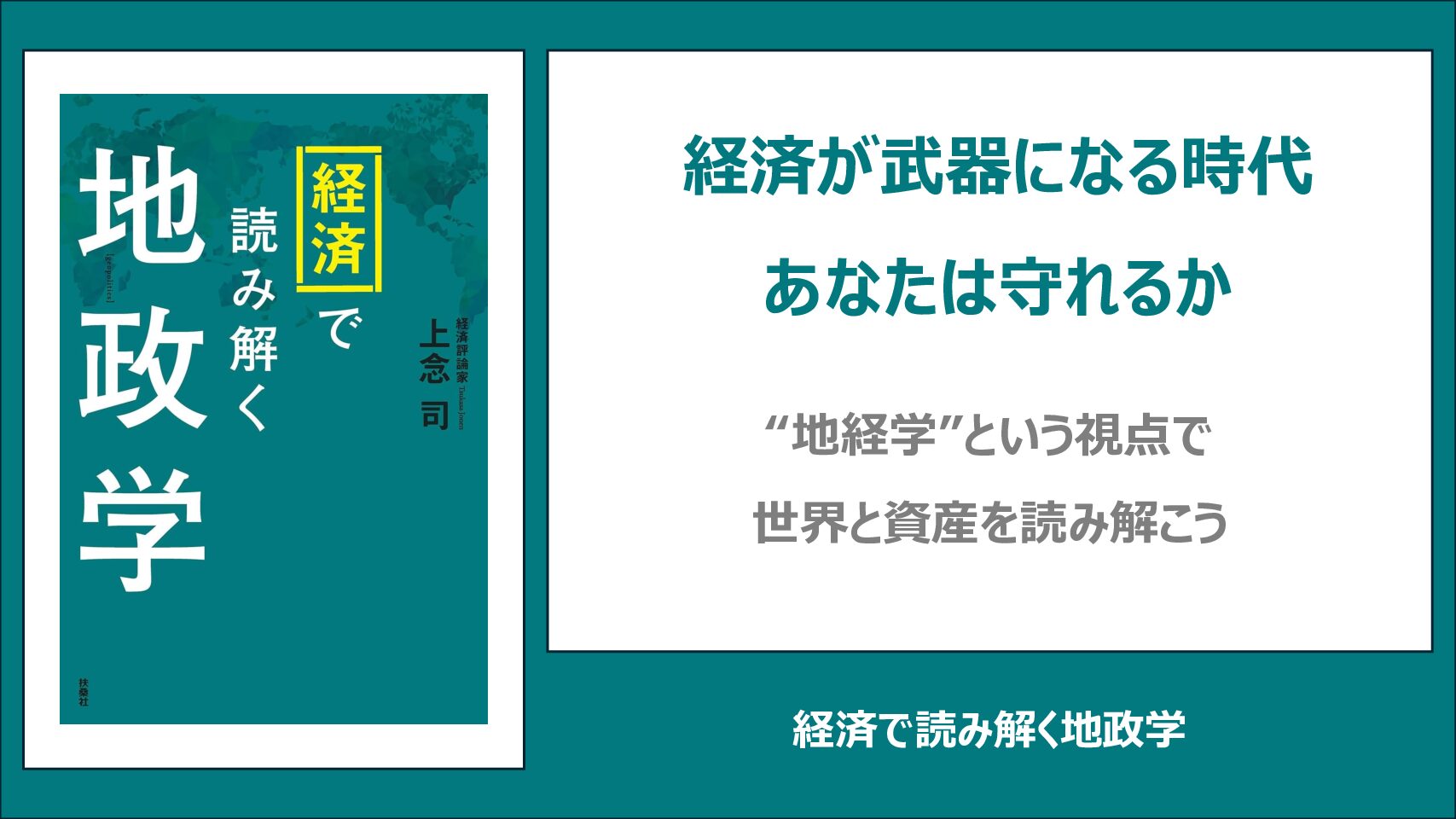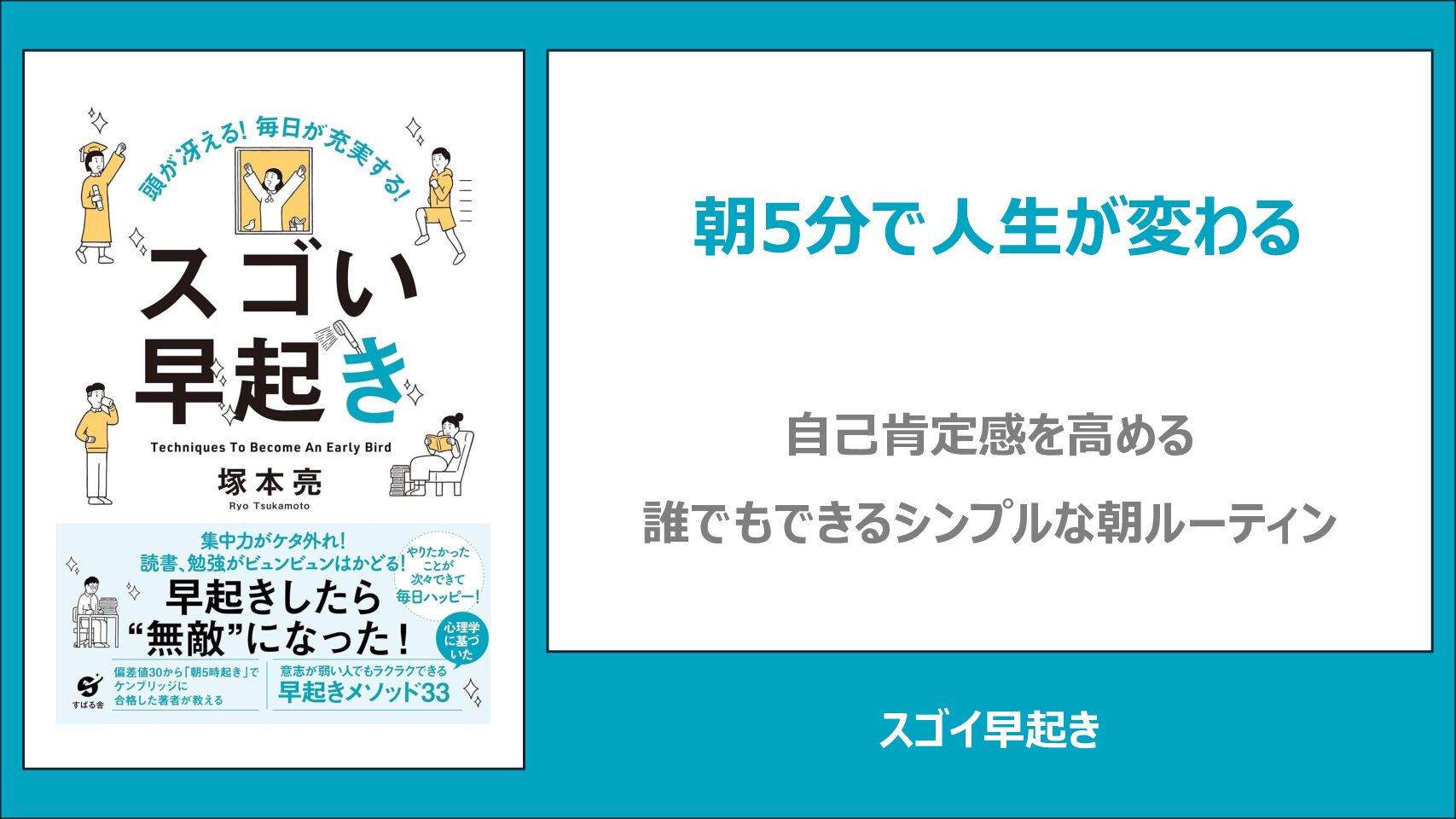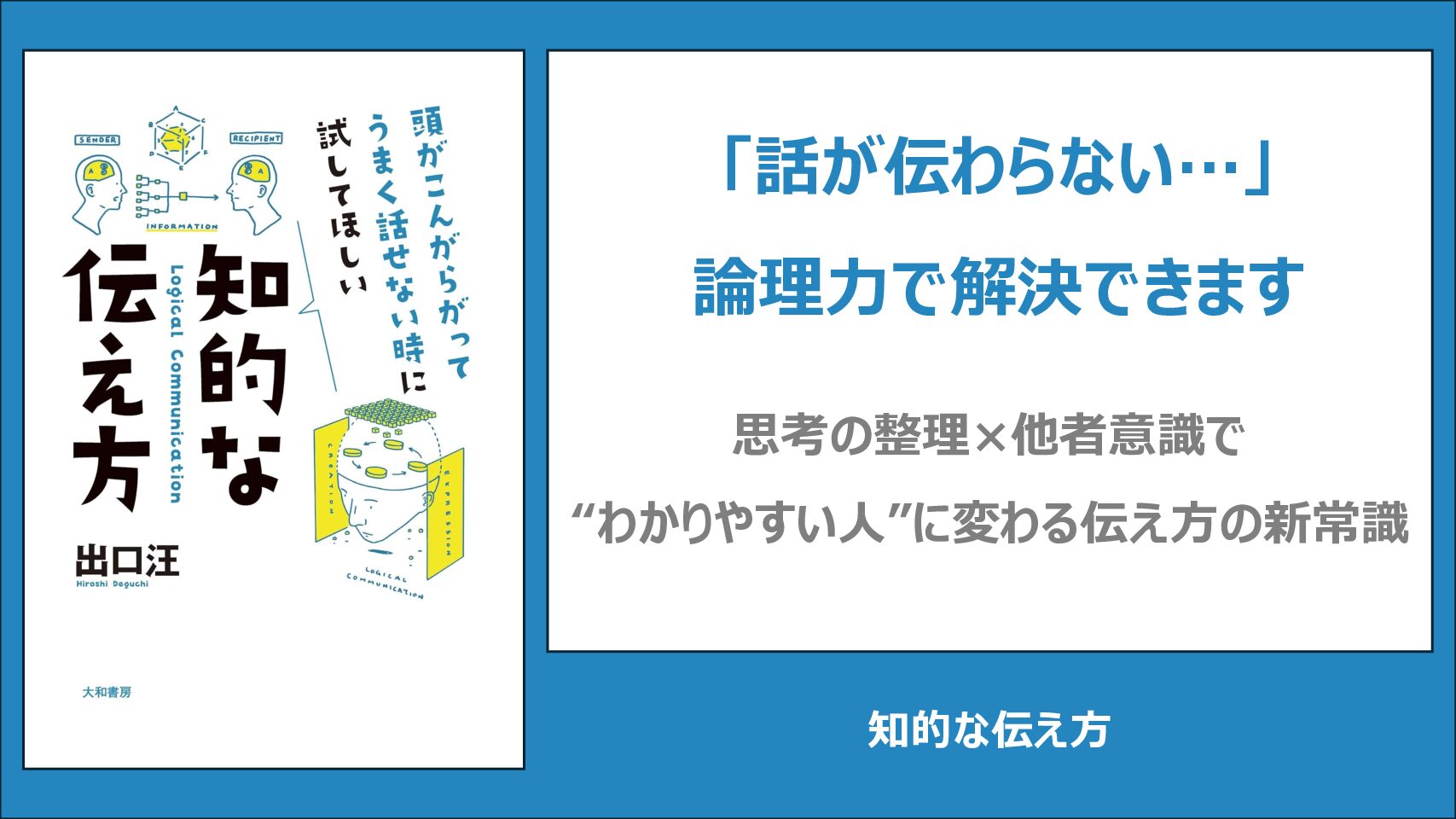この記事はで読むことができます。

最近、ニュースで“地経学”って言葉よく見かけるんだけど、何のことか分からなくて…

ああ、それ僕も気になってた。地政学とは違うのかな?

なんか世界情勢とか経済とかが関係してるって聞いたけど、個人にも影響あるのかな?

それを知るためにも、この本『地経学とは何か?』を一緒に読んでみようよ!
今、世界は武力ではなく経済で戦う時代に突入しています。国際情勢の裏側で進むパワーゲームを読み解く鍵となるのが「地経学(Geo-economics)」という新しい視点です。
本書『地経学とは何か?』では、地政学と経済学の融合によって、ロシア・中国・アメリカなどがどのように覇権を争い、日本はどんなリスクにさらされているのかを明らかにしています。そして、そうした変化が私たち個人の資産や生活にどのように影響するのかを具体的に考察しています。
地経学とは、地政学的な思惑に基づいて経済力や技術、情報を駆使して主導権を争う現代の国家戦略のことです。武力を使わない“静かな戦争”が世界中で展開されているのです。
中国の経済包囲網やロシアの資源戦略など、地経学的な動きの中で、日本は技術流出・エネルギー依存・情報戦といったリスクに直面しています。経済だけでなく、私たちの生活基盤そのものが脅かされる可能性もあります。
国家間の地経学的衝突は、株式市場やエネルギー価格、為替にも大きな影響を及ぼします。本書では、そのような不確実な世界を生き抜くために、個人が身につけるべき視点や資産防衛の考え方も具体的に示されています。
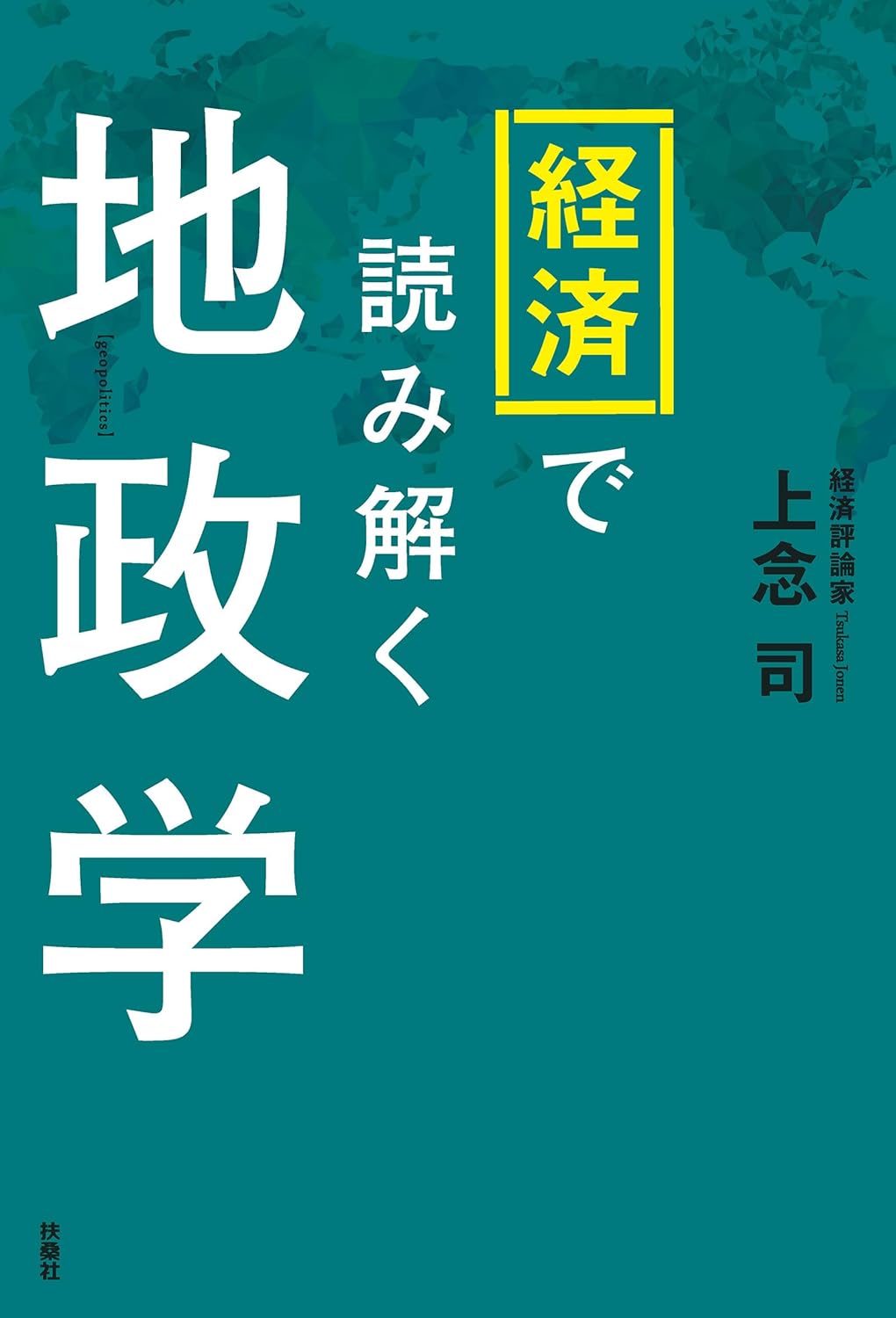
| 著者 | 上念 司 |
| 出版社 | 扶桑社 |
| 出版日 | 2023年7月30日 |
| ジャンル | 政治・経済 |
地経学とは、軍事ではなく経済や情報技術を駆使して、国家が影響力を拡大しようとする戦略のことです。これは経済制裁、貿易交渉、技術封鎖などを用いた「非武力の戦争」とも言えます。
たとえば、アメリカが中国のファーウェイに対して半導体の輸出規制をかけたのは、経済技術力を通じた安全保障の一環です。このような措置は単なる経済政策ではなく、地政学的な目的を持っています。ロシアによるエネルギー供給の制限も、経済を通じて他国を揺さぶる典型的な地経学的行為です。つまり、地経学では経済が「武器」として使われるのです。
この視点を持つことで、ニュースで報じられる制裁や企業制限が単なる経済問題ではなく、安全保障や覇権争いと密接に関係していることが理解できます。たとえば「なぜある国の輸出が急に止まったのか」「特定企業が制裁対象になった背景には何があるのか」といった問いに対し、深い洞察を得ることができるのです。
経済はグローバルに結びついているため、一国の戦略的判断が、国際的なサプライチェーンを通じて他国に波及します。私たちの生活に使われるスマホ、車、電力、食料品にも、こうした影響は確実に及んでいるのです。
本書を読むことで、地経学が「国家間の戦争の新しい形」であり、それが日常の経済活動とどれほど密接に関係しているかを認識することができます。そして、この視点を身につけることで、単なる消費者や労働者としてではなく、未来の変化に備える主体的な個人として行動できるようになります。地経学を知ることは、もはや専門家だけの話ではなく、生活者として必須の素養なのです。
日本はエネルギー・食料・技術の多くを海外に依存しており、それが国家としての弱点になっています。エネルギーの9割以上を輸入に頼り、資源を持たない日本は、輸出国の地経学的な意図に常に翻弄されるリスクがあります。
たとえばロシアによるウクライナ侵攻以降、エネルギー価格が高騰し、電力料金やガソリン価格が急激に上昇したのは記憶に新しいでしょう。このような外部要因による影響を、日本はほとんど避けることができません。
さらに、技術分野では最先端の半導体やAI関連技術の製造や素材において、他国との連携が欠かせませんが、それが逆に「外交カード」として利用されるリスクもあります。中国によるレアアースの輸出制限は、日本の製造業に大きな影響を与えました。
このように、経済的な武力行使が日常に直結する脅威となっているのです。さらに、日本の防衛戦略はこれまで物理的な安全保障に偏重してきたため、経済的な防衛力に関してはまだ整備が不十分です。
本書では、日本がこの状況にどのように対応すべきか、国家レベルでの経済安全保障の必要性を訴えています。たとえば、重要物資の国産化、同盟国とのサプライチェーン構築、技術流出防止策などが挙げられます。
そして、これは国だけの問題ではなく、私たち一人ひとりが「経済の安全保障とは何か?」を理解し、自分の働く企業や使っている製品がどのように世界の流れとつながっているかを意識することが求められるのです。もはや「政治や経済は遠い存在」ではなく、「生活の土台を守る知識」としての地経学が求められています。
国家間の経済戦争のような出来事は、個人の資産形成や生活にも直接的に影響を及ぼします。たとえば、為替が急変すれば外貨建ての資産や輸入品の価格に影響し、エネルギー価格の上昇は家計の光熱費や交通費を直撃します。
これらの背景に地経学的な要因があることを知るだけで、日常の判断が変わってきます。投資判断、就職・転職、企業経営、消費行動など、あらゆる意思決定において、「世界の構造」を知っているかどうかが、明暗を分けるようになってきているのです。
本書では、こうしたリスクに備える方法として「情報リテラシーの強化」「資産の分散」「長期的な視点」の3つを挙げています。
まず、ニュースを多面的に読み解く力があれば、誤った情報に踊らされることを避けられます。複数のメディアを比較し、国や企業の意図を想像することが求められます。次に、資産を1国や1種類に偏らせず、外貨建て資産や金、不動産、インデックス投資などに分散して持つことで、リスクを和らげることができます。さらに、短期的な動きに左右されず、長期的な視点で経済全体を見る力も重要です。地経学的リスクは数年単位で動くため、過度に短期的な判断をすると失敗する恐れがあります。
たとえば、ある国のリスクを察知し、早めに資産を移動させることで損失を避けられる可能性もあります。つまり、私たちは「個人としての経済防衛力」を持つ必要があるのです。
地経学は単なる国家戦略の話ではなく、「明日の生活を守るための視点」なのだということが、この本を通じて強く実感できます。変化の激しい時代において、自分の人生を自分で守るために、地経学を理解することは非常に有効な武器となります。
単に「どこで何が起きた」というニュースだけでなく、「なぜそれが起きたのか」「どの国が得をしているのか」といった視点でニュースを見ることが大切です。たとえば、アメリカがある企業への制裁を発動した背景には地経学的な戦略があるかもしれません。BBCやNHK、日経新聞など複数メディアを比較して読む習慣を持ちましょう。
エネルギー、食料、テクノロジー、金融など、日常生活を支える要素が海外依存であることを意識しましょう。たとえば自分が使っているスマートフォンがどこの技術に依存しているか、ガスや電気の供給元はどこかを調べてみることが第一歩です。家計の支出で海外影響を受けるものを一覧化するのも有効です。
急な為替変動や株価暴落にも耐えられるよう、資産は複数の通貨や投資先に分散しておくことが推奨されます。特定の国や業種に偏った資産形成は、地経学的リスクにさらされやすくなります。つみたてNISAやiDeCoの活用も、長期視点での安定をもたらす手段として有効です。
本書は個人の資産防衛や投資判断に「地経学」が役立つと説いており、読者の行動につながる視点を提供しています。ただし具体的な行動指針や政策提言は曖昧で、抽象的な警鐘や陰謀論的な描写に傾きがちです。さらに、一般読者が取るべき実際の対応策についての記述は乏しく、応用には工夫が必要です。よって、実際に役立てるにはややハードルが高いと評価せざるを得ません。
語り口は平易で、ニュースや社会問題と結びつけながら説明しているため、専門知識がなくても読みやすく感じられます。一方で、因果関係が強引だったり、感情的な表現が頻出するため、論理の明快さという点では一部に不透明さもあります。専門用語も逐一解説されており、導入としての親切さは評価できます。しかし冷静さに欠ける部分が目立ち、全体として説得力が損なわれている点は否めません。
地政学と経済学を結びつけた視点は興味深いものの、内容は日本の安全保障や東アジアの脅威に過度に特化しています。欧米諸国や中東、アフリカなど他地域への応用には内容が偏っており、視野は限定的です。また、特定の思想的立場を色濃く反映しており、汎用的なフレームワークとして使うには中立性を欠きます。そのため、他の分野や国際問題に応用するにはかなりの補正が必要です。
文体は平易で勢いがあり、事例も多くテンポよく読めます。一方で、煽情的な表現や陰謀論的トーンが繰り返され、読み進めるうちに疲労感を覚える部分もあります。文章構成に冗長なところがあり、内容が本質的に重複する記述も多いため、洗練度は高くありません。読者の感情に訴える記述が多い一方で、論理的な整理は弱く、読後感にモヤモヤが残ることもあるでしょう。
地政学や国際政治についての概念紹介は一通りなされており、初学者には有益な内容もあります。しかし、出典の曖昧な事例や、信憑性に疑問の残る主張も含まれており、学術的には慎重に扱うべき箇所が見受けられます。著者の視点が強く反映されているため、バランスの取れた専門解説書とは言い難いです。参考書としてではなく、主張の一つとして読むべき内容と言えます。

地経学って、ただの難しい言葉じゃなくて、今の世界を読み解くカギなんだね。

うん、特に日本みたいに経済的に影響を受けやすい国では、ちゃんと知っておくべき知識だね。

ニュースを見る目が変わりそう。個人の資産を守るためにも、もっと深く学びたいな。

僕もだよ。地経学を知るって、未来に備えることなんだね
地経学とは、国家戦略の裏にある経済の動きと、その影響が私たち個人にどう及ぶかを教えてくれます。不透明な時代だからこそ、“知っているかどうか”が、未来を大きく分けます。地経学という新たな視点を手に入れて、変動する世界をしなやかに生き抜きましょう。