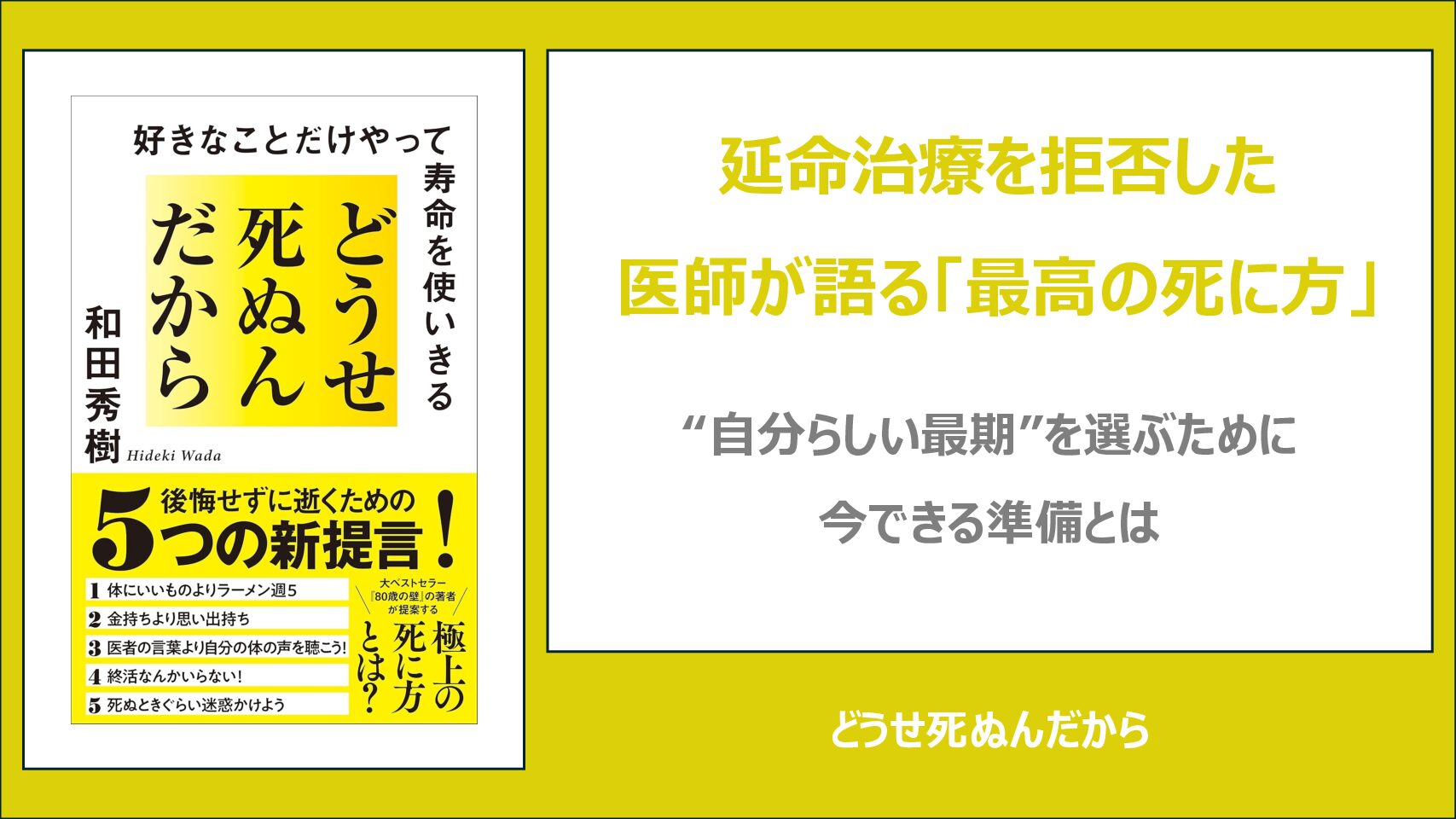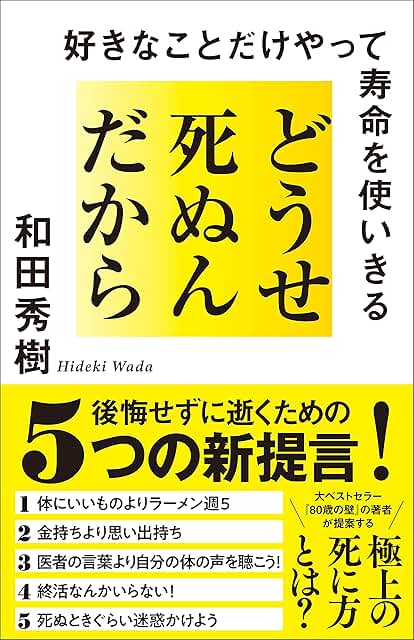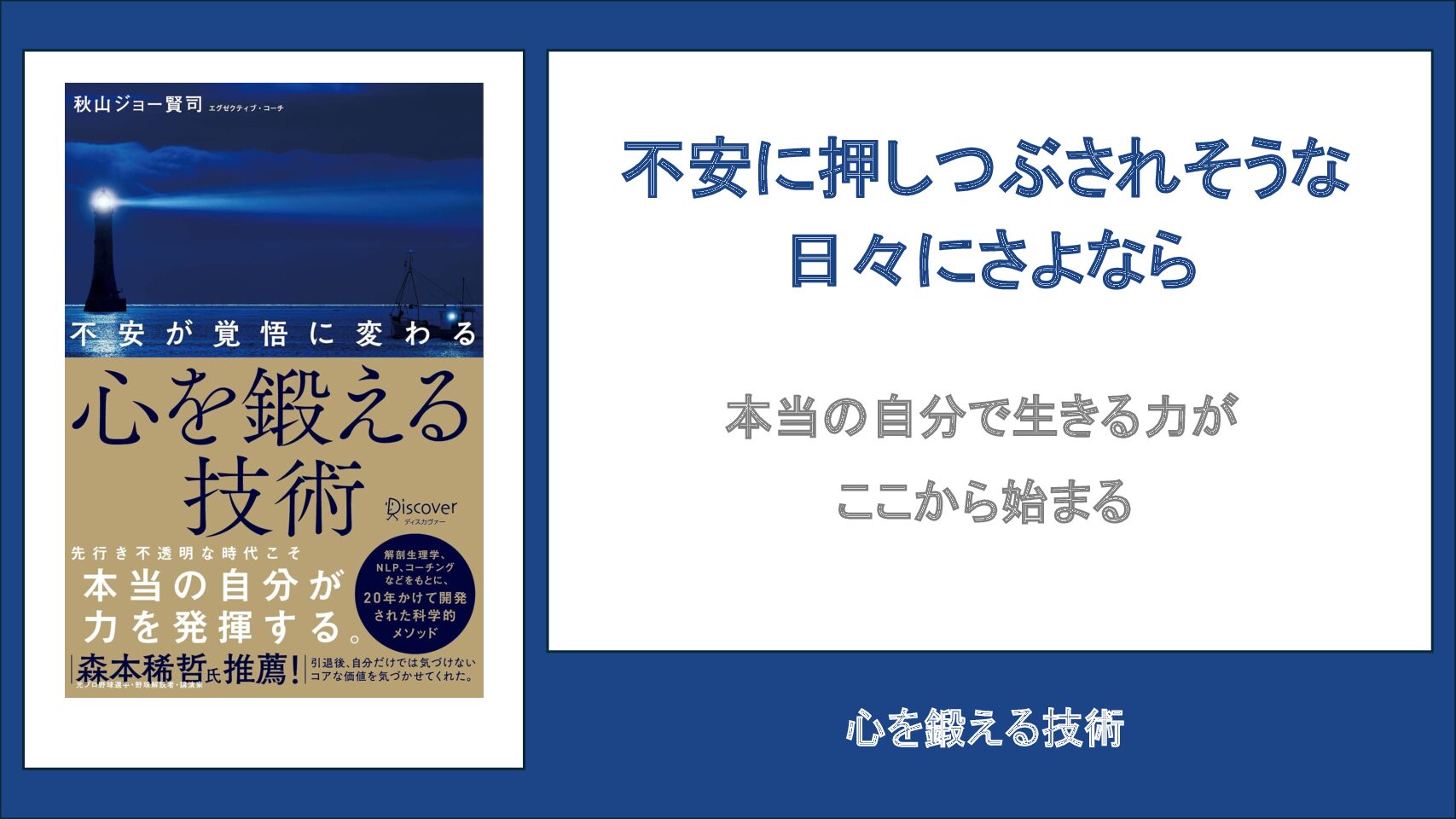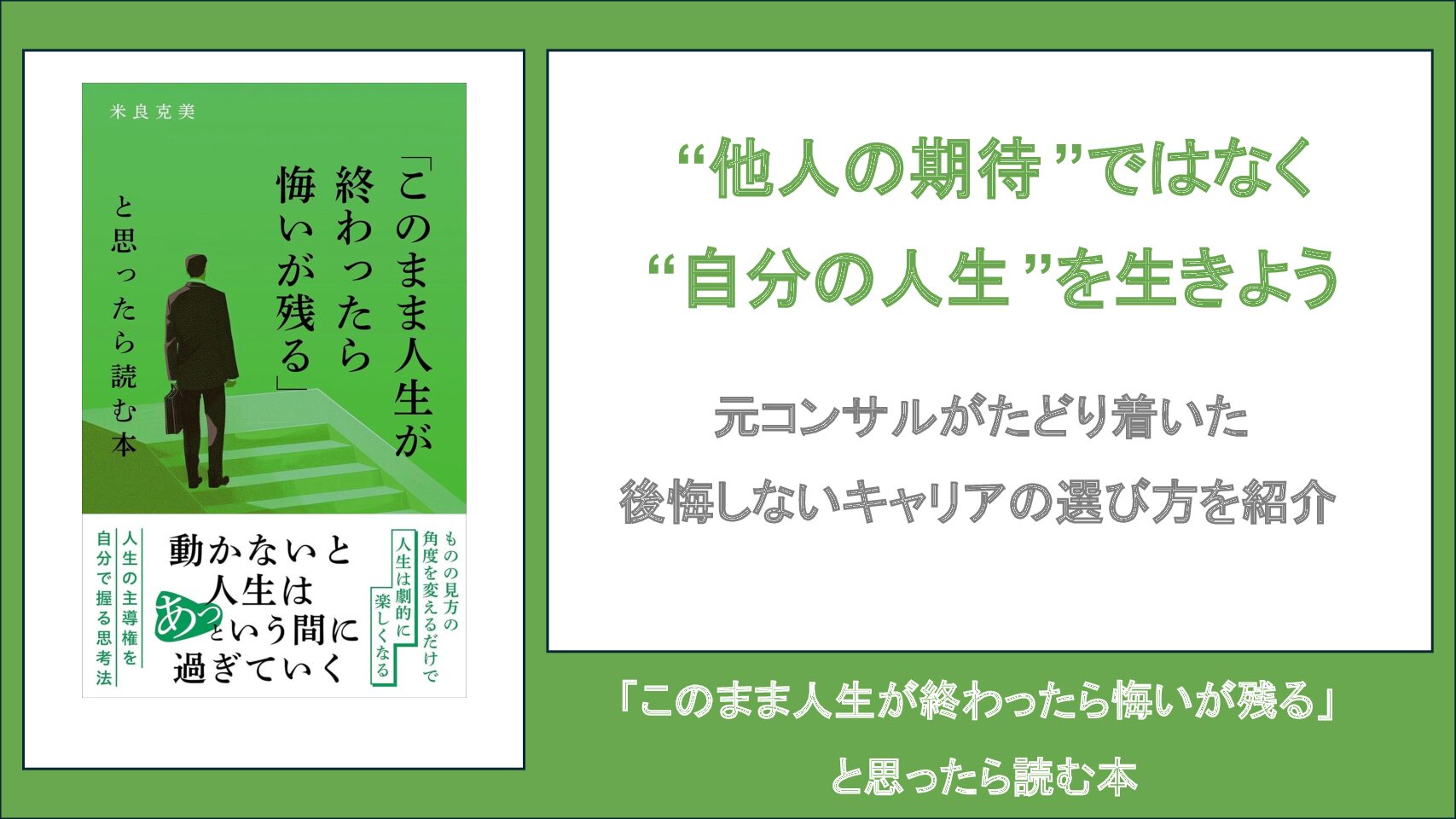この記事はで読むことができます。

ねぇTom、「延命治療を拒否した医師の話」って聞いたことある?すごく考えさせられるテーマだと思うのよ。

うん、最近そういう話題増えてるよね。医者自身が延命を選ばないって、何か理由があるんだろうな。

まさにそうなの。この本では、実際に延命治療を拒否した医師が、自分の死に方をどう選んだかが書かれているのよ。

それって、自分の最期をどう迎えるかっていう、人生の大事な選択を考えるきっかけになるかもね。
多くの人が避けて通りたいと感じる「死」というテーマ。しかし、そこから目を背けることなく向き合い、「自分らしい最期」を選び取ることこそが、真に豊かな人生の締めくくりと言えるのかもしれません。
本書では、延命治療を拒否したある医師が、自身の経験と知識をもとに語る“最高の死に方”を通して、現代医療の現場で見落とされがちな「生の尊厳」と「選択の自由」について私たちに問いかけてきます。
現役の医師である著者が、自身の最期に延命治療を望まないと決断した背景には、長年の臨床経験から見えてきた「現代医療の限界」があります。治療の延長線上に“幸福な死”があるとは限らない現実を知った彼は、命を引き延ばすことよりも、「どう生き終えるか」に価値を見出しました。
「自分らしい最期」とは、本人が納得し、後悔のない状態で迎える死を指します。そのためには、自分自身の価値観を明確にし、意思表示をすることが何より重要なのです。
著者は、延命治療を望まない意思を家族に明確に伝えることで、むしろ深い絆と理解が育まれたと語ります。家族に負担をかけたくない、という思いが正直な対話へとつながり、死に際しての後悔や葛藤が少なくなるのです。
延命治療とは、医学的手段によって命を長らえることを目的とした治療法であり、人工呼吸器や点滴、経管栄養、心臓マッサージなどが含まれます。多くの人は延命治療を「命を救うもの」と捉えますが、著者はそれを“苦しみを長引かせる処置”になる可能性があると指摘します。
実際、治療によって命は維持されても、意識が戻らず、意思表示もできず、ただベッドの上で機械につながれている患者を数多く見てきたといいます。その状態は「生きている」と言えるのか――著者は疑問を投げかけます。苦しみや不快感を感じながらも、医療機器に依存して生命だけが維持される状況は、本人の尊厳や人生観とは大きくかけ離れていることがあるのです。
また、延命治療を受けることによって、本人だけでなく家族にも精神的・経済的負担がのしかかるという現実もあります。医療費が高額になるだけでなく、家族が判断を委ねられた場合、「延命をしなかったことを後悔するのではないか」という葛藤に苦しむことも少なくありません。
著者自身は、長年の医師経験から「最期は苦しまずに、自然に迎えたい」と強く思うようになったと言います。そしてその選択は、単に治療を放棄するということではなく、「自分らしい最期を選ぶ」という能動的な行動であるとも述べています。
つまり、延命治療を拒否することは、命を諦めることではなく、自分にとっての「生の終え方」に責任を持つという選択なのです。治療を施せば施すほど“命”が延びるという幻想の裏に、尊厳や納得という視点が欠落してしまう危険性があるのだと、本書は教えてくれます。だからこそ、治療を受ける・受けないという判断を「医師任せ」にせず、自分で考え、自分で決める必要があるのです。
「自分の最期を自分で決める」という行為は、極めて個人的でありながらも社会的な意味を持つ重要な選択です。著者は、死についてあらかじめ考え、準備し、家族や医療従事者にその意思を伝えることの大切さを強調しています。
現代の医療現場では、本人の意思が不明確なまま治療方針が決まるケースが多く見られます。救急搬送されたときに本人が意識不明だった場合、医師や家族がその場で判断せざるを得なくなり、結果として望まぬ延命治療が行われてしまうこともあります。
そうした事態を避けるには、日頃から「どう死にたいか」を考え、それを明文化することが不可欠です。エンディングノートや事前指示書(アドバンス・ディレクティブ)を活用すれば、自分の意思を文書にして残すことができます。これにより、本人が口にできない状況でも、その希望が尊重される可能性が高まるのです。
また、意思表示は「自分だけの問題」ではなく、家族や医療チームの混乱や心理的負担を減らす効果もあります。家族が「本人はこうしたいと言っていた」と知っていれば、安心してその希望に沿った選択ができますし、後悔や罪悪感を抱かずに済むのです。著者も、家族に対して「自分は延命を希望しない」と繰り返し伝えることで、死を穏やかに受け入れてもらえたと述べています。
死について語ることは、日本社会ではまだまだ避けられがちですが、それこそが問題の本質です。「縁起でもない」「まだ早い」といった言葉で話題を打ち切るのではなく、命の終わりにこそ真剣に向き合うべきなのです。自分の意思を周囲に伝えることは、自分の人生を最後まで自分でコントロールするための唯一の手段なのです。
最期のときを穏やかに、後悔なく迎えるために必要なのは、高度な医療ではなく、信頼と理解のある人間関係です。著者は、自分が延命治療を望まないことを家族に伝える過程で、むしろ関係が深まったと語っています。初めは家族も戸惑い、反対する声もあったものの、何度も話し合う中で、「本人の意思を尊重しよう」という気持ちが生まれていったのです。こうしたプロセスは、単なる医療方針の決定ではなく、お互いの価値観をすり合わせ、理解し合う大切な時間でもありました。
特に日本では、家族の誰かが病気になると「本人には伝えない方がいい」と判断されることも多く見られます。しかし、著者はそれを「愛情のすれ違い」と捉えています。本人の意思を尊重しないまま進められる医療は、かえって不信感や後悔を生む結果にもなりかねません。
死について語り合うことは、実は「どう生きてきたか」「何を大切にしているか」を共有する行為でもあります。それによって、家族の絆がより深くなり、互いに対する理解が一層増すのです。著者は、死を語れる関係性がある家庭は、日頃から本音を交わせている証だと言います。
そのためには、普段から家族と対話を重ね、小さな気遣いや感謝の言葉を忘れずに積み重ねていくことが必要です。死を迎える瞬間にいきなり心を開ける人間関係は存在しません。日常の中で「ありがとう」「ごめんね」「大丈夫?」と声を掛け合えることが、最期のときの安心感につながります。
医療では解決できない“心の問題”を支えてくれるのは、人との絆であり、家族との対話です。死について正直に語れる関係を持つことが、結果として「生きること」をより豊かにしてくれるのです。
自分にとって「生きる」とはどういうことかをじっくり考えましょう。自分がどんな状態になったときに延命治療を受けたいのか、または拒否したいのかを、紙に書き出してみるだけでも気持ちが整理されます。可能であれば、エンディングノートなどを使って明文化しておくとよいでしょう。
整理した考えを、家族にしっかり伝える時間を作りましょう。重いテーマに思えるかもしれませんが、「自分の考えを伝えておきたい」と素直に話し始めれば、意外とスムーズに会話が進むこともあります。話しにくい場合は、書面や手紙という形でも十分効果的です。
普段から家族とのコミュニケーションを大切にし、信頼関係を築いておくことが、いざというときの安心につながります。日々の小さな会話や、相手を気遣う一言が、死に際しての理解ある対話を可能にします。「ありがとう」や「ごめんね」を素直に伝えられる関係を目指しましょう。
本書は高齢者を中心に、自分の死生観を明確にし、人生の終盤を納得して生きるための具体的な行動指針を数多く提供しています。とくに健康診断や薬の是非、リビング・ウィルなど、現実に役立つ情報が豊富です。ただし、著者の極端な主観や医療否定的な姿勢が万人にそのまま実用的とは限らない点で減点しました。
語り口は平易でユーモラスですが、主張が飛躍する箇所や繰り返しが多く、構成もやや冗長で読み進めるのに疲れる部分があります。個人的体験や感情的な訴えが強く、論理性を求める読者には分かりにくいと感じられるでしょう。比喩や具体例が多い反面、理路整然とした説明が不足しています。
本書は基本的に高齢者、それもある程度余裕のある生活をしている人を前提に書かれており、若者や現役世代にとっては響きづらい内容です。また、「我慢しない」「健康診断不要」といった主張はリスクの高い生活に直結しうるため、万人向けにはなっていません。読者を選ぶ構成です。
軽妙な語り口や個人的エピソードで引き込まれる反面、冗長な記述や文体のクセ、同じ内容の繰り返しが多く、集中力を持続させづらい面があります。章立てはされているものの、情報の整理が甘く、全体像をつかみにくい印象です。もう少し編集で整理されていれば評価は上がったでしょう。
著者が精神科医・高齢者医療の専門家であることから、高齢者の終末期医療に関する知識や経験に基づいた見解には説得力があります。とはいえ、医療全般への否定的姿勢が強く、専門性というよりは個人の哲学や思想に寄った内容も多いため、純粋な医学的専門性としてはやや偏りがあります。

読んでみて、すごく心に残る話だったね。

うん、死についてこんなに前向きに考えたのは初めてかもしれないよ。

私も。これを機に、自分の意思や家族との対話をもっと大切にしたいと思った。

後悔しない最期のために、今できることから始めるって大事だよね。
「死」を考えることは、「どう生きるか」を考えることでもあります。延命治療を拒否した医師の選択は、私たちに“自分らしく終える”という新しい価値観を提示してくれました。最期まで自分の人生を生き抜くために、今日から少しずつ準備を始めてみませんか?