この記事はで読むことができます。

また夜中に3回起きた…。さすがに眠すぎて仕事中に幻覚見そうだった。

うちの赤ちゃん、夜泣きスキル高すぎない?背中スイッチの感度、もはやプロだよ。

寝たと思って布団に置いた瞬間「ふぎゃー!」って。もはやトラップ。

しかも俺が寝返り打っただけでギャン泣き。俺もそろそろ電池切れる…。

ねんねトレーニングって気になるけど、泣かせる系はちょっとなあ…。

でも泣かせない方法もあるって聞いたよ。習慣を整えるだけで自然に寝られる子もいるんだって。
夜泣きに悩むパパママは多く、「いつまで続くの?」「何が原因?」と不安になることもあるはず。この記事では、赤ちゃんの夜泣きを軽減し、親子ともにぐっすり眠れる環境づくりについて解説していきます。
体調や性格だけでなく、生活リズムや睡眠環境が大きく影響していることに気づけます。
抱っこや添い乳に頼らず、赤ちゃんが自分で眠る力を育てるための具体的な工夫を紹介します。
親の睡眠不足を軽減し、家族全員が心身ともに整う「ねんね環境」の整え方が学べます。
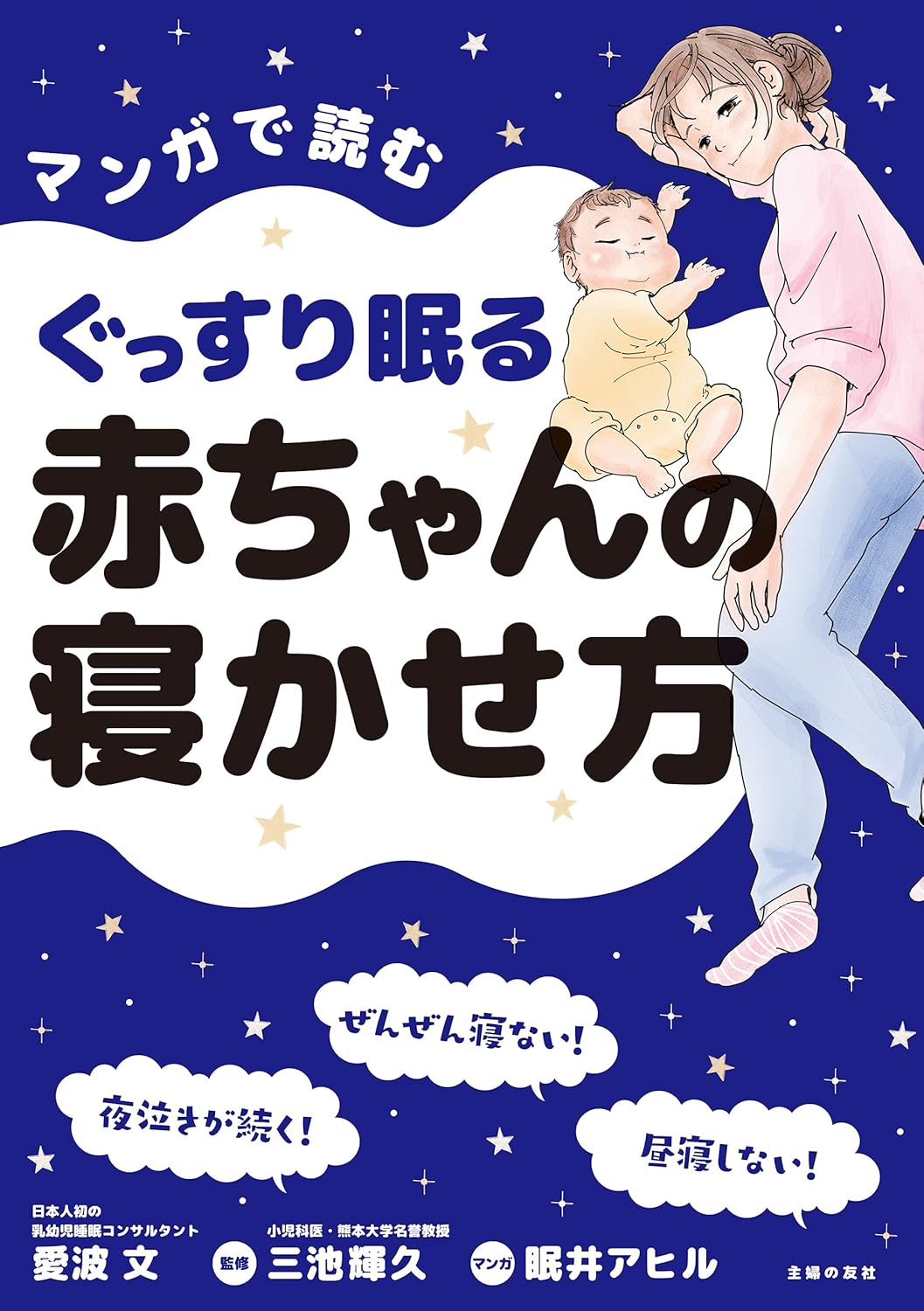
| 著者 | 愛波 文 |
| 出版社 | 主婦の友社 |
| 出版日 | 2021年2月25日 |
| ジャンル | 子育て・教育法 |
夜泣きの原因を赤ちゃんの気質や成長段階のせいにしてしまいがちですが、実は生活リズムや環境の影響も大きいとされています。
例えば、就寝時間が毎日バラバラだったり、昼寝の時間が長すぎたりすると、夜中に何度も目覚めやすくなります。また、部屋の照明や音、室温なども眠りの質を左右する重要な要素です。著者は、こうした「見落とされがちな要因」を丁寧に整えることが、夜泣き対策の第一歩だと述べています。赤ちゃんが安心して眠るためには、親の関わり方や生活習慣を見直す必要があるのです。
「泣くのが当たり前」と思ってしまうと、何も変えられません。しかし、「環境を整えれば改善するかもしれない」と視点を変えることで、夜泣きの捉え方が前向きになります。
つまり、赤ちゃん自身を責めるのではなく、睡眠の土台づくりを見直すことが重要だと気づかされる内容です。原因を「性格」ではなく「習慣」に見出す姿勢が、解決への第一歩になると感じました。
セルフねんねというと、「泣かせっぱなしにする睡眠トレーニング」と誤解されがちですが、本書ではまったく異なるアプローチが紹介されています。赤ちゃんの発達段階や性格に応じて、自然と眠れるようになる“習慣づけ”こそがセルフねんねの本質だと語られています。
たとえば、お昼寝から夜の睡眠までのスケジュールを整えたり、毎晩同じ寝かしつけの流れをつくることが大切です。「寝室に入ったら部屋を暗くする」「おやすみの絵本を読む」「音楽をかける」といったルーティンを続けることで、赤ちゃんの脳が“これから寝る時間だ”と認識するようになります。
また、泣いたときにはすぐに抱き上げるのではなく、声かけやトントンで様子を見るという段階的な関わりも推奨されています。これは決して放置ではなく、赤ちゃんの気持ちを尊重した接し方です。
「眠る力を育てる」という考え方が、親の心にも余裕を与えてくれます。“自立させる”のではなく、“安心して一人で眠れるようにサポートする”という姿勢が伝わってきます。セルフねんねは、赤ちゃんとママ・パパの信頼関係を育むための大切なプロセスなのだと納得しました。
多くの親が「赤ちゃんの個性だから仕方ない」と思いがちな夜泣きですが、実は親の関わり方を変えるだけで、改善されるケースも少なくありません。
たとえば、寝かしつけの際にスマホを見ながらトントンしていると、赤ちゃんは親の気が他に向いていることを敏感に感じ取ります。また、「寝ないと困るよ」といった焦りの気持ちも、無意識に表情や声に出てしまい、赤ちゃんに不安を与える原因になります。
著者は、「赤ちゃんの睡眠を整えるには、まず親の意識を整えることが大切」と繰り返し述べています。夜泣きに悩む前に、まずは“自分の行動”や“感情の状態”を振り返ること。そこから小さな工夫を積み重ねていけば、確実に変化が現れます。
たとえば、寝かしつけの前に部屋を整えたり、気持ちを落ち着ける呼吸を意識するだけでも、赤ちゃんの反応が変わることがあります。夜泣きを“赤ちゃんの問題”ではなく“家族のリズム”として捉えることで、取り組み方が大きく変わります。
親の見直しは決して自己否定ではなく、“変えられる可能性に目を向ける姿勢”だと本書は教えてくれます。
赤ちゃんの眠りを安定させるために、就寝前の環境をルーティン化しましょう。部屋の明かりを落とし、同じBGMや絵本で“ねんねスイッチ”をオンにすることで、赤ちゃんの脳が「これから寝る時間だ」と認識できるようになります。毎日繰り返すことで、自然と夜泣きの回数が減っていきます。
寝かしつけの手段が偏らないよう、ぬいぐるみやおくるみなど、赤ちゃんにとって“安心できるアイテム”を活用してみましょう。たとえば、ママのにおいがついたタオルや優しい音楽は、ひとりで眠る力をサポートしてくれます。寝かしつけのバリエーションが増えることで、親の負担もぐっと軽くなります。
赤ちゃんの夜泣きが続くと、つい焦りやイライラが出てしまうこともあります。そんなときこそ、「自分は今どんな気持ちで関わっているか?」を見つめ直すことが大切です。1日の終わりに数分だけでも振り返る時間を持つことで、心にゆとりが生まれ、赤ちゃんへの接し方にも良い変化が現れます。
赤ちゃんのねんねに関する悩みに対し、月齢別・原因別にきめ細かい対策が網羅されており、即実践に移せる内容が豊富です。特に「活動時間」「セルフねんね」「ねんねルーティン」など、再現性の高い具体的なテクニックが多数紹介されています。安全性や幸福度など親子双方の視点も取り入れており、実生活において多角的に活かせるのが大きな魅力です。
全体をマンガと文章で構成しており、初心者にも理解しやすいよう工夫されています。一方で、一部のページでは情報が詰め込まれすぎており、読み手によっては流れがやや追いづらいところがあります。専門用語も都度説明がされてはいるものの、やや説明不足に感じる部分もあるため、厳しめに1点減点としました。
赤ちゃんの月齢ごとの具体的なアドバイスが多いため、0歳〜5歳前後の家庭には非常に有効です。ただし、対象読者が育児中の保護者に限られるため、広く一般に応用できる内容とは言えません。一方、赤ちゃんを取り巻く周囲(保育士、祖父母など)にとっても参考になる内容がある点で、比較的汎用性は高めです「幸福度」「親の心の健康」など育児全体に活かせる視点も含まれており、他分野への応用余地もあります。
語り口はやさしく親しみやすいですが、整っていないレイアウトが多く、読みづらさを感じる箇所が散見されました。マンガ形式の導入や章ごとのテーマ分けは良い工夫ですが、全体的に情報量が多く、冗長に感じられる部分もあります。もう少し章構成がスリムで整理されていれば、読者の負担も減ったかもしれません。
小児神経科医や産婦人科医など専門家の監修もあり、科学的根拠に基づいたアドバイスが多く含まれています。また、海外の研究結果や心理学講座の引用なども見られ、信頼性の高い情報提供がされているのが好印象です。ただし、やや著者個人の体験談や主観的な表現が多く、学術的厳密性には欠ける面もあるため満点には至りません。とはいえ、実践的な内容を優先した上での選択であり、一般読者には十分な専門性と言えるでしょう。

ねんねトレーニングって泣かせるやつだと思ってたけど、全然違ったんだね。

うん、環境を整えてあげるとか、気持ちに寄り添って習慣を作るっていう考え方にホッとしたよ。

今まで「泣くのは仕方ない」って諦めてたけど、少しずつ変えていけるんだなって思えた。

俺たちが余裕を持てば、赤ちゃんも安心できるんだよね。まずは寝かしつけの流れ、見直してみようか。

よし、今夜からルーティンづくり始めよう!“おやすみの合図”からね!
夜泣きに悩む親は少なくありませんが、その悩みには“向き合い方”という解決のヒントがあります。本書は「赤ちゃんのせい」にしないアプローチで、親も一緒に成長できる優しい視点をくれます。
心がすり減る前に、今日からできることを一歩ずつ始めてみませんか?
