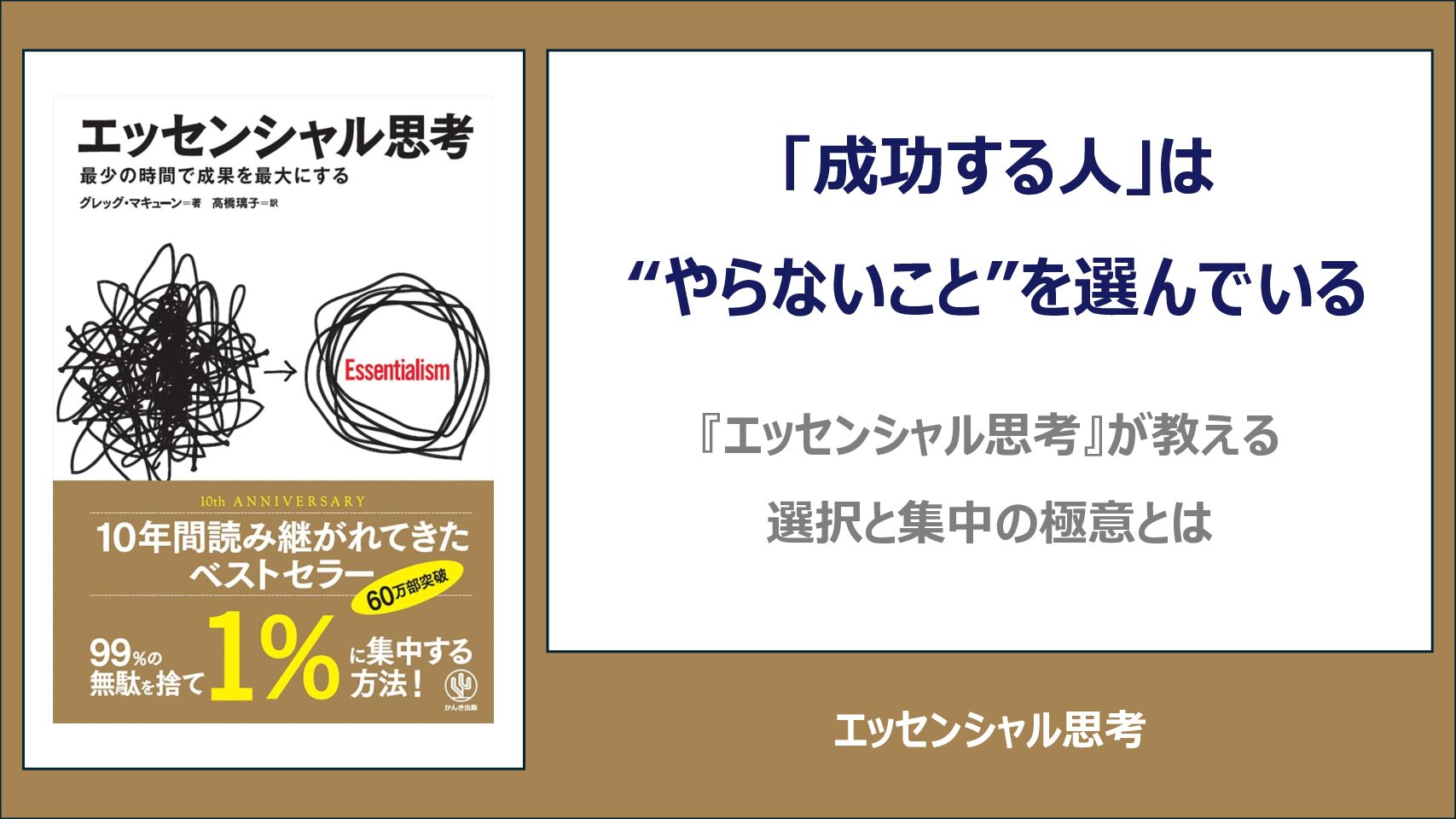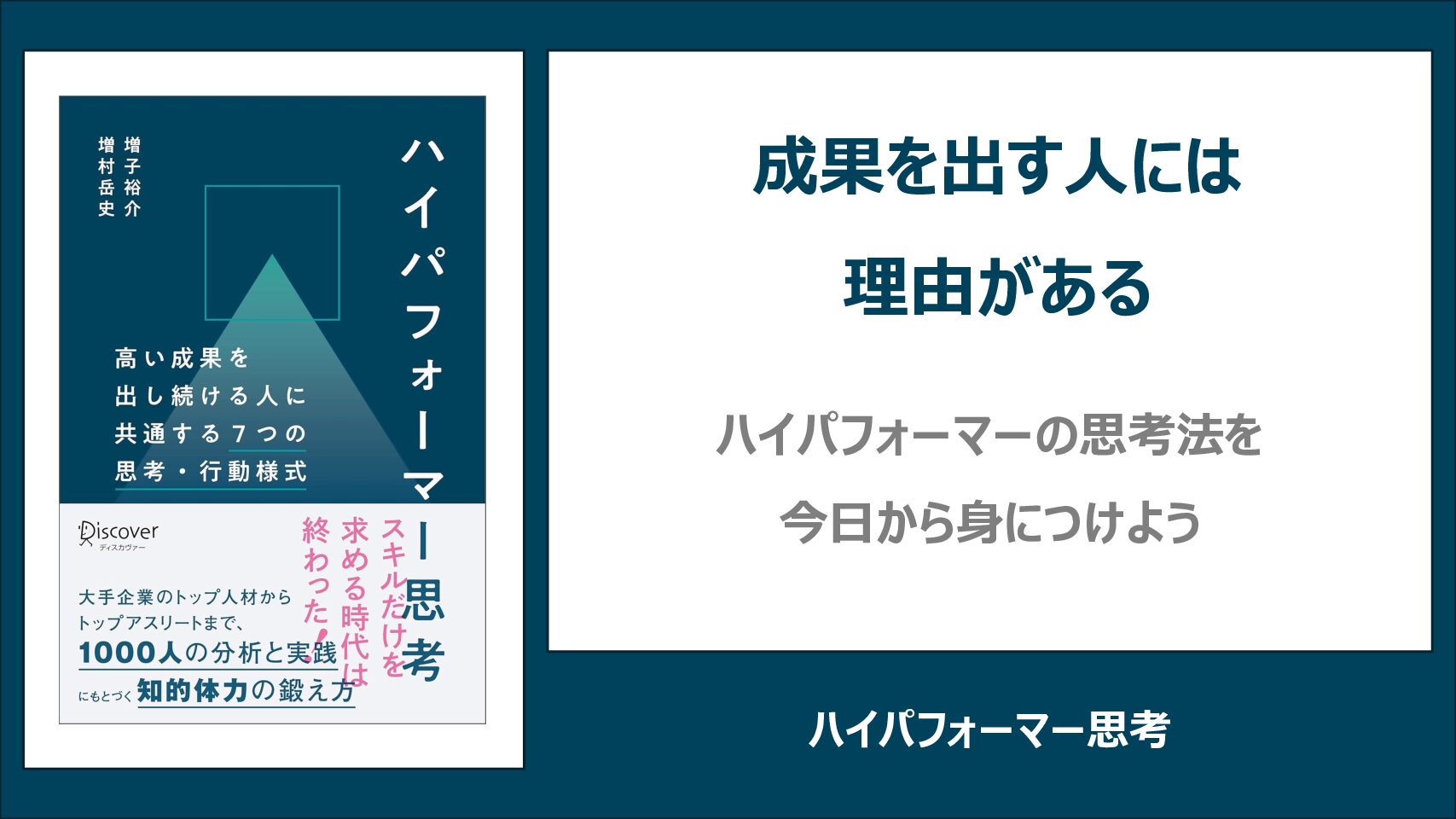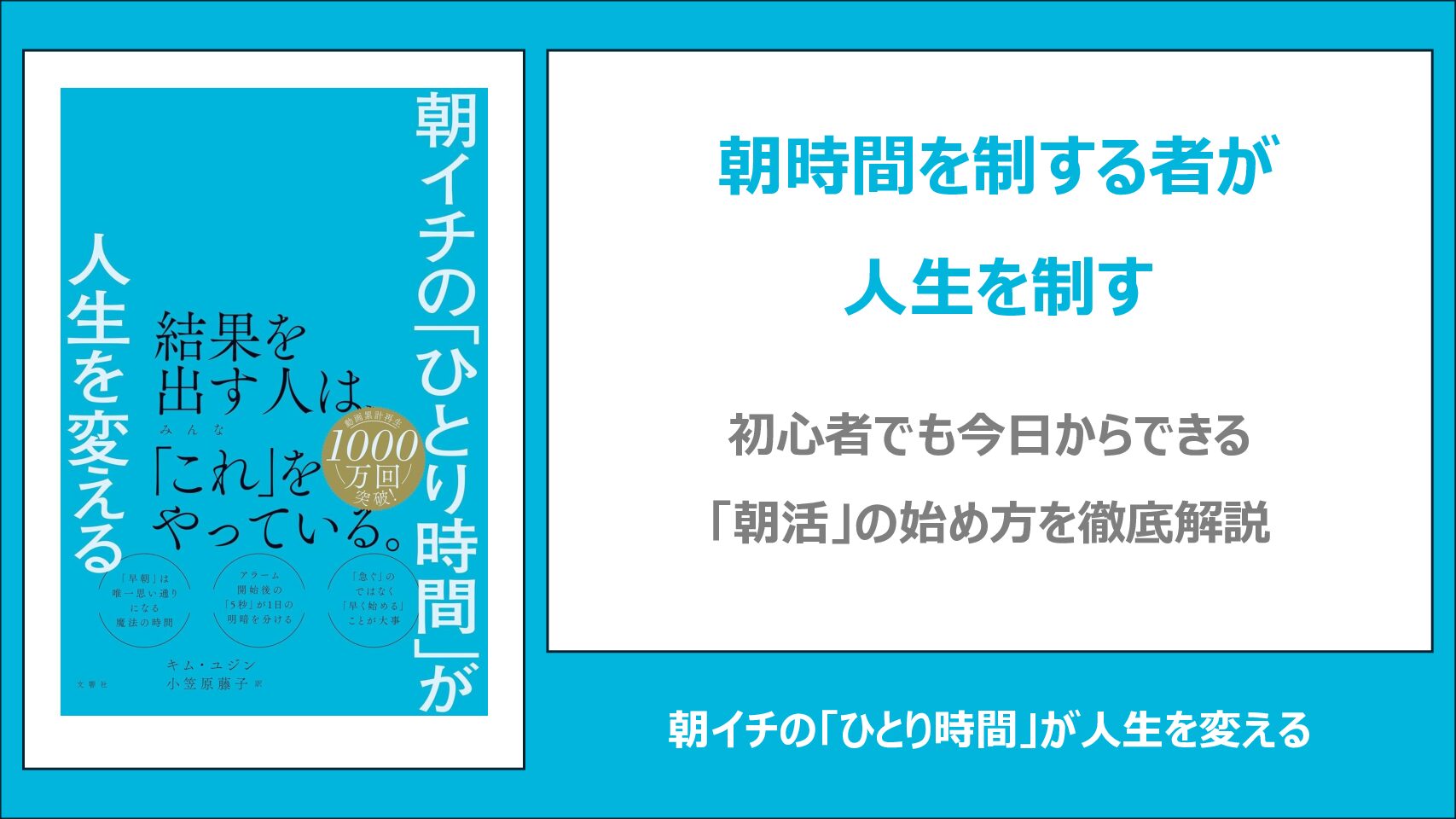この記事はで読むことができます。

ねぇTom、最近「やること多すぎて、結局何も進んでない」って日ばっかりなんだけど…これって私だけ?

いや、それめっちゃわかる!TODOリストは常に満タン。達成感ゼロ。もう嫌になるよね。

なんか「全部やる」って一見かっこいいけど、現実は時間だけ吸われて疲れるばっかり…。

それで最近『エッセンシャル思考』って本を読んだんだけど、「より少なく、しかしより良く」っていうのがすごく刺さった。
「時間がない」「忙しいのに成果が出ない」そんな毎日に心当たりがあるなら、あなたの“思考のクセ”に原因があるかもしれません。
今回は、グレッグ・マキューン著『エッセンシャル思考』から、情報過多の時代に埋もれず成果を出す「選択と集中」の極意を紹介します。
選択肢が多い現代では「全部やろう」としてしまいがちです。しかし、その結果として時間もエネルギーも分散され、何一つ本気で取り組めない状況に陥ってしまいます。
重要なことを見極め、それ以外を手放す“選択の力”こそがエッセンシャル思考の核です。「全部できる」ではなく「何をやらないか」を選ぶ力を鍛えることが求められます。
「見極める・捨てる・しくみ化する」の3ステップを日常に取り入れることがカギです。意志力ではなく、習慣と仕組みで実行し続ける環境を整えることが成功の鍵となります。
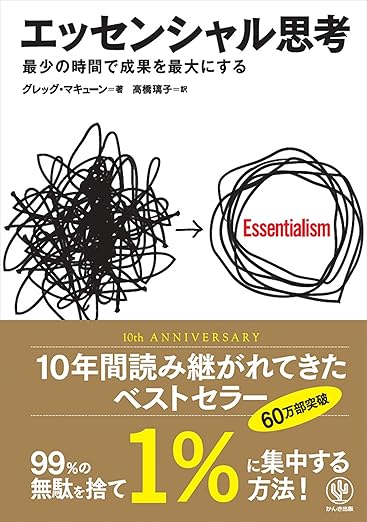
| 著者 | グレッグ・マキューン |
| 出版社 | かんき出版 |
| 出版日 | 2014年11月17日 |
| ジャンル | 生産性・時間管理 |
「全部やろうとする」のは、一見すると努力家の姿勢のように見えますが、実は非効率で成果を下げる大きな落とし穴です。本当に大事なことに集中するためには、やらないことを明確に決める“選択の勇気”が必要です。エッセンシャル思考とは「全部やらない」ことで「最大の成果を出す」思考法であり、実は多くの成功者が自然に取り入れています。
たとえば、Appleのスティーブ・ジョブズは「何をやるか」ではなく、「何をやらないか」をチームに問い続けていたことで有名です。やらないことを決めることで、最も重要なプロジェクトに集中でき、革新的な製品が生まれました。つまり、あらゆる選択肢に「イエス」と答えるのではなく、限られたものに「絶対にイエス」と言える選択だけを残すべきなのです。
本書では「90点ルール」という強力な基準が紹介されています。これは、自分が「本気で取り組みたい」「今しかない」と思えるものでなければ、たとえ70点や80点でも“ノー”と言うという考え方です。一見もったいないように思えますが、その潔さが“自分の選択”に責任を持つ力を養ってくれます。たくさんの「まあまあ良い選択」に手を出していては、最も重要な1つに力を注ぐ時間もエネルギーも残らないのです。
この考え方を実生活に落とし込むなら、まずは「今週絶対に達成したいことは何か?」を1つだけ書き出してみましょう。そしてそれに関連しない仕事・タスク・人付き合いには、意識的に距離を置いてください。最初は勇気がいりますが、やらないことを選んだ分だけ、自分が本当に集中したいことに全力を注ぐことができ、成果の出方がまるで違ってきます。
何かを得るためには、何かを捨てなければならない。これはビジネスでも人生でも避けて通れない「トレードオフ」の真理です。しかし、私たちはこの現実を避けがちです。「全部欲しい」「全部こなしたい」という願望が、自分のエネルギーや集中力を無限に消費させ、最終的にはどれも中途半端に終わってしまいます。
『エッセンシャル思考』では、サウスウエスト航空とコンチネンタル航空の例が語られています。前者は「格安・定時運航」に集中するために機内食や座席指定をあえて捨て、コストダウンとサービスの徹底に成功しました。後者はすべてを取り入れようとした結果、方針がぶれて業績を悪化させました。これはまさに、トレードオフを受け入れる勇気の差です。
現実の生活でも、似たような選択を迫られる場面が多くあります。たとえば、仕事を早く終わらせたいからと子どもとの会話を後回しにする、あるいは無理して全部の会議に出ようとするなどです。しかしそれは、貴重な時間やエネルギーを浪費し、自分が本当にやりたいことや果たすべき役割を見失う原因になります。
トレードオフを受け入れるとは、「あえて捨てる」ことで「主導権を取り戻す」ことです。何かを選ぶことで、他の何かを断ち切ること。たとえば「土曜日は一切仕事の連絡を取らない」「1日のうち90分はSNSを完全に断つ」など、明確な線引きをすることが鍵になります。そうすることで、結果として本当に大事なものがくっきりと浮かび上がってくるのです。
自分が何を優先し、何を捨てるのか?この問いを毎日自分に投げかけてみましょう。その問いに即答できるようになったとき、あなたはすでにエッセンシャル思考の第一歩を踏み出しています。
「重要なことに集中するのはいいとして、それを毎日続けるのが難しい」と感じていませんか?まさにその通り。だからこそ『エッセンシャル思考』では、“意志力”ではなく“仕組み”で自分を動かすことの重要性が強調されています。つまり、やる気や気分に左右されず、自然に集中できる環境を作るということです。
本書では、成功者たちがどのようにエッセンシャル思考を「日常化」しているかが紹介されています。たとえば、LinkedInのCEOは1日2時間の“空白時間”をあらかじめスケジュールに入れておき、自分のために思考する時間を確保しています。また、ビル・ゲイツは年に2回、完全に業務から離れて“考える週”を設けているそうです。
これらは、意思ではなくルールや仕組みで「重要なことに集中できる自分」を作っている良い例です。たとえば、集中したい作業は午前中に設定し、午後はなるべく打ち合わせを入れない。スマホの通知はすべてオフにする。夜は必ず7時間以上眠る。こうした「無意識でもできる習慣設計」が、成果の差を生むのです。
また、脳のコンディションを整えるためには、睡眠・食事・遊び・孤独な思考時間が欠かせません。エッセンシャル思考ではこれらを“投資”とみなし、自分自身という資産を最大限に活用するためのリソース管理だと位置づけています。
ここでのポイントは、「継続可能」で「仕組みにできる」こと。たとえば「考える時間」は朝イチの15分だけにしてもよいですし、「断る習慣」は定型文をメールに登録しておくだけでも効果があります。あなたが日常的に「迷わずエッセンシャルな選択ができる状態」を意図的に作ることが、継続のカギなのです。
「まあ悪くない」程度の依頼やチャンスには、思いきってノーを言う練習を始めましょう。何かを引き受ける前に「これは90点以上の価値があるか?」と自分に問いかけるのがコツです。
予定やタスクを埋めるのではなく、空白を“意図して”つくる感覚を持つことが重要です。1週間で「迷ったけど断ったこと」を記録すると判断力が養われていきます。選択肢を絞ることで、集中と余白が生まれます。
「すぐに返事をしない」ことから始めてみましょう。たとえば「検討させてください」「今は難しいかもしれません」といった返答のテンプレートを用意しておくだけでも安心感が生まれます。
断る勇気が出ない場合は、最初から条件付きで関わり方を限定する方法も効果的です。ノーと言っても案外相手は気にしないという実感を得られれば、心理的なハードルは下がります。繰り返すうちに“自分の時間”を守る感覚が強まっていきます。
朝起きたとき、または仕事を始める前に、静かに1分だけ“今日の最重要タスク”を考える時間を設けましょう。紙に一言で書き出して机に置いておくだけでも、意識がブレにくくなります。
日中迷ったときには、その紙を見て立ち戻れるようにします。夜の振り返りで「今日は最重要に集中できたか?」を点検する習慣をつければ、判断力と優先順位の精度がどんどん上がります。小さな意識の積み重ねが、大きな成果を生み出します。
この書籍は、「より少なく、しかしより良く」という原則をもとに、仕事や生活で本当に重要なことに集中するための具体的な方法を提示しています。断る技術、見極めのルール、習慣化の方法など、実行可能なテクニックが豊富で実用的です。ただし、職場環境やライフスタイルの制約が強い人には、すぐには応用しにくい部分もあります。
平易な言葉と豊富な事例で構成されており、読者が「エッセンシャル思考」の重要性と方法論を自然に理解できるよう工夫されています。比喩(クローゼットの整理など)や具体的な人物のエピソードが多用されているため、内容の抽象性を感じさせません。説明が丁寧で、読み手が迷わずに読み進められます。
ビジネスだけでなく、家庭生活や人間関係など多方面に応用できる内容になっています。誰にでも関係する「時間」「選択」「優先順位」といったテーマが中心で、読者の立場を問わず役立ちます。一方で、実行のためにはある程度の自己裁量や時間管理の自由が必要で、制約の多い環境ではフルに活かしにくい場面もあります。
語り口は軽快で、論理の流れも明快。章ごとにテーマが明確に区切られており、どこから読んでも要点がつかめます。過剰な専門用語や理論展開はなく、実感を伴ったエピソードでテンポよく読み進められます。挿話や引用も魅力的で、読書体験として心地よさがあります。
心理学や経済学、経営理論などに一定の裏付けがありますが、専門書というよりは実用エッセイに近い内容です。科学的なエビデンスを細かく検証するというより、経験則や事例を中心にした説得力で構成されています。高度な専門的知識を求める読者にはやや物足りなさを感じるかもしれません。

なるほどね〜。「やらないことを決める」って、今まで逆にしてたかも…。

わかる。「チャンス逃しそう」って思って、断れなかったのが一番の落とし穴だった気がする。

「やること」じゃなくて「やらないこと」を選ぶのって、逆に勇気いるんだね。

でもその分、自分で選んだ感あるし、心の余裕ができるんだよなぁ。
選ばないことは、自由を手にすること。「全部やろう」をやめて、「これだけはやる」を選べば、人生はもっと軽く、もっと前に進み始めます。