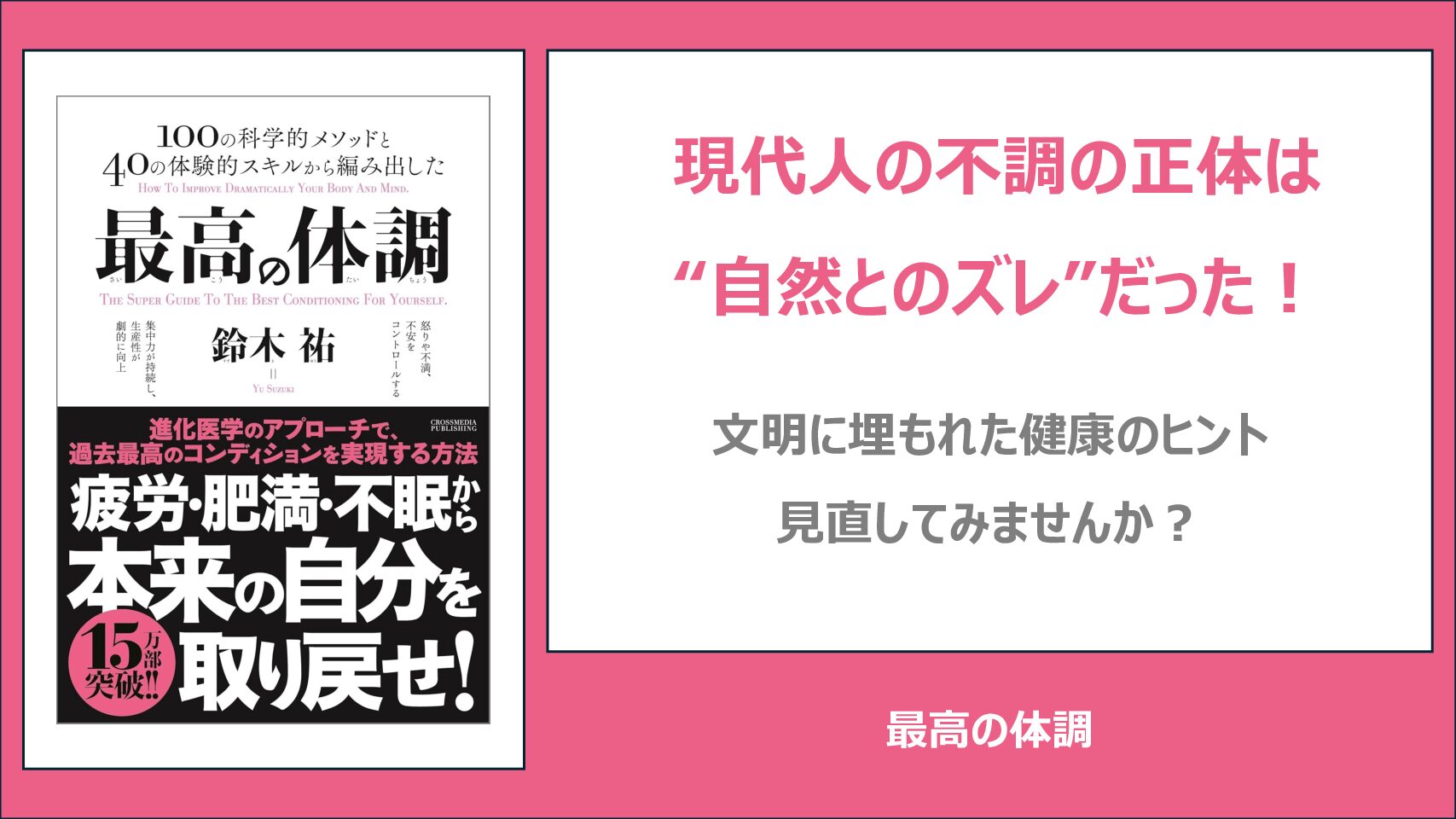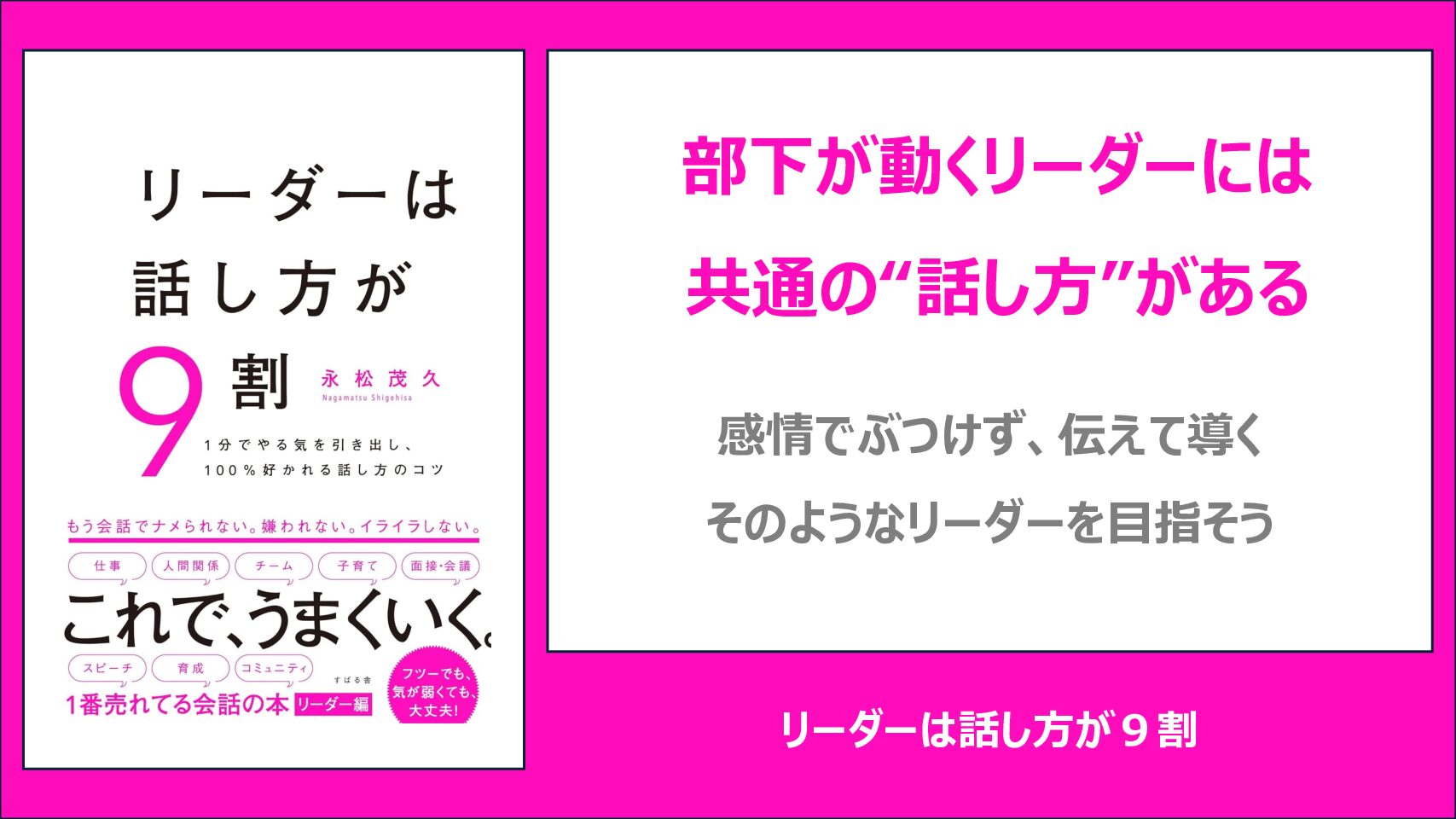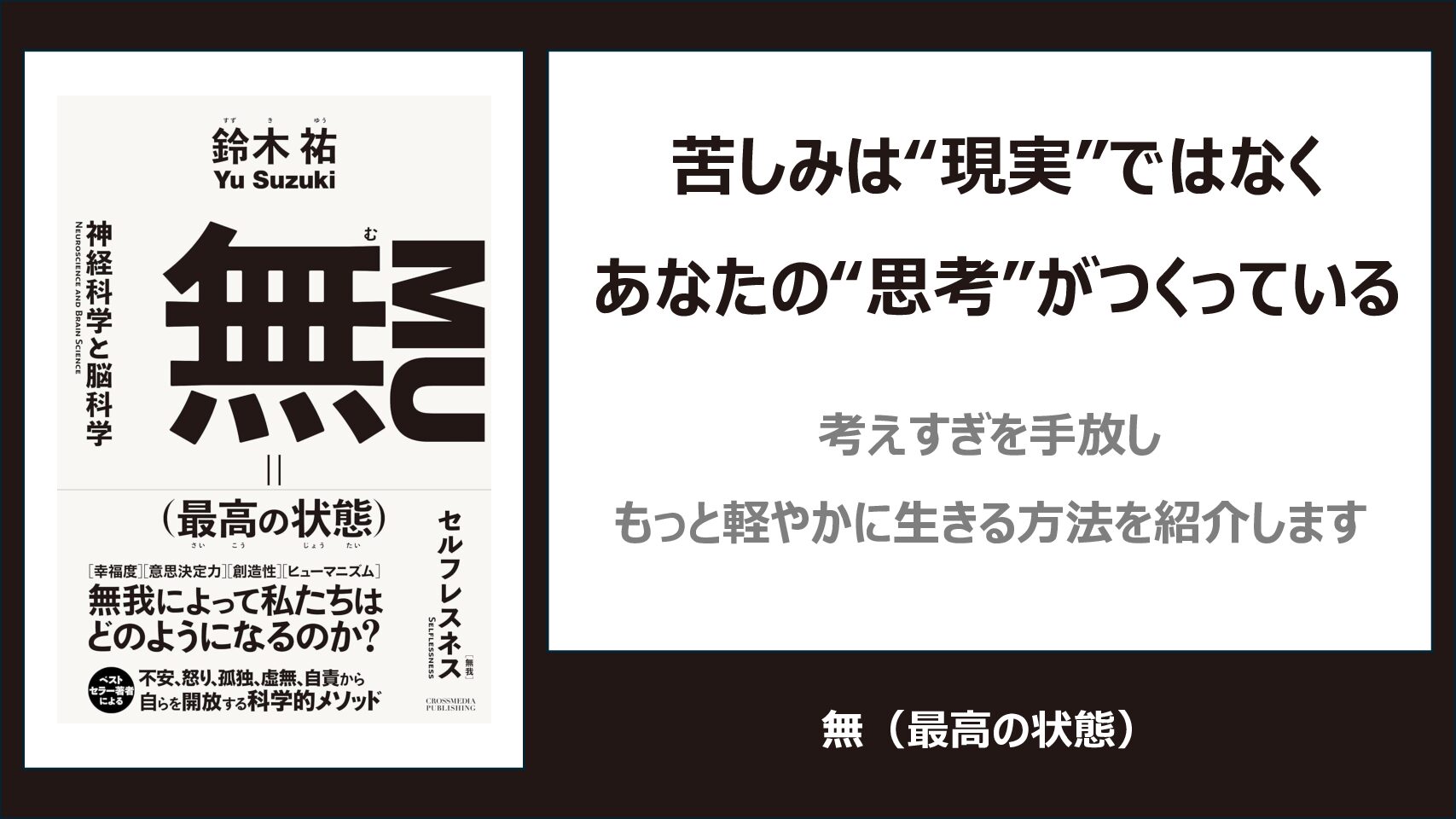この記事はで読むことができます。

ねぇTom、最近なんとなく体がだるい日が続いてるのよね…。病院に行っても「異常なし」って言われるし、なんかスッキリしないの。

それ、よく聞くよね。僕の周りでも「原因不明の不調」で悩んでる人、結構いるよ。もしかしたら、身体じゃなくて“環境”の問題かもしれないよ。

環境って?ストレスとか睡眠不足のこと?

うん、それもあるけど、もっと根本的な話。僕たちの身体って、進化の過程で獲得してきたものなんだよ。でも今の文明って、その進化のスピードに合ってないらしいんだ。

へぇ…進化と文明のズレが原因?そんなこと考えたこともなかったわ。

実は最近読んだ本に、そのあたりのことがすごく分かりやすく書かれててね。「あぁ、だから不調になるんだ!」って、目からウロコだったよ。
テクノロジーの進化により、私たちの生活は格段に便利になりました。ボタンひとつで食事が届き、スマホひとつで世界と繋がれる時代。けれど、その便利さの裏で、身体のだるさや不眠、気分の落ち込みなど、漠然とした不調に悩まされる人が増えています。
それはなぜなのか。その答えは、私たち人類の「進化」と「文明」のギャップにあるかもしれません。何万年もかけて形成された私たちの身体と脳は、今の環境に最適化されていないのです。このギャップが、気づかぬうちに身体と心に負担をかけているのです。
本記事では、そんな現代人の不調の原因を「進化医学」という視点から解説した書籍をもとに、わかりやすく紹介します。読み進めれば、あなたの不調の理由と、その解決策が見えてくるはずです。
私たちの身体は、数百万年にわたって自然環境に適応する形で進化してきました。しかし、ここ数百年の文明の急速な発展により、環境とのギャップが生じ、心身に無理がかかっています。たとえば、運動不足や睡眠リズムの乱れ、加工食品の摂取が不調の大きな原因となっています。
進化に逆らったライフスタイルを続けると、身体や脳にストレスが蓄積され、慢性的な不調に繋がっていきます。逆に、進化に沿った行動を取り入れることで、本来のパフォーマンスを発揮し、健やかな状態を取り戻すことが可能です。
自然のリズムに近い生活を意識し、小さな習慣を見直すことがギャップを埋める第一歩です。睡眠、運動、食事など、日常の中で実践できるヒントが本書には豊富に紹介されています。

| 著者 | 鈴木 祐 |
| 出版社 | クロスメディア・パブリッシング |
| 出版日 | 2018年7月13日 |
| ジャンル | 健康・フィットネス |
現代人の不調の多くは、「人類の進化の過程」と「現代社会の生活環境」のギャップから生まれています。
たとえば、人間の体は何十万年もの間、自然環境での生存に適応してきました。気温や湿度の変化、太陽の動きに合わせた生活リズム、適度な空腹状態などが前提の設計になっているのです。
ところが現代では、24時間冷暖房完備、夜でもまぶしい照明、エレベーターや車による移動、飽食状態の生活が当たり前になりました。このような文明の進歩は、快適さと引き換えに私たちの「自然な体の働き」を狂わせています。
たとえば、慢性的な頭痛や疲労、便秘、不眠などの“未病”と呼ばれる状態は、身体が過去の環境に適応したままなのに、今の生活についていけないサインなのです。著者はこうしたズレを「進化の遺産」と表現し、今の環境が“異常”なのだという新しい視点を提供してくれます。
だからこそ、私たちは不調を感じたとき「何が足りないか」ではなく「何が多すぎるのか」「何が本来の状態から逸れているのか」を考える必要があります。この根本原因を理解すれば、情報に振り回されず、自分の体の“原始設定”に沿った対処法を見出せるようになります。
人類は99%以上の歴史を、狩猟採集民として過ごしてきました。その間、空腹や断続的な食事、未加工の食材に適応してきた体は、「飢餓に強く」「過剰に弱い」性質を持っています。
しかし現代では、コンビニやファストフードが溢れ、いつでも高カロリー・高糖質の食事が手に入ります。例えば、ジュース1本で砂糖約10〜15g、白米やパンはすぐに血糖値を急上昇させますが、こうした急激な変化に人間の体は対応できません。
その結果、血糖値スパイクやインスリンの過剰分泌が慢性的な疲労や肥満の原因となっています。著者は、現代の加工食品を「進化の罠」と呼び、我々の遺伝子がこの食環境に完全に不適応であることを強調します。
また、飽食状態では消化器官が休まらず、免疫機能や腸内環境にも悪影響を与えると指摘されています。このように、“食べること”は健康の基盤ですが、その選択を間違えると進化の流れに逆らうことになり、不調が起きやすくなるのです。
だからこそ「何を食べるか」だけでなく、「いつ、どのように食べるか」も含めた見直しが必要であり、本書はそれを生物学的に説得力ある形で教えてくれます。
人間は本来、日の出とともに目覚め、日没後に休むという生活リズムを持っていました。これは進化の過程で太陽光と連動した「体内時計(サーカディアンリズム)」が作られたためです。
ところが現代では、スマホやパソコンのブルーライト、夜遅くまでの仕事や娯楽により、睡眠リズムが狂いやすくなっています。実際に、深夜0時以降に寝る人の割合は年々増加し、メラトニンの分泌リズムが乱れて不眠症やうつ傾向が増えています。
運動においても、原始時代の人類は1日平均1〜2万歩を自然に歩いていたとされていますが、現代では通勤・在宅勤務の普及で1日3000歩以下という人も珍しくありません。これでは筋力や心肺機能が衰えるだけでなく、血流が滞り、疲労や冷え性、慢性痛の原因にもなります。
著者は「動かないことが体の異常信号」として現れると述べ、少しでも自然な生活リズムを意識すべきだと語っています。たとえば、朝起きて10分でも日光を浴びる、階段を使う、座りっぱなしを防ぐなど、シンプルな行動が効果的です。
このように、睡眠と運動の“ズレ”を修正することが、現代人の不調を根本から改善する鍵となります。
まずは毎日の生活に「自然」を取り入れることを意識しましょう。たとえば、朝起きたらカーテンを開けて日光を浴び、エアコンに頼りすぎず、季節の気温を感じる時間を増やすことが有効です。休日は公園や自然のある場所で過ごすことで、身体の感覚が本来のリズムに戻りやすくなります。
加工食品や砂糖の多い食品を控え、できるだけ自然に近い食材(野菜・魚・豆類)を選びましょう。また、夜遅くの食事は避け、日中に食事を済ませることで消化リズムが整い、体の回復力も高まります。16時間断食(朝食を抜くなど)も、体に「空腹」の時間を与える手段として効果的です。
毎朝同じ時間に起き、朝日を浴びる習慣をつけることで、体内時計を整えやすくなります。スマホやPCの使用は寝る1時間前にはやめ、代わりに読書やストレッチでリラックスしましょう。また、日中は意識して階段を使ったり、1時間に1回は立ち上がって軽い運動をすることが、現代型の運動不足の解消に役立ちます。
実践的なアドバイスが豊富で、食事、運動、メンタルケアまで幅広く網羅されています。ただ、万人向けというより、生活を大幅に改善したい人向けの内容に寄っているため、やや実用範囲は絞られます。また、提案する行動の難易度(例:パレオダイエット、デジタル断食)が高めです。一部、実行に覚悟や継続的努力が必要なため、即効性は限定的でしょう。
専門用語も多くなく、ストーリーや例え話がうまく使われていて読みやすいです。一方で、進化論、文明病といった理論背景が何度も繰り返し説明されるため、ややクドい印象もあります。内容が多岐にわたるので、読者によっては焦点がぼやけて感じられるかもしれません。章ごとのつながりもやや冗長に感じる箇所がありました。
取り扱うテーマ(食事・運動・メンタルヘルス)は普遍的ですが、根本に「文明病」理論が強く効いています。現代的なストレス社会や都市生活を前提にしているため、田舎暮らしや既に健康志向な人にはフィットしにくいです。また、ビジネス・教育・育児など、他の分野への応用は若干難しい構成です。普遍的な理論よりも、特定のライフスタイル改善に特化している印象です。
語り口はフレンドリーで軽快な文体が続き、非常にスムーズに読み進められます。適度にユーモアを交えつつ、真面目な話題にもしっかり向き合っている点は好印象です。ただし、情報量がかなり多く、1章ごとに密度が高いため、一気読みすると疲れます。章末のまとめやガイドがもう少し整理されていると、さらに良かったでしょう。
進化医学や心理学の引用も豊富で説得力はありますが、すべてが最新の科学的コンセンサスとは限りません。個人的体験談や著者の仮説に依存している部分も目立つため、学術的厳密さはやや低いです。あくまで「科学的に裏付けられたライフハック集」として読むのが適切です。批判的思考を持って読む必要があり、専門書というよりは啓蒙書寄りです。

いや〜、この記事読んで、自分の生活に思い当たることがありすぎて、ちょっとゾッとしちゃったよ…。

だよね。「現代人の不調は文明とのズレにある」って、最初は大げさかと思ったけど、全部納得しちゃった。

特に“進化が追いついてない”って話、すごくリアルだった。スマホの光とか、朝日浴びる大事さとか…。

俺も朝日とタンパク質意識してみようかな。寝起きのだるさ、あれ完全に生活習慣のせいかも。

そうそう、無理して薬に頼る前に、まず生活を「自然に寄せる」っていう発想が新鮮だったよね。

文明の恩恵は受けつつ、自然とのバランスも取り戻す。なんか、今の自分たちにぴったりのテーマだったかも。
「現代人の体調不良、その原因は進化と文明のギャップにあった」という本を通じて、私たちは“自然とのズレ”がどれほど体に負担をかけているかを知ることができました。
便利で快適な現代社会。しかし、その裏で、私たちの体は何万年も前の環境に適応したまま変わっていません。本書で紹介された知見は、特別な道具や知識がなくても、誰もが日常に取り入れられるものばかりです。朝の光を浴びる、食事を見直す、自然と触れ合う。どれも小さな一歩かもしれませんが、確かな変化をもたらしてくれます。
体調の不調に悩むすべての人にとって、この本は「答え」のヒントになるはずです。あなたの不調、その原因は“あなた”ではなく、“時代のズレ”かもしれません。