この記事はで読むことができます。

ねぇTom、友達の甥っ子が、「時間はあるけど、何したらいいか分からない」って悩んでてさ。

あー、それわかるわ…。大学生活って自由すぎて、かえって何もせずに終わっちゃいがちなんだよね。

そうそう。私も当時はバイトとかでなんとなく過ごしてたかも(笑)

僕も最初はそんな感じだった。でもある時、「この時間って二度と戻ってこない」って気づいて、使い方を変えたんだ。

え、それで何を始めたの?

例えば、興味がある授業には“とにかく飛び込んでみる”とか、教授に話しかけてみるとかね。ちょっとした行動が、思ってた以上に面白い展開につながったりしてさ。

たしかに…社会人になると、時間が自由に使えるって本当に貴重なことだったって気づくよね。
大学生活は自由で、時間もあって、選択肢も多い。でもその反面、「何をすればいいかわからない」「毎日がなんとなく過ぎていく」――そんな不安を抱える大学生も多いのではないでしょうか?
この記事では、実際に京都大学で学生生活を送った著者の体験をもとに、大学生の今だからこそできる行動や、人生の土台になるような経験の積み方を紹介します。
特別なスキルも計画もいりません。必要なのは、少しだけ行動を変える“きっかけ”です。
自由すぎる時間と目的のあいまいさが、充実感を奪う原因になっています。意識を少し変えるだけで、過ごし方の質は大きく変わります。
大切なのは、特別なことをするより「今の環境をどう使うか」です。授業・出会い・失敗――すべてが“後から効く”経験になります。
行動を変えるのは難しくありません。ちょっとしたきっかけや視点の転換で、“何気ない日常”が人生の財産に変わります。
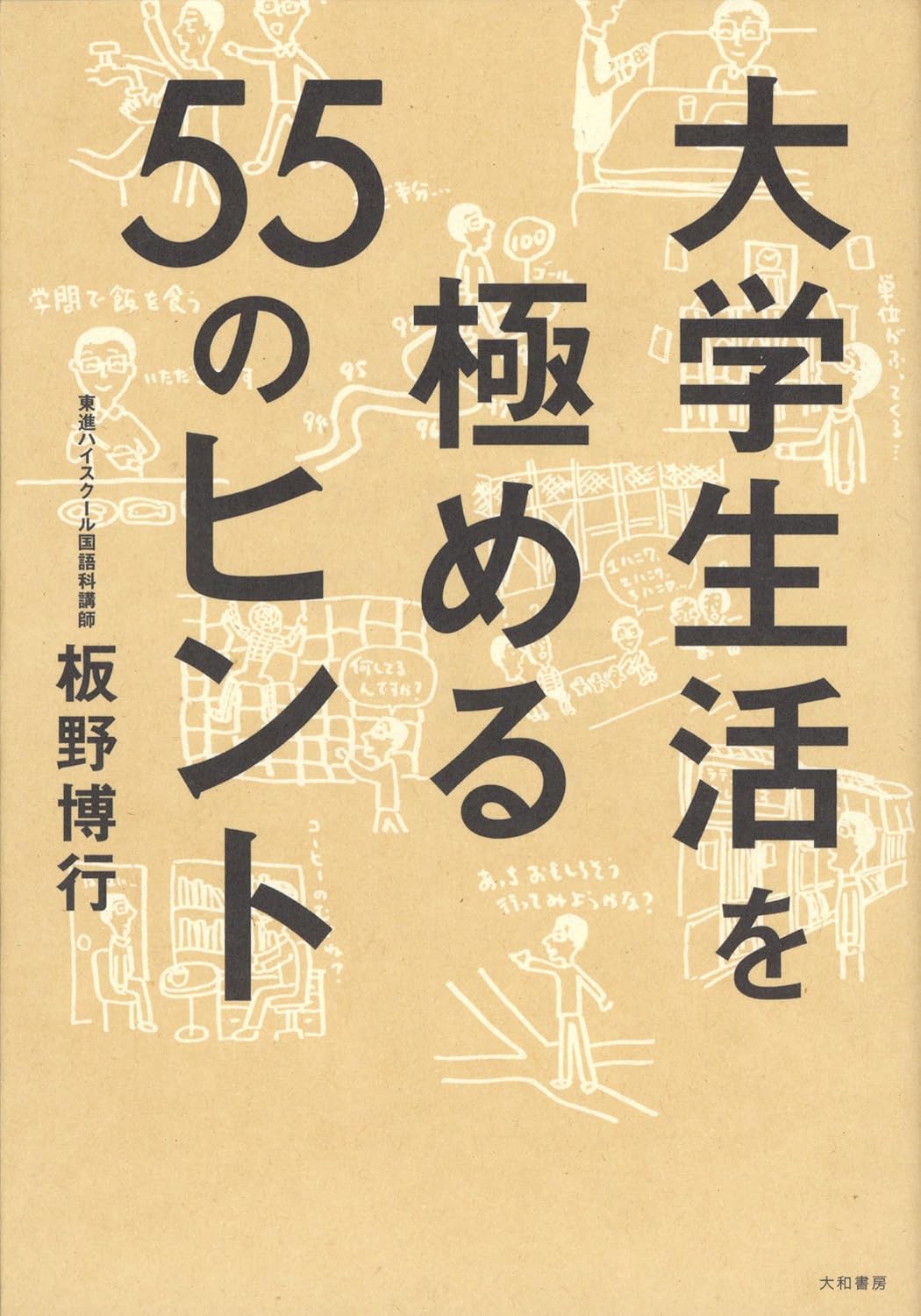
| 著者 | 板野 博行 |
| 出版社 | 大和書房 |
| 出版日 | 2015年6月22日 |
| ジャンル | キャリア・人生設計 |
大学の授業はつまらないと思われがちですが、それは“興味がない講義”をただ受けているからかもしれません。なぜなら、大学には一般的な講義のほかにも、実験型、ディスカッション型、少人数ゼミなど、自分次第で選べる学びが数多くあるからです。本書では、著者が「とりあえず面白そう」と思った授業に飛び込んだ結果、そこで出会った教授との会話が人生の転機になったと書かれていました。
たとえば、「国際会議に学生を連れて行く」というような、一見自分に無縁と思えるテーマの授業にも関わらず、参加したことで世界の広さを実感したそうです。その経験から、「授業の面白さは“受け身”ではなく“関わり方”にある」と気づき、それ以降、講義の選び方も変わったと語っています。
私自身も、大学時代に外部講師の授業を受けたことで、考え方や価値観が一気に広がった経験があります。どんな授業にも「自分の人生とどうつながるか?」という問いを持って臨むだけで、吸収できる情報の質がまるで変わります。
また、教授に声をかけたり、授業後に感想を伝えるなど、少し踏み込んだ関わりが次のチャンスにつながることもあります。“面白い授業を探す”のではなく、“自分の関わり方を変えてみる”という視点が、大学の学びを深める大きなカギになります。つまり、授業の価値は教授次第でもカリキュラム次第でもなく、自分の参加の仕方でいくらでも変えられるのです。
大学生活で得られる最大の財産の一つが、“多様な人との出会い”です。特に、「ちょっと変わった人」と関わることは、価値観を揺さぶり、自分の枠を広げてくれます。著者は、サークルやアルバイト先で「一見、常識から外れた人たち」に多く出会い、そのたびに刺激を受けたそうです。
たとえば、授業には一切出ないのに本を読みまくって哲学談義をする友人や、極貧生活でも演劇活動に人生を懸ける仲間など。そうした人たちとの会話を通じて、「正解のない生き方」に触れることで、自分の中にあった“型”が壊れていったといいます。
学生時代は、社会的な評価や枠組みから少し外れた世界をのぞける貴重なタイミングです。私自身、部活動で行った合宿で、夜通し語り合ったあの感覚は今も忘れられません。正直、就職活動では役に立たなかったけれど、“生きるってこういうことかもしれない”と思えた経験でした。
安全圏から一歩出ることで、思考の幅はぐっと広がります。つまり、「変な人」との出会いは、大学生だからこそ味わえる“自由の醍醐味”だと思います。
お金がない、時間はある――それが大学生の特権です。なぜなら、「ないからこそ考える」状況にこそ、本当の創造力が育つからです。著者は、貧乏学生としての生活を通じて、「お金をかけずにどう楽しむか」に全力を注いだと語っています。
たとえば、旅費を浮かせるためにヒッチハイクをしたり、学食だけで一ヶ月を乗り切るチャレンジをしたり。一見すると無謀にも思えますが、その中にある“知恵と工夫”は、社会に出てからも活きるスキルだと気づかされたそうです。
また、限られたお金で本を選ぶときの“選択力”や、“物を大切に使う習慣”も、浪費のない生活習慣につながっていったとのこと。私も学生時代、本屋や図書館をハシゴして一冊ずつ読み込んでいた経験が、今の読書好きの土台になっていると感じます。
お金がないからこそ、知恵と工夫で“濃い時間”を過ごせる。つまり、制限があるからこそ生まれるアイデアや経験が、将来の“生きる力”になるのだと思います。
興味が持てない授業でも、「なぜこのテーマが存在するのか」「教授は何を伝えたいのか」と問いながら受けてみましょう。内容そのものより、そこにある背景や構造に目を向けることで、自分なりの学びが見えてきます。“受け身”から“観察者”へ、意識を一段階上げることがポイントです。
サークルや授業で「この人、ちょっとクセ強そう…」と思った人こそ、話してみる価値があります。普段とは違う価値観に触れることで、視野が広がり、自分の考えにも柔軟性が生まれます。居心地のいい人間関係だけでなく、“未知との遭遇”に一歩踏み出してみましょう。
制限を嘆くのではなく、「どうすれば楽しめるか?」に頭を使いましょう。古本屋、無料イベント、自炊生活、旅の工夫――大学生のうちに“知恵で楽しむクセ”を身につけることで、将来どんな状況でも前向きに生きる力が養われます。楽しさは、お金よりも「工夫」から生まれます。
著者自身の京大での学生生活というリアルな体験をベースに、多くの大学生が抱える悩みや迷いに対して実践的なアドバイスを与えており、実用性は非常に高いです。バイトの苦労、授業の受け方、恩師との関係構築、進路の決断など、等身大の学生生活に寄り添った知恵が詰まっています。ただし、やや著者個人の経験や環境に依存する部分もあり、万人にそのまま通用するかには限界があります。
全体を通して語り口が軽快かつユーモラスで、エピソードも具体的かつ生き生きとしており、非常に読みやすいです。特に若い読者、大学生には親しみやすい言葉遣いや構成で、内容の理解もしやすい工夫がなされています。引用や比喩もうまく使われ、難解な部分はほとんどありません。
大学生活を題材にしているため、特に日本の大学生、それも京大に近い自由な校風の学生にはフィットしますが、対象を超えて応用するにはやや文脈が限定的です。大学に通っていない読者や、すでに社会に出ている人には直接的な応用が難しい部分もあります。ただし「自立」「自分で考える」といったテーマは広く響く可能性があります。
文章にリズムがあり、笑いや感動を誘うストーリーテリングが巧みで、テンポよく読み進めることができます。ところどころに挟まれるジョークや関西弁も親しみやすく、ページをめくる手が止まりません。章の構成も細かく分かれていて、一気読みしても、つまみ読みしても楽しめます。
本書は学術書ではなくエッセイやエピソード中心の人生指南書のため、専門的な知見や理論的な裏付けはほとんどありません。登場する学問の話も、専門としてではなく体験談や印象にとどまっているため、学術的な内容を期待する読者には物足りないでしょう。ただし、専門性を意図した本ではないので、役割としては妥当です。

なんかさ、大学時代のことって、思い返せばあの時間が一番“自由に考えられた”時期だったかも。

ほんとにそう。今みたいに効率とか損得ばっかりじゃなくて、無駄なこととか、意味わからないことにハマれたのって貴重だったな。

「変な人と出会う」っていうのも、確かに学生時代だから許されたことかも(笑)

うん。あの頃の出会いや発想って、あとあと“自分らしさ”の核になってる気がする。

今の大学生たちも、うまくやろうとしすぎずに、もっと“混ざりにいって”ほしいね。

そうそう。「何やるか」より、「どう向き合うか」ってことを、伝えたいなって思うよ。
大学生活は、“正解”を探す時間じゃなく、“問い”と出会うための時間。今この瞬間だからこそ味わえる自由を、大切にしてみてください。
