この記事はで読むことができます。

ねぇTom、最近除菌グッズめちゃくちゃ増えたよね。赤ちゃんいる家庭って、特に気をつかうじゃん?

うん、うちもテーブルからおもちゃまで全部アルコールで拭いてるよ。何かダメなの?

実はさ、赤ちゃんにとって“除菌しすぎ”って、逆に体に良くないこともあるんだって。

えっ…清潔第一じゃないの?除菌が健康を守るんじゃないの?

私もそう思ってたけど、読んだ本によると“腸内環境”と“免疫”に関係してるらしいよ。

腸?除菌と関係あるの?…なんか気になってきたな。
赤ちゃんの健康を守るつもりでやっている「除菌」。でも、それが腸や免疫に悪影響を与えるとしたら?今回は、除菌育児の落とし穴と、健康を支える“菌の育て方”をわかりやすくご紹介します。
菌をすべて排除しようとする育児は、実は赤ちゃんの腸や免疫力の発達を妨げている可能性があります。3歳までに多様な菌とふれあうことが、一生の健康に影響するという新たな視点を学べます。
腸内細菌は、消化や免疫だけでなく、精神の安定やアレルギーの予防にも関係しているとされています。赤ちゃん期の腸が“第二の脳”と呼ばれる理由が納得できるはずです。
除菌を減らすだけでなく、母乳や食事、環境づくりを通じて腸内環境を育てる方法が紹介されています。日常生活の中でできる“菌活”が、赤ちゃんの将来の健康につながります。
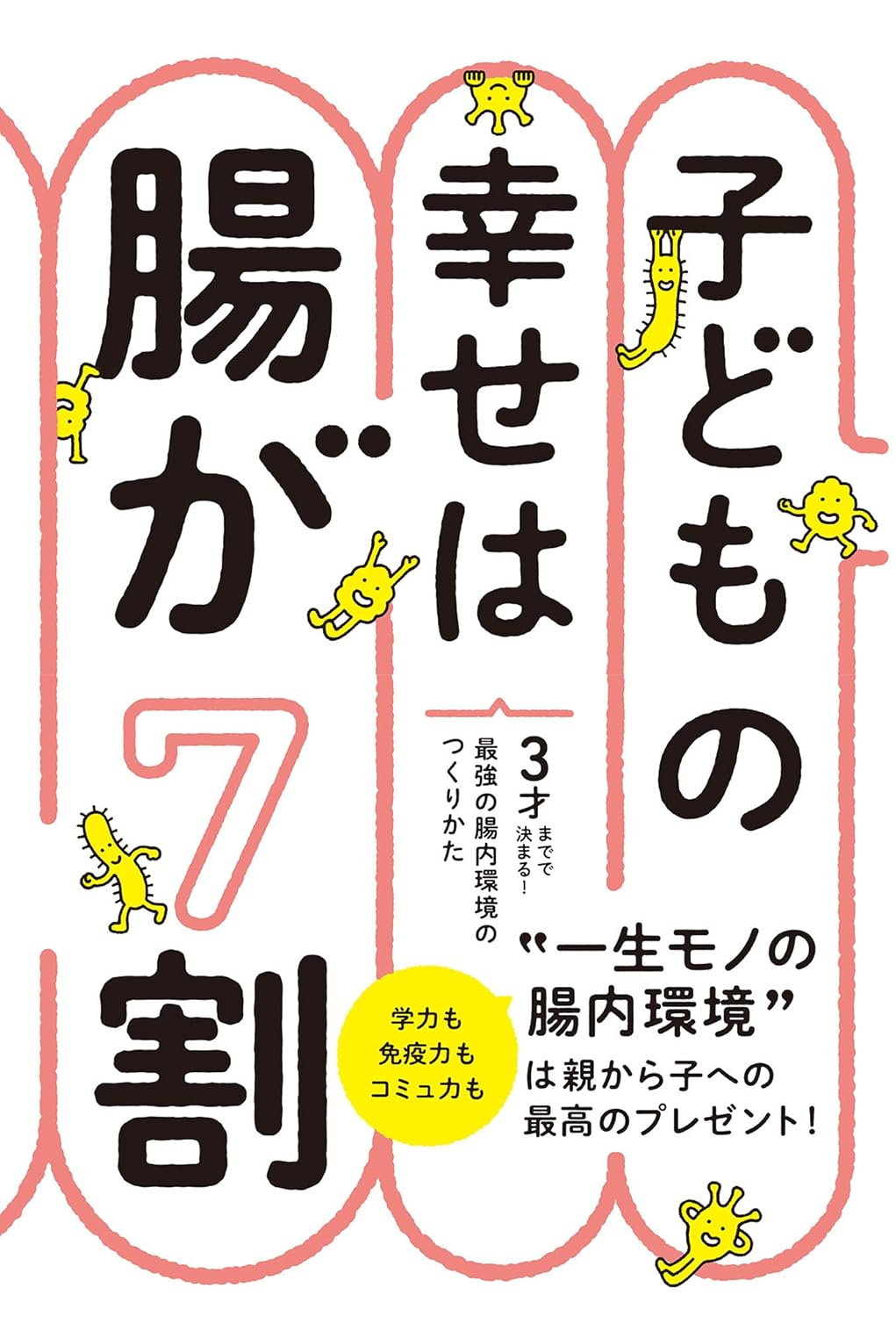
| 著者 | 藤田 紘一郎 |
| 出版社 | 西東社 |
| 出版日 | 2021年6月21日 |
| ジャンル | 子育て・教育法 |
赤ちゃんにとって清潔な環境は大切ですが、過度な除菌は腸内の多様な菌の形成を妨げるリスクがあります。著者は「赤ちゃんは菌とふれあうことで腸内環境を整えていく」と述べており、すべての菌を排除することが必ずしも健康に良いとは限らないと指摘しています。
特に、手や床、身の回りのおもちゃを頻繁にアルコール消毒していると、“必要な菌”までも除去してしまいかねません。赤ちゃんの体は、外の世界に触れながら、免疫や消化の機能を育てています。つまり、多少の汚れや菌との接触は“学び”であり“刺激”でもあるのです。
日本の育児文化は「清潔第一」の意識が強く、無意識に菌を遠ざけている場面も少なくありません。しかし実はその行為が、将来のアレルギー体質や感染症への弱さを招く可能性もあるのです。赤ちゃんの腸に必要なのは、適度に“菌と出会う環境”。過剰な除菌は、かえって赤ちゃんの体の成長を妨げているかもしれません。
腸は単なる“消化器官”ではなく、「第二の脳」と呼ばれるほど心と体に密接に関係しています。赤ちゃんの腸内環境が整っていないと、免疫力の発達が妨げられ、病気にかかりやすくなる可能性があります。
また、腸で作られる物質には、幸せホルモンと呼ばれる“セロトニン”のような神経伝達物質もあり、情緒の安定にも関係しています。つまり、腸が不安定だと、心も不安定になりやすいということです。
最近の研究では、アレルギーやうつ、不安障害などと腸内フローラの関係も注目されています。そう考えると、赤ちゃんの時期にどれだけ腸を育てられるかが、将来の体調だけでなく心の安定にもつながるのです。特に、生後半年〜3歳までの期間は腸内細菌のバランスが急速に形成される重要な時期です。
乳児期の“腸育て”は、単なる健康習慣にとどまらず、人生全体の土台づくりとも言えるでしょう。親としてこの時期にできることは、意外と多いのです。
赤ちゃんの腸内環境を育てるには、“菌を増やす”のではなく、“菌が育つ土壌を整える”意識が大切です。著者は「菌の多様性が健康をつくる」と繰り返し述べており、特定の菌だけでなく、さまざまな菌と共存することが重要だと説いています。そのためには、家の中をすべて無菌にするのではなく、適度に自然や外の環境にふれることが必要です。
たとえば、散歩中に手を土に触れさせたり、ペットと過ごしたり、兄弟との触れ合いからも菌を受け取ることができます。また、食べ物からも善玉菌を取り入れることが可能で、母乳・発酵食品・食物繊維などが役立ちます。
「全部消毒しないと不安」という気持ちを少し緩めて、菌と共に暮らす視点に切り替えることが求められています。赤ちゃんが安心できる環境と、ほどよく刺激される環境、その両方をバランスよく整えることで、腸は本来の力を発揮します。腸を育てるとは、赤ちゃんを“自然と共に育てる”ということなのかもしれません。
「なんとなく」で除菌するのではなく、食後・排泄後など“本当に必要な場面”だけに絞って実施してみましょう。おもちゃや床は毎回消毒するのではなく、汚れが目立ったときに水拭きする程度でも十分です。清潔よりも“安全な自然”を取り入れることが、腸の成長につながります。
赤ちゃんを連れて近所を散歩したり、公園で土や草に触れさせたりすることで、多様な菌と出会う機会が自然と増えます。兄弟やペットとの関わりも、腸内環境の多様性を育てる貴重な体験です。「触っちゃダメ」ではなく「たまにはOK」にするゆるやかな気持ちも大切です。
母乳や発酵食品など、赤ちゃんの腸に良い栄養素を意識して取り入れましょう。また、1日3回の食事リズムや睡眠時間を整えることも、腸のリズムを整える基礎になります。生活習慣そのものが、腸内細菌の活動をサポートする“栄養”になります。
本書は、乳幼児の腸内環境を整えるための育児方法や生活習慣を、実際の子育てに活かせる形で多数紹介しています。特に予防接種の重要性や、菌との適切な接触の推奨など、実用的なアドバイスが豊富です。ただし、実践が難しい家庭環境も想定されるため、万人にとって即応用できるとは限らない点で1点減点しました。
全体を通じて語り口がやさしく、例え話や比喩も多く、専門知識のない読者でも理解しやすく書かれています。漫画や慣用句なども効果的に使われており、読者の興味を引きつけながらスムーズに読み進められる構成です。
赤ちゃんや小さな子どもを育てている親向けの内容が中心であり、それ以外の層には直接的な応用は難しいです。また、特定の文化圏(日本)の生活習慣に密着したアドバイスも多く、他国では取り入れにくい内容も含まれます。
一貫してやさしい日本語で書かれており、親しみやすい文体です。章立てやパートごとの整理も明確で、情報が詰め込まれすぎることもなく、リズムよく読めるよう工夫されています。
医師監修であり、腸内細菌や免疫に関する科学的知識がしっかり取り入れられていますが、専門書ではないため文献的裏付けはやや乏しく、説明も一部は簡略化されています。学術的に厳密さを求める読者には物足りないかもしれません。

Tom、今回読んだ本、かなり衝撃だったよね。「清潔にしなきゃ」って思ってたことが逆効果だったなんて…。

ほんとそれ。除菌シートでテーブル拭いてた自分に「ちょっと待って」って言いたくなったよ。

これからは“菌と仲良くなる育児”にしていこうって思った。気にしすぎず、でも放任しすぎず。

うん、バランスが大事ってことね。腸って本当にすごい役割をしてるんだな…。

知れば知るほど、育児って“体の仕組み”を育てることなんだなって感じたよ。
赤ちゃんの健やかな成長は、目に見えない「腸の中」で始まっています。除菌よりも“菌を育てる”育児へ――そのヒントがこの1冊に詰まっています。
今の育児を見直したい方にこそ、ぜひ手に取って読んでいただきたい1冊です。
