この記事はで読むことができます。

ねぇTom、最近また自己啓発系の本読んでるんだけど…読んだ内容が全然思い出せなくてさ…。

それ、めちゃくちゃ分かる。読んだときは「いいこと書いてるな~」って思うのに、1週間後にはほぼ忘れてるやつでしょ?

そうそう。読んだ意味あった?って自分で突っ込みたくなる(笑)

でもね、それって意志が弱いとかじゃなくて、“記憶に残りやすい読書法”を知らないだけかもしれないよ。

えっ、そんな方法あるの?

あるある。精神科医の樺沢先生って知ってる?読書と記憶の関係について、すごく実践的な方法を教えてくれててさ。

えー気になる!読書って、ただ読むだけじゃダメなのかな?
読書しても、内容をすぐに忘れてしまう――そんな悩みを抱える人は少なくありません。けれど、それは「記憶力がないから」ではなく、「記憶に残りにくい読み方をしているだけ」かもしれません。
この記事では、精神科医・樺沢紫苑さんの著書『読んだら忘れない読書術』をもとに、読んだ内容をしっかり記憶に残す3つのコツをご紹介します。「読んだのに思い出せない」を卒業し、読書を“使える知識”に変えていきましょう。
読んだだけで満足してしまい、記憶に定着させる工夫をしていないことが原因です。読書の「インプット」だけでなく、「アウトプット」をセットにすることが重要です。
読む・話す・書くというシンプルなステップが、記憶と理解を強化します。少しの意識の変化で、読書が“結果につながる”時間になります。
SNSや日記、友人との会話などを通じて、自然にアウトプットを増やす工夫が紹介されています。無理なく続けられるヒントが満載です。
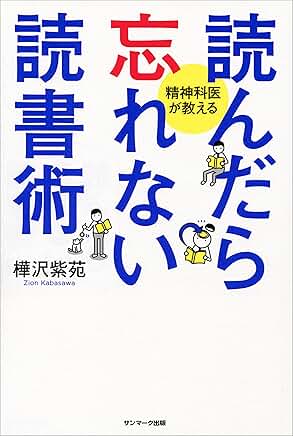
| 著者 | 樺沢 紫苑 |
| 出版社 | サンマーク出版 |
| 出版日 | 2015年4月20日 |
| ジャンル | 勉強法・学習法 |
読書の記憶を定着させるには、読んだ直後に「人に話す」ことが効果的です。なぜなら、脳は“使った情報”を重要だと認識し、長期記憶として保存するからです。
著者の樺沢さんは、「インプット:アウトプット=3:7」が理想と語っています。つまり、読むだけでは3割しか力が発揮されず、アウトプットこそが本当の学びを作るのです。実際に、読んだ内容を家族や友人に話すだけで、理解も深まり、記憶にも残りやすくなるといいます。
これは私自身も実感していて、「こんな本読んだよ」と人に話したことは、意外とずっと覚えています。話すことで、自分の中で再整理され、「どこが印象的だったか」もより明確になるんですよね。
また、アウトプットを前提に読むと、自然と「何を伝えようか」と意識が変わり、読み方も深くなります。話す相手がいなければ、SNSやメモアプリに簡単に感想を書くのでも十分です。
結論として、読書は“読むだけ”で終わらせず、「誰かに話す」ことで記憶が何倍にも残るのです。
読書中に「これは自分にとってどういう意味か?」と考えながら読むと、記憶への定着力が一気に高まります。なぜなら、脳は“感情や経験と結びついた情報”を強く記憶するからです。著者は、「人に話す」だけでなく、「自分で書く・まとめる」ことの重要性も説いています。
具体的には、読んだ内容を3行で要約したり、「この本のポイントは○○だ」と自分なりに結論づける方法です。この“自分なりの言葉”に置き換える行為が、ただのインプットを“使える知識”に変えてくれます。
実際、私も本を読みながらメモを取る習慣をつけたことで、あとから振り返ったときの理解度がまったく違いました。特に印象に残ったフレーズや気づきを、手書きで書き留めるだけでも記憶の持続時間が変わります。
要約やメモには、うまく書こうとする必要はありません。自分の言葉で「なるほど」と思った部分を残せばOKです。読書は“受け取るだけ”でなく、“自分で咀嚼する”ことで初めて身につきます。
つまり、「読んだ内容を自分の頭で再構築する」ことが、記憶に残る最大のコツなのです。
読書を習慣にしても、「アウトプットが続かない」と感じる人も多いはずです。そこで大切なのは、頑張りすぎず、日常に“軽くアウトプットする場”をつくることです。樺沢さんが提案するのは、「読後3分以内に感想を一言書く」など、ハードルの低い方法。
たとえば、読んだ本の表紙を撮ってInstagramに「一言レビュー」を投稿するだけでも、立派なアウトプットになります。大切なのは、「完璧にまとめよう」とせず、読後の熱が冷めないうちに“記録する・伝える”こと。
私はこのブログを通じて、読書記録の振り返りがとても楽になりました。「読んだだけで終わらないぞ」という意識が、結果的に読書の質を底上げしてくれます。
また、こうした記録は後で見返すことで“復習”になり、記憶をさらに強化できます。気軽に続けられるからこそ、アウトプットの習慣は生活に根づきやすいのです。
つまり、“重く考えないアウトプット”こそが、読書の記憶を強く、長く残す秘訣なのです。
読書後24時間以内に、家族や友人に「この本、こんなこと書いてて面白かったよ」と一言だけでも伝えてみましょう。会話がなくても、X(旧Twitter)やLINEのオープンチャットなどで感想をシェアするのもおすすめです。「誰かに話す前提」で読むだけで、読書の集中力と記憶力が驚くほど変わります。
読書ノートを作る必要はありません。スマホのメモアプリでもOKなので、「この本の要点は○○」「印象に残った一文」「自分にとっての意味」の3点を読後すぐに書き出してみましょう。言葉にして残すことで、読書の理解が深まり、あとで振り返るときの手がかりにもなります。
完璧なまとめや長文レビューは必要ありません。読後に一言つぶやく、日記アプリに短い感想を書く、写真付きでSNSに記録するなど、自分が気軽に続けられるアウトプット手段を選びましょう。読書後3分以内に動くことをルールにすれば、内容の記憶がより鮮明に残ります。
読書の記憶定着方法やアウトプット術、スキマ時間の活用法など、実践可能なテクニックが豊富に紹介されています。ただし、一般的な「読書術」から逸脱するほどの独自性にはやや欠け、既知の内容も多く見受けられます。再現性は高いものの、やや理想論に偏る記述も見られ、万人に同じ効果が出るとは限りません。とはいえ、読書を習慣化したい人には手堅い指針となるでしょう。
豊富な例や比喩(料理の鉄人理論、試食理論など)によって内容は非常に噛み砕かれており、読み手の理解を助ける工夫がされています。精神科医としての経験や脳科学の知見を引用しながら、理屈と感情の両面からアプローチしている点も親切です。ただ、話が横道にそれることが多く、焦点がややぼやける箇所もあります。構成にもう少し整理があれば、さらに明快さが増す印象です。
「読書による自己成長」という主題は広く支持されるものですが、実際の内容は著者個人の成功体験に強く根ざしています。精神科医や情報発信者にとっては応用範囲が広いかもしれませんが、業種やライフスタイルによっては活かしにくい場面もあるでしょう。また、SNSや書評のアウトプットに重きを置く提案が多く、内向的な読書家にはフィットしにくい側面もあります。
話し言葉に近い口調で書かれており、親しみやすさはありますが、繰り返しや主張の過剰な強調が多く、冗長に感じられる場面が目立ちます。全体に勢いはあるものの、編集の練度が高ければもっとスマートに伝わったはずです。啓発書らしいノリが苦手な読者には、読みにくさを感じるかもしれません。
脳科学や精神医学の観点に基づいた説明はあるものの、専門的な裏付けはあくまで補足程度であり、論拠の深さには限界があります。科学的データの扱い方も、やや都合の良い引用が目立ち、学術的な厳密さを求める読者には物足りないでしょう。専門知識の紹介というよりは、あくまで著者の読書術の説得力を補うツールとしての位置付けにとどまっています。

なるほど〜、読書ってただ読むだけじゃもったいないんだね。

そうなんだよ。読んだ内容って、アウトプットしないとすぐ消えるからね。

「人に話す」とか「メモする」とか、意外と簡単なことなのに、やってなかったかも。

うん、それを“ちょっと意識するだけ”で、記憶力も理解力もガラッと変わるんだよ。

今日から試してみる!読んだ本を3行でまとめるっての、私にもできそうだし。

それで十分!続けることが一番大事だから、完璧目指さずに気軽にね。
本を読むことは“スタート”であり、“ゴール”ではありません。読んだ内容をアウトプットする習慣が、あなたの知識を“本物の力”に変えてくれます。
