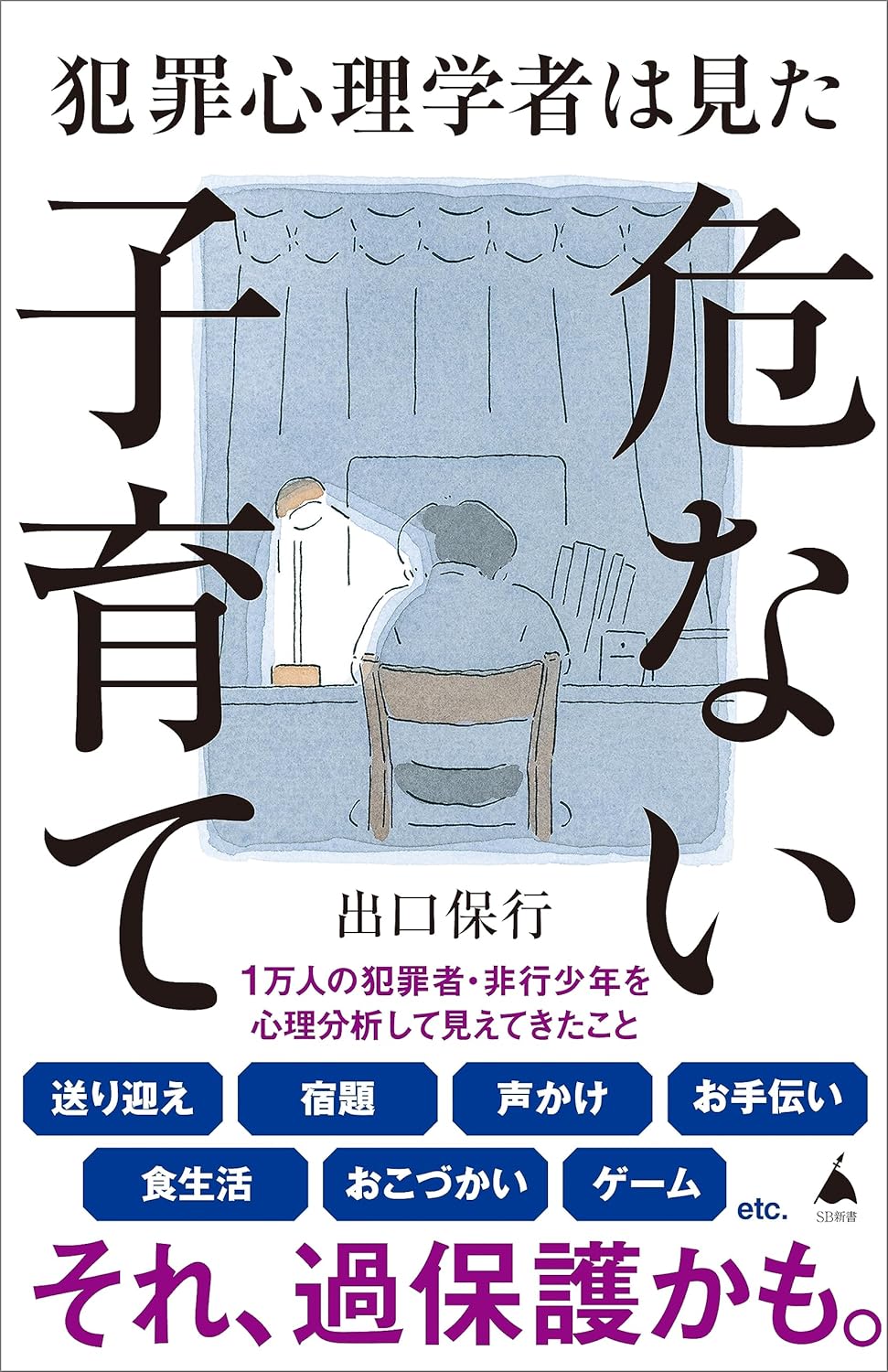この記事はで読むことができます。

最近、子どもが全然言うこと聞かないんだよね…。注意してもヘラヘラしてるし、真剣に向き合っても響いてない感じ。

それ、俺もある!頑張って叱ってるつもりなんだけど、どこかで間違ってるのかなって不安になるときあるよ…。

本とか調べてみても、「褒めましょう」「叱りすぎないで」みたいな一般論ばかりで、結局どうすればいいかわかんない。

それなら『危ない子育て』読んでみて。親の“思い込み”や“関わり方のクセ”が、子どもの反応を変えてるって書いてあってめっちゃ納得した。

え、親の問題ってこと…?ドキッとするけど、知る価値ありそう。

そう。ちょっと反省もしたけど、逆に「今からでも変えられる」って前向きになれたよ!
子育てでつまずいたとき、子どもを変えようとする前に“親の接し方”を見直してみませんか?本記事では、子どもが言うことを聞かない本当の理由と、失敗しないための関わり方を3つの視点から解説します。
反抗や無関心の背景には、親の“4つの関わり方のズレ”が影響しているかもしれません。子どもの問題行動を通して、親自身の接し方を振り返る視点が得られます。
「叱ってるのに伝わらない」状態の裏側には、愛情や信頼の断絶が隠れているケースがあります。その見えないズレを修正することで、子どもの行動が変わり始めます。
親が完璧でなくても大丈夫。間違いに気づき、関わり方を見直す姿勢が、子どもの心を再び開く鍵になります。
子どもが非行に走る背景には、親の養育態度が大きく関わっているというのが本書の主張です。著者は、親のタイプを「過保護型」「高圧型」「甘やかし型」「無関心型」の4つに分類し、それぞれが子どもの心にどんな影響を与えるのかを解説しています。どのタイプも一見、子どもを想っているように見える関わり方ですが、実際には子どもが“自分で考え、選び、責任を持つ力”を奪ってしまっている点に共通しています。
たとえば、過保護型はすべてを先回りして与え、子どもが失敗する機会を奪ってしまいます。高圧型は親の価値観を押し付け、子どもに“自由に感じる・考える”余地を与えません。甘やかし型はルールを作らず、無関心型はそもそも関心を持ちません。いずれの型も、子どもの内面に“空白”を作り出し、その空白がやがて社会との摩擦や逸脱行動を引き起こす温床になるのです。
本書を読むことで、「自分の育て方は大丈夫だろうか?」という問いを持つことができるようになります。そして、自分がどのタイプに近いかを知ることが、育児の改善の第一歩になると気づかされます。
非行少年の多くが共通して語るのは、「親に本音を話せなかった」「顔色ばかり見ていた」という経験です。親からの過干渉や過度な命令、あるいは完全な放置は、子どもに「自分は信頼されていない」という思いを植え付けます。この“親への不信感”が、やがて家庭という居場所を失わせ、子どもは外の世界に居場所を探し求めるようになります。
たとえば、高圧的に育てられた子どもは、「どうせ怒られるから本音は隠そう」となり、やがて家庭内で感情を表現しなくなります。その反動として、非行グループに受け入れられることで承認欲求を満たそうとするのです。一方で、甘やかされて育った子どもは、外の厳しいルールに適応できずにトラブルを起こしやすくなります。
本書では、子どもが非行に至るプロセスが、決して一夜にして起こるものではなく、長期にわたる関係性の中で形成されることが繰り返し強調されています。親子の信頼関係が欠けたとき、その空白に“問題行動”が入り込むという構図は、家庭内コミュニケーションのあり方を根本から問い直す材料になります。
親である以上、誰しも子育てに不安や悩みを抱えています。本書が力強く伝えているのは、「間違ったことに気づいたら、そこから変わればいい」というメッセージです。完璧な子育てを目指すあまり、失敗を恐れて行動できなくなるよりも、大切なのは“振り返って修正する姿勢”なのです。
たとえば、過去に怒鳴ってしまったことや、忙しさから無視してしまったことがあったとしても、あとから「さっきは怒りすぎたね」「ちょっと疲れてて気づけなかった、ごめんね」と子どもに伝えることは、それだけで信頼関係の修復につながります。子どもにとって重要なのは、完璧な対応よりも、“親が本気で向き合ってくれている”という実感です。
また、著者は「親の変化を子どもは敏感に感じ取る」と述べています。親が丁寧に対話を重ね、自分の関わり方を変えていく姿を見せることこそ、子どもの変化を引き出す最も確実な方法なのです。育児とは、親子で一緒に成長するプロセス。失敗を受け入れ、今日から変わる勇気を持つことが、子どもの未来を切り拓く力になります。
まずは自分の育児スタイルが「過保護型」「高圧型」「甘やかし型」「無関心型」のどれに当てはまるかを確認しましょう。たとえば、子どもの代わりに何でもやってしまうなら過保護型、叱ることが多ければ高圧型の可能性があります。客観的に自分を振り返ることで、修正ポイントが明確になります。
子どもに「今日は楽しかった?」「困ったことあった?」と聞くなど、小さな対話の積み重ねが信頼関係を育てます。アドバイスや指示よりも、まず“聞くこと”を優先し、子どもが安心して話せる関係を目指しましょう。信頼の土台があれば、多少の失敗や反抗があっても大きく道を外れることはありません。
その日の子どもへの対応を簡単にメモしておくだけでも、自分の関わり方を客観的に見直すことができます。感情的になったときや、忙しさで適当になってしまったときの記録を読み返すことで、次の改善につなげやすくなります。完璧を求めるのではなく、「昨日より少しよくなる」を目指す視点が重要です。
実際の非行事例を通じて、親の養育態度がどのように子どもに影響するかを具体的に示しており、家庭での子育ての見直しに役立つ内容です。4つの子育てタイプに分類し、それぞれに潜むリスクを丁寧に解説している点は、行動の指針になり得ます。ただし、「こうすればうまくいく」という直接的な成功法は提示されず、抽象的に感じる読者もいるかもしれません。また、薬物や非行の深刻なケースはやや極端で、すべての家庭にそのまま当てはまるとは言い難いです。
豊富な実例と解説により、心理学の専門用語や理論が噛み砕かれて説明されており、読み手に伝わりやすい構成です。サイモンズの4類型やエリクソンの発達段階などの基本理論も、生活感のある言葉に置き換えているのが好印象です。一方で、文量が非常に多く、情報の重複や散漫な説明が見られる箇所もあり、全体としてはやや冗長です。特に教育虐待や薬物犯罪の描写は衝撃的で、読者によっては読み進めづらいかもしれません。
サイモンズ式の4タイプ分類などは普遍的な視点を提供しており、多くの親が自分の子育てを振り返る手がかりになります。しかし、本書のベースは非行や犯罪という特殊なケースに寄っており、日常的な子育てに悩む親にとっては少しスケールが違う可能性もあります。極端な事例中心であるため、自分の子育てにどう応用すべきか迷う読者も出てきそうです。汎用性を高めるには、もっと軽微な問題や日常の場面に対応したアドバイスがほしいところです。
著者の語り口は一貫しており、専門家としての誠実な姿勢が伝わってくる構成です。事例紹介→分析→解説という流れはわかりやすいですが、ページ数が非常に多く、重いテーマが続くため読了には体力が必要です。また、繰り返しややや感情的な表現もあり、テンポよく読めるとは言いにくい点があります。ショッキングな表現に引き込まれる反面、読者の心理的負担が大きくなる場面も散見されます。
著者は法務省で1万人以上の非行少年を分析してきた実績を持ち、心理学の知見も豊富に活用されています。事例の描写もリアルで、専門職ならではの観察眼と分析力が感じられます。また、マインドコントロールや教育虐待といった社会的に注目されるテーマにもきちんと触れています。学術的裏付けと臨床的経験のバランスが取れており、内容の信頼性は高いと評価できます。

読んでみてちょっと反省した…。まさか自分が「過保護型」だったとは思ってなかった。

俺も!良かれと思ってやってたことが、実は子どもの成長を妨げてたかもって気づかされたよ。

でも「完璧じゃなくていい」って言葉に救われたよね。子育てって修正しながらでいいんだって。

ほんとそれ。気づいた時点でOK、そこから関わり方を変えればいいって前向きになれた。

まずは“聞く姿勢”を意識してみようかな。今日からさっそくできそうだし。

うん、お互い焦らずちょっとずつ変えていこ!
子育てで大切なのは、正しいやり方を知ることより、“関わり方を見直す勇気”です。本書は、子どもが発するサインに気づき、親としてできることを再確認させてくれます。
今の関係に少しでも違和感があるなら、立ち止まって考えるきっかけとして、ぜひ手に取ってみてください。