この記事はで読むことができます。

最近さ、会議で「どう思う?」って聞かれても、何も言えないことが増えてきて…。

あー、わかる。それ私もよくあるよ。「自分の意見を持って」って言われても、何を基準に考えたらいいのか分からないんだよね。

学生のときは“答え”があったけど、社会人になると“正解がない”場面ばかりじゃん?

うんうん。最近「自分で考えろ」って言われるのが一番プレッシャーだもん…。

で、色々調べてたら『10歳でもわかる問題解決の授業』って本を見つけたんだよ。

それ俺も読んだ!小学生向けかと思ったら、社会人こそ読むべき内容でびっくりした。
自分で考える力は、もともとの才能ではなく“育てられる力”です。本記事では、小学生向けに書かれた内容をベースにしながら、社会人にも通じる「考える技術」をわかりやすくご紹介します。
「考える力がない」と感じるのは、思考力ではなく“問いの立て方”にズレがあることが多いからです。正解を探すのではなく、仮説を立てて動ける力が今の時代に求められています。
複雑な問題に向き合うときは、感情や経験に頼るだけでは限界があります。本書では誰でも実践できる「考えるための5つのルール」が紹介されています。
「わからないから動けない」から、「わからないから考える」へ。試行錯誤を前向きに進める力こそが、ビジネスの現場で信頼される“考える力”になります。
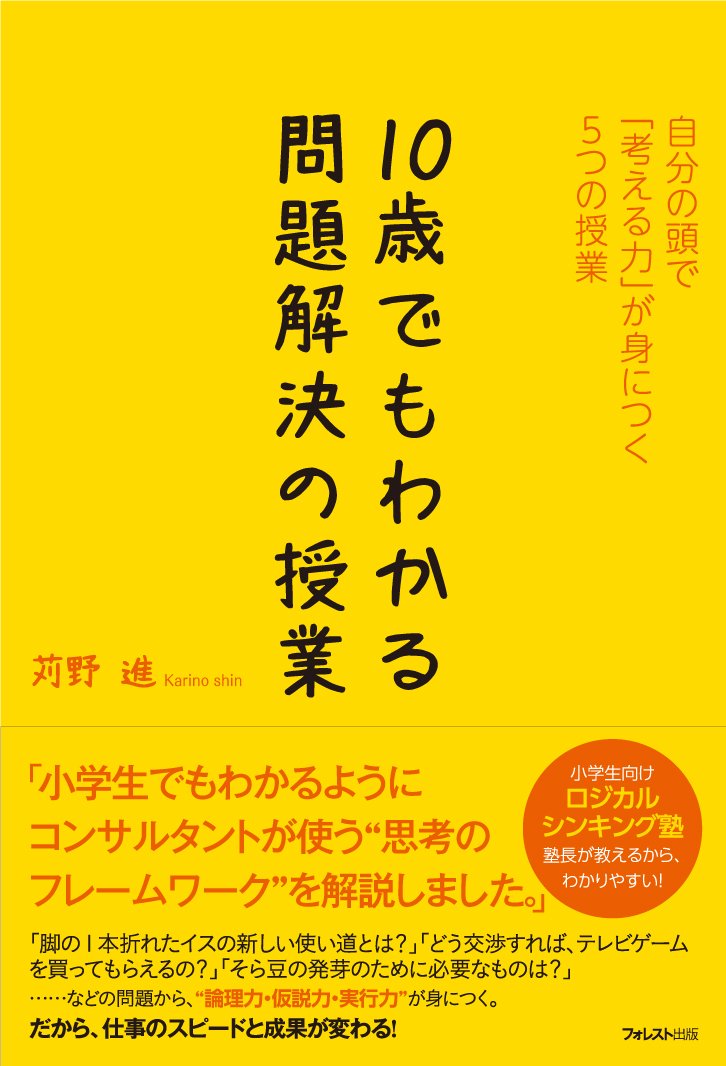
| 著者 | 苅野 進 |
| 出版社 | フォレスト出版 |
| 出版日 | 2017年10月2日 |
| ジャンル | スキルアップ・自己研鑽 |
本書ではまず、「問いを立てる力」が考える力の出発点だと語られています。多くの人が「どれが正解か?」という視点で考えをスタートさせてしまい、そのせいで思考が止まってしまうのです。
けれど、社会に出ると“正解のない問題”ばかりで、答えが用意されていないケースがほとんど。そこで必要になるのが、「そもそも何を問うべきか?」という思考のスタンスです。
たとえば「売上が落ちた」ではなく、「なぜ落ちたのか?」「その背景には何があるか?」と掘り下げて問いを再定義する力。これこそが、問題解決の糸口になります。著者は、「良い問いこそが、良い答えを生む」と繰り返し述べており、この視点が非常に印象的です。
問いを立てることは難しいと思われがちですが、具体的なフレームワーク(5W1Hや対比など)を使えば誰でも習得可能です。つまり、考える力とは“問う力”であり、それが仮説構築や行動の第一歩になります。受け身ではなく、自分から問い直す姿勢が、社会で求められる“思考力”を形作るのです。
「まず調べてから考える」のではなく、「まず仮説を立ててから調べる」。これが、本書で提案されている“考えるためのルール”のひとつです。情報を集める前に、現時点での仮説を立てることで、思考に方向性が生まれます。
たとえば「この商品の売れ行きが悪いのは、ターゲットのニーズとズレているからでは?」という仮説を立ててから、データやヒアリングでそれを検証する。このサイクルを何度も繰り返すことで、問題解決の精度が上がっていくのです。
また、仮説は外れてもかまいません。むしろ、外れることで「新しい視点」に気づけることも多く、柔軟に方向を変える思考力も養われます。
このプロセス自体が「自分の頭で考える力」そのものであり、主体性を持った判断を生み出します。受け身で「答えを探す」のではなく、能動的に「仮説を動かす」感覚が、考える力の根幹になります。
「失敗=悪いこと」という固定観念を手放すことも、本書が伝えている重要なメッセージです。特に日本の教育では、正解を出すことに重きが置かれ、間違えることに対する恐怖心が強くなりがちです。しかし、考える力は「うまくいかなかった原因を振り返る」中でこそ深まっていきます。
たとえば、ある選択肢を選んだ結果うまくいかなかったとしても、その理由を言語化することで次の判断材料になります。本書では「失敗ノート」という考え方が紹介され、うまくいかなかった事例を記録・整理する習慣が、次の成功の鍵になると述べられています。
これはまさにPDCAサイクルの“Check”と“Act”を思考習慣として根づかせる方法とも言えます。また、失敗した自分を否定せず、学びの材料として扱う視点は、自己効力感の向上にもつながります。思考力とは、成功を生む力だけでなく、「失敗をどう扱うか」という姿勢にも深く関わっているのです。
仕事や会話の中で「この前提は正しい?」「そもそも何が問題?」と一度立ち止まって問いを立て直してみましょう。正解を探す前に“自分が何を考えているか”を明確にすることが、考える力を鍛える第一歩になります。毎日のちょっとした疑問をメモする習慣が、思考のクセを変えていきます。
何かを調べるときは、事前に「自分はこうじゃないかと思う」と仮説を立ててから行動に移してみましょう。これだけで調査や行動に目的意識が生まれ、情報の取捨選択も早くなります。仮説が外れても、それは次の仮説を立てるための材料になると前向きに捉えましょう。
うまくいかなかった経験はそのままにせず、なぜ失敗したのか、次はどうすればよいかを紙やアプリに書き出してみましょう。失敗を可視化することで、同じミスを繰り返さず、思考の深さが蓄積されていきます。反省ではなく「学び」として扱う視点が、考える力を一段深めてくれます。
本書は社会人の日常的な意思決定や問題解決に直接役立つ技術や思考法を、豊富な例とともに紹介しています。仮説思考・フレームワーク活用・試行錯誤のプロセスといった、実務に即応する具体的なスキルが丁寧に解説されています。実行可能な行動指針が随所に盛り込まれており、読み終えた直後から実践に移せる内容です。特に「考え方の型」を身につけさせる構成は実務家にも教育者にも有益です。
小学生向けの教育現場をベースにした比喩や例が多く、論点が明確で読み手の理解を助ける工夫がされています。専門用語も少なく、具体例から一般化するプロセスもていねいです。ただし、文章構造が散文的で、文の繋がりが弱い箇所が散見され、読解にやや集中力を要する場面もありました。その点で、若干の読みづらさを感じる読者もいるかもしれません。
教育、ビジネス、家庭生活など、あらゆる分野に応用可能な「考え方のスキル」を中心に据えており、対象や状況を問わず活かせます。年齢・職業を問わない普遍的な問題解決力を育てるための知見が広範囲にわたって盛り込まれており、どの立場の人にも響く設計です。小学生から経営層まで活用できる例の展開も、読者層の広さを担保しています。
構成は丁寧で、要所にまとめや練習問題が設けられているため、復習や内省を促す良い工夫があります。一方で、全体に話が長く、冗長と感じられる部分が少なくありません。また、話し言葉に近い文体が続き、読書としてのテンポを欠く箇所もあります。編集次第でよりスムーズに読める構成になったと感じられます。
ビジネスコンサルタントの経験に裏打ちされた論点と、教育現場での実践に基づく視点がバランスよく織り込まれています。問題解決やロジカルシンキングに関する内容としては、基礎から応用まで広くカバーしており、初学者にとって十分な専門性があります。ただし、学術的な裏付けや理論的深掘りは抑えめで、専門的読者にはやや物足りなさが残るかもしれません。

読んでよかったなあ。思考力って、なんとなく“頭の良さ”のことだと思ってたけど違ったね。

うん、ちゃんと「考え方」には型があるんだってわかったのが大きかった!

「正解を探す」から「問いを立てる」に切り替えるだけで、会話も仕事も動き出す気がする。

しかも、小学生でも使えるっていうのが逆にいいよね。うちらもここから鍛えていけそう。
「考える力がない…」と感じているあなたにこそ読んでほしい一冊です。正解がない時代に必要なのは、“自分で問い、仮説を立て、行動し、見直す”という思考のサイクル。
本書はその土台となる思考力を、やさしく、具体的に教えてくれます。
